将来の年金不安や預金金利の低さを背景に、手堅い収益源としてマンション投資が改めて注目されています。しかし「区分所有は本当に儲かるのか」「2025年に買う価値はあるのか」と迷う方は少なくありません。本記事では、マンション投資 区分所有 2025年の市場環境から資金計画、税制優遇までを丁寧に解説します。読み進めれば、物件選びから出口戦略まで自信を持って判断できる視点が身につくでしょう。
区分所有という選択肢の特徴を押さえる
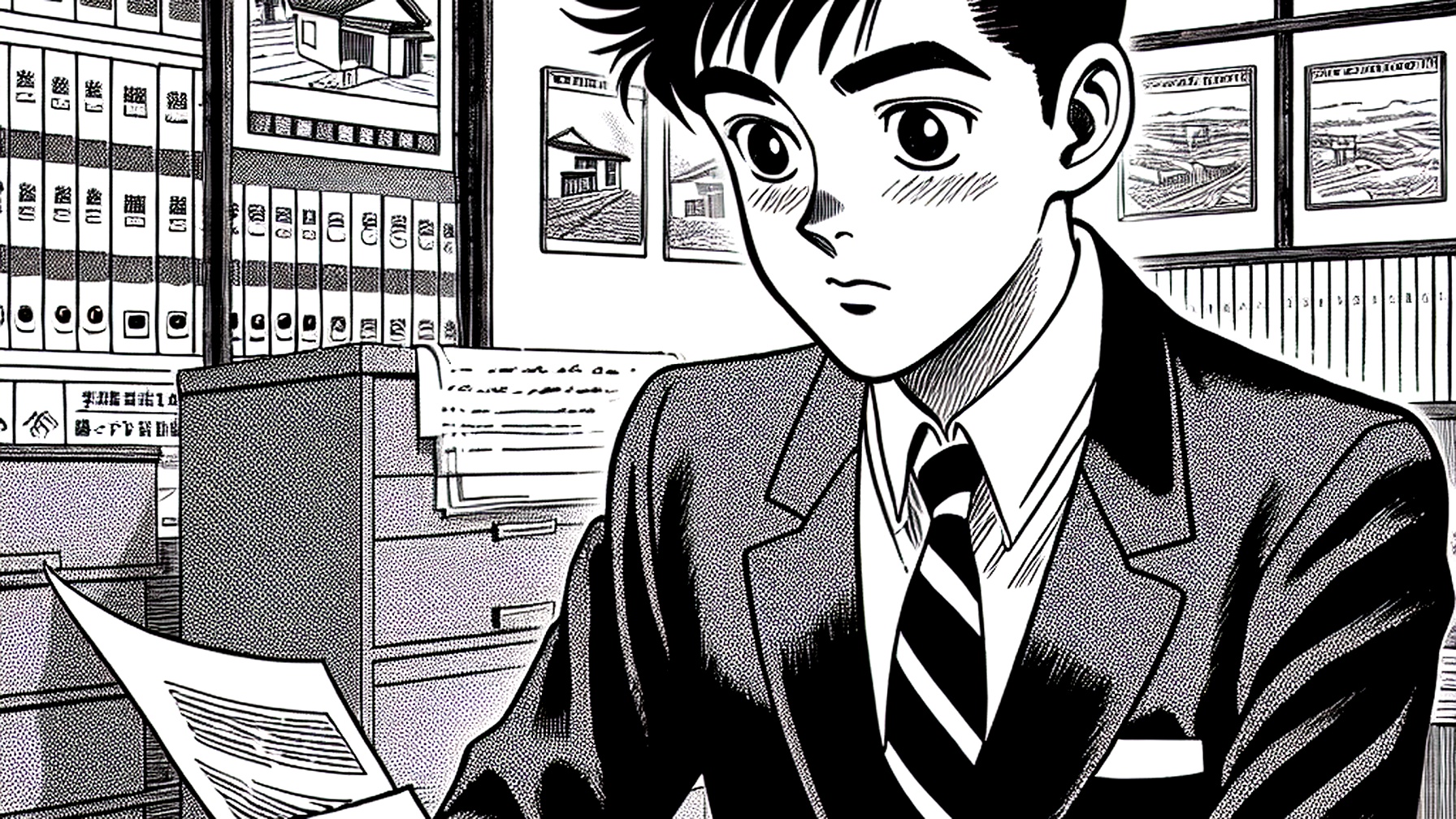
重要なのは、区分所有と一棟購入の違いを正確に理解することです。区分所有はマンションの一室を購入し、共用部の維持管理を管理組合に委ねられる点が最大の特徴です。そのため、日常的な修繕や法定点検の手間が少なく、会社員でも運用しやすい形態といえます。
また、初期投資額が抑えやすいことも魅力です。東京都心の新築一棟マンションが数億円規模なのに対し、区分所有なら三千万円台から始められるケースも珍しくありません。一方で、専有面積が小さいため、空室が発生すると家賃収入がゼロになるリスクも忘れないようにしましょう。
さらに、建物や設備の改善に自分だけで踏み切れない点には注意が必要です。バルコニーの防水工事やエントランスのリニューアルは管理組合の合意が欠かせません。つまり、区分所有では他の区分所有者と良好な関係を築き、総会に積極的に参加する姿勢が収益を守るカギになります。
2025年の市場動向と価格の現実
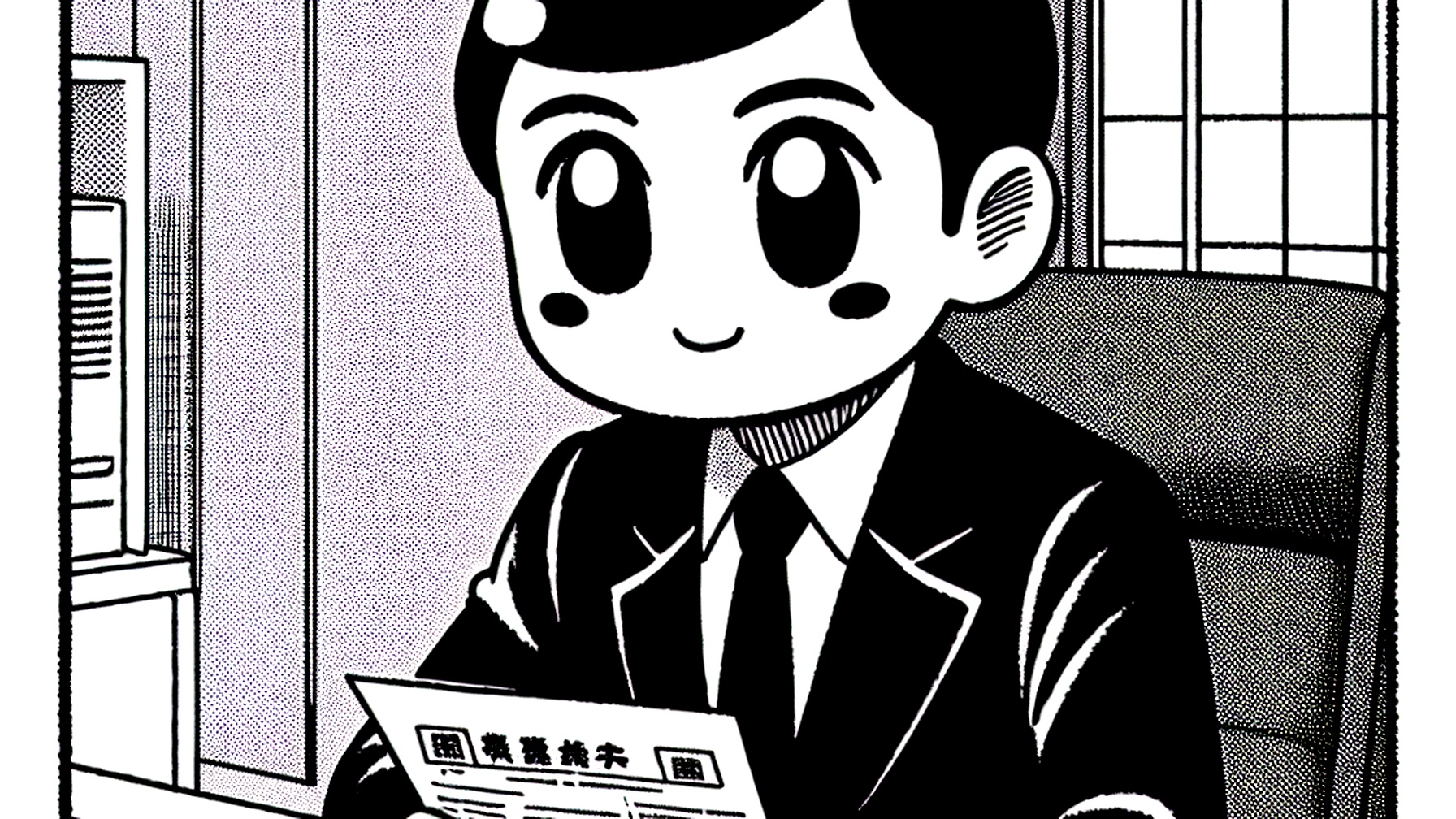
まず押さえておきたいのは、価格と需要の最新データです。不動産経済研究所によると、2025年9月時点の東京23区新築マンション平均価格は7,580万円で、前年比3.2%上昇しました。背景には資材高騰と労務費上昇があり、供給戸数は横ばいでも価格がじわりと上がる構図です。
一方、賃貸需要は都心部を中心に底堅い状況が続いています。総務省の住民基本台帳によれば、23区の人口は微増傾向で、特に単身世帯比率が高水準です。単身者向けワンルームは駅近立地であれば平均空室期間が1カ月未満に収まるデータもあり、適切な賃料設定を行えば回転は速いといえます。
ただし、郊外や築古物件では二極化が進んでいます。家賃が下落傾向にあるエリアでは、購入価格の安さだけで判断すると収益が伸び悩む可能性が高いでしょう。物件を検討する際は、将来の再開発計画や人口動態まで視野に入れ、家賃下落耐性のある立地かを見極めることが欠かせません。
キャッシュフローとローンの考え方
ポイントは、表面利回りではなく実質利回りで判断する姿勢です。実質利回りは家賃収入から管理費・修繕積立金、固定資産税などの経費を差し引き、さらに空室損失を織り込んで計算します。都心ワンルームの平均表面利回りが4%台でも、実質では2%台に下がるケースが多いので注意が必要です。
融資を利用する場合、金利と返済期間がキャッシュフローを大きく左右します。例えば3,500万円を金利1.8%、35年元利均等で借りると、月々の返済額は約11万円です。想定家賃が13万円なら手残りは2万円弱ですが、管理費と修繕積立金で月1.5万円かかれば赤字になります。つまり、金利が0.3%上がるだけでも収支は簡単に逆転するため、金融機関の比較は怠れません。
加えて、繰上返済のタイミングを計画に組み込むとリスク耐性が高まります。家賃収入から月1万円を積み立て、5年後に60万円を元本返済に充てるだけでも、総返済額は数十万円減少し、空室時の負担も軽くなります。現実的なキャッシュフロー表を作成し、厳しめのシナリオでも黒字を維持できるか確認しましょう。
リスク管理と出口戦略を先に描く
実は、区分所有の成否は「出口」で決まると言っても過言ではありません。購入時点で売却価格の下落幅を見積もり、保有期間と売却時期のシナリオを描いておくことが大切です。不動産流通推進センターのデータでは、築20年を過ぎると平均成約価格が新築時の60%前後に落ち着く傾向があります。
このため、築後15年以内に買い、10年程度で売却する「短中期回転型」か、減価償却メリットを享受しつつ20年以上保有する「長期インカム型」か、方針を明確にしましょう。短中期ならリフォーム費用を抑え、売却益狙いで設備更新を最小限にする戦略が機能します。長期保有なら、給排水管の更新費用まで含めた修繕計画が欠かせません。
また、災害リスクの確認も欠かせない時代です。東京都都市整備局の洪水ハザードマップでは、荒川下流域に浸水想定の高い地域があります。火災保険に水災補償を付帯すると保険料は上がりますが、損害額を考慮すれば必要経費といえるでしょう。想定外の出費を保険と積立金でカバーできるよう、購入前にリスク試算を行うことが長期安定運用につながります。
2025年度に活用できる税制・優遇制度
まず、賃貸用区分マンションでも減価償却費を経費計上できる点は大きな節税効果を生みます。木造22年、鉄筋コンクリート47年という法定耐用年数に基づき、建物部分を定額法で償却すれば、年間家賃の数割を非課税化できるケースもあります。
さらに、耐震基準適合証明を取得した中古マンションを取得すると、登録免許税と不動産取得税の軽減措置(2026年3月31日取得分まで延長予定)が受けられます。具体的には、登録免許税の税率が2.0%から0.3%へ、不動産取得税が固定資産税評価額から最大1200万円控除されるため、数十万円単位のコスト削減が可能です。
加えて、2025年度も継続する「既存住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置」は賃貸住宅にも適用されます。一定の断熱改修を行い自治体の確認を受けると、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されるため、長期保有を前提とする場合は検討する価値があります。このような制度は申請期限や工事要件が細かいため、必ず専門家に確認しましょう。
まとめ
ここまで、区分所有マンション投資を2025年に始めるうえで押さえるべき視点を整理しました。立地と管理体制、実質利回り、融資条件、リスクと出口戦略、そして税制優遇を総合的に判断することが安定収益への近道です。結論として、数字を冷静に積み上げ、制度を正しく活用する投資家が最後に笑います。まずは気になる物件のキャッシュフロー表を作り、厳しめの条件でも黒字を確保できるか検証してみてください。行動を起こすことで、資産形成の第一歩が現実のものになります。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 – https://www.soumu.go.jp
- 不動産流通推進センター 成約価格データ – https://www.retpc.jp
- 東京都都市整備局 ハザードマップ – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp
- 国土交通省 住宅税制ガイド 2025年度版 – https://www.mlit.go.jp

