収益物件を初めて買おうとすると、情報の多さに戸惑う方が少なくありません。自己資金はいくら必要か、融資は通るのか、物件タイプで収益性は変わるのか——次々に疑問が湧きます。本記事では、収益物件の購入手順を時系列で整理しながら、マンション、アパート、一棟ビルなどタイプ別の違いまで丁寧に解説します。読み終えた頃には、自分に合う物件を選び、金融機関と交渉し、リスクをコントロールする流れが具体的にイメージできるはずです。
収益物件の基本を押さえる
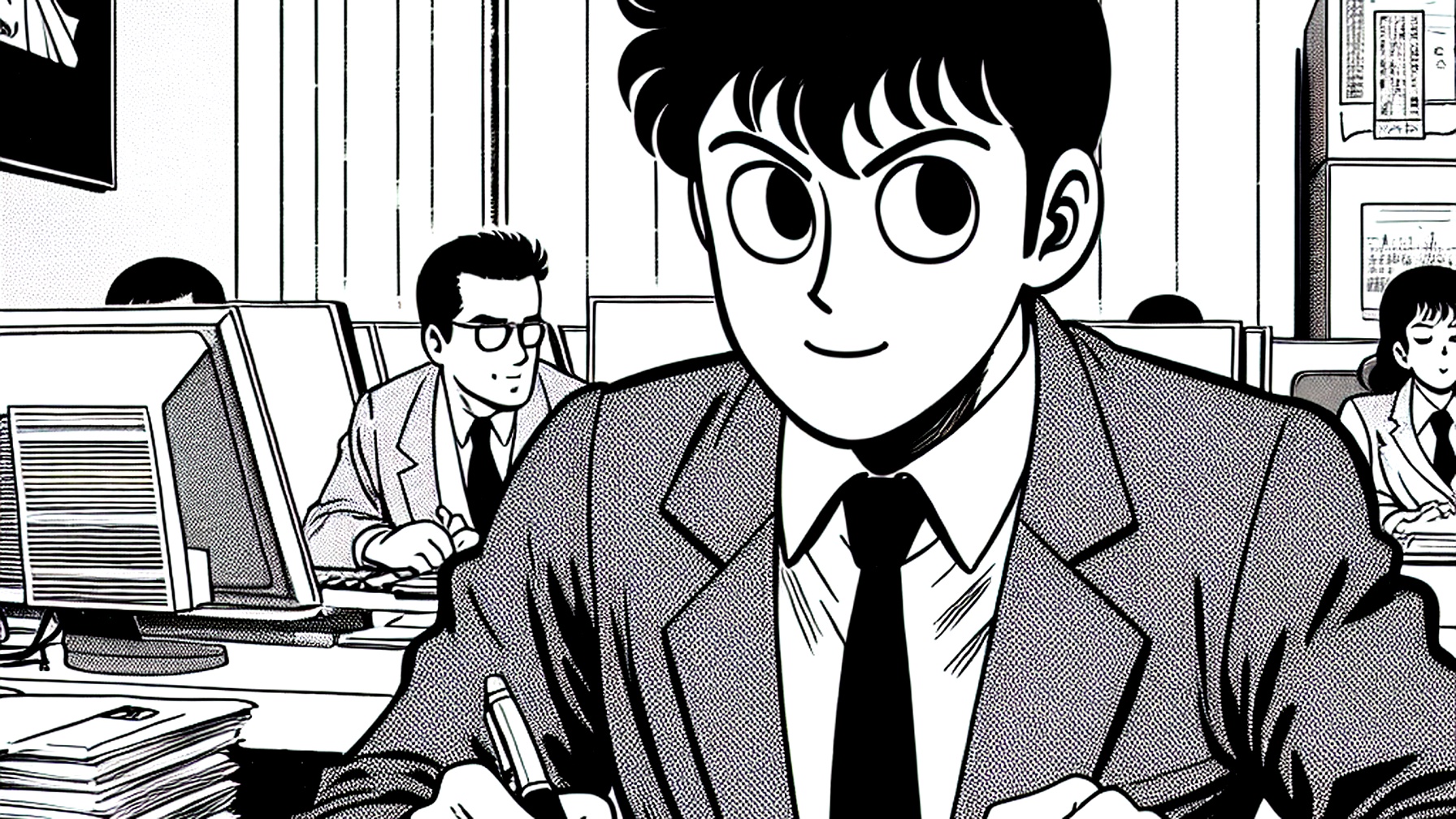
重要なのは、収益物件を「家賃という事業収入を生む資産」と捉える姿勢です。国土交通省の不動産価格指数(2025年7月速報)によると、全国の住宅系物件は前年同月比4.2%上昇しました。一方で、総務省の住宅・土地統計調査では2024年の全国平均空室率が13%に達しています。この数字が示すように、価格上昇と空室リスクは表裏一体です。購入前に「賃料—運営費—融資返済=キャッシュフロー」という計算式を体で覚えておくと、目先の利回りに惑わされにくくなります。
次に、利回りの見方を整理しましょう。表面利回りは年間家賃収入を購入価格で割った値で、広告に多用されます。しかし固定資産税や管理費、修繕費を差し引いた実質利回りが投資判断の核です。たとえば表面8%でも、運営費が家賃収入の30%なら実質は5.6%に落ち込みます。つまり実質利回りが6%を超える物件は、最近の低金利を勘案すると相対的に魅力的といえます。
加えて、エリアの人口動態を確認する習慣が欠かせません。国立社会保障・人口問題研究所の推計では、2035年までに地方圏の人口が10%減少する一方、東京23区は横ばいです。賃貸需要は人口動向と強い相関があるため、地方高利回り物件を狙う場合でも、大学や工業団地の再開発など局所的な需要源を裏付けとして持つことが重要になります。
購入手順を時系列で理解する
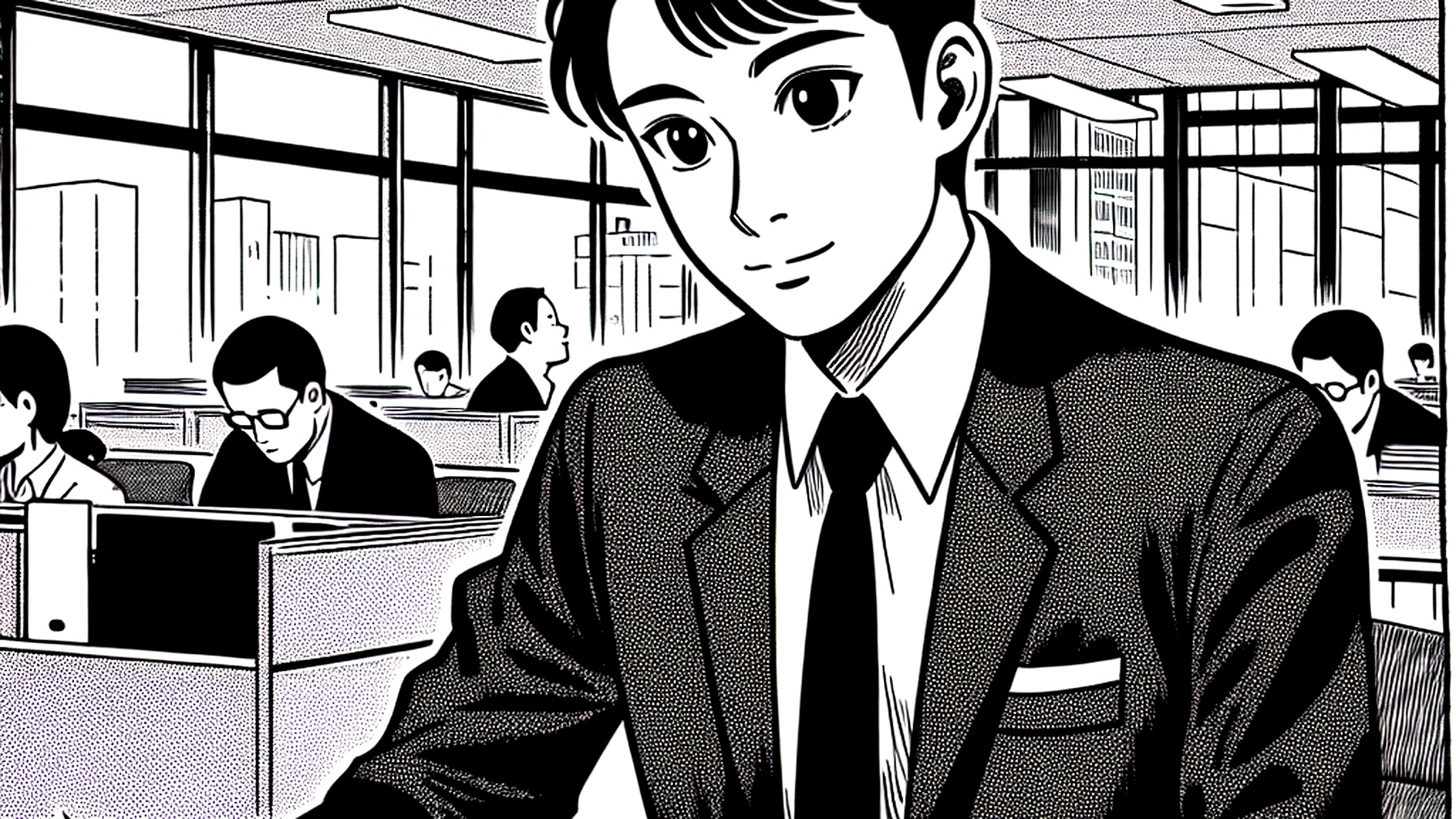
まず押さえておきたいのは、手順を可視化すると抜け漏れを防げる点です。流れを簡潔に示すと下記のようになります。
- 目標設定と資金計画
- 物件情報の収集と現地調査
- 収支シミュレーションの作成
- 買付申込と融資事前審査
- 売買契約締結
- 本審査通過後の決済・引き渡し
目標設定では、年間キャッシュフローをいくら得たいかを具体的に決めます。会社員が副業で手取り月5万円を狙う場合、実質利回り6%の物件なら、価格1,000万円前後が目安になります。次に資金計画ですが、金融機関は自己資金10〜20%を求める傾向が強いです。つまり1,000万円の物件なら諸費用込みで250万円程度を現金で準備しておくと審査が通りやすくなります。
物件情報はレインズマーケットインフォメーションや民間ポータルで一次スクリーニングし、候補を3件程度に絞った後に現地調査へ進みます。ここで近隣物件の賃料相場、築年数と修繕履歴、昼夜の騒音状況を確認すると、机上では見えないリスクを減らせます。買付申込書を提出したら、同時に金融機関へ資料を出し、仮審査を走らせるスピード感が重要です。
契約から決済までは平均1〜2か月ですが、2025年の電子契約普及率は70%を超えています。電子署名を活用すると郵送のタイムラグがなくなり、融資実行日の前倒しが期待できます。決済当日は司法書士立会いのもと、残金決済と所有権移転登記が行われ、鍵を受け取った瞬間から賃料収入が発生します。
物件タイプごとの違いとリスク
ポイントは、物件タイプによって収益構造と運営負担が大きく異なることです。区分マンションは一室単位で購入でき、初期投資が比較的小さいため初心者向きです。ただし、一棟物件と比べて管理組合のルールに縛られるため、大規模修繕積立金の増額判断に自分の意見が通りにくい側面があります。また、戸当たり家賃が低いと空室一つで収入がゼロになる点にも注意が必要です。
一棟アパートは土地と建物を丸ごと所有するため、減価償却費を活用した節税効果が見込めます。実は木造で築浅のアパートなら、最短22年で建物価格を償却できるため、所得税率が高い会社員にはメリットが大きいです。しかし修繕計画を自分で立てなければならず、屋根や外壁の大規模改修が発生すると、一度に数百万円の出費となる点は覚悟が要ります。
一棟RC(鉄筋コンクリート)マンションや商業ビルは、耐用年数が長く金融機関からの評価も高い反面、購入価格が大きくなるので借入額も膨らみます。日本政策投資銀行の調査では、2024年度の法人向け不動産融資平均金利は1.5%でしたが、借入額が1億円を超えると審査書類の精度や連帯保証の要否が厳しくなります。また、テナントが退去すると賃料水準の見直しが必要になるため、商圏分析が欠かせません。
つまり、初期投資を抑えて投資経験を積みたいなら区分マンション、キャッシュフローと節税効果を狙うなら一棟木造、規模拡大と資産価値の安定を優先するなら一棟RCという住み分けが基本ラインです。ただし、エリアの需要構造と自分の資金力を照らし合わせて選択することが成功への近道になります。
融資とキャッシュフローの読み方
まず押さえておきたいのは、融資条件がキャッシュフローを左右するという事実です。たとえば金利1.2%と1.7%では、8,000万円を30年返済した場合の総支払額が約730万円違います(元利均等計算)。この差は実質利回りを約0.6ポイント押し下げるため、物件選定と同じ重みで金融機関選びを行う必要があります。
金融機関は物件評価と個人属性の両面を審査します。物件評価では「積算価格」と「収益還元価格」を比較し、低い方を基準に融資額を決定するのが一般的です。一方、個人属性では年収、保有資産、勤務先規模が主要な判断材料になります。2025年度からは全国保証協会の保証付ローンが拡充され、年収500万円未満でも返済比率40%以内なら上限1億円まで融資可能なケースが出てきました。
キャッシュフローを算出する際は、空室率と修繕費を保守的に見積もります。東京都住宅供給公社の最新レポートでは、築20年超のワンルーム平均空室率が15%です。これを踏まえ、最低でも家賃収入の15%を空室損として、さらに家賃収入の10%前後を修繕積立に回すと安全域が広がります。つまり、表面利回り8%なら差引3%台でもローン返済後に黒字を確保できるかが判断基準です。
さらに、短期と長期の金利動向を読む視点が欠かせません。日銀は2025年4月にマイナス金利政策を解除しましたが、物価安定目標2%が続く限り、急激な利上げは考えにくいとの見方が市場では優勢です。ただし、10年物国債利回りが1%を超える局面では固定金利を検討する余地が生まれます。シミュレーションソフトで「金利2%上昇」シナリオを入力し、返済比率が収入の45%を超えないか確かめる作業を怠らないでください。
2025年の制度と市場動向を踏まえた戦略
実は、2025年度には投資用物件に直接関わる補助金は多くありません。その代わり、省エネ性能を満たすと融資優遇を受けられるグリーンリノベーション促進事業が継続されており、耐震・断熱改修後の物件は金利が0.3ポイント下がる場合があります。期限は2026年3月申請分までですから、築古物件を買ってリフォームする戦略と相性が良いと言えます。
市場動向では、賃料指数が都市部と地方で二極化しています。三大都市圏の賃料は過去3年で平均6%上昇した一方、地方中枢都市以外では横ばいが続いています。テレワーク定着により「駅徒歩15分圏」でも入居が付きやすくなったため、少し駅から離れていても、ネット回線と宅配ボックスを備えるだけで競争力が向上します。
また、空き家対策特別措置法の改正で、2025年8月から管理不全空き家に固定資産税が最大4倍課税されるようになりました。これにより、相続で空き家を抱えた個人が低価格で売却するケースが増えています。市場に出た築古戸建てや小規模アパートをリノベーションし、短期で入居付けして価値を高める「バリューアップ転売」戦略も現実的な選択肢です。
結論として、市場全体が右肩上がりではない今こそ、データをもとに地域特性と制度優遇を掛け合わせた戦略が差別化要因になります。自らの資金力と時間的余裕を冷静に見極め、購入手順を着実に踏むことで、中長期の安定収益が見込めるポートフォリオを構築できるでしょう。
まとめ
ここまで、収益物件 購入手順 違いを中心に、物件選びから融資、制度活用までを一気通貫で解説しました。手順を可視化し、実質利回りとキャッシュフローに軸足を置けば、タイプが違う物件でも比較が容易になります。さらに、2025年の制度と市場動向を踏まえた戦略を採れば、初心者でも致命的な失敗を避けられます。まずは自己資金と目標キャッシュフローを整理し、信頼できる不動産会社と金融機関に相談する第一歩を踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数 2025年7月速報 – https://www.mlit.go.jp/
- 総務省 住宅・土地統計調査 2024年版 – https://www.stat.go.jp/
- 国立社会保障・人口問題研究所 日本の将来推計人口 2023年推計 – https://www.ipss.go.jp/
- 日本政策投資銀行 不動産マーケットレポート2024 – https://www.dbj.jp/
- 東京都住宅供給公社 賃貸住宅市場レポート2025 – https://www.to-kousha.or.jp/

