40代になり、老後資金や子どもの教育費が気になり始めた頃、「今から不動産投資を始めても遅くないのだろうか」と悩む人は多いものです。住宅ローン残債や転職リスクなど不安材料はあるものの、実は40代だからこそ得られる強みも少なくありません。本記事では、同世代のリアルな成功事例を通じて具体的な戦略を解説し、資金計画から物件選びまで一連の流れを体系的に学べる内容にまとめました。読むことで「自分にもできる」と感じられる道筋が見え、次の一歩を自信を持って踏み出せるようになります。
40代が不動産投資で有利な理由
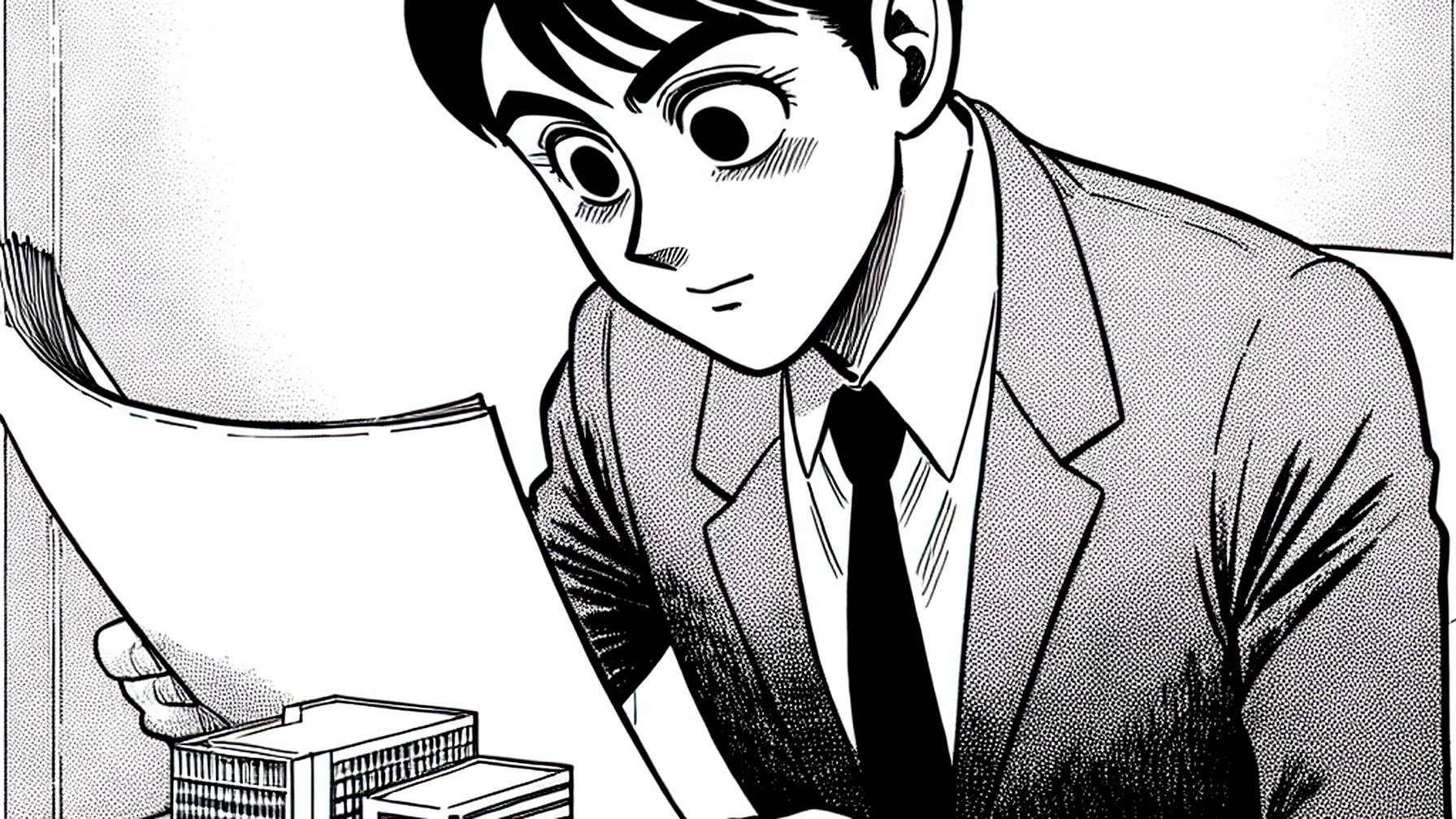
まず押さえておきたいのは、40代が持つ信用力と経験値が投資の武器になるという点です。住宅金融支援機構の2025年度統計によれば、40〜49歳の平均年収は会社員全体の中で最も高く、金融機関の融資審査で優遇されやすい傾向が見られます。また、社会人生活が20年以上になることで、社内外に築いたネットワークから物件情報や専門家を紹介してもらえる確率も高まります。
一方で残りの就労年数が20年前後に限られるため、返済期間やキャッシュフローの組み立てには若年層以上に計画性が求められます。つまり、「借りられる額」と「返せる額」を混同しない冷静さこそが40代成功者の共通点と言えます。さらに、子育てや親の介護などライフイベントが具体化し、将来の支出を現実的に見積もれるため、過度に楽観的なシミュレーションを避けやすいこともメリットです。
最後に、40代は税負担がピークに達しやすい時期でもあります。不動産所得による減価償却を活用すれば課税所得を圧縮でき、手取り収入を実質的に増やす効果が期待できます。これらの点を踏まえたうえで、次章から具体的な成功事例を見ていきましょう。
成功事例1:共働き夫婦が築く堅実ポートフォリオ
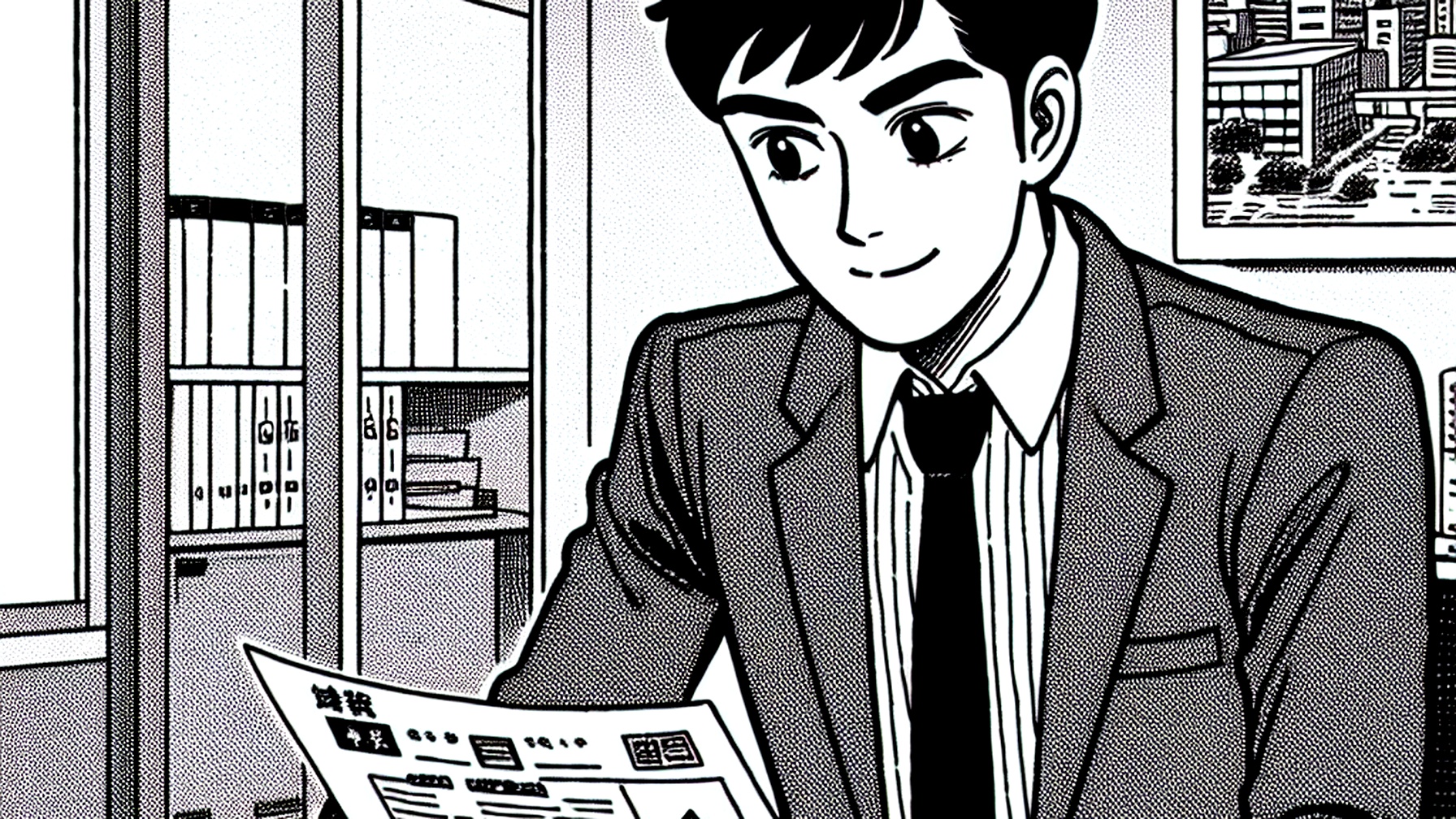
ポイントは、安定したダブルインカムをてこに低リスク運用を心がけた点にあります。東京都内で共働きのAさん夫婦は、世帯年収1,200万円を背景に区分マンションを2戸保有し、表面利回り5.2%のキャッシュフローを確保しています。
最初の物件は2021年に築15年・価格2,800万円で取得しました。住宅ローンと同水準の変動金利1.4%で2,200万円を借入れ、諸費用200万円を含め自己資金は800万円に抑えました。購入時から居住中のテナントが更新を希望したため、初年度の空室リスクはゼロでした。家賃収入年間156万円に対し返済額は年間100万円、管理費・修繕積立金が年24万円だったため、年間32万円の手残りと72万円の減価償却費で合計104万円の課税所得圧縮に成功しました。
2戸目は2024年に同一沿線で購入し、管理会社を一本化してスケールメリットを獲得しました。国土交通省「賃貸住宅市場景況調査」では、単身世帯比率が今後も都心部で高止まりすると示されています。Aさんはこのデータを根拠に空室期間を最大1カ月と想定し、シミュレーションを組んだうえで購入を決断しました。
結果として、2025年9月時点で2戸合計の年間手残りは約70万円に増加し、さらにローン元本返済による資産形成が年間110万円進んでいます。夫婦はこのキャッシュフローを教育資金の積立に振り向け、投資と生活を両立させています。
成功事例2:転勤経験を生かした地方区分マンション戦略
実は、転勤族こそ地方物件の目利き力を磨きやすい立場にあります。メーカー勤務のBさん(47歳)は、これまで北陸と九州を含む4都市に駐在し、各エリアの賃貸需要を肌で感じてきました。その経験を生かし、2022年から福岡市内のワンルームマンションを3戸取得し、現在まで平均稼働率98%を維持しています。
福岡市は総務省「住民基本台帳人口移動報告」で転入超過が全国上位にあり、ワンルーム需要が底堅いと判断しました。購入価格は1戸1,300万円前後で、金利1.8%のアパートローンを利用。家賃は月5.8万円ですが、固定費が低く抑えられるため表面利回りは5.4%です。
Bさんは物件選定の際、駅徒歩7分以内とバス・地下鉄の二路線利用を必須条件にしました。さらに、現地管理会社との打ち合わせをオンラインで月1回行い、退去予定が出た段階で壁紙や照明をアップグレードする方針を共有しています。これにより、平均空室期間は14日と全国平均(国交省推計の42日)を大きく下回っています。
年間キャッシュフローは3戸合計で約90万円です。Bさんは現在の住居が社宅扱いで住宅費が不要なため、手残りを全額繰上返済に充て、52歳までの完済を目指しています。返済完了後は、家賃収入がそのまま年金の上乗せになる計画です。
成功事例3:相続対策とリタイアプランを兼ねた一棟投資
基本的に、高額所得者が税負担と資産継承を同時に考えるなら一棟アパート投資が有効です。医師であるCさん(49歳)は、年収2,000万円を超えるゆえに所得税・住民税の負担が重く、また大学生の子どもに将来の資産を残す目的で2023年に埼玉県内の木造新築アパート(総額9,200万円、8戸)を購入しました。
ローンは35年・金利2.2%でフルローンを組み、年間返済額は約400万円です。一方、年間家賃は720万円で、管理費・固定資産税を差し引いた手残りはおおむね200万円。さらに建物価格6,000万円に対して年間200万円の減価償却費を計上できるため、課税所得を大幅に圧縮しています。
国税庁の「路線価図」に基づくと、Cさんの土地評価額は購入時よりも2%上昇しており、相続財産としての安全性も確保できています。また、木造アパートは法定耐用年数が22年と短いため、帳簿価額の減少スピードが速く、将来的な売却時に譲渡所得を抑えられる点も見逃せません。
Cさんは管理を外部委託し、月1回のオンライン報告で状況を把握するだけに留めています。医業に専念しながら資産形成と相続対策を同時に進められていることが、精神的なゆとりにつながっていると語っています。
40代投資家が押さえるべき資金計画
重要なのは、返済期間を短縮し過ぎず、適度なキャッシュフローを確保してライフイベントに備えることです。金融庁「家計の金融行動に関する世論調査」によると、40代は平均貯蓄額が約650万円ですが、教育費ピークに備えて流動性資金を厚めに保有する世帯が多いことがわかります。
そこで、自己資金は物件価格の20〜30%を目安にし、残りを長期ローンで調達するバランスが無理のない戦略になります。金利タイプは変動と固定のミックスも検討し、金利上昇局面に備えて返済比率を家計収入の30%以内に抑えると安心です。
また、空室や修繕費に対応するため、家賃収入の20%相当を毎月別口座に積み立てる仕組みを作ると、突発的な支出に慌てることがありません。例えば月家賃が20万円なら、4万円を自動振替で積み立て、残りを返済と生活費に振り向けるイメージです。
最後に、2025年度の所得税法では、不動産所得が赤字の場合でも給与所得との損益通算は引き続き認められています。ただし、過度な節税目的の過大借入れは税務調査で否認される可能性があるため、純粋な投資採算性を最優先に判断する姿勢が欠かせません。
まとめ
ここまで見てきたように、40代の不動産投資は信用力、経験値、税務メリットという三つの強みを生かせば十分に成功が狙えます。共働き夫婦の堅実運用、転勤経験を武器にした地方戦略、相続対策を兼ねた一棟投資など、ライフスタイルに合った手法を選ぶことが鍵です。返済期間とキャッシュフローのバランスを取りつつ、空室リスクや金利変動に備えた資金計画を立てれば、老後の収入源と資産形成を同時に実現できます。まずは自身の家計を棚卸しし、無理のない自己資金割合を設定したうえで、信頼できる金融機関や管理会社に相談してみてください。確かな一歩を踏み出せば、10年後の安心感は大きく変わります。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅市場動向調査 2024年度版 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 2025年版 – https://www.soumu.go.jp
- 住宅金融支援機構 住宅ローン利用者実態調査 2025年度 – https://www.jhf.go.jp
- 金融庁 家計の金融行動に関する世論調査 2024年 – https://www.fsa.go.jp
- 国税庁 路線価図・統計情報 2025年 – https://www.nta.go.jp

