REITに興味はあるけれど、実際にどこで買えば良いのか決め切れずに時間だけが過ぎていませんか。ネットで検索しても証券会社や銀行の宣伝が並び、比較基準がはっきりしないと感じる人は多いです。そこで本記事では、2025年9月時点で利用できる代表的な購入窓口を整理し、手数料やサービスの違いを具体的に解説します。読み終えるころには「REIT おすすめ どこで」という疑問に対し、自分に合った答えを持てるはずです。
REITの基本と魅力をおさらい
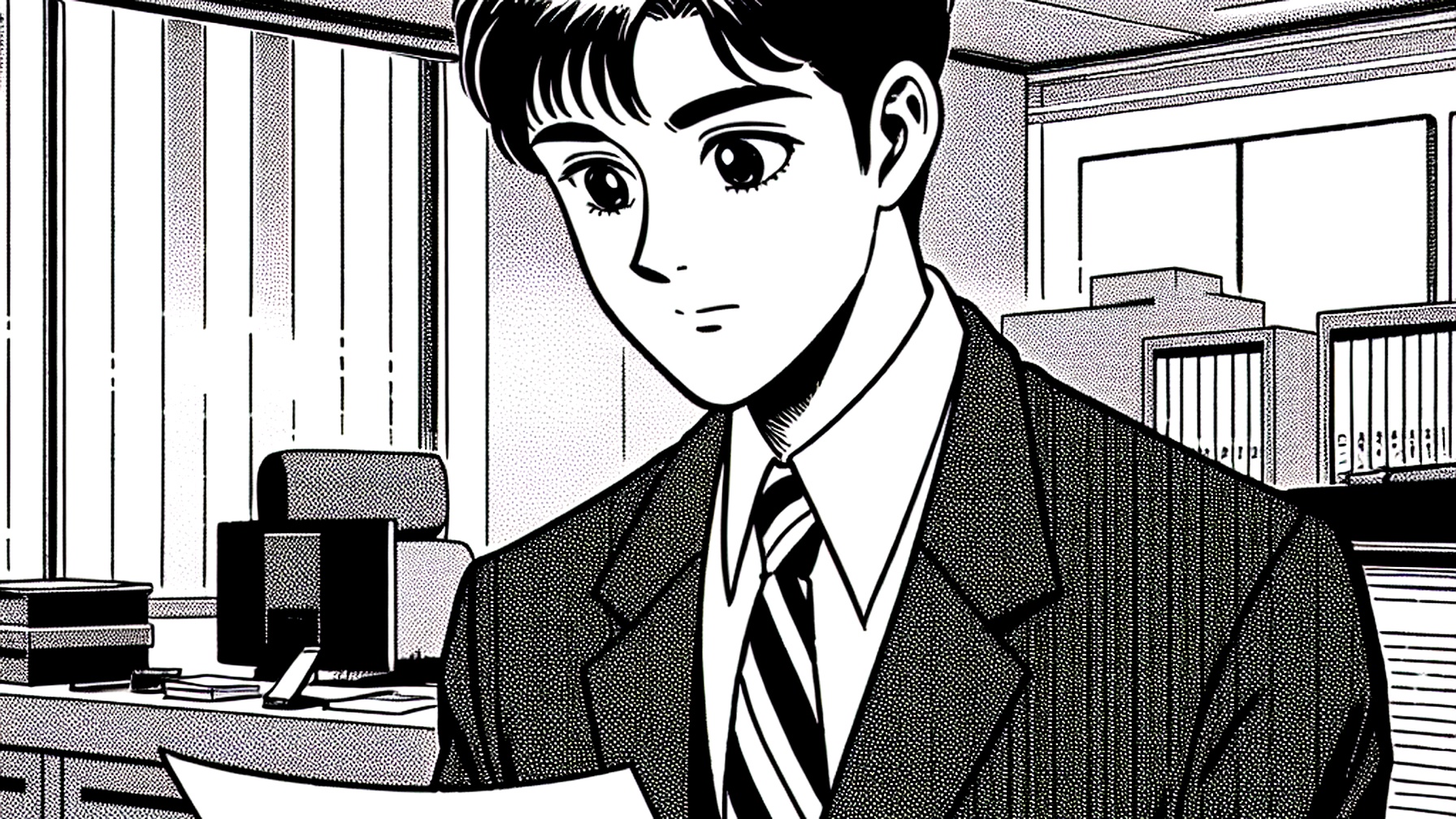
まず押さえておきたいのは、REITが不動産を小口化した金融商品であり、分配金と値上がり益の両方を狙える点です。東京証券取引所の統計によると、2024年度のJ-REIT平均分配利回りは3.8%前後で推移しました。これは上場株式の平均配当利回りをやや上回る水準です。
実は、REITにはオフィス型や物流倉庫型など複数のタイプがあり、物件用途によって収益構造が異なります。オフィス型は景気の影響を受けやすい一方で、物流型はEC需要の拡大により比較的安定した賃料収入を得ています。つまり、自分がどの経済分野に期待するかを考えながら商品を選ぶことが重要です。
さらに、J-REITは法律上、利益の90%以上を分配すれば法人税が実質的に免除されます。この仕組みが高い分配利回りを支えるため、債券と株式の中間的な資産としてポートフォリオの分散に役立ちます。加えて、1口あたり数万円で投資できる点も初心者にとって参入障壁が低いと言えるでしょう。
購入場所で変わる三つのコスト
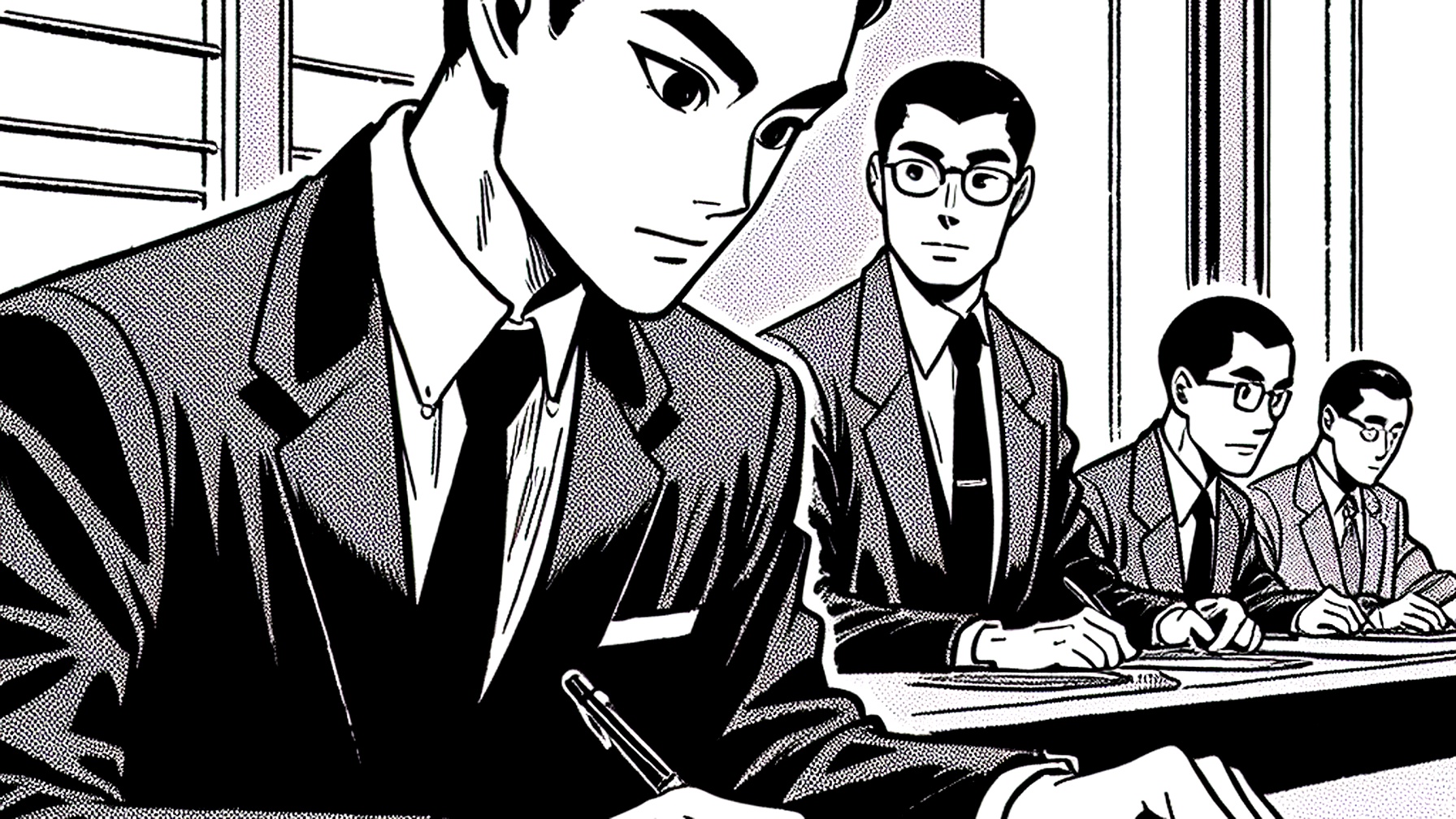
ポイントは、同じREITでも購入窓口によって①売買手数料②信託報酬③税負担の三つのコストが変わることです。まず売買手数料はネット証券が圧倒的に低く、2025年9月時点で大手三社の現物株手数料は一取引あたり99円から0円まで下がっています。一方、銀行窓口では0.5%前後の手数料が一般的で、数十万円の取引でも数千円の差が生じます。
次に、信託報酬は商品そのものに内包された運用管理費であり、購入窓口では変わりません。しかし、同じタイプのREIT型ETF(上場投資信託)と比べると、個別REITのほうが経費率が高いケースがあります。したがって、インデックス型ETFを組み合わせて低コスト化する選択肢も検討価値があります。
最後に税負担です。REITの分配金と譲渡益には20.315%の税率が課されますが、2024年に拡充された新しいNISA制度を利用すれば年間360万円まで非課税投資枠が確保できます。これを使うかどうかで実質利回りは大きく変わるため、購入窓口と同時に口座区分を決めることが大切です。
ネット証券を選ぶメリットと注意点
重要なのは、低コストと情報量の多さがネット証券の最大の強みだという点です。取引手数料がほぼゼロになったことで、分配金利回りをそのまま享受できる環境が整いました。また、スマートフォンアプリでリアルタイムに価格と分配予定を確認できるため、忙しい会社員でも機動的な運用が可能です。
しかし、サービスが自己完結型であるため、銘柄選定からリバランスまで自分で判断する必要があります。使い方を誤ると情報過多に陥り、短期の値動きに振り回されるリスクも増えます。そこで、まずは月次レポートや決算短信の読み方を学び、利回りだけでなくLTV(負債比率)や稼働率といった指標をチェックする習慣をつけましょう。
さらに、2025年度から東京証券取引所が開始した「グリーンREIT指標」は、環境性能の高い物件に着目した新しい比較軸です。ネット証券の多くはこの指標に連動するスクリーニング機能を提供しているため、ESG投資に関心がある人は活用する価値があります。
銀行窓口・対面サービスの使いどころ
一方で、対面サービスにはコンサルティングを受けられる安心感があります。特に高齢の投資家や資産規模が大きい人は、相続対策や不動産そのものの売却予定と絡めて相談できるため、銀行窓口を選ぶ意義があります。
また、地方銀行や信託銀行は独自の私募REITを扱うことがあり、公募REITにはない物件情報を得られる場合があります。私募REITは証券取引所に上場していない分、流動性は劣りますが、分配金利回りが安定しやすい点が特徴です。担当者とリスクを共有しながら長期保有を前提にするなら検討余地があります。
ただし、手数料はネット証券より高めであり、営業トークが商品の良い面を強調しがちなのも事実です。契約前に目論見書を持ち帰り、運用報告書の実績を自分で確認する姿勢が欠かせません。対面を生かすには、相談と比較を繰り返す時間的コストを許容できるかが分かれ目になります。
2025年NISAで広がる非課税メリット
まず押さえておきたいのは、2024年に恒久化された新NISAがREIT投資と相性抜群だという点です。成長投資枠の年間240万円とつみたて投資枠120万円を合わせ、最大360万円まで非課税で保有できます。これは年間3.8%の利回りなら、分配金ベースでおおよそ13万6千円の税負担がゼロになる計算です。
さらに、非課税期間が無期限になったことで、分配金を再投資しやすくなりました。分配金を自動的に買付余力へ回す「配当再投資サービス」を提供するネット証券を選べば、複利効果を最大限に生かせます。一方で、非課税枠は再利用できないため、銘柄入れ替えの頻度は慎重に考える必要があります。
2025年度税制改正大綱によると、NISA口座内でREITを保有した場合でも、借入を行う等のレバレッジ型ETFは対象外になる可能性が示唆されています。したがって、伝統的なJ-REITや市場全体に分散したETFを中心に組むと制度の恩恵を確実に享受できます。
まとめ
ここまで、REITを買う場所ごとのコストとサービスの違いを整理しました。低コストと情報量を重視するならネット証券が最有力ですが、対面での相談や私募REITを求める場合は銀行窓口も選択肢になります。さらに、2025年の新NISAを活用すれば、分配金の税負担を抑えながら長期の資産形成が可能です。自分の投資スタイルと時間の使い方を見極めたうえで、最適な窓口と銘柄を選びましょう。今日から一歩踏み出すことで、ゆとりある将来設計に近づけます。
参考文献・出典
- 金融庁 NISA特設ページ – https://www.fsa.go.jp/policy/nisa/
- 東京証券取引所 J-REIT市場データ – https://www.jpx.co.jp/
- 一般社団法人投資信託協会 REITレポート – https://www.toushin.or.jp/
- 国土交通省 不動産市場動向調査 2025年5月版 – https://www.mlit.go.jp/
- 日本銀行 金融システムレポート 2025年4月 – https://www.boj.or.jp/

