不動産投資で事務所物件を購入しようとすると、「銀行はいくらまで貸してくれるのか」「居住用とは何が違うのか」といった疑問が次々に浮かびます。自己資金をどれだけ用意すべきか、返済計画は成り立つのかを判断するには、借入限度額の仕組みを理解することが欠かせません。本記事では、不動産投資ローン 事務所 借入限度額の決まり方を基礎から解説し、2025年9月時点の金利水準や審査基準を踏まえた実践的な対策までまとめます。読後には、ご自身の資金計画を具体的な数字で描けるようになるはずです。
不動産投資ローンの基本を押さえる
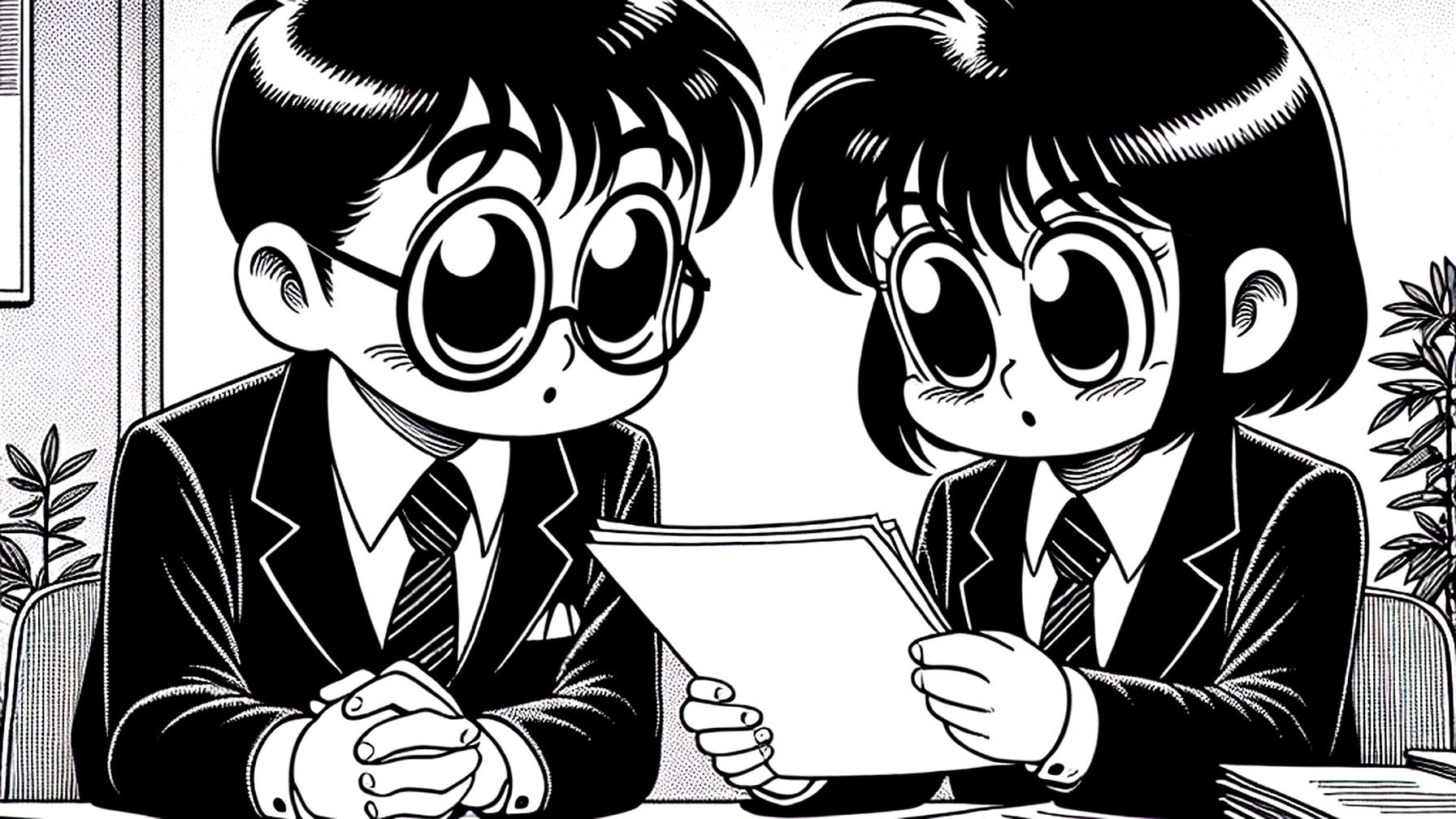
まず押さえておきたいのは、不動産投資ローンがそもそも事業性融資であるという点です。自宅を買う住宅ローンと異なり、返済原資は家賃収入と物件売却益に依存します。そのため金融機関は、個人属性だけでなく物件の収益力と将来性を厳しく精査します。
金融庁のガイドラインによると、投資ローンの審査ではLTV(ローン・トゥ・バリュー)とDSCR(デット・サービス・カバレッジ・レシオ)が重視されます。LTVは「物件評価額に対して何%借りるか」を示し、一般に70〜80%が目安です。DSCRは「家賃収入が元利返済の何倍あるか」を示し、多くの銀行は1.2倍以上を安全圏に設定します。つまり表面利回りが高くても、空室リスクや修繕費を差し引いた実質利回りが低いと、借入限度額は抑えられます。
2025年9月現在、主要行の変動金利は1.5〜2.0%、10年固定は2.5〜3.0%が一般的です(全国銀行協会)。金利が1%上がると月々の返済額はおおむね10〜12%増えます。したがって借入限度額を算定する際は、「想定金利+1%」でストレステストを行い、余裕を持った資金計画を立てることが肝心です。
事務所物件ならではの審査ポイント
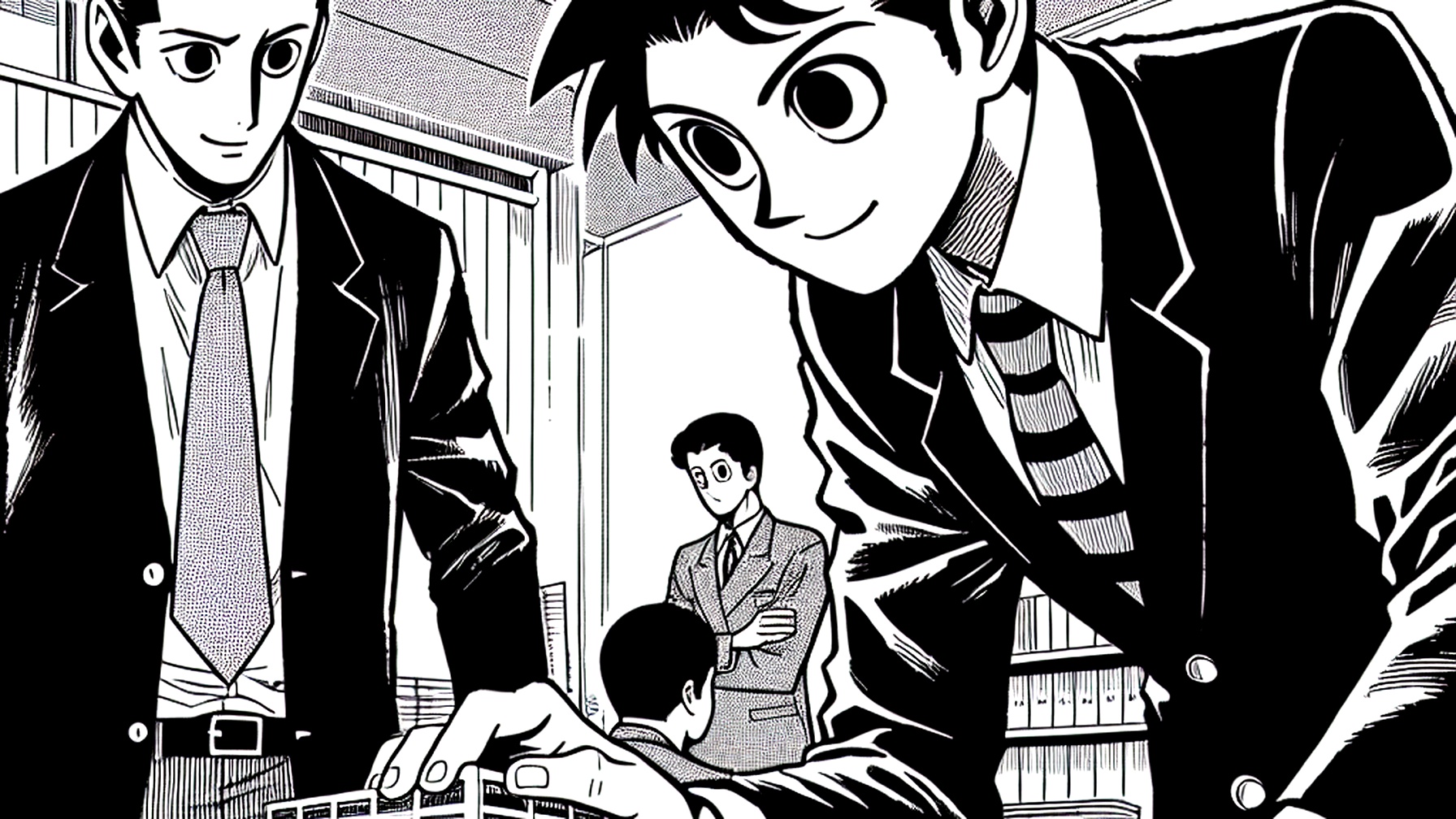
次に、事務所物件特有の評価項目を見ていきましょう。事務所用途は住居に比べてテナントの入れ替わりが激しく、収益の安定性が読みづらいと認識されています。この特徴が、直接的に借入限度額を押し下げる要因になるのです。
具体的には、金融機関は「平均空室率」と「契約期間の長さ」に注目します。国土交通省の不動産価格指数(2025年上期)によれば、三大都市圏の中規模オフィスの平均空室率は5.4%で、同地区のファミリー向け賃貸の2.8%より高めです。その差を補うため、銀行は予想家賃を10〜15%低めに見積もり、DSCRを再計算します。その結果、住居用なら80%まで出るLTVが、事務所では70%に制限されるケースが珍しくありません。
さらに、建物の構造と用途地域も重要です。鉄筋コンクリート造(RC造)や耐震補強済みであれば資産価値が下がりにくいため、評価額が高く算定されます。一方、築古で空室率が高い物件は、リノベーション計画やリーシング戦略を示さない限り、借入限度額が厳しく抑えられる傾向があります。
借入限度額を左右する三つの指標
重要なのは、借入限度額が「個人属性」「物件属性」「金融機関の方針」という三つの指標の掛け算で決まる点です。どれか一つが弱いだけで、想定より低い金額しか借りられないことがあります。
まず個人属性では、年収、金融資産、過去の借入実績がチェックされます。日本政策金融公庫の調査(2025年度)によると、自己資金が物件価格の20%を超えると、審査通過率は70%から85%へ上がります。次に物件属性では、立地、築年数、用途制限、維持修繕履歴が評価されます。築20年以内の駅近オフィスは、築30年超の郊外オフィスよりもLTVが最大10ポイント高くなる傾向があります。
最後に金融機関ごとの方針です。同じ属性でも地方銀行は「地元での雇用創出効果」を重視し、都銀は「稼働率の高さ」を重視するなど、評価軸に差があります。つまり複数行を比較し、自身の物件と事業計画にマッチする銀行を選ぶことで、借入限度額を引き上げられる可能性があります。
2025年度の金融環境と活用可能な制度
実は、2025年度は金融環境が穏やかに推移しており、事務所向け融資の裾野も広がりつつあります。日銀の短観(2025年6月調査)では、全国の銀行の貸出態度判断DIが+15と、前年より4ポイント改善しました。つまり融資に前向きな銀行が増えているということです。
また、2025年度税制では「中小企業等経営強化法の即時償却措置」が継続しており、新規耐震改修や高効率空調設備を導入する場合、設備投資額の全額を即時償却できます。これによりキャッシュフローが改善し、金融機関に提示する返済計画に余裕を持たせられます。期限は2026年3月末申請分までなので、適用を検討している投資家は早めに動く必要があります。
一方、補助金や特例措置には申請要件と審査期間があるため、融資実行のタイミングとずれると資金繰りに影響する点には注意が必要です。制度活用を前提に借入限度額を計算する場合は、補助金不採択のシナリオも想定し、自己資金やつなぎ融資でカバーできる体制を整えておくと安心です。
限度額を引き上げるための具体戦略
ポイントは、銀行が重視する情報を先回りして提示し、リスクを低減させることです。第一に有効なのが、詳細な収支シミュレーションの提出です。家賃の想定下落率を年1%、空室率を最大15%といった保守シナリオで試算し、金利上昇2%にも耐えられる旨を示すと、銀行の心証が大きく改善します。
第二に、テナント斡旋会社との専任媒介契約書や、リノベーション工事の見積書を添付する方法があります。これにより「購入直後に稼働率を引き上げる具体策」が証明でき、実質的な家賃保証と同等の効果を生みます。
さらに、複数の金融機関に同時並行で打診する「プロパー交渉」も有効です。競合状況が生まれることで、LTVが5ポイント程度上がったり、金利が0.2%下がる事例も珍しくありません。ただし過度な同時申込みは信用情報に照会履歴が残り、マイナス評価になることもあるため、最大3行程度に絞るのが現実的です。
まとめ
本記事では、不動産投資ローン 事務所 借入限度額の決まり方を、金利動向、審査基準、制度活用、交渉術の四つの視点から整理しました。借入限度額は「個人属性×物件属性×金融機関方針」の掛け合わせで決まるため、一つひとつの要素を底上げする工夫が必要です。まずは保守的な収支計画と十分な自己資金を用意し、複数行にアプローチして最適な融資条件を引き出しましょう。行動を先延ばしにせず、今日から資料作成に着手することが、理想の事務所投資を実現する近道です。
参考文献・出典
- 全国銀行協会 – https://www.zenginkyo.or.jp
- 金融庁「金融検査マニュアル」 – https://www.fsa.go.jp
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 日本政策金融公庫「2025年度中小企業の設備投資動向」 – https://www.jfc.go.jp
- 日本銀行「短観」2025年6月調査 – https://www.boj.or.jp

