老後の生活費が年金だけで足りるか不安だと感じる人は少なくありません。特にインフレや医療費の上昇が続くと、預金を取り崩すペースが想定より早まることがあります。そこで注目されるのが毎月安定した家賃収入を得られる収益物件です。しかし、物件価格や利回りだけで飛びつくと、返済や修繕費で手元資金が枯渇する恐れがあります。本記事では「収益物件 老後資金 収支計算」という三つの視点から、初心者でも再現しやすい手順を解説します。読み終えたときには、具体的なキャッシュフロー表の作成方法と2025年度の税制を踏まえた資金計画の立て方がイメージできるでしょう。
老後資金を左右するキャッシュフローの考え方
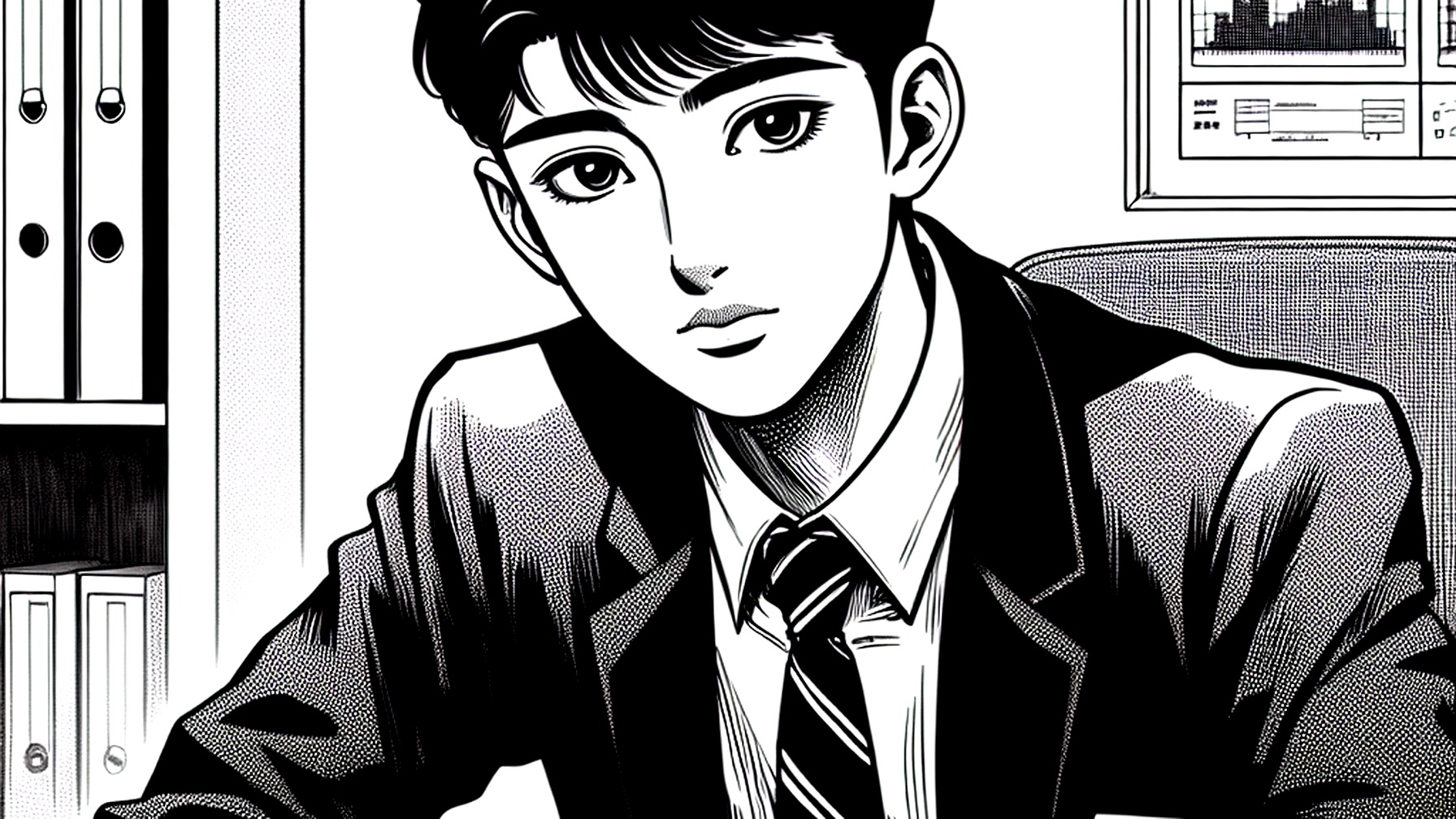
重要なのは、収益物件から得られる家賃が実際に自由に使えるお金になるまでに、どれだけ費用が差し引かれるかを明確にすることです。総務省「家計調査」では、高齢夫婦の平均消費支出は月約28万円とされています。仮に年金で22万円受給できても月6万円の不足が生じます。つまり、少なくとも月6万円の正味キャッシュフローを安定的に生む物件を保有できれば、老後資金のギャップを埋められる計算です。
まず家賃収入から管理費、修繕積立、固定資産税、空室損を差し引き、さらにローン返済額を引いて「手取りキャッシュフロー」を求めます。この手取りがプラス6万円を上回るかどうかが、老後資金計画の出発点となります。一方で、築年が古い物件は取得価格が抑えられる反面、修繕費や空室リスクが高くなるため、手取り額が大きく変動します。
また、日本銀行が公表する2025年6月時点の住宅ローン平均金利は変動型で1.1%程度です。しかし将来の金利上昇を1%織り込む保守的なシナリオを用意しておくと、老後に突発的な支出が生じても慌てずに済みます。
収益物件選びで失敗しないための収支計算
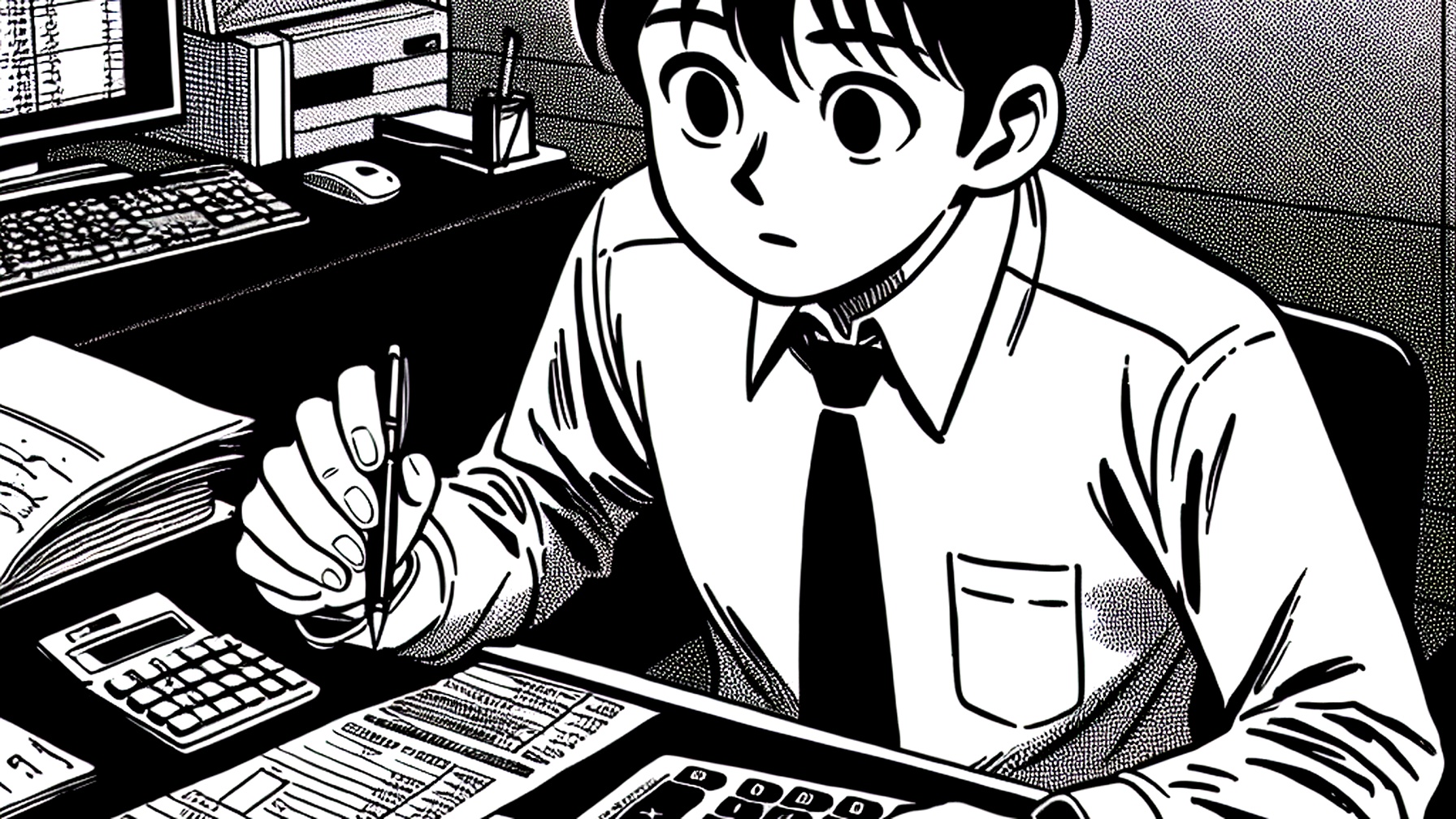
ポイントは、表面利回りではなく実質利回りを基準に比較することです。実質利回りは「年間手取りキャッシュフロー÷物件価格」で算出し、管理費などの運営コストを含めます。都心ワンルームの場合、表面利回り4.5%でも実質3%に下がる例が珍しくありません。
次に、ローンを含めた自己資金割合を決めます。金融機関の融資姿勢は2025年現在、居住用区分マンションなら80%融資が一般的です。自己資金20%に諸費用7%を加えると、購入時に物件価格の27%が現金で必要になります。例えば3,000万円の物件なら810万円を準備する計算です。
さらに、空室率の設定が甘いと収支は簡単に崩れます。国土交通省「住宅市場動向調査」によると、東京都心区分マンションの平均空室率は6%ですが、郊外は12%を超えます。想定家賃を月8万円、空室率12%で計算すると年間家賃は約84万円になり、空室率6%の約90万円より6万円下振れします。この差がそのまま手取りを圧迫するため、立地と物件種別に応じた空室率設定が欠かせません。
最後に、ローン返済比率が家賃収入の50%を超えると、金利上昇や修繕費増加時にキャッシュフローが赤字に転落しやすい傾向があります。返済比率40%以下に抑えると、予備費を確保しながら安定運営が期待できます。
具体的なシミュレーション方法
実は、収支計算を表計算ソフトで作るときは「三つのシート」を分けておくと可視化しやすくなります。第一シートに購入時のイニシャルコスト、第二シートに年間運営コスト、第三シートにローン返済と税引き後キャッシュフローをまとめる、といった形です。
ここでは、築10年・価格2,500万円・家賃7.5万円の区分マンションを例にします。自己資金30%とし、金利1.2%、期間25年で試算すると、月返済額は約8.4万円です。家賃より返済が大きいように見えますが、減価償却費による節税効果を含めると税引き後キャッシュフローはプラス1.1万円となります。
空室1カ月を見込むと年間家賃は90万円から82.5万円に減少します。この場合でもキャッシュフローはプラス2.5万円で済むかどうかを再計算し、厳しい条件に耐えられるか確認します。さらに、金利2.2%への上昇シナリオを加えると返済額は約9.5万円に増えます。ここまで織り込んでなお年間トータルで黒字なら、老後資金として心強い支えになります。
なお、一般的に認知されているiDeCoやNISAのような投資枠と異なり、不動産の収支は現金フローで可視化できるため、複利計算の前提が不要です。したがって、毎年の収支計算を更新し、将来資金の不足額を早期に察知できるメリットがあります。
2025年度税制を踏まえた資金計画
まず押さえておきたいのは、賃貸用区分マンションの減価償却期間が47年、築10年物件なら残存37年で計算される点です。この期間内は毎年一定額を経費計上でき、所得税と住民税が軽減されます。国税庁の試算では、年収700万円の給与所得者が200万円の減価償却を活用すると、年間約54万円の税負担が減るケースがあります。
また、2025年度も引き続き「住宅借入金等特別控除」は自己居住用に限定されるため、収益物件には適用されません。一方で、所得税の損益通算は今のところ制限を受けていないため、本業の給与所得と赤字が相殺できる余地があります。ただし、赤字計上が長期化すると金融機関の評価が下がり次の融資が難しくなるため、あくまで短期的な資金繰り対策ととらえましょう。
さらに、相続税対策としても賃貸マンションは有効です。総務省「令和6年(2024年)路線価」では、更地評価より賃貸中評価が約30%低下する地域が多いと示されています。2025年9月時点でもこの評価減は有効であり、将来の相続を見据えて物件を持つ選択肢は依然として魅力的です。
注意すべきは、2025年度税制改正大綱で示された「広大地評価の見直し」が予定どおり実施されると、土地の相続税計算が変動する可能性がある点です。大規模土地を含む物件を検討する場合は、税理士と連携して個別試算を行いましょう。
まとめ
ここまで「収益物件 老後資金 収支計算」を軸に、キャッシュフローの構造、物件選び、シミュレーションの手順、2025年度税制のポイントを整理しました。手取りキャッシュフローが老後の不足額を補えるかを基準に物件を選び、空室や金利上昇を織り込んだ収支計算を継続的に更新することが成功の鍵です。これから投資を始める方は、まず家計の不足額を明確にし、保守的なシナリオでも黒字化できる物件に的を絞りましょう。行動に移すことで、老後資金への不安は着実に小さくなります。
参考文献・出典
- 総務省統計局「家計調査」2025年版 – https://www.stat.go.jp/data/kakei/
- 国土交通省「住宅市場動向調査」2024年度 – https://www.mlit.go.jp
- 日本銀行「主要金融指標 住宅ローン金利」2025年6月 – https://www.boj.or.jp
- 国税庁「所得税法令集 減価償却資産の耐用年数表」2025年度 – https://www.nta.go.jp
- 総務省「令和6年(2024年)路線価」 – https://www.rosenka.nta.go.jp

