アパート経営に興味はあるものの、「本当に年収700万円を達成できるのか」と不安を抱く方は多いはずです。物件価格の高騰や空室率の上昇が報じられると、初心者ほど一歩を踏み出しにくくなります。しかし、収益構造を理解し、数字に基づく戦略を立てれば、今からでも安定したキャッシュフローを作ることは十分可能です。本記事では、アパート経営で年収700万を目指すうえで欠かせない収益性の考え方、資金計画、物件選定、リスク管理、そして2025年度の制度活用までを順を追って解説します。読み終えるころには、具体的に動き出すための指針が見えてくるでしょう。
アパート経営で年収700万円を実現する仕組み
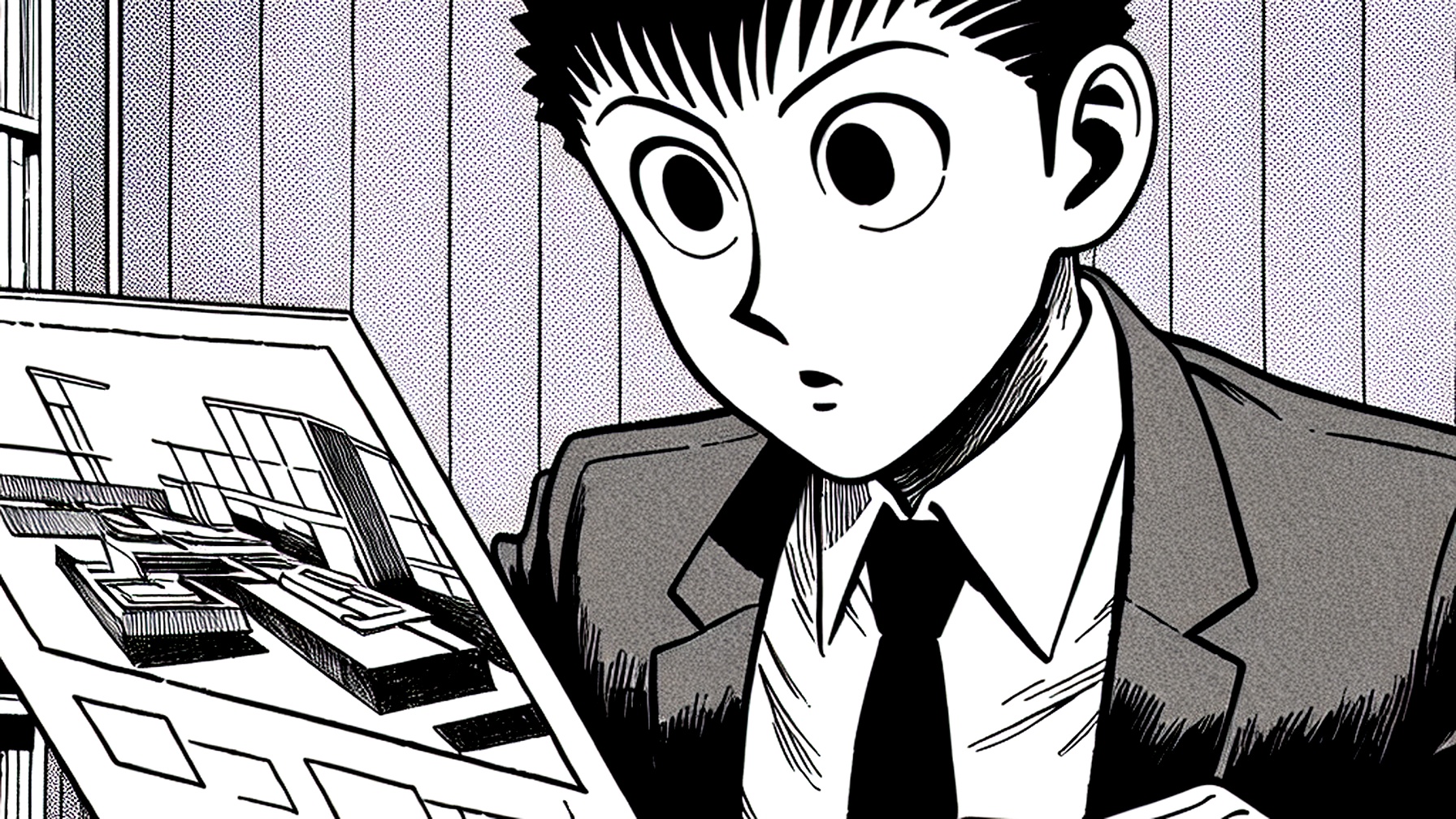
ポイントは、家賃収入から経費と返済を引いた後の純利益を年700万円に乗せる計算を先に固めることです。ここで大切なのは、表面利回りではなく、実際に手元へ残る実質利回りを意識する姿勢になります。
まず家賃設定ですが、首都圏ワンルームなら月7万円前後が平均的です。仮に10戸を運営すれば年間家賃収入は840万円となります。ここから管理費、修繕費、固定資産税、空室損、ローン返済を差し引くと、残りはおよそ年300〜400万円になるケースが一般的です。つまり家賃単価を上げるか、戸数を増やすか、経費を圧縮しない限り700万円には届きません。
一方で、ファミリー向け2LDKを6戸そろえ、月11万円で満室運営できれば年間家賃収入は792万円です。設備更新を含めた支出を月30%以内に抑え、金利2.0%程度の融資を活用すれば、年間手残りは約550万円まで伸びます。このように物件タイプと経費率の組み合わせで収益性は大きく変わるため、最初の計算段階が勝負となります。
重要なのは、単純に家賃を上げるのではなく、入居者が納得する付加価値を用意することです。高速インターネットやIoT設備を標準装備にすると、家賃単価を維持しながら長期入居を促せます。長期入居は空室損を下げ、結果として年収700万円の実現を現実的なものにします。
必要な自己資金と融資戦略

まず押さえておきたいのは、自己資金を2割確保すると融資条件が大幅に良くなるという事実です。住宅金融支援機構のデータによると、自己資金比率20%超の投資家は、平均金利が0.6ポイント低い結果が示されています。
自己資金を1,500万円、物件価格7,500万円と仮定すると、融資額は6,000万円です。変動金利2.3%、期間25年で試算すると、年間返済額はおよそ310万円になります。ここに管理費や修繕費を加え、支出合計が家賃収入の70%以内に収まれば、年収700万円の目標が見えてきます。自己資金を厚くするほど返済負担が軽くなるため、目標達成までの期間短縮にもつながります。
また、地方銀行や信用金庫は2025年に入り、不動産投資向け融資を選別する姿勢を強めています。物件の収益力と個人の属性をセットで審査する傾向が高まり、サブリース頼みの計画は評価されにくい状況です。したがって、収支シミュレーションを金融機関に示す際は、空室率15%・金利上昇1%など保守的な前提を入れ、耐性の高さをアピールすることが効果的です。
さらに、法人設立による融資枠の拡大も検討に値します。法人であれば減価償却費をコントロールしやすく、所得税の累進課税を回避しつつキャッシュを手元に残せます。ただし設立・維持コストが生じるため、総戸数10戸以上を保有する規模になった時点での移行が目安と考えましょう。
収益性を高める物件選びと運営
重要なのは、立地と入居ニーズが噛み合う物件を選び、さらに運営面で付加価値を乗せることです。国土交通省土地総合情報システムでは、駅徒歩10分以内の物件は、徒歩15分超と比べ家賃単価が約17%高いと報告されています。
駅近物件は取得価格も高いものの、空室リスクが低く賃料下落も緩やかです。結果として、実質利回りが郊外物件を上回るケースは珍しくありません。近年は郊外でもバス便が充実し、テレワークが普及したことで、郊外立地でもニーズが復活しているエリアがあります。しかし、人口減少が進む地方都市では需給バランスが崩れやすいため、賃貸需要の定点観測が欠かせません。
運営面では、退去時の原状回復を最小限にする素材選びが利益を押し上げます。フロアタイルや全室同一クロスを採用すれば在庫を共通化でき、単価を抑えながら工期も短縮できます。さらに、スマートロックや宅配ボックスを導入すると、若年層だけでなくシニア層からも支持を得やすく、募集期間の短縮に直結します。
家賃アップ施策として、ペット共生・楽器可といった差別化も有効です。規約整備や防音対策には費用がかかりますが、競合物件が少ない分、長期入居につながりやすいメリットがあります。維持管理まで含めたトータルプランを描くことで、単年ではなく長期での収益最大化が狙えます。
空室率21.2%時代のリスク管理
実は空室対策こそ、年収700万円の可否を左右する最大の要素です。2025年7月の全国アパート空室率は21.2%で、前年より0.3ポイント改善したものの高水準が続きます。空室が長期化すると家賃収入が途絶え、経営は一気に苦しくなります。
第一に、マーケティング視点で募集条件を見直します。家賃の下げ幅を5%以内に抑えつつ、敷金ゼロや短期違約金設定で入居ハードルを下げる方法が有効です。初期費用を抑えた分、退去時に補填できる仕組みを組み込めば、手残りを大きく損なわずに成約率を高められます。
第二に、管理会社との情報共有を密にし、内見から申込への転換率を週次で確認します。成約まで平均二週間を超えるようなら、写真の質や内装の色味を変える意思決定を早めます。2025年はSNS経由で物件検索を行う入居希望者が4割を超えたという総務省の調査もあり、オンライン内見動画のクオリティが募集成績を左右します。
最後に、長期的なリスクとして、エリア人口の中期予測を常にチェックしましょう。市区町村の人口ビジョンや再開発計画を確認し、賃貸需要が縮小すると判断すれば、早期の売却や用途変更を検討する勇気も必要です。損失を小さく抑える撤退戦略は、攻めの投資と同じくらい重要な経営判断といえます。
2025年度の税制と補助制度を賢く使う
基本的に、賃貸住宅の減価償却制度は2025年度も大きな変更はなく、木造アパートなら法定耐用年数22年で計上します。築古物件を取得した場合は、残存耐用年数を短縮できる特例を活用し、初年度の経費を厚くすることでキャッシュを確保できます。
2025年度は、中小企業向けの省エネ投資促進税制が継続しており、高効率給湯器や断熱改修に投資した額の10%を税額控除できます。アパート経営法人でも適用可能なため、設備更新を検討する際は必ず試算しておきたいところです。期限は2026年3月取得分までと定められています。
さらに、住宅セーフティネット法に基づく登録住宅は自治体から改修補助を受けられる場合があります。所得が低い入居者へ安心して貸し出せる仕組みを整えることで、家賃保証付きの入居需要を取り込める利点があります。自治体ごとに補助額や募集条件が異なるため、着手前に窓口で最新要項を確認してください。
一方で、終了済みのグリーン住宅ポイントや家賃支援給付金は2025年時点で利用できません。制度名を鵜呑みにせず、有効期限と対象経費を必ず確認し、確実に使える施策だけを織り込む姿勢が安全です。
まとめ
ここまで、アパート経営で年収700万を達成するための収益構造、資金計画、物件選び、空室対策、税制活用について一気に見てきました。重要なのは、家賃収入から逆算して収支シミュレーションを作り、保守的な前提で耐性を確かめるプロセスを怠らないことです。さらに、入居者目線で価値を高める工夫と、走りながら制度や市場の変化に合わせて軌道修正する柔軟さが、長期的な成功を左右します。年収700万円という数字は高い壁に見えますが、今日から準備と行動を積み重ねれば、確かな目標へと変わります。まずは資金計画と物件調査から一歩踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省住宅統計調査 – https://www.mlit.go.jp/
- 総務省統計局「通信利用動向調査」 – https://www.stat.go.jp/
- 日本銀行「貸出・資金循環統計」 – https://www.boj.or.jp/
- 国税庁「法人税基本通達」 – https://www.nta.go.jp/
- 住宅金融支援機構「融資利用者調査」 – https://www.jhf.go.jp/

