アパート経営に興味はあるものの、自己資金が少なくて踏み出せない人は少なくありません。とくに「初期費用は数百万円以上必要」という情報を見ると、不安が膨らみますよね。この記事では、初期費用を100万円に抑えても現実的にアパート経営を始める方法を、2025年9月時点の最新情報と筆者の経験を交えて解説します。読み終えたとき、資金を理由にあきらめていたあなたの視界がクリアになるはずです。
アパート経営に必要な初期費用の内訳
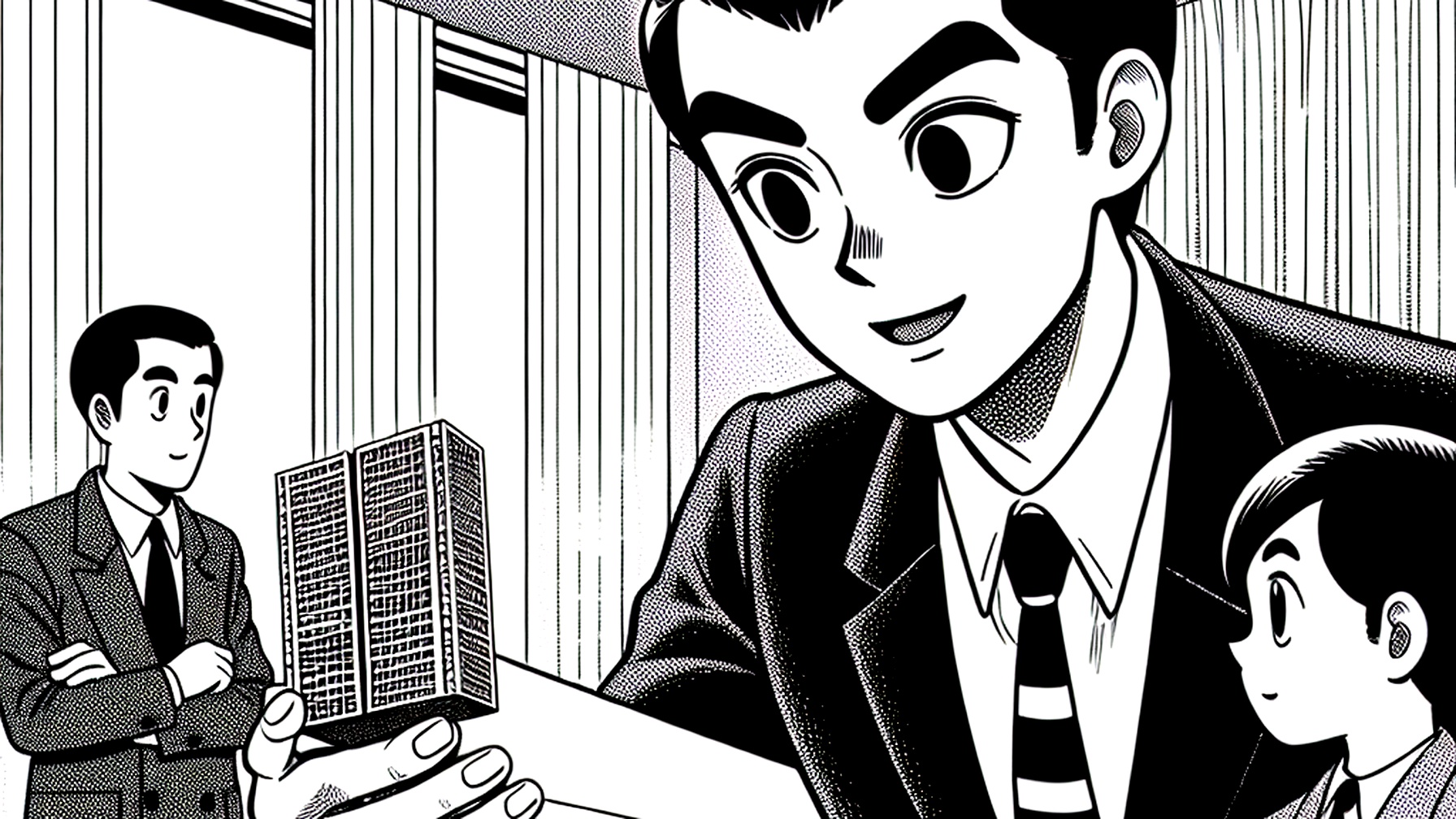
まず押さえておきたいのは、初期費用の中身を細かく分解すると対策が立てやすくなるという点です。大きな金額に見えても、項目ごとに工夫すれば削減できる部分は多くあります。
- 物件取得時の頭金
- 登記費用・司法書士報酬
- 仲介手数料・印紙税
- 火災保険料・鍵交換費などの諸経費
国土交通省の「不動産価格指数」によると、地方の築古アパートは一棟1,500万円前後の案件が増えています。頭金を1割に抑えられれば150万円で済みますが、さらに交渉で売買価格を5%下げられれば、頭金は実質100万円弱に。つまり数字だけを見て尻込みするより、費目ごとのコントロールが重要なのです。
司法書士報酬や仲介手数料は報酬体系が自由化されているため、複数社に見積もりを取って比較すれば1〜2割の差が出ることも珍しくありません。また、火災保険は5年一括より1年更新の方が初年度負担を抑えられるケースがあります。これらを組み合わせると、頭金以外の費用を30万円程度に抑えることも十分可能です。
100万円で始めるための資金調達アイデア
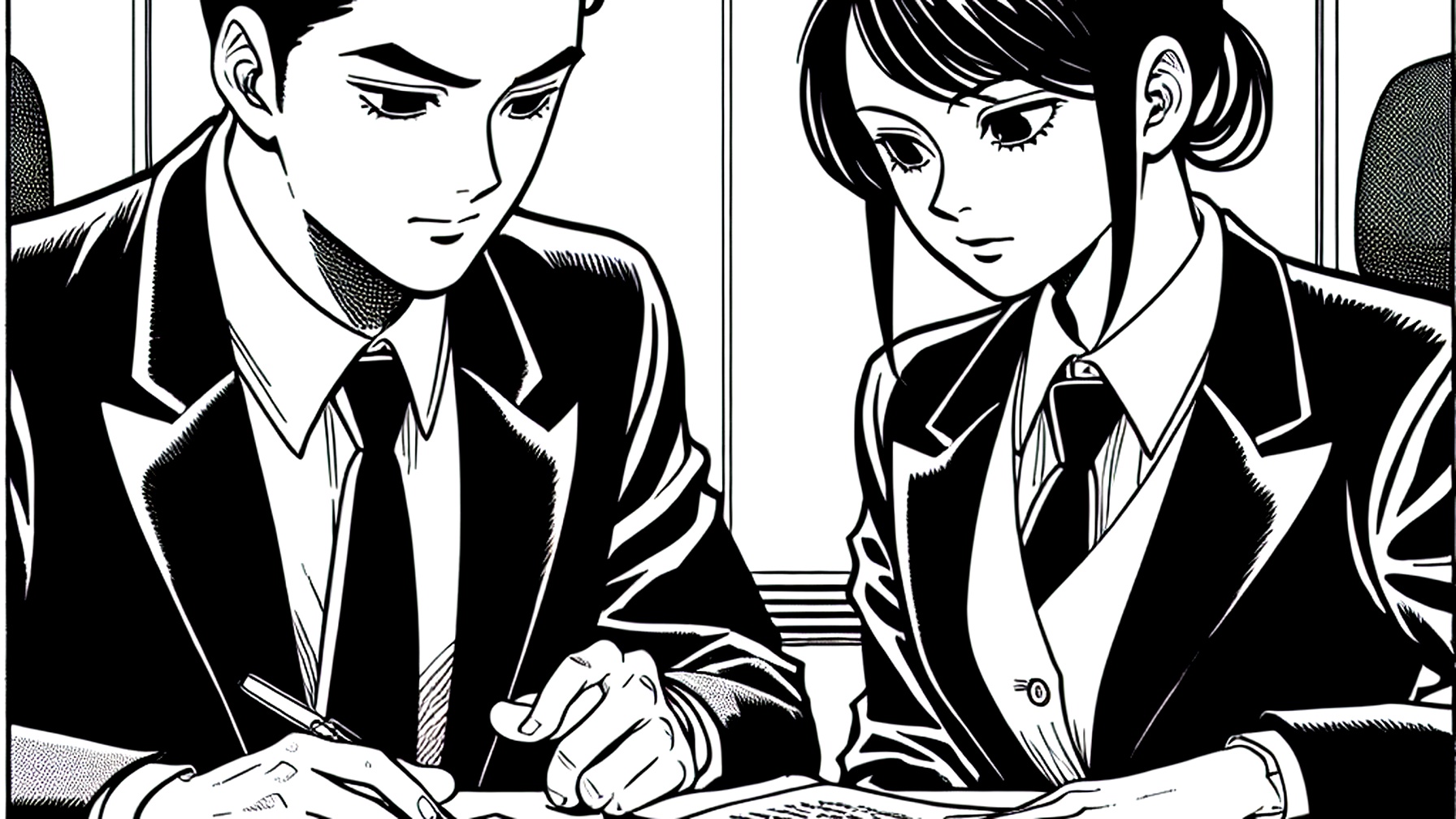
ポイントは、自己資金を単に貯金でまかなう発想にとどまらないことです。金融機関の選び方と交渉次第で、手元資金を最小限に維持したまま融資を引く道が開けます。
日本政策金融公庫の「中小企業経営力強化資金」は2025年度も継続しており、創業枠として自己資金の10%超を用意すれば利用可能です。物件価格1,000万円なら、自己資金100万円で申請ラインに乗る計算になります。公庫は固定金利が低めで、返済期間も最長20年と長いのでキャッシュフローに余裕が生まれやすい点が魅力です。
さらに、地方銀行や信用金庫のアパートローンは「土地評価が高い築古物件」ならLTV(Loan to Value=融資比率)90%を超えるケースもあります。実は、売主が法人であれば「オーナーチェンジ融資」という形で敷金・礼金をそのまま引き継ぎ、諸経費の一部を内部資金で賄えることもあります。こうした交渉を重ねれば、手元100万円でも融資実行にこぎつける可能性は十分にあります。
最後に、家族からの贈与を活用する選択肢も忘れないでください。2025年度の「相続時精算課税制度」は2,500万円まで非課税であり、将来の相続対策として利用すれば贈与者・受贈者双方にメリットがあります。
低コスト物件の選び方と注意点
実は、初期費用を抑えるには物件選定の段階でほぼ勝負が決まっています。築年数が古いほど価格は下がりますが、修繕リスクとのバランスを見極める視点が欠かせません。
国土交通省住宅統計によると、2025年7月時点の全国アパート空室率は21.2%で前年比0.3ポイント改善しています。都心近郊の駅徒歩10分圏では15%前後まで低下しており、このエリアを狙えば空室リスクを抑えられます。具体的には、築25年程度の木造アパートを1,000万円前後で仕入れ、リフォームでデザイン性を高める戦略が効果的です。
ただし、建物状況調査(インスペクション)を実施しないまま契約すると後で大規模修繕が発生し、結果的に高くつく恐れがあります。調査費用は5〜8万円ですが、屋根や基礎の劣化を事前に把握できれば交渉材料となり、価格を下げる根拠にもなります。言い換えると、数万円の調査費用が数十万円の値引きにつながることもあるのです。
入居者ニーズに合ったリフォームは投資回収期間を短縮します。例えば、バストイレ別への変更は一戸あたり40万円程度で可能ですが、家賃を月5千円上げられれば約7年で回収でき、その後は純利益に変わります。100万円の初期費用で始める場合でも、物件の伸びしろを見極める視点が不可欠です。
キャッシュフローを黒字に保つ管理術
重要なのは、取得後すぐに安定したキャッシュフローを作ることです。黒字を確保できれば、突発的な修繕費が発生しても経営が傾くリスクを抑えられます。
まず家賃設定は「周辺相場より1割安いスタート」で入居を早期に決め、満室後に設備向上とともに相場水準へ引き上げる方法が有効です。日本レジデンシャル研究所の調査では、満室経営の物件は空室発生率が半分以下に下がり、広告費も年間30%削減できると報告されています。
管理会社の選定も大切です。サブリースは家賃保証が魅力的に映りますが、手残りが1〜2割減る場合があります。自主管理を選ぶなら、入居者対応や設備点検を外部業者に個別委託する「ハイブリッド型」にすることでコストと手間のバランスを取れます。
加えて、減価償却費の計上で課税所得を圧縮し、実質手残りを増やす視点も必要です。木造アパートの法定耐用年数22年に対し、築25年超の物件だと4年で償却できるため、帳簿上の損金を早期に計上できます。税金面でのキャッシュフロー改善策を取り入れると、手元資金の回収スピードが一段と加速します。
2025年度の制度活用でコストを抑える
ポイントは、制度を「使えるかもしれない」ではなく「確実に使えるものだけ」に絞ることです。2025年度に有効な制度を活用すれば、初年度の資金負担をさらに軽くできます。
日本政策金融公庫の「地域活性化・雇用促進資金」は空き家の再生を伴うアパート事業にも利用可能で、通常融資より金利が0.4%低く設定されています。また、国土交通省が継続する「住宅セーフティネット登録住宅改修事業補助金」は、入居者向けのバリアフリー改修費を最大50万円補助する制度です。期限は2026年3月申請分までなので、2025年内に工事計画を立てると確実に間に合います。
なお、太陽光発電を設置する場合は経済産業省の「住宅用ZEH補助金」は対象外ですが、固定価格買取制度(FIT)は2025年度も継続中で、売電収入を家賃以外の収益源として組み込めます。こうした制度を正確に把握し、事業計画に盛り込むことで金融機関からの評価も上がり、融資条件が好転するケースが多いです。
まとめ
ここまで、初期費用を100万円に抑えてアパート経営を始める具体策を解説しました。費目を細分化して無駄を削り、政策金融公庫や地方銀行の高い融資比率を活用すれば、自己資金を最小化できます。築古物件をインスペクションで見極め、リフォームと家賃設定を戦略的に行えば、購入直後からキャッシュフローを黒字化することも可能です。制度活用による金利・改修費の負担軽減も視野に入れましょう。行動を後回しにせず、まずは物件情報を集めながら金融機関と相談を始めることが、100万円スタートを現実にする第一歩です。
参考文献・出典
- 国土交通省住宅統計調査 2025年7月速報値 – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省 不動産価格指数 2025年6月 – https://www.mlit.go.jp
- 日本政策金融公庫 中小企業経営力強化資金 – https://www.jfc.go.jp
- 経済産業省 固定価格買取制度(FIT)ガイドライン 2025年度版 – https://www.meti.go.jp
- 国税庁 法定耐用年数表(令和7年度) – https://www.nta.go.jp

