会社員として働きながら不動産投資に興味を持っても、「忙しくて時間がない」「本当に副収入になるのか」といった不安は尽きません。私も相談を受けるたびに、同じような悩みを共有してきました。本記事では、実際に月給制の会社員が物件を取得し、キャッシュフローを伸ばしていったリアルな成功事例を軸に、2025年9月時点で活用できる制度やリスク対策まで丁寧に解説します。読み終えるころには、自分でも再現できる手順と注意点がイメージできるはずです。
会社員が不動産投資で成功しやすい理由
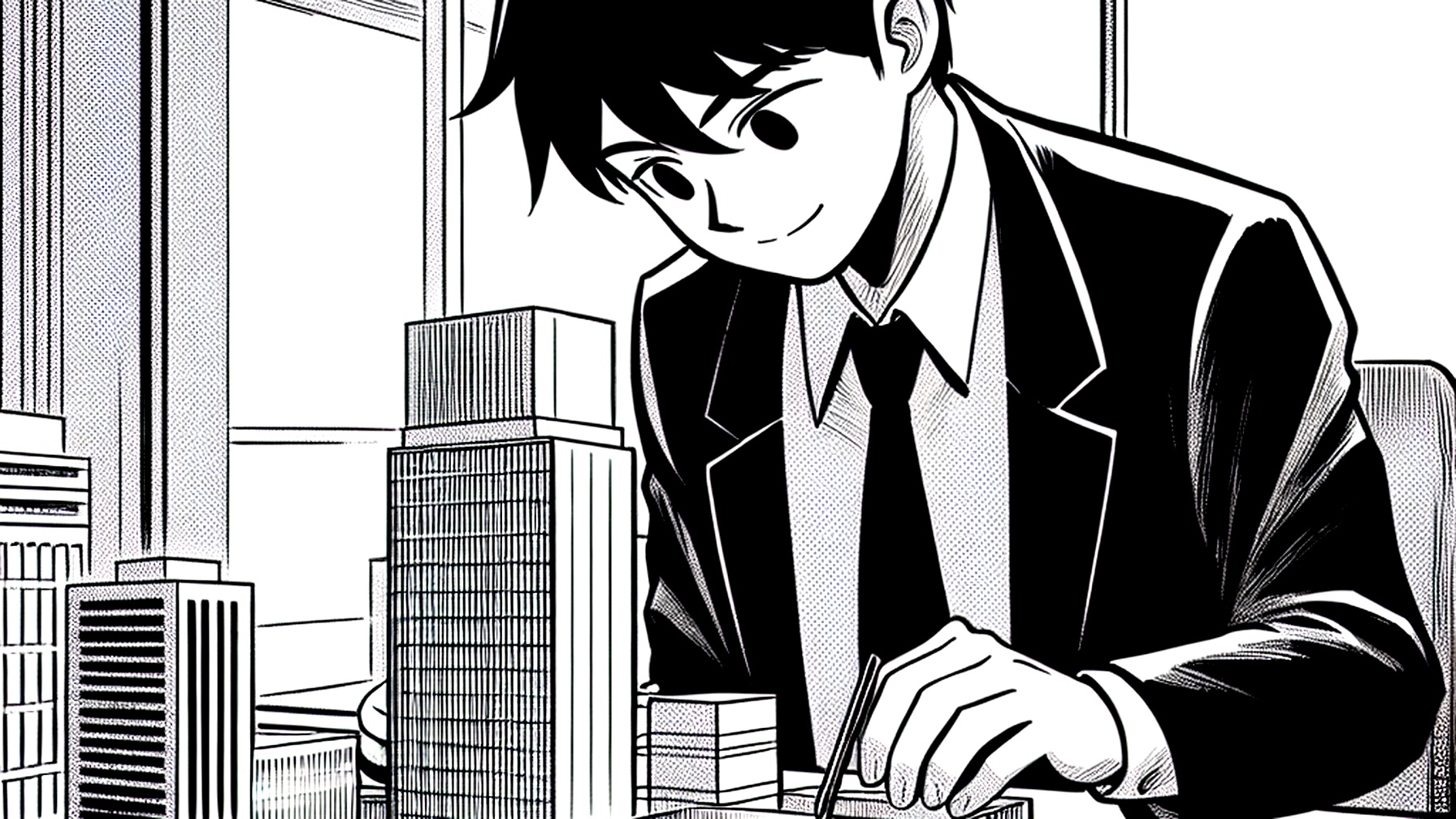
重要なのは、会社員が持つ「安定収入」という強みを最大限に生かすことです。給与所得は金融機関にとって返済能力の客観的な指標になり、融資審査の通過率を押し上げます。
まず、年収400万円前後でも勤続3年以上なら、地元の信用金庫で返済比率35%以内の融資が受けられるケースが多いです。給与振込を同じ金融機関に移すだけで、金利が年0.2%下がった事例もあります。実は、このわずかな差が30年返済なら総支払額を数百万円変えるため、会社員という属性が大きな武器になります。
一方で、安定収入がある安心感からシミュレーションを甘く見積もり、結果的に赤字になる人もいます。つまり、強みを借入だけに頼らず、管理コストや修繕積立まで含めて現実的な計画を立てることが成功の前提となるのです。
キャッシュフローと融資戦略をどう組み立てるか
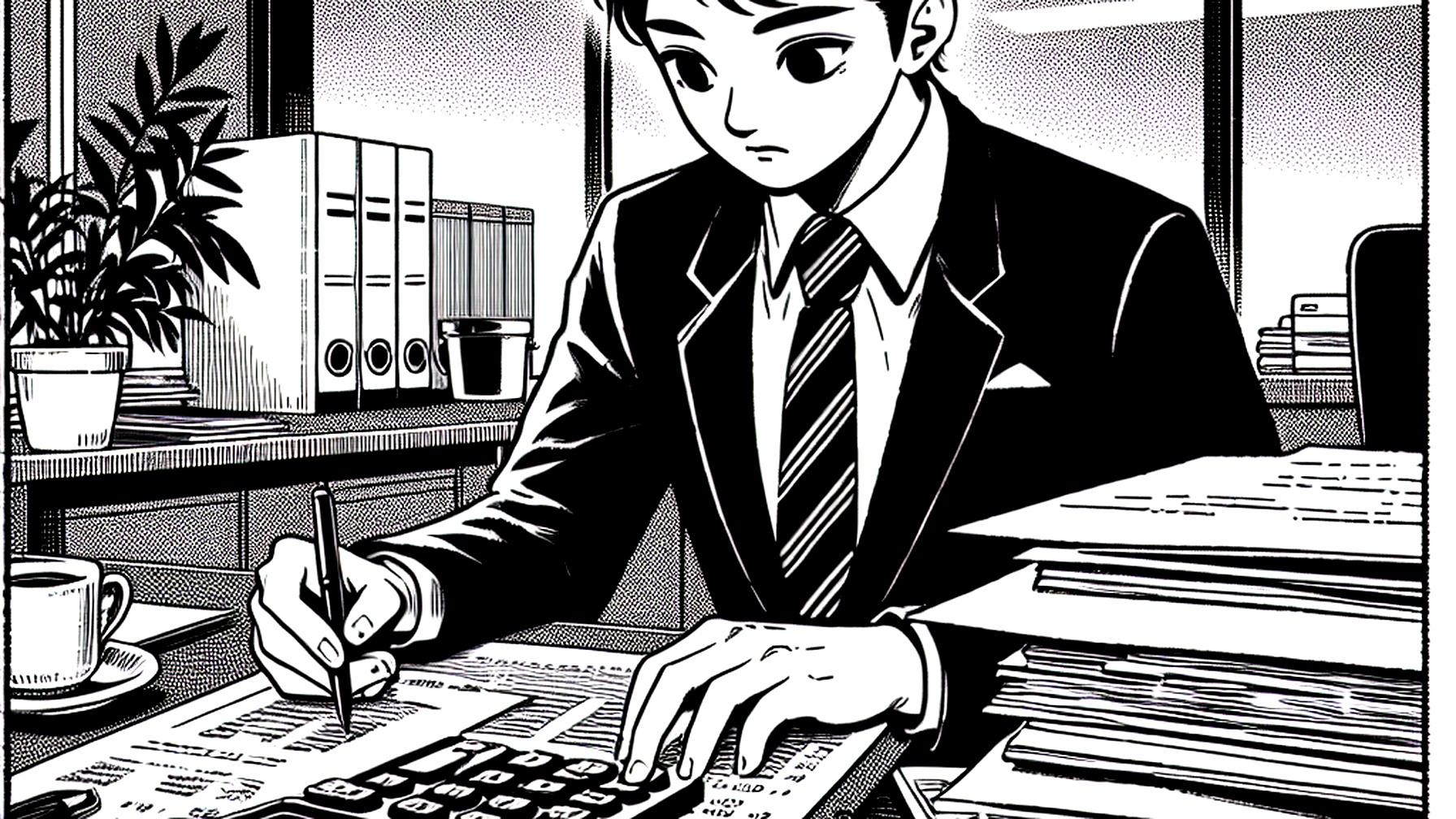
ポイントは、手元に残る現金を最大化しながら、将来の修繕費を先回りして確保する設計です。ここでは年収500万円の営業職Aさんの例を紹介します。
Aさんは自己資金300万円を用意し、築12年の1LDK区分マンション(2,400万円)をフルローンで購入しました。金利は1.7%、期間30年、毎月返済は約8万円です。管理費と修繕積立金が2.2万円、固定資産税月割り8千円、家賃は11.5万円で入居が決まりました。この結果、表面利回りは5.75%ですが、返済後に1.5万円の純キャッシュフローが残ります。
さらに、Aさんは2025年度も継続している「住宅借入金等特別控除(投資用区分は対象外)」に頼らず、青色申告による65万円控除と減価償却を駆使しました。減価償却費が年間50万円超となり、所得税と住民税を合わせて約18万円節税できたことで、実質キャッシュフローは月3万円相当に増えています。こうした二段構えの戦略が、給与一本に依存しない安全網をつくる鍵となります。
物件選びの具体的成功事例
まず押さえておきたいのは、立地と築年数のバランスです。地方都市で利回り10%超を狙うより、首都圏郊外の駅近で利回り5〜7%でも安定入居が見込める方が初心者には向いています。
典型例として、千葉県船橋市で築18年の木造アパートを購入したBさん(IT系会社員・年収650万円)を見てみましょう。総額4,800万円、自己資金500万円、残りを2.0%・25年で借入。最寄駅から徒歩6分、全8戸のうち1戸空室でしたが、入居付けを家賃1.2万円下げて即決。購入後に外壁塗装とLED照明交換を行い、年間電気代を約4万円削減。結果として、満室時の実質利回りは当初想定の6.8%から7.5%へ上昇しました。
Bさんが特に重視したのは「人口動態データ」と「自治体の再開発計画」です。国勢調査によると船橋市の15〜39歳人口は2020年比で2025年も微増が予測されており、駅前の商業施設拡張計画もプラス材料でした。数字の裏付けがあるため、売却出口を設定しやすく、5年後に利回り6%で売り出しても損失が出にくい流動性を確保できています。
失敗を防ぐ運営と出口戦略
実は、購入後の運営こそ会社員投資家が差をつけやすい部分です。勤務時間中に物件トラブルが起きても、管理会社との連絡体制さえ整えれば影響は最小限になります。
Cさん(メーカー勤務・年収720万円)の例では、築25年の区分マンションを取得後、設備トラブルを想定して月5千円の家財保険オプションを付けました。入居者の給水管破損により15万円の修繕が必要になりましたが、保険適用で自己負担0円。保険料は年間6万円でも、リスクヘッジとして十分に回収できています。
また、出口戦略として「築30年時点でリノベ再販」か「賃料を1割下げて長期保有」の二択を決めておくと迷いが減ります。国土交通省の『不動産価格指数』では、築30年超の区分所有でも駅徒歩10分以内は下落幅が緩やかです。数字を見ながら早期売却せず、賃料調整による長期保有を選ぶ柔軟性が損失を防ぐのです。
2025年度に活用できる制度と税制のポイント
さらに、2025年9月時点で有効な制度を押さえておくと、収益を底上げできます。会社員投資家に関係が深いのは次の3点です。
まず、2025年度も継続する「固定資産税の新築住宅軽減」は、40㎡以上280㎡以下の新築賃貸住宅に対し3年間税額が1/2になります。ワンルームアパートを土地から購入して建築する場合、年間十数万円の節税効果があります。
次に、「賃貸住宅省エネ改修促進事業」は、外壁断熱や高効率給湯器設置などの改修費に対し一戸当たり最大60万円補助(2025年度申請分)を受けられます。入居促進につながるだけでなく、補助金が自己資金の圧縮にも寄与します。
最後に、所得1,000万円以下の会社員は青色申告特別控除65万円を満額で使える点も見逃せません。電子帳簿保存とe-Tax提出が前提ですが、クラウド会計ソフトを導入すれば実務負担は大きくありません。控除枠をしっかり確保しながら、修繕費を毎年計画的に計上することで、キャッシュフローの季節変動を平準化できます。
まとめ
不動産投資 成功事例 会社員というキーワードを振り返ると、鍵は「給与という安定収入をテコに、綿密な数字管理と制度活用でリスクを抑える」ことに尽きます。融資を引きやすい立場を生かしつつ、青色申告や省エネ補助金でキャッシュフローを底上げすれば、月数万円の余裕が生まれます。まずは自己資金の範囲でシミュレーションし、信頼できる管理会社と組むところから始めてみてください。今日から一歩踏み出せば、数年後には「会社員を続けながら家賃収入もある」新しいライフスタイルが現実になるはずです。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 国勢調査オンライン – https://www.stat.go.jp
- 国土交通省 賃貸住宅省エネ改修促進事業 2025年度概要 – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku
- 各地域信用金庫 住宅ローン金利情報(2025年9月時点) – https://www.shinkin.co.jp
- 国税庁 青色申告の手引き(令和7年度版) – https://www.nta.go.jp

