人口減少のニュースを聞くたびに、「今からアパート経営を始めても本当に借り手がつくのだろうか」と不安になる方は少なくありません。実は適切な立地選定と長期視点の資金計画を組み合わせれば、初心者でも安定した家賃収入を得ることは十分に可能です。本記事では、2025年9月時点の最新データを交えながら、「アパート経営 立地選定 長期投資」という三つのキーワードを軸に、物件購入前に押さえるべきポイントを丁寧に解説します。読み終えたときには、立地を見極める具体的な手順と長期的に収益を伸ばす戦略がイメージできるはずです。
アパート経営を長期投資と捉える視点
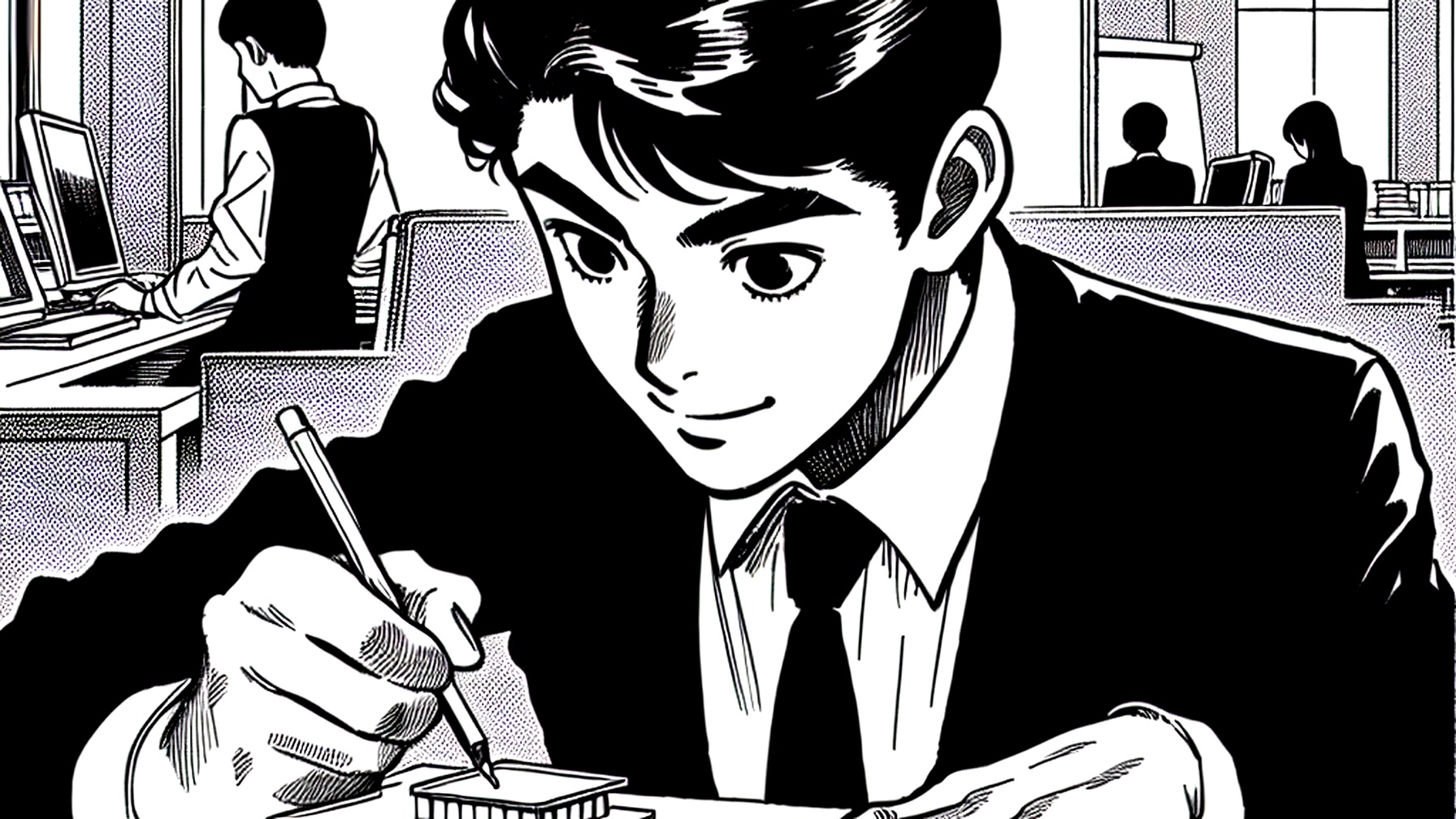
まず押さえておきたいのは、アパート経営が株式や投資信託とは異なる「実物資産への長期投資」である点です。物件は時間の経過とともに価値が変動しますが、土地はゼロにはならず、家賃収入というキャッシュフローが継続的に得られる特性があります。このため、短期的な価格の上下よりも、20年から30年先まで視野に入れた戦略が欠かせません。日本政策金融公庫の2025年度調査では、平均保有年数が18年を超えるオーナーが最も高い収益率を示しています。つまり、長期保有を前提にすれば、修繕費や空室率の変動を平準化でき、リスクを抑えながら複利的に資産を増やすことが可能です。
しかし長期で見れば、金利環境や人口動態、地域計画など外的要因が複雑に絡み合います。また、固定資産税やローン返済という支出も続くため、短期の家賃アップだけで収支を語るのは危険です。長期投資と位置づけるなら、初期段階で「出口戦略」まで考慮し、売却益と運営益のバランスを測るシミュレーションが不可欠になります。そして立地選定こそが、そのシミュレーションの前提条件を大きく左右する要素なのです。
立地選定で押さえる三つの軸
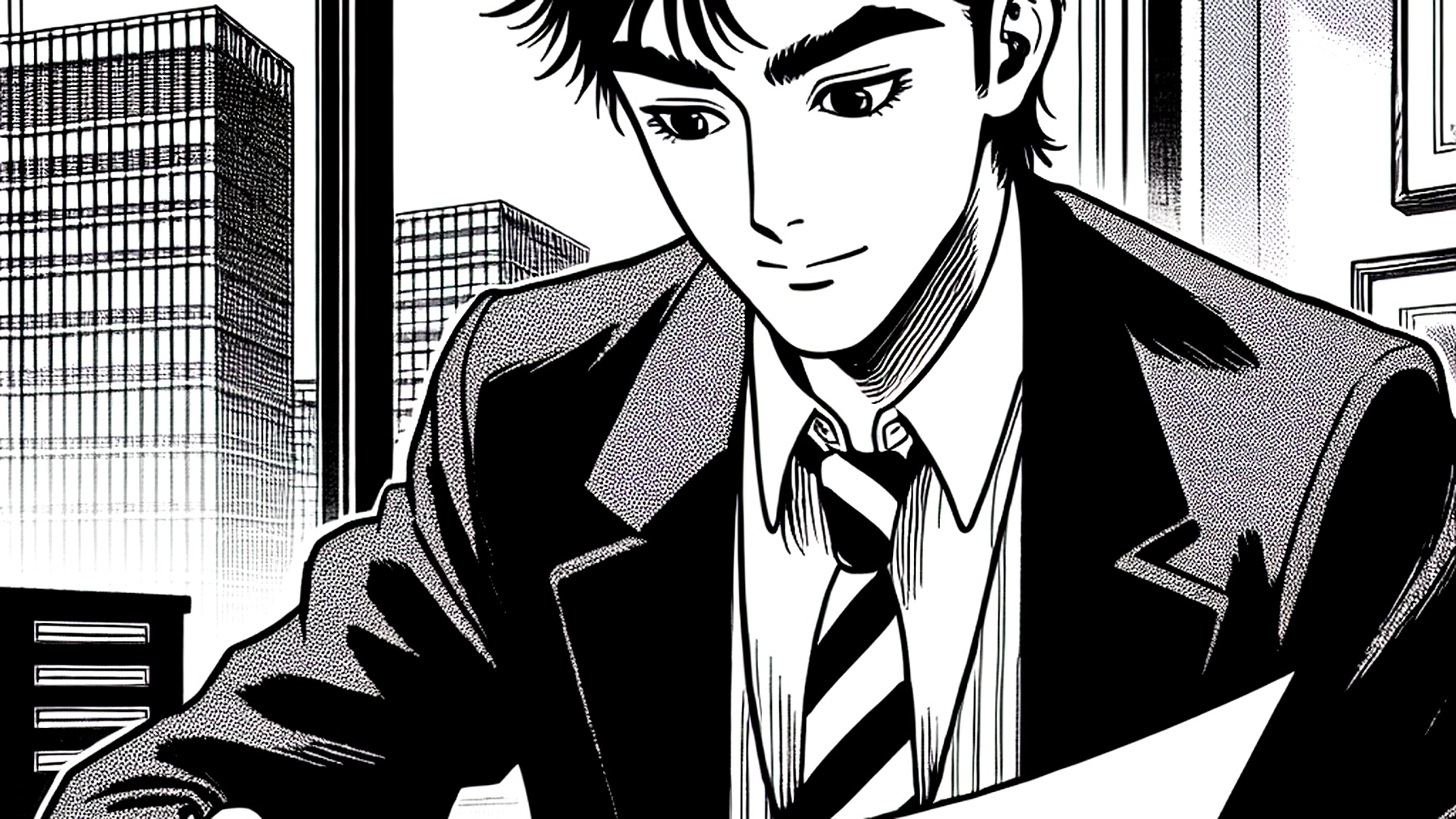
重要なのは、立地を「需要」「競合」「将来性」という三つの軸で評価することです。需要とは入居希望者の数であり、駅距離や生活利便施設の有無が大きく影響します。競合は周辺にある同種物件の供給状況で、築年数や設備水準が家賃設定力を左右します。将来性には再開発計画や人口推計が含まれ、長期的な資産価値を支えます。
具体的には、総務省統計局の住民基本台帳人口移動報告を参照し、過去5年間の人口増減率がプラスか横ばいの市区町村に注目します。さらに、国土交通省「都市計画基本図」で地域の用途地域や商業集積の動きを確認し、需要を裏付けるデータを集めましょう。最後に、現地調査で平日と週末の昼夜の人流を観察し、空室リスクを体感的に測ることが大切です。数字と肌感覚を合わせることで、机上の分析にリアルな説得力が生まれます。
一方で、表面利回りだけを重視して郊外や築古物件を選ぶと、競合の罠にはまることがあります。家賃設定で周辺に合わせざるを得ず、将来の大規模修繕と合わせて収益が伸び悩むケースが典型です。長期投資としては、利回りが1〜2%低くても需要が底堅い駅徒歩10分圏内や再開発エリアを優先する方が、総収入は高くなる傾向があります。ポイントは、利回りだけの数字に惑わされず、三つの軸を総合評価する姿勢です。
データで読む需要と供給のバランス
実は、空室率の推移を読み解くことで需要と供給のバランスを把握できます。国土交通省住宅統計によると、2025年7月の全国アパート空室率は21.2%で、前年比0.3ポイント改善しました。この数字だけを見ると市場は僅かに良化したように映りますが、エリア別にみると都心5区は12.8%、地方中核都市では26.5%と大きな差があります。長期投資を成功させるには、平均値ではなくピンポイントの市場データが必須です。
また、日本銀行の金融システムレポートでは、賃貸住宅ローン残高が過去最高を更新する一方で、返済延滞率は1%未満と低位で推移しています。これは、適切な立地であれば家賃収入が返済を十分にカバーしている証拠と読めます。ただし、将来的な金利上昇リスクを考慮し、変動金利で借りる場合は返済比率を家賃収入の50%以下に抑える安全マージンを持ちたいところです。
最後に、需給バランスのチェックには、賃貸ポータルサイトの掲載件数推移を月単位で追う方法も有効です。新規掲載が急増しているエリアは競争が激しく、家賃下落の可能性があります。逆に一定期間掲載数が横ばいなら需要が吸収されていると判断できます。データを定点観測しつつ、現地の賃貸仲介店で最新の成約事例を聞き取り、数字と現場の声をセットで検証する姿勢が結果的に空室リスクを下げます。
資金計画とリスク管理の基本
ポイントは、家賃収入を単なる収益と捉えず、修繕費・税金・返済の原資と位置づけることです。金融機関の審査基準は自己資金10〜20%が目安ですが、長期投資では追加で修繕積立を毎月家賃の5%程度積み立てると安定感が増します。日本政策金融公庫の事例分析によると、修繕積立を計画に組み込んだオーナーは、築15年以降の収支悪化が抑えられています。
さらに、火災保険や家賃保証などの付帯サービスも、支出とリスク低減効果を天秤にかけて選ぶことが大切です。家賃保証を付ける場合は、「免責期間」「滞納発生時の支払い上限」を必ず確認しましょう。不明確なまま契約すると、想定外の自己負担が生じ、キャッシュフローを圧迫しかねません。
結論として、資金計画をシビアに立てるほど、立地選定で多少高値づかみになっても長期的にはリカバーできます。金利変動や空室リスクを織り込んだ複数シナリオを用意し、最悪ケースでも手元資金が尽きないラインを確認してください。シミュレーションを通じて初めて、立地と資金計画がかみ合った「持続可能な投資」に近づきます。
2025年度の制度活用と今後の展望
まず押さえておきたいのは、2025年度も継続する住宅ローン控除と耐震・省エネ改修に関する固定資産税減額措置です。これらは居住用部分に適用される制度ですが、オーナー住戸付きアパートを計画する場合、長期的な税負担を下げる効果があります。適用条件は耐震基準適合証明や断熱性能の向上を示す書類の提出で、期限は2026年3月入居分までと明示されています。
また、環境省の「2025年度賃貸住宅ZEB化支援事業」は、高性能断熱材や太陽光発電を導入することで、工事費の一部を補助する制度です。上限は戸当たり150万円で、申請受付は予算消化までの先着順となっています。省エネ設備を導入すれば、光熱費込みの定額賃料プランを提案でき、競合物件との差別化につながります。
一方で、過去に話題となったグリーン住宅ポイントのように既に終了した制度も多数あります。制度活用を前提にした資金計画は、必ず公式サイトで最新の募集状況を確認し、行政書士や金融機関と連携して手続きを進めることが重要です。将来的にはカーボンニュートラルを背景に、省エネ性能が高い物件ほど評価が高まる流れが続くと見込まれます。制度をきっかけに設備水準を底上げし、長期的な物件価値を高める戦略が有効です。
まとめ
ここまで、「アパート経営 立地選定 長期投資」を軸に、長期視点で成功するための考え方を整理しました。需要・競合・将来性を総合的に評価し、データと現地調査で空室リスクを見極める姿勢が第一歩です。次に、金利上昇や修繕費を織り込んだ資金計画を立て、制度活用で支出を抑えつつ物件価値を底上げします。これらを丁寧に積み上げれば、20年先も安定した家賃収入を享受できる持続可能な投資が実現します。今日からデータ収集と現地視察を始め、自分だけの長期ポートフォリオを設計してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 2025年版 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局 人口移動報告 2025年7月 – https://www.stat.go.jp
- 日本政策金融公庫 2025年度「賃貸住宅経営実態調査」 – https://www.jfc.go.jp
- 日本銀行 金融システムレポート 2025年4月 – https://www.boj.or.jp
- 東京都都市整備局 住宅市場動向調査 2025年 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp

