サラリーマンの副業ブームで「アパート経営が手堅い」と聞いたものの、ネット検索をすると「アパート経営 やめとけ」という警告も目に付き、不安になっていませんか。自己資金も限られ、融資に踏み切る勇気が出ない読者にとって、失敗事例は他人事ではありません。しかし、悲観的な声の背景を正しく理解し、数字と仕組みを押さえれば、リスクを抑えながら資産形成につなげることは可能です。本記事では、最新データと現場経験を踏まえ、「やめとけ」と言われる理由を分解し、その対策までを初心者向けに解説します。読み終えたとき、あなたは自分にアパート経営が向くかどうか、そして始めるなら何から手を付けるべきかを判断できるようになるでしょう。
そもそも「やめとけ」と言われる背景
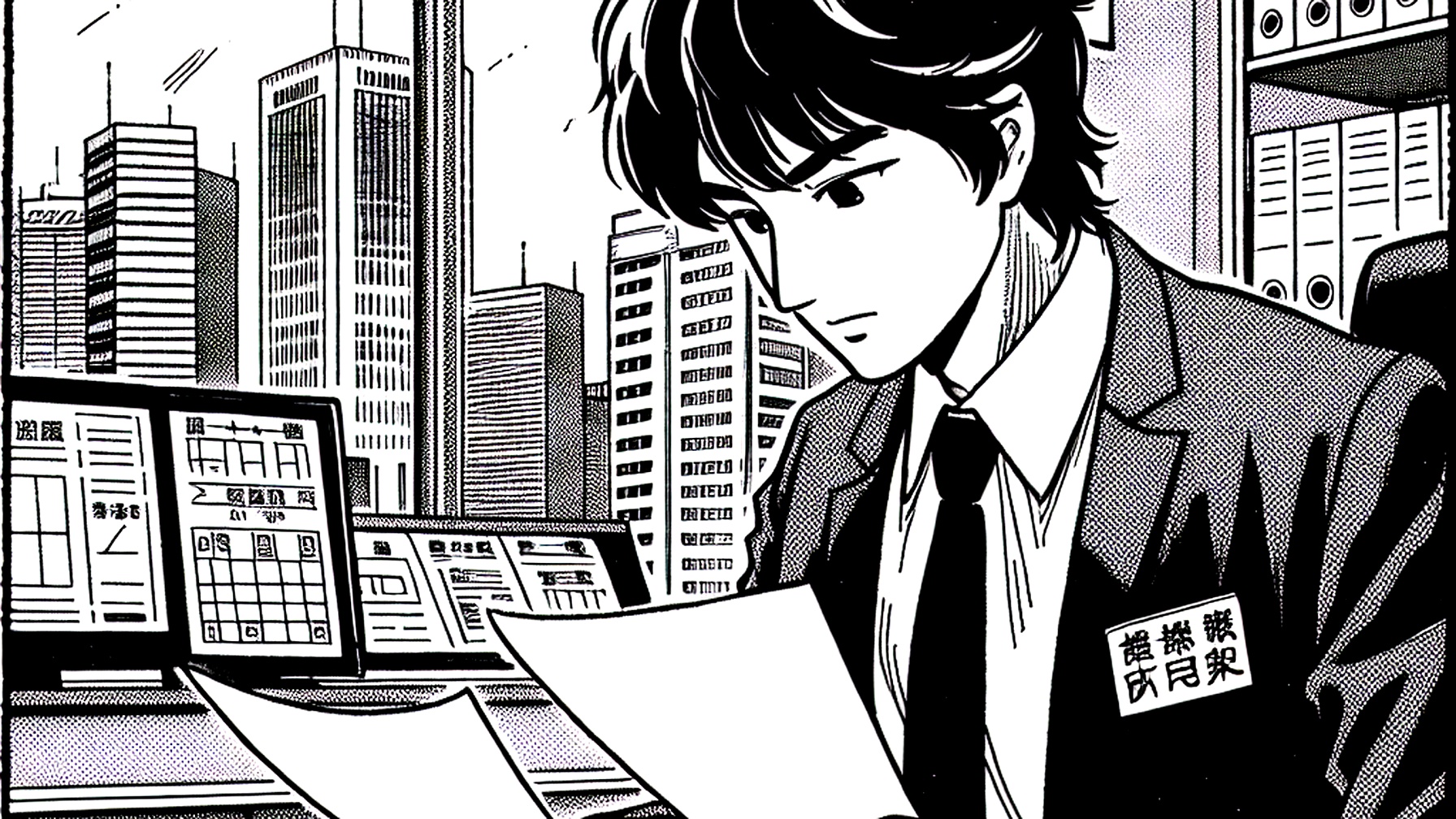
重要なのは、「やめとけ」というアドバイスが感情論だけでなく、過去に起きた具体的な損失事例に基づく点です。かつてのサブリース家賃減額問題や、想定外の修繕費で赤字に陥った大家の話は、一気に拡散されました。また、総務省統計局によると国内世帯数の伸びは2023年をピークに横ばいとなり、将来的な賃貸需要の鈍化が懸念されています。
一方で、情報を鵜呑みにしてチャンスを逃すのは早計です。失敗例の多くは、過度な借入れや立地リサーチ不足といった基本的ミスに起因しています。つまり、リスクの原因を切り分け、対策を講じれば「やめとけ」は「やる価値あり」に変わる余地があるのです。
さらに、不動産投資は株式や仮想通貨と異なり、物件ごとのリスクとリターンが大きく変わります。実は、金融機関が融資を出す基準も年々厳格化し、事業計画を精査する流れが定着しました。結果として、以前より杜撰なプランでは資金調達が難しくなり、逆に言えば審査を通る計画なら一定の安全性が担保されているとも言えます。
空室リスクは本当に高いのか
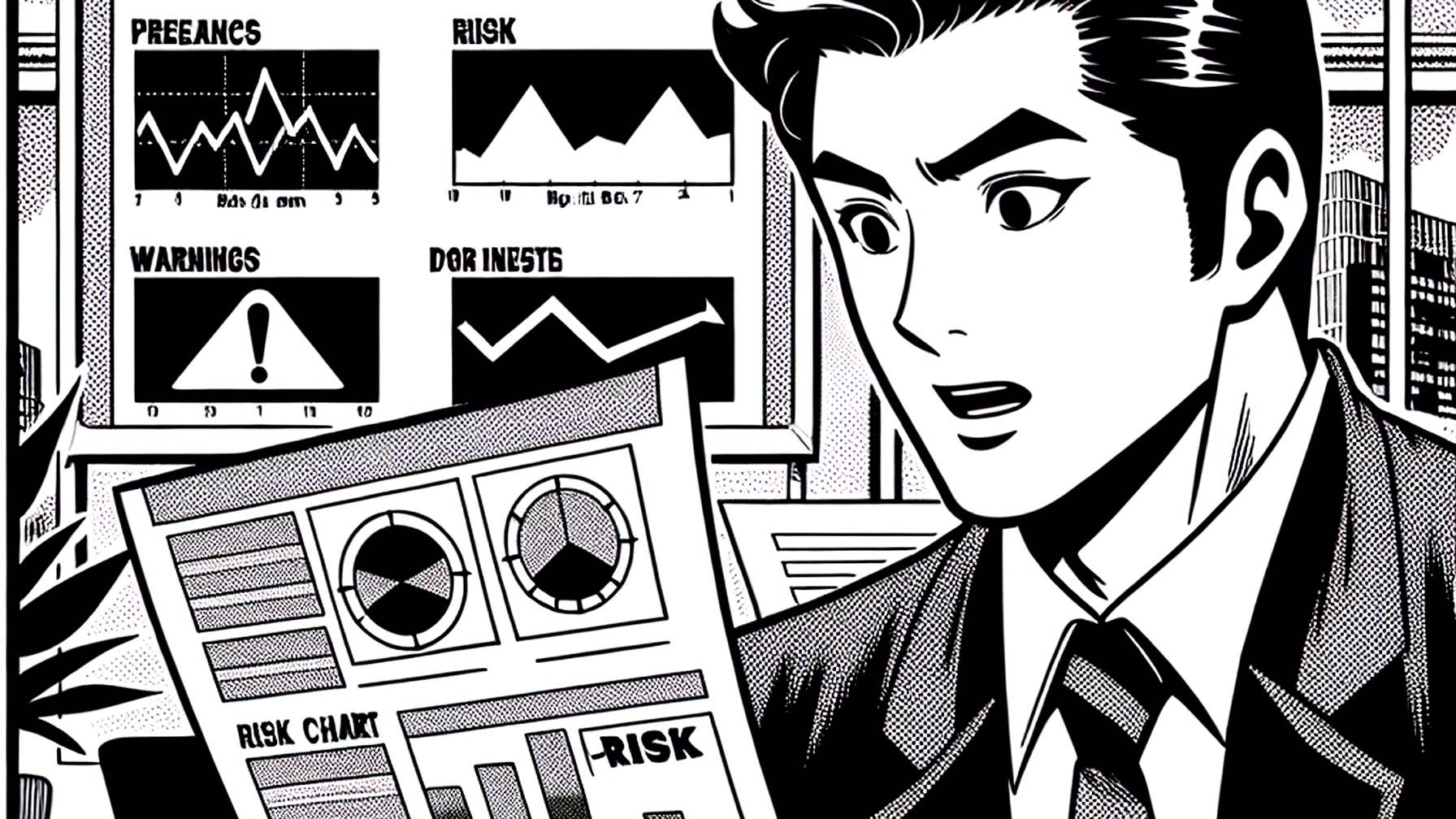
まず押さえておきたいのは、空室が利益を直撃する最大の要因である点です。国土交通省住宅統計の2025年7月速報では全国のアパート空室率は21.2%と発表されました。数字だけを見ると高く感じますが、前年比では0.3ポイント改善しており、エリアごとの差はさらに大きいことが分かります。
空室率が高くなる地域には共通点があります。人口減少が進む郊外や、似たような築古物件が乱立する商業地の裏通りなどです。実は、同じ市区町村内でも駅徒歩5分以内に限定すると空室率が10%を下回るデータもあり、立地選定が空室リスクの半分以上を決めると言っても過言ではありません。
また、空室が長期化する背景には賃料設定の硬直性があります。家賃相場サイトの少額ディスカウントを嫌い、数千円の値下げを渋った結果、数か月の機会損失が発生するケースが頻発しています。つまり適切なマーケットリサーチと柔軟な家賃戦略を採用すれば、平均空室期間を半減させることも難しくないのです。
最後に、2025年度も継続する「賃貸住宅省エネ改修促進事業」の補助金を利用すれば、断熱改修や給湯器交換にかかる費用の1/3が補助されます。省エネ性能を向上させることで、光熱費を気にする入居者のニーズに応え、競合物件と差別化できる点は見逃せません。
見落としがちなキャッシュフローの罠
ポイントは、家賃収入だけを見て「表面利回り10%だから安全」と判断しないことです。手残りを左右するのは、返済額、管理費、固定資産税、そして突発的修繕費まで含めた実質利回りです。特に築20年超の木造アパートでは、10年内に外壁塗装と屋根張替えで合計300万円以上かかる場合があります。
キャッシュフローを圧迫する代表格が金利上昇リスクです。2025年9月現在の変動金利は0.9%前後ですが、日本銀行は緩和縮小を示唆しており、将来的に1%後半まで上がるシナリオも想定されます。たとえば、借入残高5,000万円を0.8%から1.8%に引き上げると、年間返済額は約50万円増加します。予備資金が枯渇していればこの差額が即赤字につながります。
一方で、減価償却費という非現金支出を活用すれば、税引前黒字でも手元キャッシュを残すことが可能です。木造なら法定耐用年数22年ですが、築年数を差し引いた償却期間が短くなるほど、初期数年は大きな節税効果を得られます。つまり、長期保有で償却が尽きるタイミングまで見通し、売却出口を計画することがキャッシュフロー防衛の鍵になります。
さらに、管理会社への支払手数料は3%が目安といわれますが、複数物件を委託することで2%以下に交渉できる場合もあります。固定費を1%下げるだけで、年間粗利は数十万円単位で改善するため、地味な圧縮策こそ長期運営を支える土台になるのです。
税金と融資の最新ポイント
実は2025年度税制改正で、不動産所得に対する損益通算ルールは大きく変わっていません。赤字が給与所得と相殺できる仕組みは維持され、適正な経費計上による節税メリットは継続します。ただし、国税庁は過大な修繕費の一括計上に対する監視を強めており、経費区分の裏付け資料が必須です。
融資面では、地方銀行が2024年から導入した「DSCR(債務返済比率)1.2倍以上」という審査目安が定着しました。つまり、年間家賃収入が年間返済額の1.2倍以上ある計画でなければ融資が難しい状況です。しかし、この基準をクリアできる物件は、そもそも安全域が広いとも言えます。
さらに、2025年4月からスタートした「省エネ賃貸促進ローン」は、断熱性能等級4以上の新築アパートを対象に金利を0.3%優遇する制度です。省エネ基準を満たす設計にするだけで、長期的な返済負担軽減と入居者満足度向上の両方が得られます。制度は2027年3月融資実行分までの期限付きなので、新築を検討している人は早めに活用を検討すると良いでしょう。
最後に、個人名義での経営と法人化の選択ですが、所得900万円を超えるあたりから法人税率の方が低くなるケースが多くなります。ただし、設立費用や事務負担も増えるため、3棟以上・家賃年収2,000万円超が分岐点と覚えておくと判断しやすくなります。
失敗を防ぐための具体的なステップ
まず、物件検索を始める前に家計のバランスシートを作り、自己資金と緊急予備資金を分けて把握しましょう。投下自己資金は物件価格の20%が理想ですが、子どもの教育費や住宅ローン返済など他の支出計画と重ならないか確認することが欠かせません。
次に、エリアを絞り込む際は「将来人口」「再開発計画」「大学・病院など求人の源」の三つをチェックします。たとえば、東京都心の再開発エリアでは、築古でも駅近ならファミリー層の需要が底堅い一方、地方都市の郊外では家賃下落が加速しています。
購入を決める前には、必ず長期修繕計画を作成してください。屋根、外壁、給排水管の耐用年数を書き出し、10年ごとの費用を積み上げれば、年間予算として何万円を積立てるべきか見えます。ここを怠ると、数年後に突然数百万円の出費が生じ、追加借入れに追い込まれる危険があります。
最後に、管理会社選定は面倒でも3社以上面談し、賃貸付け実績と設備トラブル対応のスピードを数字で比較しましょう。入居者満足度が上がれば口コミで地域評価が高まり、募集コストが下がる好循環につながります。結局のところ、アパート経営は「人と数字」をどれだけ丁寧に扱えるかに尽きるのです。
まとめ
本記事では「アパート経営 やめとけ」と言われる理由をデータと事例で検証し、空室リスク、キャッシュフロー、税金・融資制度の要点を整理しました。重要なのは、悲観的な意見を鵜呑みにせず、立地選定と資金計画を徹底することです。具体的には、空室率の地域差を把握し、長期修繕費をシミュレーションに織り込み、優遇制度を活用して金利と税負担を抑えることが成功のカギになります。今すぐできる第一歩として、家計のバランスシートを洗い出し、気になるエリアの人口動態を調べてみましょう。行動を起こせば、リスクは数字に置き換えられ、漠然とした不安は着実な計画へと変わります。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 2025年7月速報 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局 家計調査報告 2024年版 – https://www.stat.go.jp
- 国税庁 タックスアンサー 不動産所得 – https://www.nta.go.jp
- 日本銀行 金融システムレポート 2025年4月 – https://www.boj.or.jp
- 中小企業庁 賃貸住宅省エネ改修促進事業 2025年度概要 – https://www.chusho.meti.go.jp

