初心者の方ほど、「家賃が毎月入るなら安心」と考え、収益物件への投資を急ぎがちです。しかし実際には、想定外の空室や修繕費が利益を奪い、最悪の場合は赤字に転落します。本記事では、収益物件 危険を回避するために押さえるべきポイントを基礎から解説します。読了後には、リスクを言語化し、数字で判断できる力が身につくはずです。
儲かると言われる収益物件に潜む落とし穴
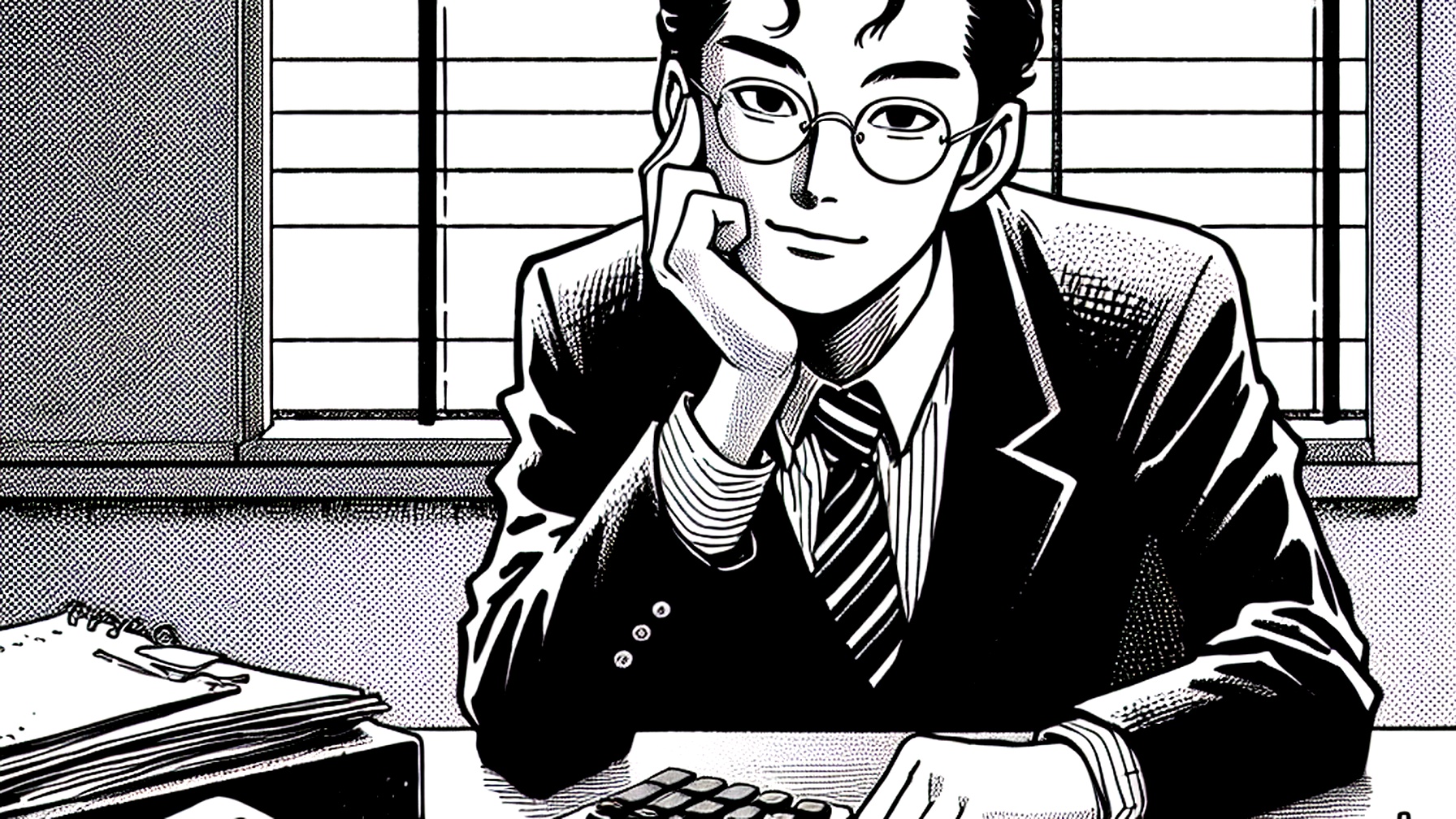
まず押さえておきたいのは、「家賃収入=安定」ではないという事実です。表向きの利回りだけで判断すると、思わぬ維持費や長期空室で収支が崩れる危険があります。
投資用マンションの広告では、想定利回りが6%を超える数字が強調されます。しかし国土交通省の2024年賃貸住宅実態調査によると、築15年超の平均空室率は20%前後に達しています。つまり、広告の前提が崩れた瞬間に手取り利益が半減しかねません。また、区分所有の管理費と修繕積立金は築年数とともに上昇し、家賃下落と同時に二重の圧迫要因となります。
さらに、物件紹介時点では見えにくい修繕リスクも無視できません。日本ERIの2025年調査では、築30年を超えるRC造では外壁改修に平均300万円超が必要との結果が出ています。資金計画に予備費を組み込まなければ、大規模修繕のたびに追加融資を求められ、金利負担が増す構図に陥ります。
表面利回りの罠とキャッシュフローの読み解き方
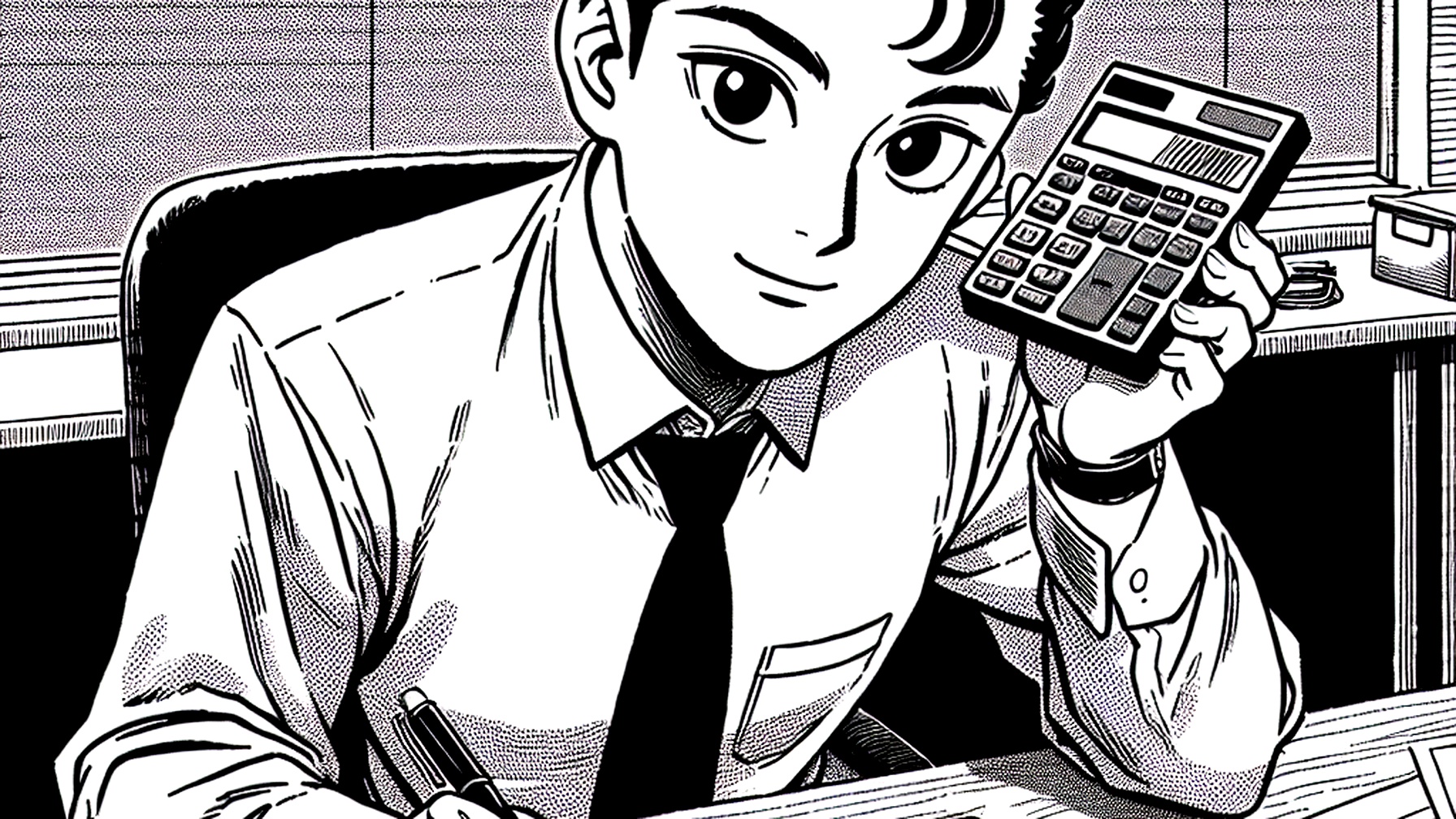
ポイントは、税引き後キャッシュフローを必ず算出することです。表面利回りは収益性の「外観」に過ぎず、実態を示しません。
まず空室率を保守的に25%で置き、年間家賃収入を試算します。次に、管理費・修繕積立金・固定資産税・火災保険を差し引き、ネット利回りを算出します。そのうえで金融機関への年間返済額を引いて、手元に残るキャッシュを確認してください。
例えば、家賃年収120万円・ローン金利2%・期間25年の場合、返済額はおおよそ63万円です。管理費などで30万円、空室損15万円が差し引かれると、手取りは12万円しか残りません。ここに築古物件特有の給排水管交換費用が突然発生すれば、あっさり赤字転落します。
実は、税金の取り扱いも見落とされがちです。2025年度の所得税法では、減価償却による損失を給与と損益通算できますが、赤字額が大きいと金融機関の追加融資審査が厳しくなる傾向があります。キャッシュフローと節税効果を分けて評価し、短期的な税還付に頼りすぎない判断が不可欠です。
立地リスクと人口動態を見抜く視点
重要なのは、入居需要を長期的に支える地域かどうかを読み解くことです。国立社会保障・人口問題研究所が公表する2045年までの自治体別推計人口は、立地判断の基礎資料となります。
具体的には、物件所在地の将来人口が5%以上減少するエリアでは、家賃下落と高空室率の二重苦になりやすいです。一方で、大学移転や再開発計画が進む都市近郊では、人口減でも世帯数が維持されるケースがあり、賃貸需要が底堅いこともあります。数字を読む際は「人口」と「世帯数」をセットで確認しましょう。
また、主要駅からの徒歩分数に加え、最寄りスーパーや病院までの距離もチェックが必要です。高齢化が進む地域では、生活インフラの近さが入居継続率に直結します。つまり、単なる交通利便性だけでなく、日常利便性を含めた総合立地力が問われる時代です。
最後に、行政の都市計画変更リスクにも目を向けてください。用途地域の見直しや再開発に伴う建築規制は、賃料水準や将来の建替えコストに影響します。自治体が公開する都市計画図や議事録を確認し、不確定要素を先回りして把握する姿勢が、安全運用への近道です。
法規制・税制変更が与える影響
実は、法改正は投資家の収支を大きく揺さぶります。2024年4月に改正された賃貸住宅管理業法は、管理会社に対する業務基準を強化し、委託手数料が上昇する傾向を招きました。手数料が1%上がるだけで、年間家賃600万円の一棟アパートでは6万円のコスト増です。
さらに、2025年度税制では、住宅取得等資金贈与の非課税特例が継続する一方、不動産取得税の軽減措置は既に段階的縮小が始まっています。個人名義での新規取得コストが上がるため、法人化による節税ニーズが高まりました。しかし法人設立には登録免許税や毎年の均等割など固定費も生じます。数値シミュレーションを行い、節税額が固定費を下回らないか事前確認が必要です。
また、建築基準法は2025年1月施行の改正で、既存不適格建物の増改築手続きが厳格化されました。古い木造アパートを購入して再生する戦略は、構造計算書の追加提出や耐震補強が義務化され、工事コストが膨らみます。規制動向を知らずに購入すると、想定利回りが崩壊しかねません。
失敗を防ぐためのチェックリストと実行手順
まず、購入前に「三つの余裕」を確保しましょう。具体的には、毎月返済額に対する家賃収入の余裕、突発修繕に備える資金余裕、そして金利上昇に耐える返済余裕です。
次に、物件資料を受け取ったら七日以内に現地視察を行い、昼夜の騒音や周辺治安を自分の目と耳で確認します。写真だけでは分からないゴミ集積所の位置や道路幅が、入居者満足度を左右するからです。視察後は、家賃査定サイトだけでなく、実際の募集広告をチェックし、想定賃料を1割下げたシナリオで再計算してください。
そして、金融機関への融資相談は少なくとも三行に打診し、提示条件を比較しましょう。2025年9月時点で、地方銀行と信用金庫の金利差は最大0.8%あります。わずかな差でも長期では数百万円の違いになります。
最後に、契約時には重要事項調査報告書を必ず取得し、修繕積立金の滞納状況や将来計画を確認します。特に区分マンションでは、積立不足があると将来的に一括徴収があり得ます。リスク情報をすべてテーブルに並べ、自己資金比率の調整や購入見送りを判断する冷静さが、収益物件 危険を遠ざける最大の武器です。
まとめ
ここまで、収益物件 危険を見抜くための五つの視点を解説しました。表面利回りに惑わされず、キャッシュフローを保守的に試算し、人口動態や法規制の変化まで検証する姿勢が重要です。実地調査と複数シナリオでのシミュレーションを徹底すれば、大きな失敗は避けられます。最初の一歩を慎重に踏み出し、長期で安定した不動産投資を実現してください。
参考文献・出典
- 国土交通省 賃貸住宅実態調査 2024年版 – https://www.mlit.go.jp/
- 日本ERI 建物修繕コスト調査 2025年版 – https://www.j-eri.co.jp/
- 国立社会保障・人口問題研究所 将来人口推計 2023 – https://www.ipss.go.jp/
- 総務省 地方税制度概要 2025年度 – https://www.soumu.go.jp/
- 法務省 建築基準法改正概要 2025年 – https://www.moj.go.jp/

