手堅い資産形成を目指しマンション投資を検討しているものの、新築と中古のどちらを選ぶべきか迷う人は多いでしょう。価格、利回り、維持費、そして空室リスクまで比べる項目が多いため、初心者ほど判断が難しく感じます。本記事では2025年9月時点の最新データを基に、新築マンション投資と中古マンション投資の特徴を丁寧に整理します。読むことで物件タイプごとのメリットとリスク、さらに2025年度に活用できる税制優遇まで理解でき、自分に合った戦略を描けるようになります。
マンション市場の現状を押さえる
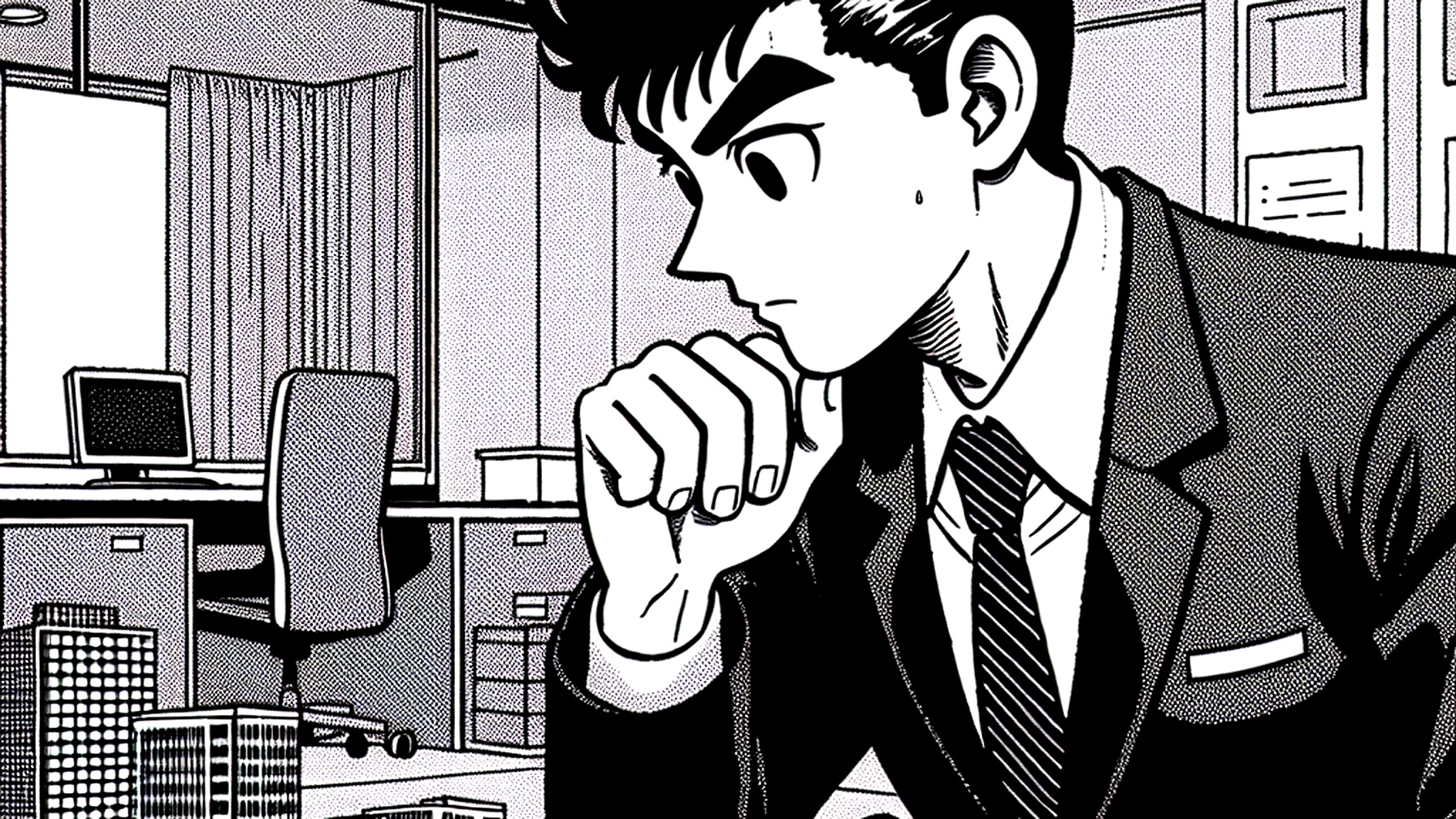
重要なのは、市場動向を数字で確認してから投資戦略を立てることです。2025年の不動産経済研究所によると、東京23区の新築マンション平均価格は7,580万円で前年比3.2%上昇しました。一方で国土交通省の不動産価格指数を見ると、中古マンションの価格は同期間で1.1%の微増にとどまり、伸び率に差が出ています。つまり新築は価格上昇が続き、中古は比較的緩やかな値動きという構図が鮮明です。
次に注目したいのは賃料水準です。東京都都市整備局の家賃統計では、23区の平均賃料は前年対比0.8%の上昇にとどまり、価格ほどの伸びは見られません。賃料が大きく増えないまま新築価格だけが上がれば、利回りは縮小します。また空室率はコロナ禍後に改善したものの、23区でも5%前後で推移しており、エリアによる差が広がっています。
最後に人口動向を確認します。総務省の住民基本台帳人口移動報告によれば、23区の転入超過は2024年に再び増加へ転じましたが、郊外への人口流出も続くという二面性があります。都心部の需要は底堅いものの、サブマーケットでは空室リスクが高まる可能性がある点を忘れないでください。
新築マンション投資の特徴と注意点
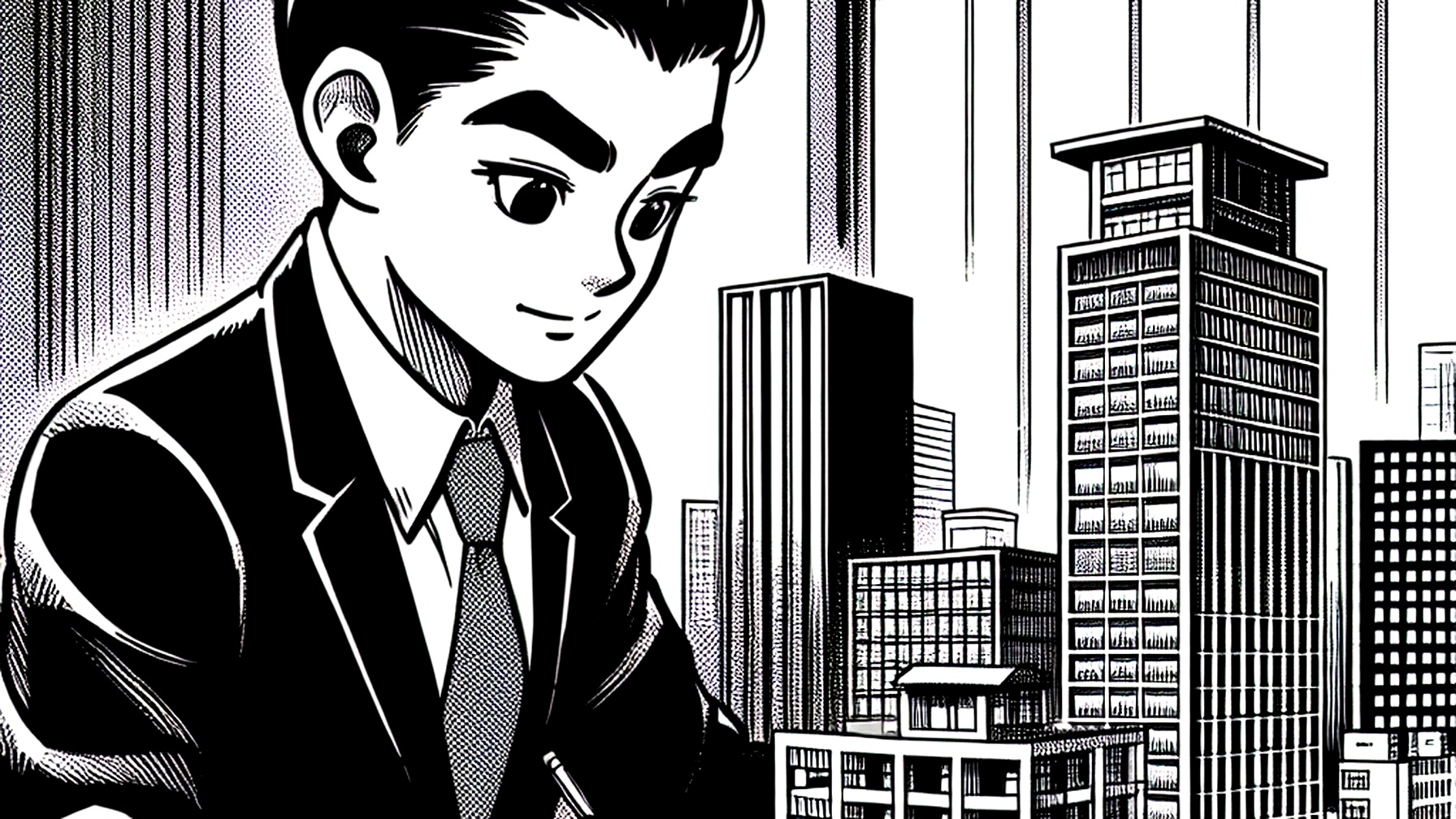
まず押さえておきたいのは、新築マンション投資が「設備の最新性」と「修繕リスクの低さ」を強みとする点です。最新の耐震基準やIoT設備を備える物件は、入居者から選ばれやすく、当初の空室リスクを抑えられます。さらに長期修繕計画がスタート地点から整備されているため、築10年程度までは突発的な大規模修繕が発生しにくい利点があります。
しかし初期費用が高いことは無視できません。新築価格が上昇する一方で賃料の伸びが限定的なため、表面利回りは関東圏で平均4%台に低下しています。低金利の長期融資を受けられればキャッシュフローは組みやすいものの、自己資金比率が低い場合は月々の返済比率が高まりがちです。また固定資産税の新築軽減期間(最長5年間)は魅力ですが、その後の税負担増も計算に入れる必要があります。
加えて売却戦略にも注意が必要です。築5年を過ぎると新築プレミアムが剝落し、価格が数%下落するケースが多いのが現実です。短期転売を狙うと、仲介手数料や登録免許税がリターンを圧迫します。つまり新築マンション投資は「長期保有で安定賃料を得る」シナリオに向いており、短期でのキャピタルゲインは期待しすぎない姿勢が安全です。
中古マンション投資の魅力とリスク管理
ポイントは、購入価格が抑えられる分、利回りを高めやすいことです。国土交通省のデータでは、首都圏中古マンションの築20年物件は新築の6割程度の価格水準ですが、賃料は新築比で8割前後にとどまります。このギャップが実質利回りを押し上げ、物件によっては表面6%超になる事例も珍しくありません。つまり限られた自己資金でレバレッジを利かせやすいのが中古の魅力です。
一方で修繕リスクは避けられません。築15年を超える物件では給排水管の交換や外壁補修が近づくため、長期修繕計画と修繕積立金の残高確認が不可欠です。積立不足の場合、購入直後に一時金を請求されるケースがあります。建物検査(インスペクション)を実施し、躯体や設備の劣化状況を数値で把握しておくと、想定外の出費を抑えやすくなります。
さらに管理組合の運営状況も重要です。総会の議事録を読めば、滞納率や大規模修繕への合意形成の度合いが分かります。管理が行き届いていれば資産価値を長く維持しやすく、出口戦略も描きやすいものです。価格と利回りだけで判断せず、ソフト面のチェックを徹底する姿勢が、中古マンション投資成功の鍵になります。
新築と中古のキャッシュフロー比較
実は、新築と中古の違いは購入時点の数字だけでは測れません。保有期間中の収支と売却時の手残りまで通算して比較することが欠かせます。ここではモデルケースを用いて、10年間保有した場合のキャッシュフローを示します。
- 新築:購入価格7,500万円、表面利回り4.2%、自己資金1,500万円、金利1.3%(35年)、修繕一時金なし
- 中古:購入価格4,500万円、表面利回り6.0%、自己資金900万円、金利1.6%(30年)、購入5年目に修繕一時金100万円
この前提で試算すると、年間手取り収支は新築が約52万円、中古が約85万円となります。ただし新築は固定資産税の軽減で当初5年の税負担が低減し、長期で見ると差が縮まることも分かります。売却時を想定すると、築15年の新築物件は購入価格比▲8%、築30年の中古物件は▲15%程度で売れると想定されるため、キャピタルロスは中古のほうが大きくなりがちです。つまりキャッシュフロー優位の中古と、資産価値維持で優位な新築という対比構造になりやすいのです。
投資家は自己資金比率、返済比率、そして保有期間を踏まえて選択する必要があります。短期でのキャッシュフロー重視なら中古、長期での安定運用と資産価値維持を狙うなら新築が向くという整理をしておくと判断がブレにくくなります。
2025年度の資金調達と税制優遇
まず押さえておきたいのは、2025年度も住宅ローン控除が投資用物件には適用されない点です。投資家が利用できる制度としては、不動産取得税の軽減措置、登録免許税の特例税率、固定資産税の新築軽減が代表例になります。例えば新築物件の場合、固定資産税は床面積50〜120㎡であれば3年間(耐火建築物は5年間)、課税標準が2分の1になるため、運営初期のキャッシュフローを改善できます。
資金調達面では、メガバンクとノンバンクの金利差が依然として1%以上ある状況が続いています。2025年4月の日銀政策修正により長期金利が0.4%台へ上昇したため、変動金利は横ばいでも固定金利はじわりと上がっています。固定派なら早めの融資実行が得策ですが、変動派は金利上昇リスクを1.5%程度まで織り込んだシミュレーションを準備しましょう。
また、賃貸住宅管理業法の改正に伴い、管理会社へ支払う報酬の透明性が高まりました。委託料が家賃の5%を超える場合、その根拠を説明義務化したことで、運営コストを抑えやすくなっています。新築・中古いずれを選ぶにせよ、融資条件と運営コストを同時に見直し、総費用を最小化する姿勢がリターン最大化の近道となります。
まとめ
ここまで見てきたように、「マンション投資 新築 中古」の選択は価格と利回りだけでなく、修繕リスクや出口戦略まで含めた総合判断が必要です。新築は設備や資産価値の維持に強みがある一方、初期投資が重く利回りが低めです。中古は高利回りを狙える半面、修繕コストや管理体制の見極めが欠かせません。まずは自己資金と返済比率を把握し、長期のキャッシュフローをシミュレーションしてください。そうすれば、新築と中古のどちらを選んでも、ブレない投資判断で安定した資産形成を進められるはずです。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 東京都都市整備局 住宅市場動向 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp
- 総務省統計局 住民基本台帳人口移動報告 – https://www.stat.go.jp
- 国税庁 固定資産税関連情報 – https://www.nta.go.jp

