都心の大型ビルだけでなく、中小規模の事務所物件にも投資マネーが流れ込み始めました。しかし「事務所 不動産投資ローン 固定金利」と検索しても、住宅向け情報ばかりで要点がつかみにくいと感じる方が多いはずです。本記事では、事務所物件の市場動向からローンの組み方、固定金利を選ぶ際の判断基準まで体系的に整理します。読了後には、金融機関との交渉で迷わない知識と、長期の返済計画をシミュレーションできる視点が得られるでしょう。
事務所物件投資の魅力とリスク

ポイントは、住居系とは異なる収益構造を理解することです。実はオフィスワーカーの回帰が進み、2025年上期の東京23区平均空室率は4.2%まで下がりました(ビルディング経営研究所調べ)。この数字はコロナ禍ピーク時の半分以下であり、賃料も緩やかに回復しています。
まず魅力から見ていきます。事務所賃料は坪単価で設定され、面積が広いほど総賃料が増えるため、住宅より高い利回りを確保しやすいです。またテナント契約期間が2〜3年と長めで、更新料が入るケースもあり、安定的なキャッシュフローが期待できます。さらに法人契約であれば家賃滞納率が低く、管理の手間が減る点も見逃せません。
一方でリスクも存在します。景気変動に敏感な業種が入居する場合、空室期間が長引く可能性があります。加えて、共用部の電気代やエレベーター保守料などの運営費が重くなるため、ネット利回りが想定より下がることがあります。つまり物件選定では賃料水準だけでなく、管理コストを丁寧に試算する姿勢が重要です。
最後に立地について触れます。国土交通省の地価LOOKレポートによると、2025年も業務系ゾーンの地価は「上昇」判定が4期連続で50%を超えています。都心5区はもちろん、湾岸や駅直結ビルの稼働率も高止まりです。反対に駅から遠い築古ビルは、改修コストが高まりやすいので慎重な判断が求められます。
不動産投資ローンの審査と組み方
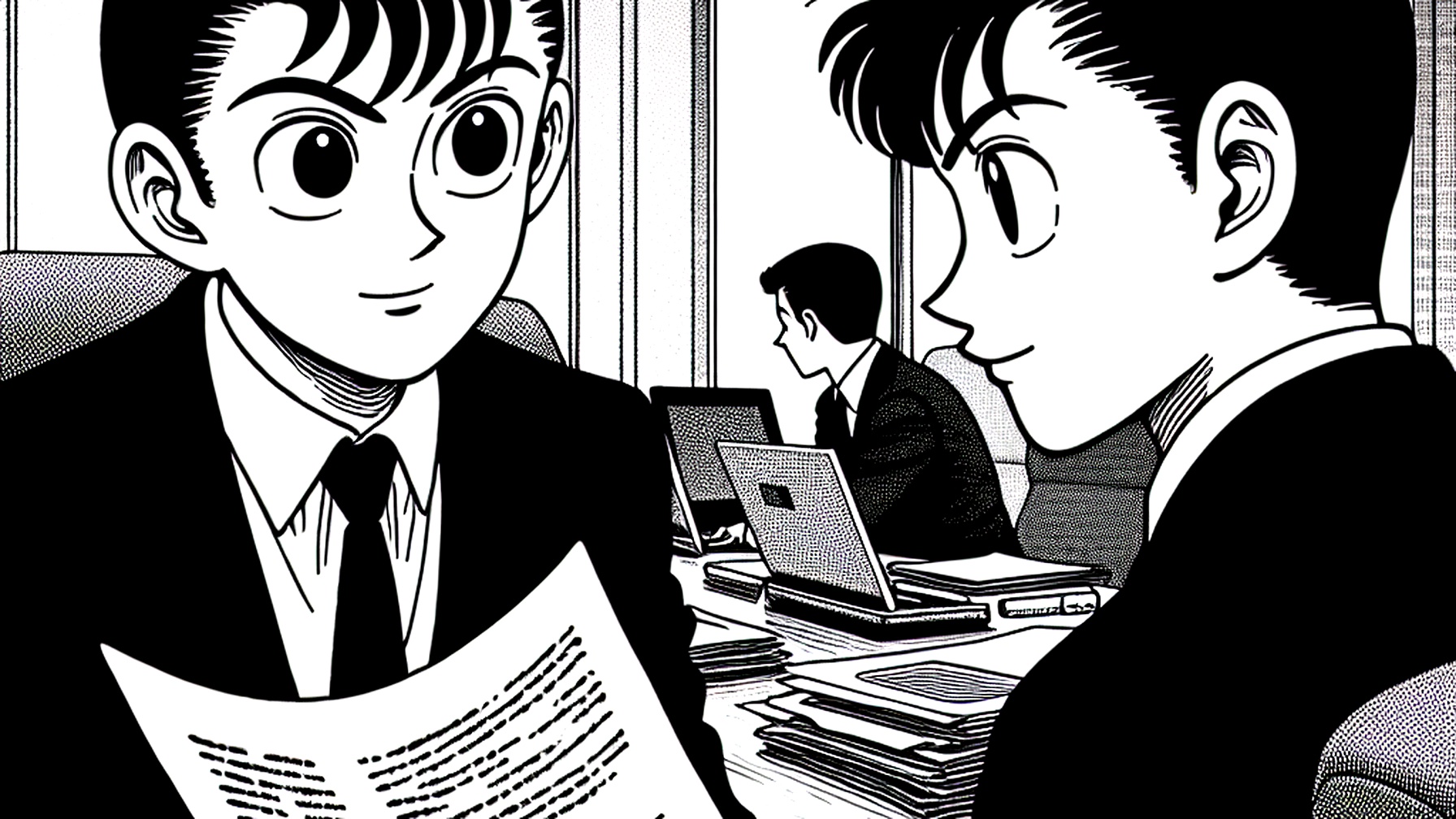
基本的に、事務所向けの不動産投資ローンは住宅投資より審査が厳格です。金融機関は稼働率やテナントの業種まで詳細にチェックするため、事前に収支計画を練り込むことが成功の鍵となります。
まず押さえておきたいのは融資比率です。住宅系ではフルローンが得られる場合もありますが、事務所では自己資金20〜30%が標準とされています。頭金を多めに入れると返済比率が下がり、審査が通りやすくなる点もメリットです。さらに、共用部修繕積立金の予備費として購入額の5%程度を別口座に確保しておくと、金融機関からの評価が上がります。
次に重視されるのがDSCR(Debt Service Coverage Ratio、元利返済カバー率)です。都銀では1.2倍以上、地銀や信用金庫では1.4倍程度を求める傾向があります。例えば年間賃料収入が1,500万円、運営費が300万円、年間返済額が1,000万円ならDSCRは1.2倍です。この数字を改善するには、固定金利で返済額を安定させるか、借入期間を延ばして月々の返済を抑える方法があります。
最後に書類準備について触れます。テナントとの賃貸借契約書、直近3年分の決算書、物件の長期修繕計画書が必須です。特に修繕計画が曖昧だと「将来の資金繰りリスク」と判断され、金利が上乗せされるケースもあるため、管理会社と連携して実態を数字で示しましょう。
固定金利を選ぶか変動か、判断の軸
重要なのは、金利上昇局面でのキャッシュフロー耐性です。全国銀行協会の2025年9月データによると、事務所 不動産投資ローン の固定10年金利は2.5〜3.0%、一方の変動金利は1.5〜2.0%が目安となっています。
まず固定金利のメリットを整理します。最大の利点は返済額が契約期間中変わらないため、長期のシミュレーションが立てやすいことです。例えば3億円を金利2.7%、20年元利均等で借りると、年間返済額は2,033万円で一定です。空室リスクを織り込んでも、最悪シナリオが描きやすく、資金繰りの破綻確率を下げられます。
一方で固定金利は初期負担が大きい点がデメリットです。変動金利との差が年1%ある場合、同じ3億円借入で金利1.7%なら年間返済は1,754万円となり、差額は約280万円になります。この浮いた資金を内部留保に回せば、修繕やバリューアップに再投資できるため、短期でリターンを高めたい投資家には魅力的です。
判断の軸は、市場金利の動向と自己資金の余力にあります。日本銀行が2025年春に長期金利目標を0.75%へ引き上げた影響で、固定金利は小幅に上昇しました。今後さらに上がると読めば早期に固定で抑える選択が合理的です。ただし自己資金に厚みがあり、金利上昇局面でも返済比率を維持できるなら、変動を取りつつ途中で固定へ切り替える「スイッチング戦略」も有効です。
最後に注意点を挙げます。固定期間終了後の金利は再度市場連動となるため、返済期間全体での平均金利を試算する必要があります。また、全期間固定型は団体信用生命保険料が別途発生するケースもあるので、総コストで比較しましょう。
2025年度の融資戦略とシミュレーション
まず押さえておきたいのは、2025年度の金融機関ごとのスタンスです。都銀は大型案件を優先しつつ、DSCR1.2倍を確保できれば固定2.6%前後での提示が目立ちます。一方、地方銀行や信金は地域密着型の中小ビルに積極的で、金利2.8%前後でも融資期間25年と長めに設定できる場合があります。金額だけでなく期間条件まで含めて交渉する視点が不可欠です。
次にシミュレーション例を示します。取得価格2億円、自己資金5,000万円、借入1億5,000万円、固定金利2.7%、期間20年とします。年間家賃収入は1,400万円、運営費率15%を想定すると、年間手取りは1,190万円です。年間返済額は約1,017万円なので、税前キャッシュフローは173万円、DSCRは1.17倍になります。ここに入居率95%シナリオや金利3.2%上昇後シナリオを当てはめ、耐性を検証しておけば、金融機関との面談で説得力が増します。
融資を引き出すコツは、複数行を同時進行で打診し、提示条件を比較することです。その際、固定金利の期間を10年と15年で並べてもらうと、総返済額の差が一目瞭然になります。また、2025年度の「中小企業成長促進保証制度」を活用すると、法人が購入する際に信用保証料の一部が補助され、金利負担を0.1%程度抑えられる可能性があります(期限:2026年3月申込分まで)。
最後に、固定金利であっても繰上返済の可否と手数料を要確認です。手数料が残高の2%と高い銀行もあれば、固定期間外なら無料の銀行もあります。将来の出口戦略として売却や借換えを視野に入れるなら、ペナルティ条件を細かく比較しましょう。
まとめ
本記事では、事務所物件の市場環境からローン審査のポイント、固定金利と変動金利の比較、そして2025年度の具体的な融資戦略まで解説しました。安定収益を狙うなら固定金利で返済額を固める手法が有効ですが、金利差を利用してキャッシュフローを厚くする戦略も選択肢になります。重要なのは、複数シナリオで資金繰りを検証し、金融機関に対して説得力のある計画書を提示することです。行動に移す際は、この記事で得た知識をベースに、実際の金利条件や物件特性を照らし合わせ、最適な融資プランを組み立ててください。
参考文献・出典
- 国土交通省 地価LOOKレポート2025年Q2 – https://www.mlit.go.jp/
- 全国銀行協会 住宅ローン・不動産投資ローン金利推移(2025年9月) – https://www.zenginkyo.or.jp/
- ビルディング経営研究所 オフィスマーケットデータ2025 – https://www.building-lab.or.jp/
- 中小企業庁 中小企業成長促進保証制度 2025年度概要 – https://www.chusho.meti.go.jp/
- 日本銀行 金融政策決定会合資料 2025年4月 – https://www.boj.or.jp/

