アフターコロナで働き方や住まい方が大きく変わり、投資用マンションのニーズも予想以上に多様化しました。「今からでも一棟買いに挑戦できるのか」「都心価格が上がる中で本当に利益を出せるのか」と悩む人は少なくありません。本記事では、最新データと2025年度の制度を踏まえつつ、マンション投資を一棟買いで始める際のポイントを基礎から解説します。読了後には、物件選定から資金計画、運営戦略まで具体的な判断軸が整理できるはずです。
アフターコロナで変わった賃貸需要
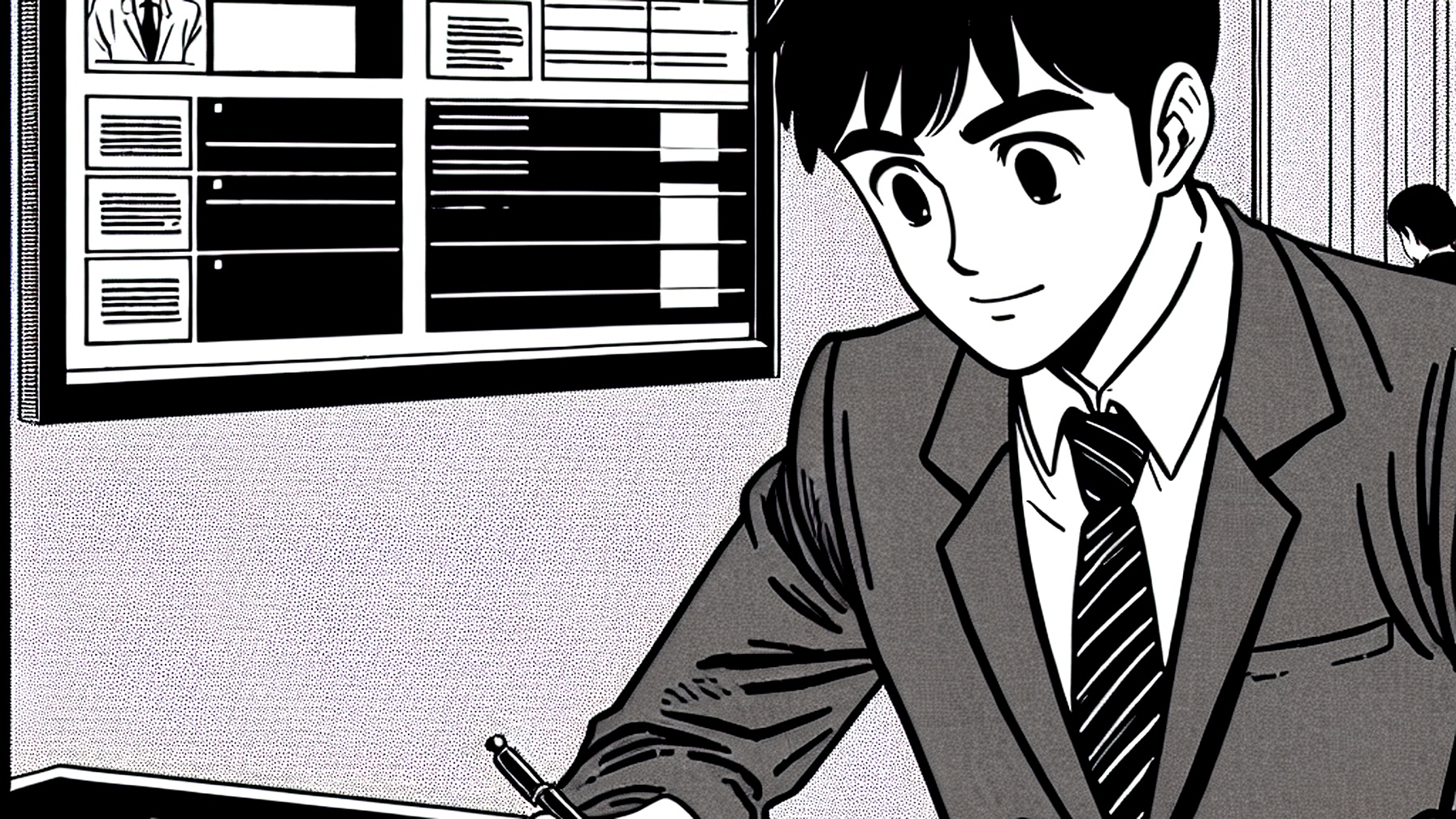
まず押さえておきたいのは、賃貸市場の構造がコロナ以前とは異なる点です。テレワークが常態化した結果、都心への通勤需要が一部緩和された一方、駅近で通信環境が良い物件は依然として高い成約率を維持しています。国土交通省の住宅市場動向調査(2025年4月公表)によると、首都圏のワンルーム平均空室期間は18.2日とコロナ禍ピーク時の25.6日から大幅に短縮しました。つまり、リモート主体でも「アクセスの良さ」と「ネット環境」を同時に満たす物件は選ばれ続けているのです。
一棟買いの場合、間取りを一括で最適化できる点が強みになります。専有部すべてに高速Wi-Fiを標準装備し、宅配ボックスを大容量タイプに更新するだけで、成約スピードが平均1.4倍になった事例もあります。また、在宅時間の増加に伴い遮音性への関心が高まったため、共用廊下に吸音材を追加施工するオーナーも増えました。追加投資額は総工費の3〜4%程度ですが、賃料アップ率は平均5%と採算が合いやすいです。
こうした需要変化を素早く取り込むには、区分所有よりも一棟での意思決定が欠かせません。管理組合の合意を待たず、内外装と設備をまとめて更新できるからです。アフターコロナの変化が一過性ではなく、中期的な傾向である以上、投資判断に反映させる価値は高いと言えるでしょう。
一棟買いのメリットとリスク
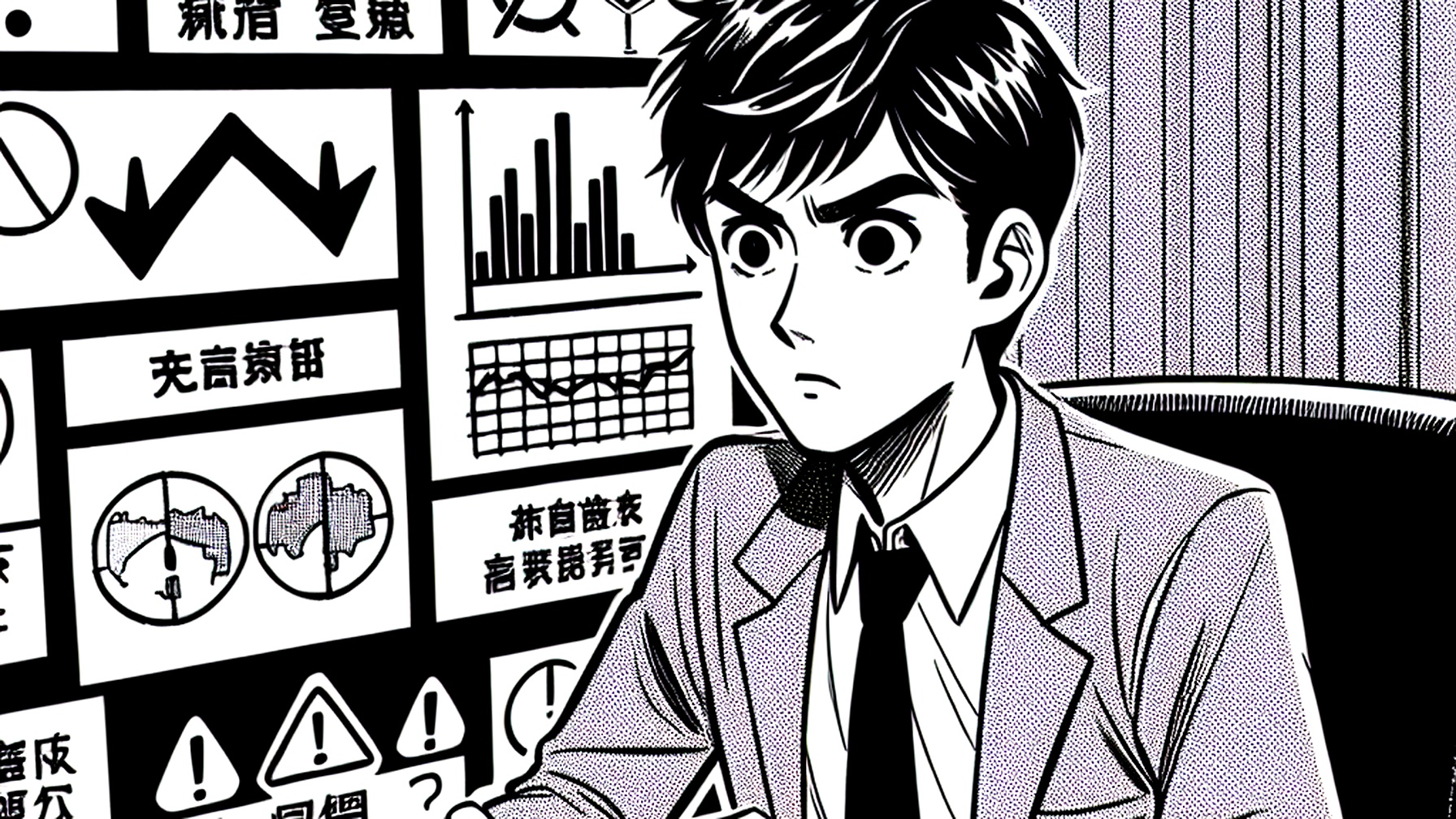
重要なのは、一棟買いが「収益とリスクの両刃」である点を理解することです。メリットは、まずキャッシュフローの安定です。複数戸の家賃収入を束ねるため、1室空室でも全体の収支が崩れにくい構造になります。さらに、土地と建物を一括取得するため、減価償却を柔軟に計画でき、所得税や住民税のコントロールがしやすくなります。
一方で、初期投資は大きく、金融機関の融資審査も厳格です。2025年時点で主要ノンバンクの一棟向け融資はLTV(Loan to Value=物件価格に対する融資比率)70%前後が上限で、自己資金を30%用意できないと案件が止まるケースが多いです。また、共用部の修繕費はオーナーが全額負担するため、長期修繕計画と積立金管理を怠ると突発的な大規模支出に直面します。
リスクを軽減する方法として、まず利回りだけに着目しないことが挙げられます。利回りが高い地方物件でも、人口減少エリアであれば将来の空室リスクが跳ね上がります。加えて、耐震基準適合証明がない築古物件を買うと、金融機関の評価が下がり、修繕費もかさみがちです。つまり、表面利回りより、実質利回りと資産価値のバランスを評価する姿勢が欠かせません。
物件選びで押さえるべき最新指標
ポイントは、従来の駅徒歩分数や築年数に加え「エリア再開発の進捗」と「人口当たりのサブスクリプション需要」を読んでいくことです。例えば東京23区では、湾岸部の再開発エリアでサブスク型家具サービスの契約率が30%近くに上がり、家具なしの空室が選ばれにくくなっています。こうした生活スタイルの変化は、賃料設定にも直接影響するため収支計画に織り込む必要があります。
また、不動産経済研究所のデータによると、2025年9月時点の新築マンション平均価格は7,580万円で前年比3.2%増でした。価格上昇が続く局面では、中古一棟の再生投資に妙味が生まれます。具体的には築25〜30年、RC造、延床400〜600㎡程度の中規模マンションを購入し、内装と共用部をリノベーションして家賃を10%上げる手法が有効です。施工費を含む総投資額が東京23区内でおおむね1億8,000万円前後なら、家賃収入年間1,500万円前後を狙え、表面利回り8%以上を確保できます。
最後に、現地調査では昼と夜の2回足を運び、騒音や治安を肌で感じることが大切です。オンライン図面だけでは得られない情報が意思決定の精度を高めます。つまり、データと現地体験を組み合わせるアナログなプロセスが、今もなお成功率を左右するのです。
2025年度の融資環境と税制優遇
実は、金融機関の姿勢にもアフターコロナの影響が色濃く出ています。メガバンクは区分投資に厳しくなった半面、エリア需要に合致した一棟案件には前向きです。2025年度の代表的商品として、固定金利1.6%・35年返済でLTV70%までのローンが登場し、金利変動リスクを抑えたいオーナーに選ばれています。地方銀行や信用金庫は地域振興を掲げ、築古再生プランに対して最長30年・変動金利0.9%の優遇を打ち出すケースもあります。
税制面では、アパート・マンションの大規模修繕に活用できる「賃貸住宅エコ改修支援事業(2025年度)」が継続中です。外壁断熱や高効率給湯器の導入に対して工事費の3分の1以内、上限300万円の補助が受けられます。適用条件に省エネ基準適合が含まれるため、事前のエネルギー評価は必須ですが、採択されれば利回り改善効果が大きいです。
さらに、不動産所得の青色申告特別控除(65万円)は電子帳簿保存と電子申告を行えば継続して適用できます。クラウド会計ソフトを導入して仕訳を自動化すれば、帳簿負担を減らしながら節税メリットを享受できます。このように、融資と税制を組み合わせてキャッシュフローを最適化する視点が、投資成否を左右します。
長期安定経営のための運営戦略
まず押さえておきたいのは、管理会社任せにしない主体的な運営です。空室が出た際に自ら周辺相場と募集条件を確認し、家賃微調整やキャンペーン内容を管理会社と協議する姿勢が、稼働率を底上げします。また、入居者コミュニティを可視化するLINE公式アカウントを用意し、設備不具合や要望をリアルタイムで吸い上げると、クレームが未然に防げます。
2025年の入居者ニーズ調査では、IoT家電との連携とスマートキー導入を評価する回答が6割を超えました。戸あたり2万円弱で後付けできるスマートロックを導入すると、鍵交換コストが削減できる上、非対面内見にも対応できます。さらに、SDGs志向の若年層は共用部の再生可能エネルギー表示を重視する傾向にあるため、屋上に2〜3kWの太陽光パネルを設置し、共用部電力に充当するだけでも付加価値となります。
中長期的には、空室が3戸以上同時に発生したタイミングでフルリノベーション区画を作る「入れ替え戦略」も有効です。この手法では、旧来の賃料水準を維持しながらも一部住戸だけハイグレード仕様に変更し、平均賃料を押し上げます。総投資額の回収は3〜4年が目安で、資産価値の底上げにもつながります。運営フェーズでの積極投資が、結果として出口戦略の選択肢を広げるのです。
まとめ
アフターコロナの環境下でマンション投資を一棟買いで行う場合、需要トレンドの変化をいかに素早く取り込むかが鍵になります。駅近と通信環境へのニーズは依然として強く、設備更新や遮音性強化が賃料アップに直結します。融資と税制優遇を組み合わせた資金計画を立て、長期修繕計画を伴うリスク管理を徹底すれば、キャッシュフローは安定します。最後に、データだけでなく現地の肌感覚を大切にし、主体的に運営改善を続ける姿勢が成功を引き寄せます。今日からできる第一歩として、候補エリアの再開発情報と金融機関の最新融資条件をチェックしてみましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅市場動向調査 2025年版 – https://www.mlit.go.jp
- 不動産経済研究所 新築マンション市場動向 2025年9月 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 総務省 テレワーク人口実態調査 2024年版 – https://www.soumu.go.jp
- 中小企業庁 賃貸住宅エコ改修支援事業 2025年度公募要領 – https://www.chusho.meti.go.jp
- 東京都都市整備局 再開発情報ポータル 2025年9月更新 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp

