アパート経営に興味はあるものの、「何から着手すれば良いか分からない」「自己資金が少なく不安」という声をよく耳にします。特に昨今は空室率の高さや金利動向がニュースで取り上げられ、踏み出せずにいる方も多いでしょう。実は、正しい手順を踏み、2025年度に使える補助金を賢く活用すれば、初期負担を抑えつつ収益性を高めることが可能です。本記事では、物件選びから運営管理までの流れを整理し、最新の補助金情報を交えながら、初心者がつまずきやすいポイントを分かりやすく解説します。
アパート経営の全体像をつかむ
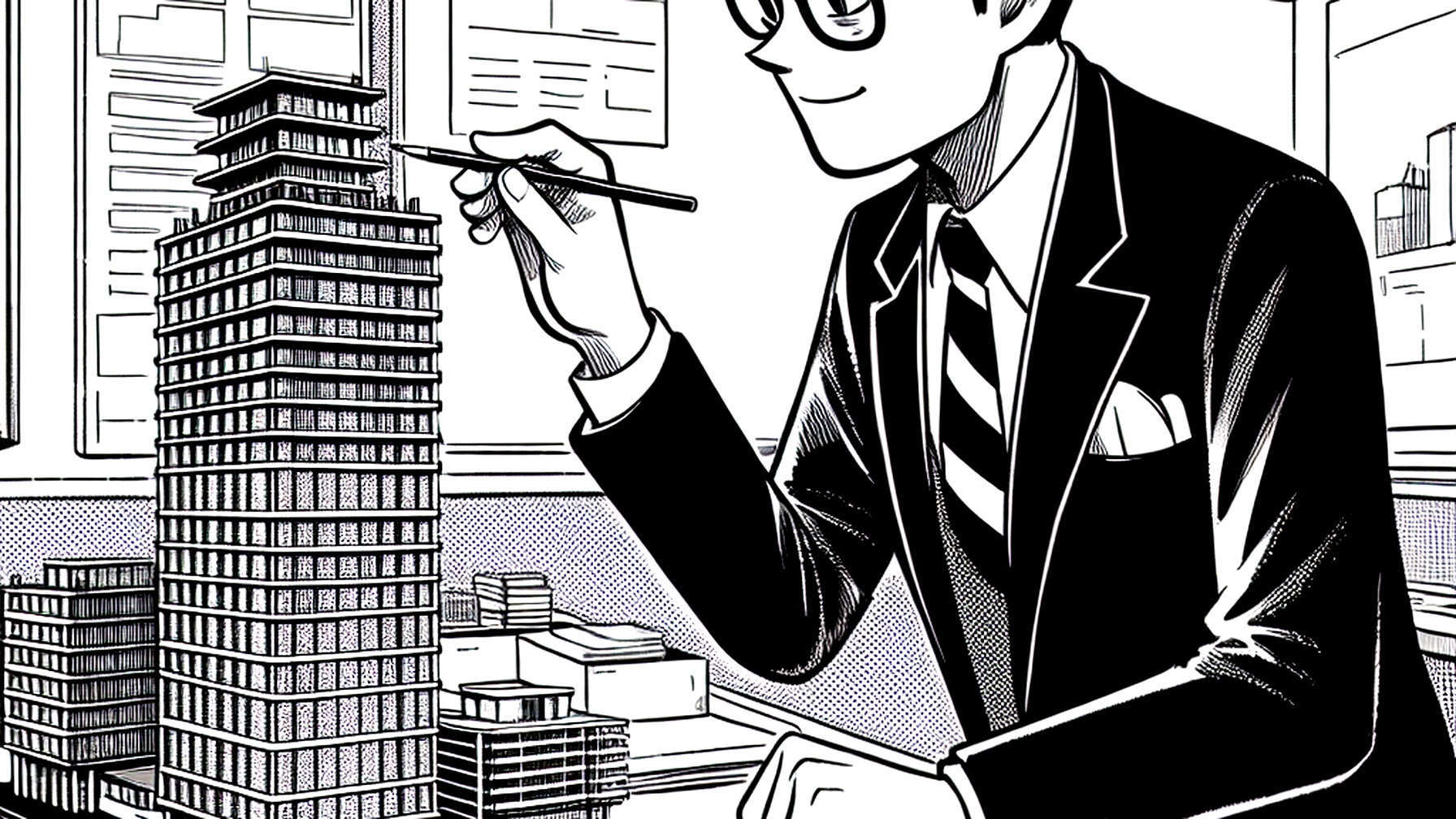
まず押さえておきたいのは、アパート経営が「購入」「運営」「出口戦略」という三つのフェーズで成り立つ点です。この流れを理解せずにスタートすると、思わぬコスト増や運営トラブルに直面しやすくなります。購入段階では立地と利回りのバランスが要であり、運営段階では入居者募集と維持管理が収益の安定性を左右します。最後に出口戦略として、売却時期と方法をあらかじめ設計しておくことで、資産価値を最大化できます。
国土交通省の住宅統計によると、2025年7月時点の全国アパート空室率は21.2%(前年比‐0.3%)です。つまり平均すると5戸に1戸が空いている計算になり、立地とターゲット設定を誤ると即赤字になりかねません。一方で、地方主要駅徒歩圏や大学周辺など需要が底堅いエリアを選べば、空室率を10%以下に抑えられるケースもあります。このように、経営の成否は市場調査の質で大きく変わることを意識しておきましょう。
物件選定から融資取得までのステップ
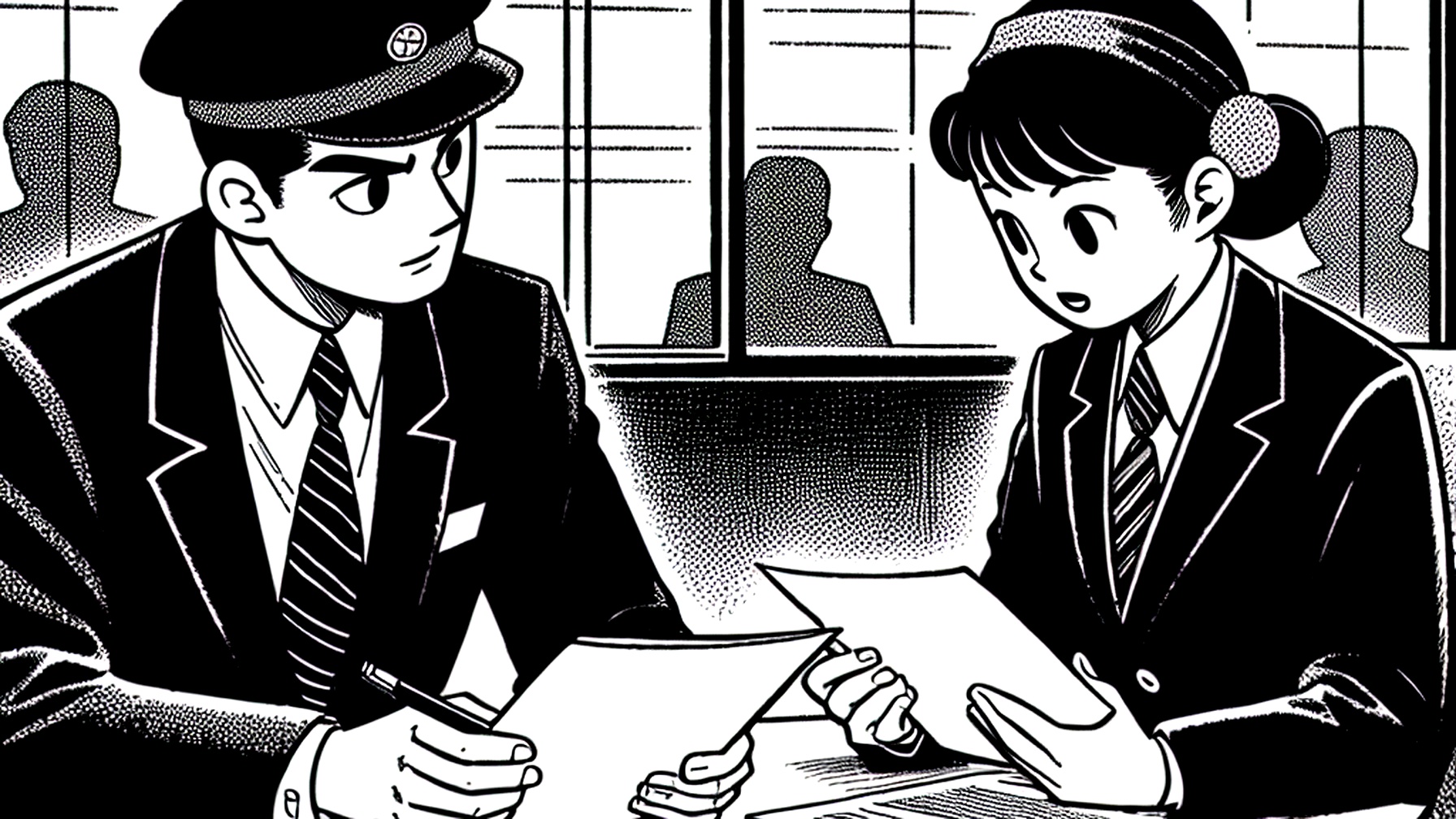
実は、物件探しと並行して融資戦略を立てることが、成功への近道になります。物件を買い付けた後に金融機関へ駆け込むと、審査が長引きチャンスを逃す恐れがあるからです。そこで、以下の三段階を踏むとスムーズです。
1. 自己資金の棚卸し 2. 金融機関の事前ヒアリング 3. 条件に合う物件の絞り込み
自己資金については、物件価格の20〜30%を用意できれば理想的です。これにより金利が0.2〜0.4%低くなるケースが多く、30年返済で見ると総支払額が数百万円縮まります。また、金融機関に事前相談する際は、本人の属性(年収・勤続年数)だけでなく、購入予定物件の収支シミュレーションを提示すると評価が高まります。金利タイプは固定と変動がありますが、2025年9月時点の主要地銀平均は変動1.8%、固定3.1%前後です。金利上昇局面を想定し、返済比率が家賃収入の50%を超えないよう設計すると安全です。
2025年度に使える主な補助金と申請ポイント
ポイントは、国のエネルギー対策と地域創生策を同時に活用することです。2025年度に利用できる代表的な補助金は次の二つです。
・住宅省エネ支援事業2025 ・中小企業省 事業再構築補助金(賃貸住宅の省エネ改修枠)
住宅省エネ支援事業2025では、既存アパートの断熱改修や高効率給湯器の導入に対し、戸当たり上限120万円が交付されます。採択率は過去3年平均で約60%と比較的高く、工事費の2〜3割が賄える点が魅力です。申請の手順は、①登録施工業者による見積もり取得、②オンライン申請、③完了報告の三段階で、最初の見積もりに不備があると審査が3週間以上遅れるため注意が必要です。
一方、事業再構築補助金は、本来中小企業向けですが、法人オーナーが空室を活用してコワーキングスペースへ転用する場合などに活用できます。工事費の最大2/3、上限3,000万円と手厚いものの、ビジネスモデルの革新性が求められ、採択率は30%前後にとどまります。採択されている事例を研究し、地域課題を解決する計画を盛り込むことが鍵となります。
さらに、自治体独自の補助金も見逃せません。たとえば東京都足立区の「賃貸住宅省エネ化推進事業」は、2025年度も継続が決定しており、区内アパートの屋上防水や断熱塗装に対し費用の1/3(上限200万円)が交付されます。自治体の制度は公表から締め切りまでの期間が短い傾向があるため、定期的に公式サイトをチェックする習慣を付けておきましょう。
安定経営を実現する運営管理のコツ
重要なのは、入居率だけでなくキャッシュフロー全体を最適化する視点です。まず家賃設定では、周辺相場の95%程度を初期値とし、入居が決まりやすい状態を作ります。満室化後に2年ごとの更新時に1〜2%の家賃改定を行うと、長期で見ると収益が滑らかに伸びていきます。また、空室対策としては、入居者ターゲットごとに設備投資をメリハリ付けることが有効です。学生向けにはインターネット無料、ファミリー向けには宅配ボックスなど、費用対効果を見極めましょう。
修繕計画では、「10年で外壁、15年で屋上防水、20年で設備総入れ替え」が目安といわれますが、実際には立地の気候条件や建物構造で前後します。国土交通省の長期修繕計画ガイドラインでは、築20年時点で建築費の25〜30%が累積修繕費の平均とされています。補助金を組み合わせれば、この負担を3〜4割減らすことも可能です。資金繰りを安定させるため、家賃収入の月額5%を修繕積立に充当し、想定外の出費に備えると安心です。
補助金を活かした長期リフォーム戦略
実は、補助金は一度きりの活用にとどまりません。同じ物件でも、対象工事が異なれば別年度で再度申請できるケースがあります。たとえば2025年度に窓の断熱改修で住宅省エネ支援事業を利用し、2027年度に屋上太陽光設置で再エントリーするような計画です。こうした長期戦略を立てると、収益改善と物件価値向上を同時に狙えます。
リフォームの優先順位は「収益に直結する改修」を第一に考えると良いでしょう。空室が多い場合は、室内の水回り更新やアクセントクロスで早期満室を図り、その後に共用部や外壁を整える流れが一般的です。補助金を利用する際は、事業完了後に5年間は売却できないなどの制約が付く制度もあるため、出口戦略と矛盾しないか必ず確認してください。施工会社や行政書士と早い段階から情報共有し、申請スケジュールと工事工程を同期させることが、トラブル防止の決め手となります。
まとめ
アパート経営を成功させるには、正確な市場調査、適切な融資戦略、そして補助金を絡めた修繕計画という三本柱が欠かせません。今回紹介した「住宅省エネ支援事業2025」や自治体独自の制度を活用すれば、初期費用を20〜30%減らしながら物件の競争力を高められます。まずは自己資金とターゲットエリアを整理し、金融機関と補助金窓口へ同時にアプローチして情報を集めてみてください。早めの行動が、将来の安定収益と資産形成への第一歩となるはずです。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査(2025年7月版) – https://www.mlit.go.jp
- 環境省 住宅省エネ支援事業2025 公式サイト – https://www.env.go.jp
- 中小企業省 事業再構築補助金 公式サイト – https://jigyou-saikouchiku.go.jp
- 東京都足立区 賃貸住宅省エネ化推進事業 – https://www.city.adachi.tokyo.jp
- 総務省 統計局 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp

