診察や研究に追われる毎日でも、安定した資産形成を図りたいと考える医師は少なくありません。しかし、初めてのアパート経営では想定外の修繕費が収益を圧迫し、思い描いたキャッシュフローが実現しないケースが目立ちます。本記事では、医師ならではの高収入と信用力を生かしつつ、修繕費をコントロールして持続的な不動産収益を得る方法を解説します。読み終えれば、購入前の資金計画から長期のメンテナンス戦略まで、具体的な行動手順が見えるはずです。
なぜ医師にアパート経営が向いているのか
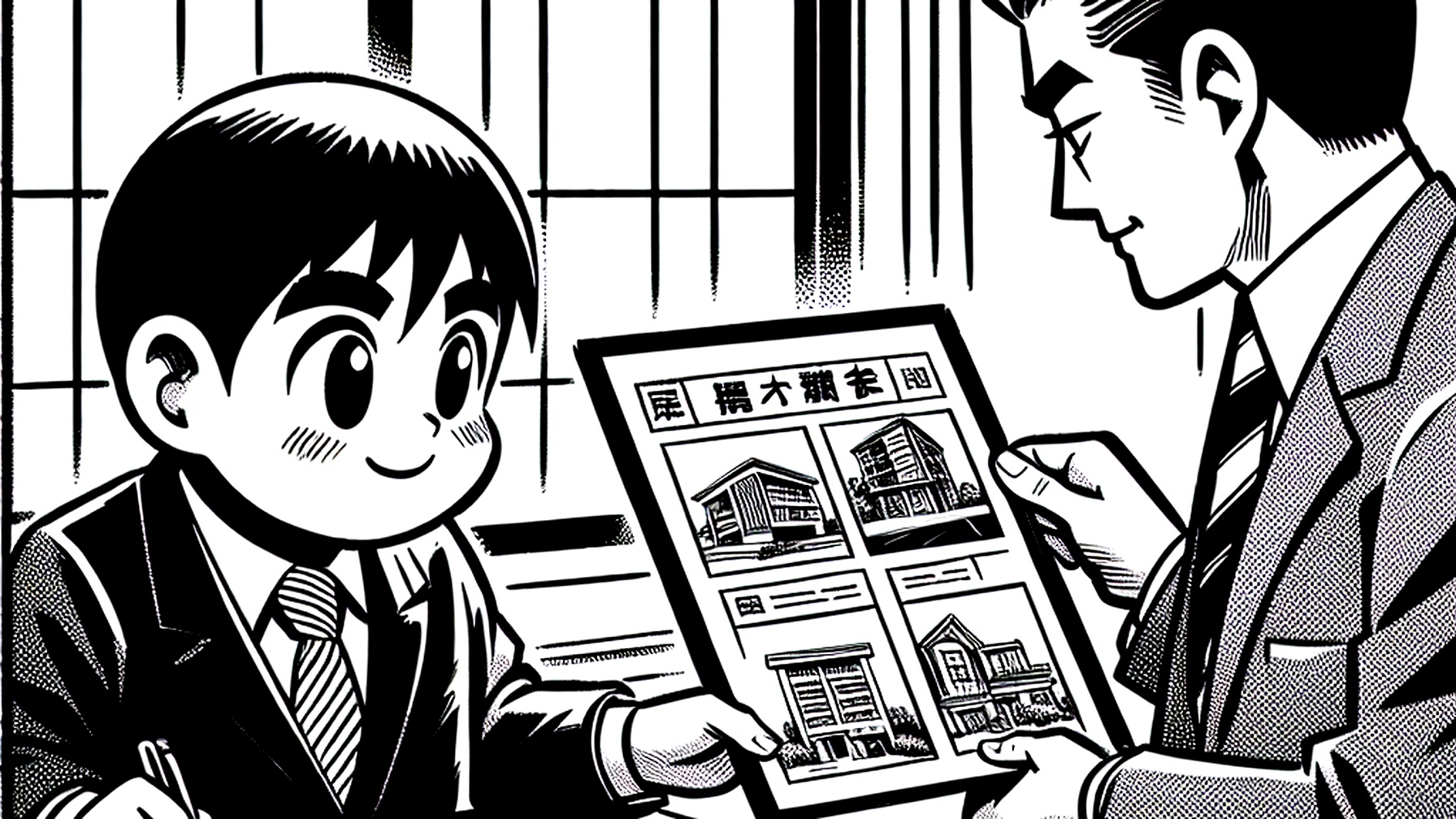
重要なのは、医師が持つ信用力と安定収入が金融機関から高く評価される点です。これにより低金利で長期融資を受けやすく、自己資金を温存しながら規模を拡大できるメリットがあります。
まず医師の平均年収は厚生労働省の統計で1,300万円前後とされ、他業種と比べても段違いです。この収入は返済能力の裏付けとなり、条件の良いローン審査を通過しやすくします。一方で勤務時間が不規則なため、物件管理を外部に委託する必要がありますが、その費用を賄える収入水準があることも強みです。
また医師という職業ブランドは入居者へ安心感を与え、家賃設定を多少高めにできる場合があります。実際、都心の医師オーナー物件では平均賃料が周辺相場比3%高いという東京商工リサーチの2025年調査も報告されています。
しかし、国土交通省の住宅統計によると2025年7月の全国アパート空室率は21.2%で、依然として高水準です。立地選定や物件管理を誤れば、高収入であっても赤字に陥るリスクは避けられません。つまり医師だからこそ、数字に基づく経営判断と綿密な修繕計画が欠かせないのです。
修繕費を見落とさないキャッシュフロー設計
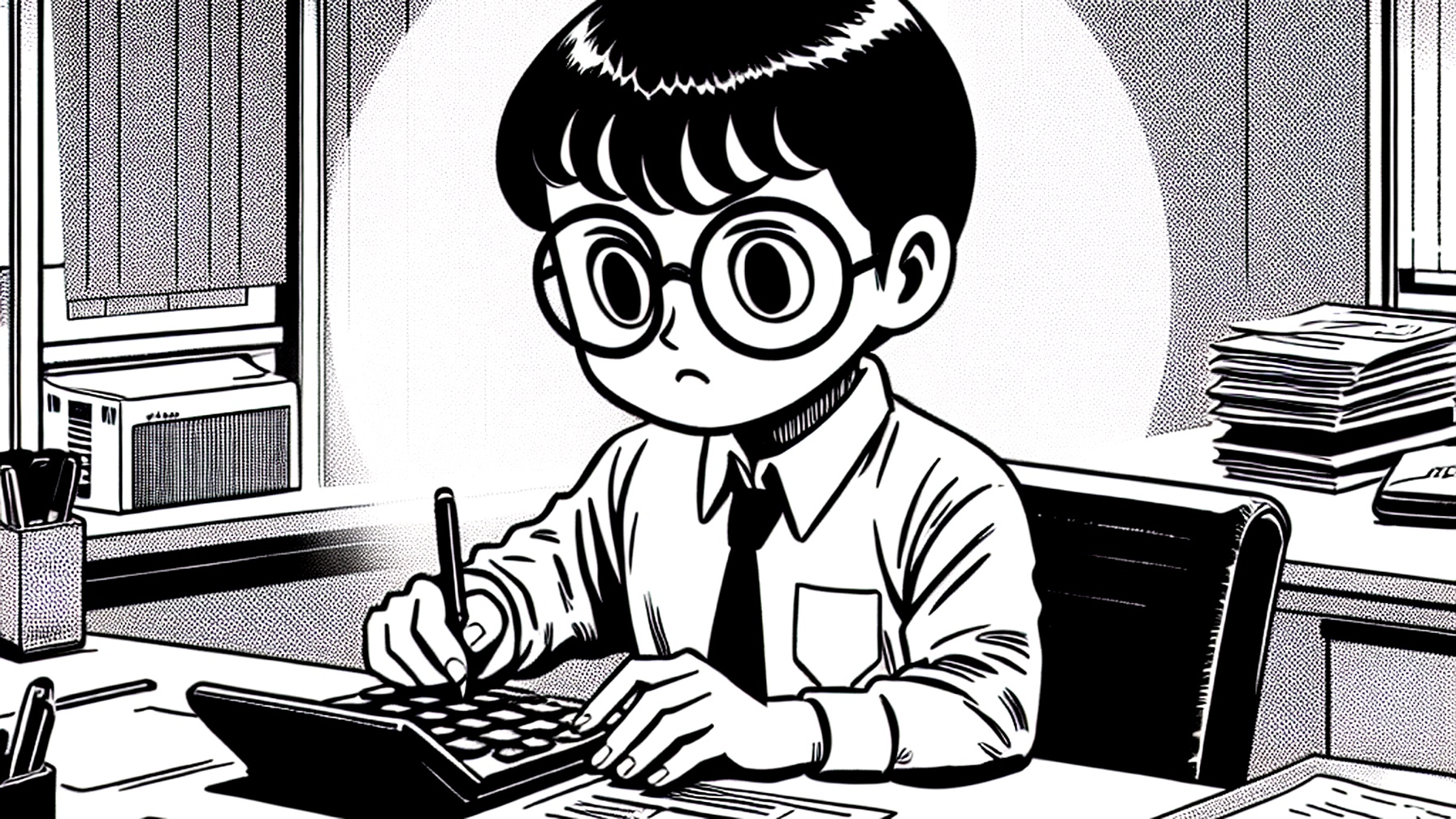
ポイントは、家賃収入の中に計画的な修繕積立を組み込むことです。家賃-ローン返済-管理費だけでは黒字に見えても、数年後の大規模修繕で一気に赤字転落する例が頻発します。
たとえば築20年・木造8室のアパートでは、外壁と屋根の改修に約300万円、給排水管更新に約150万円が発生するのが一般的です。この合計450万円を12年で割ると、年間約37万円、月3万円強を修繕積立として確保しておく必要があります。医療業界の給与振込口座に連動させて別口座へ自動送金すれば、忙しい勤務中でも積立が続きやすい仕組みになります。
さらに、国税庁の耐用年数表を参考にしながら、設備ごとの交換周期を一覧化すると見通しが立てやすくなります。エアコン10年、給湯器13年、屋根・外壁15年など、あらかじめ内部留保を積むことで資金繰りは安定します。
実は修繕費を経費計上するタイミングも重要です。工事内容が資本的支出か修繕費かで税務上の取り扱いが変わり、節税効果が異なります。税理士に工事見積もりを事前相談し、損金算入の可否を確認すると無駄な納税を抑えられます。
医師ならではの融資戦略と税制メリット
まず押さえておきたいのは、医師が利用できる事業性融資の幅広さです。金融庁のガイドライン改定以降、医師の開業資金とアパート経営資金を抱き合わせで提案する地銀が増えました。このパッケージは物件を担保に取るため、金利1.2%前後で固定20年といった好条件が提示されることがあります。
一方で高収入ゆえに高い税率が適用されるため、減価償却費を活用した所得圧縮が大きなメリットになります。木造アパートなら耐用年数22年、鉄骨なら34年ですが、中古物件を購入すれば短縮償却が可能です。所得が1,800万円を超えると税率43%に達する医師にとって、年間200万円の減価償却だけで86万円の税負担軽減効果が見込めます。
また2025年度も継続する「賃貸住宅省エネ改修支援事業」を利用すれば、断熱窓交換や高効率給湯器導入で最大200万円の補助が受けられます。補助金は取得価額から差し引く形になるため、減価償却との二重取りはできませんが、キャッシュアウトを直接減らせる点で資金繰りを楽にします。
つまり医師がアパート経営で実現できるのは、融資条件の優位性と税務効果の両取りです。修繕費を抑える工事をうまく補助金でカバーすれば、さらなる収益向上が期待できます。
長期安定を支える修繕計画の立て方
実は修繕計画を「時間軸」で整理すると、費用が読みやすくなります。新築または購入直後から30年後までを5年刻みで区切り、その期間に発生する工事と概算費用を一枚の表にまとめる方法が効果的です。
作業は専門会社に任せてもよいのですが、医師自身が概要を把握しておくことが肝要です。なぜなら、工事の優先順位を判断する際に医療現場と同様のリスク管理思考が役立つからです。例えば屋根防水を先送りにすると漏水リスクが高まり、数百万円規模の室内補修が後追いで発生する可能性があります。
【修繕計画作成の流れ】
- 建物診断報告書を取得し、劣化状況を数値化
- 部位ごとの残存耐用年数を判定
- 5年ごとの工事項目と費用を一覧表に落とし込む
上記のように工程を区切ることで、毎年のキャッシュフローに与える影響を定量的に把握できます。医療業務で培ったエビデンス重視の姿勢を応用すれば、感覚的な修繕ではなくデータに基づく投資判断が可能になります。
さらに入居者満足度を高める小規模リフォームを計画に織り込んでおくと、空室率低下にもつながります。具体的には共用部のLED照明化やWi-Fi導入で、費用対効果の高い改善が実現します。結果として修繕費が“コスト”から“投資”へと性格を変え、長期の収益最大化に寄与します。
2025年度に活用できる補助制度と注意点
まず知っておきたいのは、補助制度は募集時期と要件が厳格である点です。2025年度の国交省「賃貸住宅省エネ改修支援事業」は、外壁断熱・高性能窓・高効率給湯器のいずれかを含む改修に対し、工事費の3分の1、上限200万円が補助されます。申請は施工前に行い、完了報告までで概ね6か月を要するため、スケジュールの余裕が不可欠です。
一方で、地方自治体が独自に行う「子育て世帯向け空き家活用補助」や「防災改修助成」はエリア限定です。医師が勤務病院近隣で物件を選ぶ場合は、自治体サイトを確認し、重複受給の可否を必ずチェックしましょう。
ただし、補助金を受けると資産価値向上が見込める一方で取得価額が減るため、減価償却費が減少します。税金とキャッシュの総合効果をシミュレーションし、どちらが有利か判断することが大切です。
また金融機関によっては、補助金を含めた総工費ベースで再評価を行い、追加融資枠が縮小するケースも報告されています。融資契約前に担当者へ確認し、後々の資金計画に齟齬が出ないよう注意しましょう。
まとめ
結論として、アパート経営で成功する医師は「修繕費を制する者はキャッシュフローを制する」という原則を徹底しています。高い信用力を背景に好条件の融資を引き出し、減価償却と補助金を駆使して税金と現金流出を抑えつつ、長期的な修繕計画でリスクを低減する姿勢が不可欠です。今日紹介した積立方法や制度活用を実践すれば、忙しい診療の合間でも安定した不動産収益を構築できるはずです。まずは物件選定と同時に30年先までの修繕表を作るところから始めてみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 2025年版 – https://www.mlit.go.jp/
- 厚生労働省 医師・歯科医師・薬剤師統計 2024年 – https://www.mhlw.go.jp/
- 金融庁 事業性融資に関するガイドライン 2025年 – https://www.fsa.go.jp/
- 東京商工リサーチ 賃貸住宅市場動向レポート2025 – https://www.tsr-net.co.jp/
- 国税庁 耐用年数表 令和7年度版 – https://www.nta.go.jp/
- 環境省 省エネ改修補助金案内2025年度 – https://www.env.go.jp/

