不動産投資に興味はあるものの「新築は高くて手が出ない」「築古はリスクが怖い」と悩む方は多いでしょう。実は、適切に選びさえすれば築古物件は高利回りを狙えるうえ、初期投資も抑えられます。本記事では、2025年時点の最新データを基に「収益物件 築古物件 ランキング」を読み解き、初心者が安全に一歩目を踏み出すための視点と手順を解説します。読み終えるころには、物件選びの軸と資金計画のヒントが具体的にイメージできるはずです。
収益物件としての築古物件が注目される背景
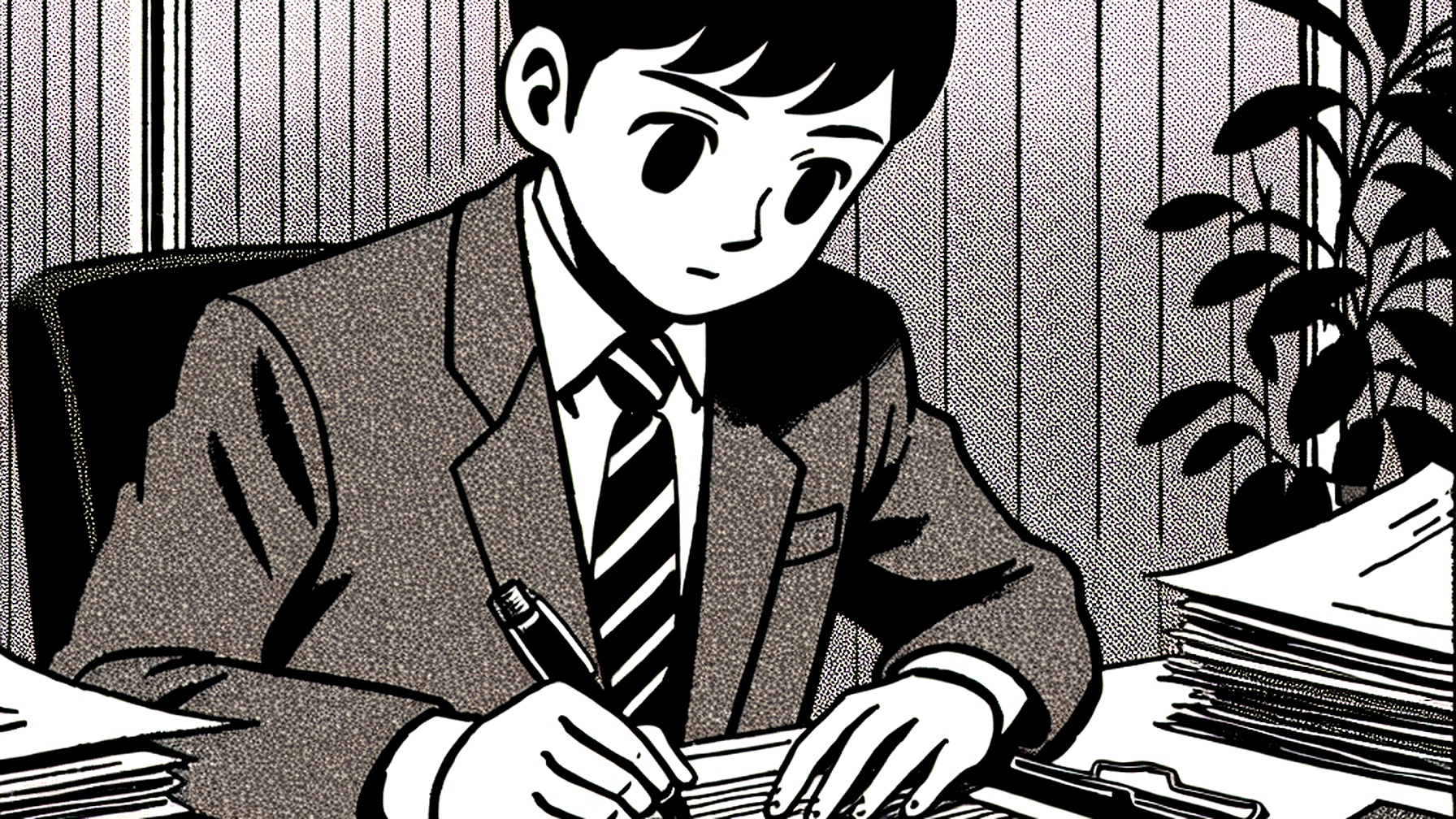
まず押さえておきたいのは、築古物件が投資家から再評価されている理由です。国土交通省の「住宅・土地統計調査」によると、2024年時点で全国の空き家率は13.6%ですが、その多くが築30年以上の戸建やアパートです。数字だけを見ればリスクに映りますが、一方で取得価格が下がっているため、利回りは築浅より2〜3%高い傾向にあります。つまり、適切なエリアとリフォーム戦略を組み合わせれば収益性は十分確保できるのです。
さらに人口が減少している地方でも、医療機関や大学が集中する「小さな都心」は需要が底堅く、築古でも空室率が低い事例が報告されています。リモートワークの定着により、家賃を抑えて広さを求める動きが地方中心部に流れている点も追い風です。加えて、建物価格が減価償却しきった築古は簿価が低いため、将来の売却益が非課税となる長期譲渡所得のメリットを享受しやすい点も見逃せません。
【最新版】築古物件ランキングと選定基準
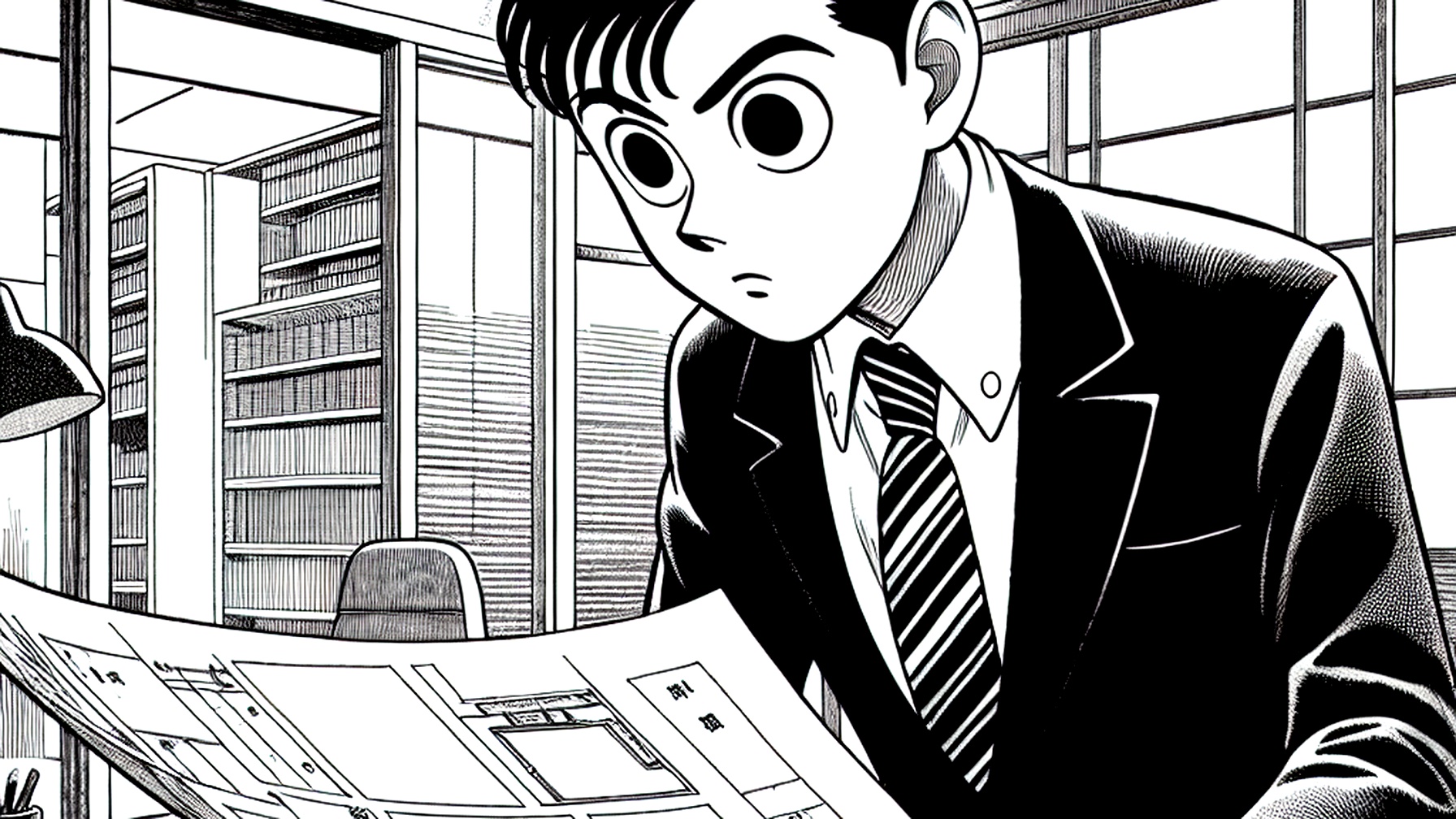
重要なのは、築古物件を一括りにせず“稼げるタイプ”を見極める視点です。ここでは、全国の家賃相場データ(レインズ・2025年6月公表)と公表利回りを組み合わせ、安定度と収益性の両面からランク付けしました。
- 都市近郊の築25〜35年RCマンション区分
- 地方中核市の築30年以上RC一棟
- 政令市郊外の築40年木造アパート
- 郊外駅徒歩圏の築30〜50年戸建
- 中山間地域の築50年以上古民家
最上位は都市近郊のRC区分です。取得価格が下落している一方、駅徒歩10分圏ならファミリー層の需要が底堅く、平均実質利回りは7.2%と安定しています。次いで地方中核市のRC一棟が続きます。地方は敬遠されがちですが、人口20万人以上の市なら家賃下落が緩やかで、土地値も底支え要因となります。下位に位置づけた古民家は再生コストが読みにくく、民泊需要が読めるエリアに限定しないとリスクが高まります。
ランキングを活用する際は「自分の投資目的」と「再投資計画」に合致するかどうかを確認してください。キャッシュフローを重視する場合は利回りトップのRC一棟を検討し、資産性を優先するなら都市近郊区分を選ぶとバランスが取りやすくなります。
築年数と利回りの関係を数字で読む
ポイントは、築年数が進むほど家賃下落が緩やかになる「家賃逓減曲線」の性質です。独立行政法人住宅金融支援機構の2025年度調査では、築20年までに平均家賃は新築比25%下がりますが、築30年を過ぎると下落幅は年1%未満に収束します。一方、物件価格は築25年以降も右肩下がりで、土地値まで落ち込むことも少なくありません。
この価格下落と家賃下落のギャップが利回りを押し上げる要因です。たとえば築32年のRC区分マンションを1,000万円で取得し、年間家賃84万円を確保した場合、表面利回りは8.4%になります。管理費修繕積立金や固定資産税を差し引くと実質利回りは約6.5%ですが、それでも新築区分と比べ1.5〜2倍の水準です。
家賃設定の際は周辺相場だけでなく、内外装の改修内容と設備グレードを必ず比較してください。築古でも宅配ボックスや無料Wi-Fiを導入すれば、家賃維持に寄与し、空室期間の短縮にもつながります。また、保守的なシナリオとして空室率15%・修繕費年間家賃の10%でシミュレーションし、赤字にならないか確認することが安全策となります。
2025年度のリフォーム補助金と税制を活用する方法
実は、2025年度は築古物件のバリューアップに使える補助金が拡充されています。国土交通省の「住宅エコリフォーム推進事業(2023年開始・2025年度継続)」では、既存住宅の断熱改修や高効率給湯器の導入に対し上限60万円が交付されます。条件は、所有者または賃貸オーナーが性能向上を伴うリフォームを行うことです。
また、中小企業庁が管轄する「省エネ投資促進税制(2025年度)」を利用すると、高効率空調やLED照明への投資額の10%相当を税額控除できます。住宅用設備も対象に含まれるため、アパート共用部の照明改善は狙い目です。
耐震補強については、自治体ごとに補助上限が異なりますが、東京都は木造住宅で最大150万円、地方都市でも50〜100万円のメニューが一般的です。断熱と耐震を同時に行うと、物件価値を押し上げるだけでなく保険料割引も受けられる場合があります。
補助金を申請する際は「交付決定前に工事契約をしない」ことが鉄則です。契約を先行させると交付対象外となるため、スケジュール管理を事前に行いましょう。さらに、金融機関に提出する収支計画書に補助金額を反映させることで、融資条件が有利になるケースもあります。
空室リスクを抑える運営と出口戦略
まず、長期保有を前提にしても「出口戦略」を早期に描くことが欠かせません。築古物件は修繕周期が短くなるため、10年後に再販するのか、土地活用へシフトするのかで運営方針が変わります。
運営面では、賃貸借契約の更新料や駐車場収入など“隠れキャッシュフロー”を確保すると安定度が増します。特に地方RC一棟は敷地に余裕があるため、EV充電設備を設置し月極利用料を取る例が増えています。環境省の「EV充電インフラ導入促進事業」は2025年度も継続予定で、補助率は設備費・工事費の2分の1です。
空室対策として、ターゲットをファミリー・シニア・外国人と細分化し、それぞれのニーズに合わせたリフォームを実施する方法が有効です。たとえば、ファミリー向けにワークスペースを設置すると在宅勤務層の支持を得やすくなります。外国人居住者には多言語対応の家電マニュアルを備えるだけでも募集効率が上がります。
出口として売却を選ぶ場合、「築40年以内」「耐震補強済み」「エリア家賃が下げ止まり」という条件を満たすと、REITや買取再販業者のニーズが期待できます。売却益を次の投資に回しポートフォリオを拡大することで、複利的に資産を増やすことができるでしょう。
まとめ
築古物件は確かに修繕リスクを伴いますが、取得価格の安さと家賃下落の鈍化が生む高利回りは大きな魅力です。都市近郊と地方中核市を中心に物件タイプを比較し、補助金や税制を活用すれば、初期投資を抑えながら価値を高めることができます。次の休日には、ランキング上位エリアを実際に歩き、管理会社やリフォーム業者と面談してみてください。行動を起こすことで、数字だけでは見えない収益の手触りを掴めるはずです。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅・土地統計調査(2025年版) – https://www.mlit.go.jp
- レインズ マーケットインフォメーション(2025年6月公開データ) – https://www.reins.or.jp
- 住宅金融支援機構 住宅市場動向調査(2025) – https://www.jhf.go.jp
- 中小企業庁 省エネ投資促進税制(2025年度版) – https://www.chusho.meti.go.jp
- 環境省 EV充電インフラ導入促進事業(2025年度) – https://www.env.go.jp

