不動産投資に興味はあるものの、「本当に資産は増えるのか」「相続税を抑えられるのか」と不安を抱く方は少なくありません。特にアパート経営はまとまった資金が必要なため、一歩を踏み出せずに情報収集だけで終わるケースも多いです。しかし正しい知識を押さえれば、家賃収入で資産を育てつつ、将来の相続にも備えられます。本記事ではアパート経営を軸に、資産形成と相続対策を両立させる方法を基礎から解説します。
アパート経営が資産形成に向く理由
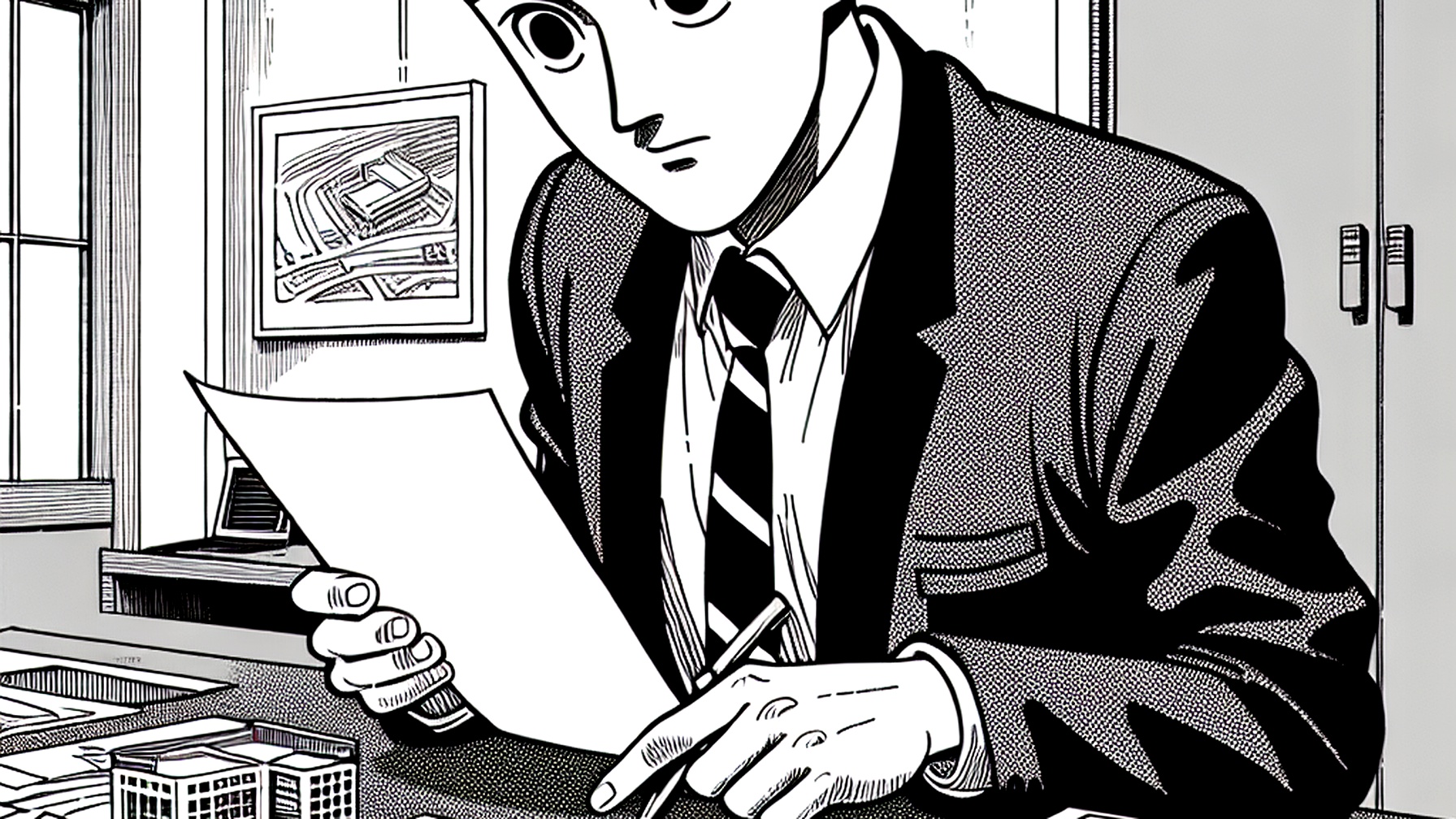
まず押さえておきたいのは、アパート経営が「定期的な現金収入」と「資産価値の維持」という二つの面で優れている点です。家賃収入は株式配当よりも変動が緩やかで、長期的な計画を立てやすい特徴があります。
国土交通省の住宅統計によると、2025年8月時点の全国アパート空室率は21.2%で、前年より0.3ポイント改善しました。都心部や主要地方都市では15%前後まで低下しており、需要が底堅いことが読み取れます。つまり適切な立地を選べば、安定収益を得られる土台が整っていると言えます。
さらに不動産はインフレと連動しやすい資産です。物価が緩やかに上がる局面では家賃も同調しやすく、現金のみで保有するより購買力を保ちやすい利点があります。また、賃貸物件は評価額が路線価で算定されるため、市場価格より低く評価されやすく、後述する相続税の軽減にも直結します。
一方でリスクがゼロではありません。空室の長期化や修繕費の増大は収益性を圧迫します。したがって物件選定の精度と運営の工夫が、資産形成のスピードを決定づけるポイントになります。
資産形成を加速させるキャッシュフロー管理
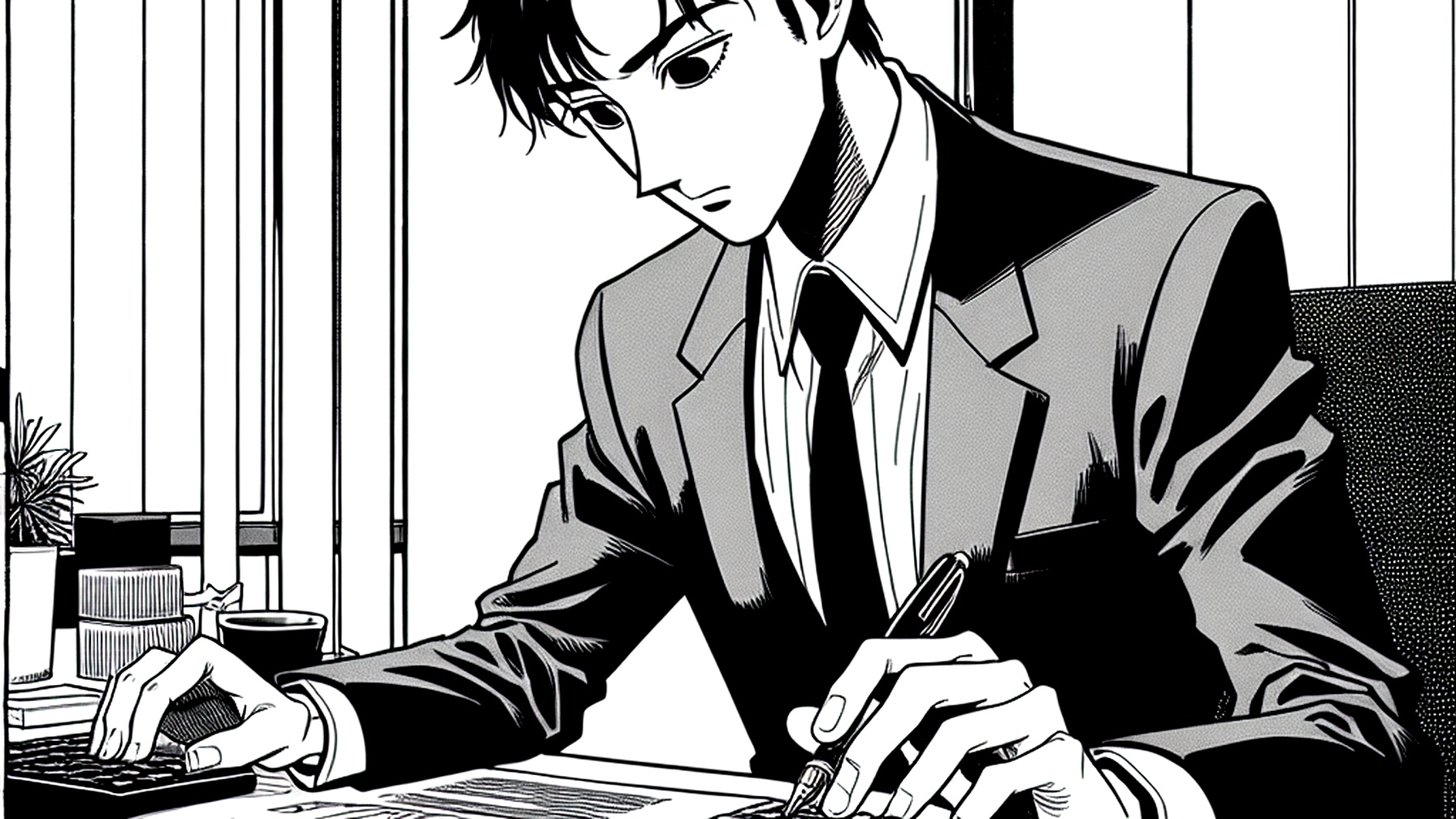
重要なのは、家賃収入から支出を引いた「手残り」を常に把握することです。表面利回りが高く見えても、管理費や修繕積立を差し引けば実質利回りが大幅に下がる場合があります。
まず毎月の返済額は家賃収入の50〜60%以内に抑えると、空室が発生しても資金繰りが安定します。この比率は金融機関の融資審査でも重視されており、繰上げ返済を行う際の判断基準にもなります。また、修繕費として年間家賃収入の10%程度を前もって積み立てておくと、大規模修繕のタイミングで慌てずに済みます。
キャッシュフロー表を作る際は、楽観シナリオと同時に「空室率25%」「金利上昇1.5%」といった保守的な条件も盛り込むと、想定外の状況にも対応しやすくなります。実はこのシミュレーションを定期的に更新することで、保有資産全体の健全度が可視化され、買い増しや売却の判断を迅速に下せます。
さらに2025年度の所得税法では、建物減価償却費を損益計算に組み込めるため、帳簿上の赤字を他の所得と損益通算し、所得税を節税することも可能です。こうして手取りを増やしたうえで、次の投資資金へ再投下すれば、複利効果で資産形成を加速できます。
相続対策としてのアパート活用法
実はアパート経営は、相続税評価額を圧縮できる資産として高い人気があります。現金1億円を保有したまま相続すれば、そのまま課税対象になりますが、同額でアパートを建築した場合、貸家建付地の評価減や借家権の控除が適用され、評価額が60%程度に下がることも珍しくありません。
2025年度の税制では、基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人」が維持されています。とはいえ地価が高い都市部では控除枠を超えるケースが多く、資産圧縮効果の大きいアパートは依然として有効な選択肢です。一方で、過大な借入れは相続人の負担を重くする可能性があります。したがって借入期間や金利の見直しを含め、家族全体で返済計画を共有することが不可欠です。
また、2025年度から導入された「相続時精算課税制度の電子申告簡素化」により、贈与と相続の一体的な管理がしやすくなりました。生前にアパートの持分を少しずつ贈与し、将来の相続税負担を分散する手法も検討の余地があります。ただし制度選択は専門家のアドバイスを受け、贈与税と相続税の比較を行ったうえで最適化を図ることが重要です。
最後に忘れてはならないのが、遺言書の整備です。共有持分が増えるほど運営方針がまとまりにくくなり、トラブルが起こりやすくなります。信託の活用や遺言執行者の指定を通じて、物件管理の権限を明確にしておくと、相続開始後もスムーズな運営が可能になります。
2025年度の税制と公的支援で押さえたいポイント
ポイントは「確定している優遇策だけを活用する」ことです。不透明な制度改正を当てにすると、資金計画が狂う恐れがあります。2025年度に有効な主な支援策は次のとおりです。
- 登録免許税の軽減措置(2026年3月31日取得分まで)
- 住宅取得等資金贈与の非課税特例(2027年12月31日贈与分まで、一般住宅1,000万円上限)
- 省エネ性能向上リフォームの固定資産税減額(翌年度分1/3減額、築年数不問)
登記費用や贈与税の負担を抑えるこれらの制度は、アパート経営にも適用可能です。たとえば親から贈与を受けた資金で耐震補強を行えば、入居者募集に有利になるだけでなく、固定資産税も軽減できます。
また、金融機関の融資姿勢にも注目です。日本銀行のマイナス金利政策は2025年10月現在も維持されており、変動金利型ローンは1%前後が主流です。ただし、将来の金利上昇リスクに備え、固定金利へ切り替えるタイミングを検討する余地はあります。融資契約時に「当初固定10年、その後変動へ自動切替」といった条項を確認し、返済額の変動幅を把握しておくと安心です。
成功する物件選びと長期運営のコツ
まず押さえておきたいのは、「立地こそがリスク管理の最大要素」という事実です。都心部は価格が高いものの、人口流入が続く限り空室率が低く、賃料下落も限定的です。一方、郊外は土地値が安く利回りが高く見えますが、長期的な人口減少リスクが大きく、出口戦略が難しくなる傾向があります。
物件を選ぶ際は、駅徒歩10分以内かつ築25年以内を目安にすると、空室リスクを最小化できます。築年数が古い場合でも、配管や屋根を改修済みであれば、修繕コストを抑えながら運営期間を延ばせます。リノベーション費用が家賃アップにつながるかを試算し、投資回収期間を5〜7年以内に設定すると収益性を評価しやすくなります。
運営段階では、入居者とのコミュニケーションが意外に効果的です。小規模なアンケートを実施し、「宅配ボックスの設置」「インターネット無料化」などニーズを拾い上げると、競合物件との差別化になります。これらの設備投資は一室あたり2,000〜3,000円の家賃アップに直結する事例が多く、投資回収も早いです。
最後に出口戦略です。日本不動産研究所のデータでは、築30年超の木造アパート価格は築15年比で約40%下落しています。したがって大規模修繕を行う前に、売却益と修繕後家賃の増加分を比較し、どちらがキャッシュフローに寄与するか検討することが不可欠です。ここまでをトータルで管理できれば、アパート経営は資産形成と相続対策を両立させる強力な手段になります。
まとめ
本記事ではアパート経営が資産形成と相続対策の両面で効果的な理由を解説しました。家賃収入による現金の積み上げと、相続税評価額の圧縮が同時に狙える点が最大の魅力です。空室リスクを抑える立地選び、キャッシュフローを守る資金計画、そして2025年度税制を活用した節税策を組み合わせれば、安定した資産拡大曲線を描けます。まずは試算表を作成し、専門家とともに長期シナリオを組み立てる行動から始めてみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 – https://www.mlit.go.jp
- 財務省 税制改正概要2025 – https://www.mof.go.jp
- 日本銀行 金融政策決定会合議事要旨 – https://www.boj.or.jp
- 日本不動産研究所 不動産価格指数 – https://www.reinet.or.jp
- 総務省 相続税・贈与税統計 – https://www.soumu.go.jp

