不動産価格の上昇や相続税の強化で、「このまま現金だけで資産を持ち続けて大丈夫か」と不安に感じる人が増えています。特にアパート経営は、安定収入を得ながら相続税評価額を下げる手段として注目されています。しかし、空室リスクや資金繰りの難しさを聞くと一歩を踏み出せないのも事実です。本記事では、最新のデータを交えながら「アパート経営 相続対策 資産形成」を同時に進める方法を解説します。読み終える頃には、自分に合った投資戦略と初期行動が見えてくるはずです。
アパート経営が相続対策になる理由
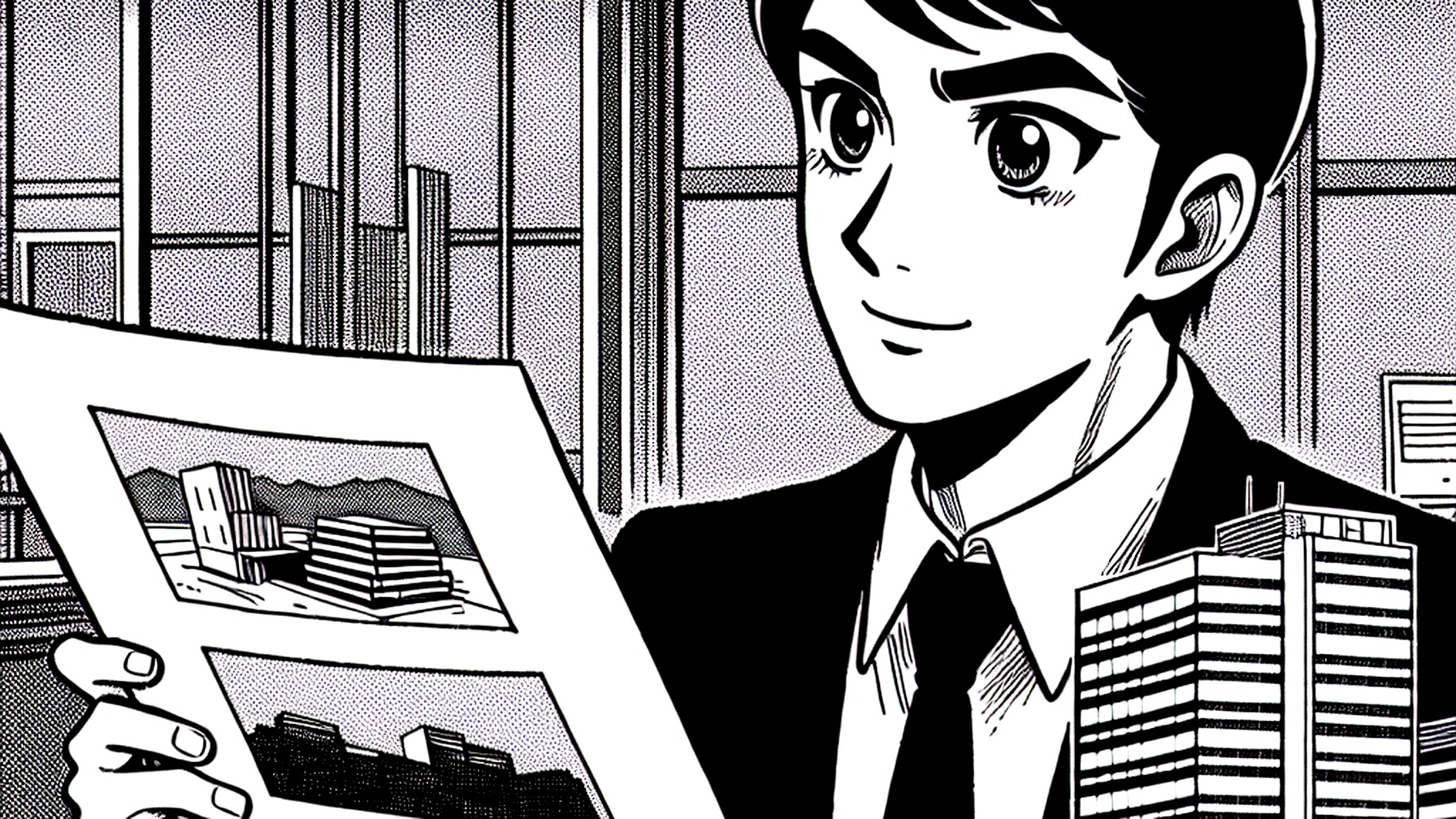
重要なのは、賃貸用不動産が相続税評価額を圧縮できる点です。土地は「路線価方式」で市場価格の八割前後、建物は「固定資産税評価額」で新築価格の五割程度になるため、同じ三千万円の現金より課税対象額が小さくなります。
まず、現金三千万円を相続すると基礎控除を超えた部分がそのまま課税対象です。一方で、三千万円を自己資金にアパートを建て、総額一億円の物件を取得した場合、評価額は土地建物合わせて約六千万円に下がります。つまり、実際の資産規模を拡大しながら課税対象額を抑えられるわけです。
さらに、小規模宅地等の特例が有効であれば、賃貸部分の土地評価額は五〇%減額されます。この特例は2025年度も継続しており、賃貸経営を続ける限り適用が可能です。ただし、相続開始前三年以内に取得した物件は対象外になる場合があるため、早めの準備が欠かせません。
一方で、形だけの節税を狙い高額物件を購入すると資金繰りが破綻し、相続人が売却を迫られるケースもあります。相続対策としてのアパート経営は、収益性と融資返済計画が両立してこそ効果を発揮すると覚えておきましょう。
資産形成につながる収益モデル
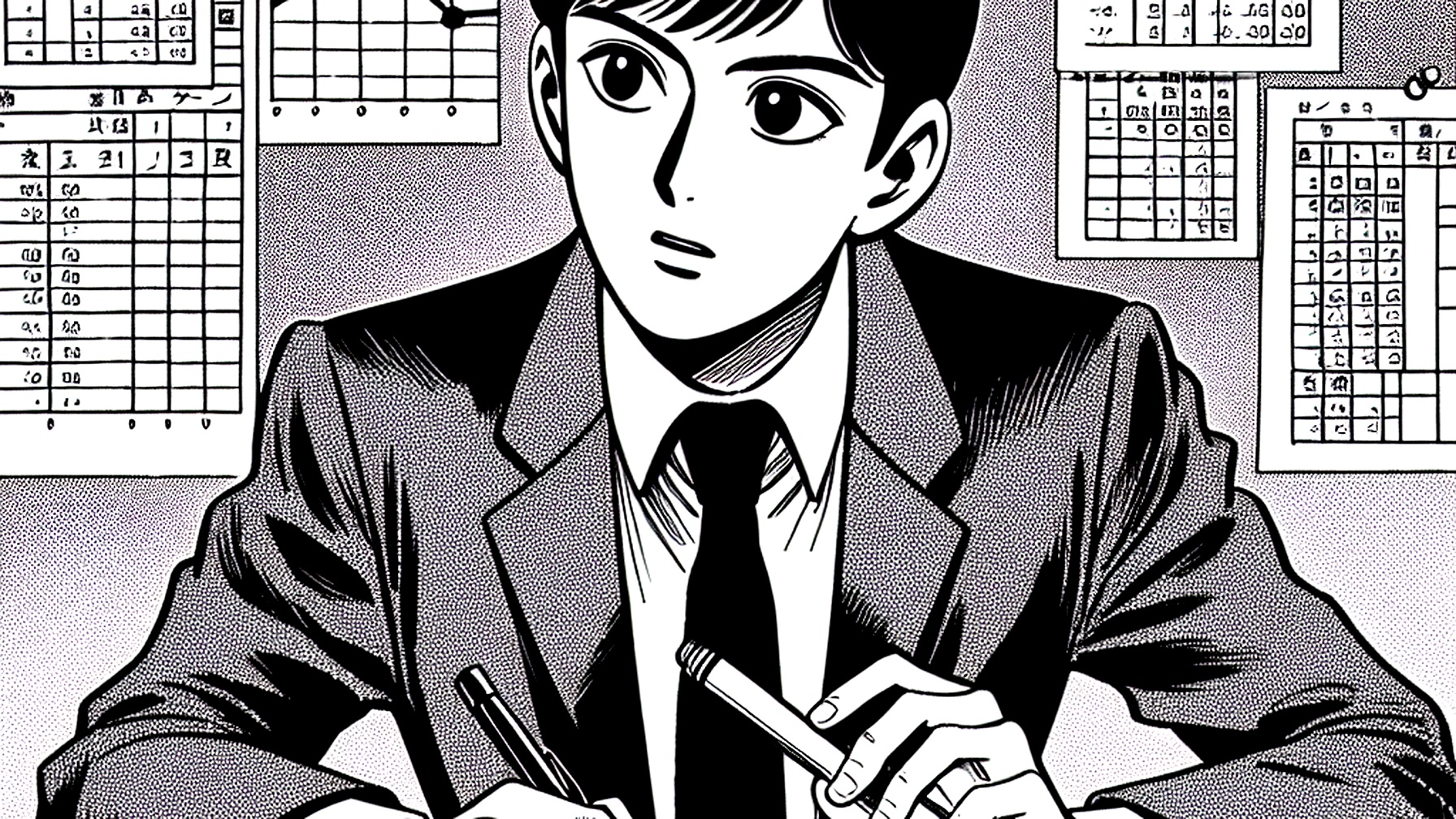
ポイントは、キャッシュフローと物件価値の両面で資産を増やす設計です。国土交通省の2025年8月調査では全国アパート空室率が21.2%ですが、都市中心部は10%台前半にとどまっています。立地と間取りを選べば、家賃収入でローン返済と維持費をまかないつつ手残りを生み出せます。
実は、家賃収入だけでなく減価償却による「帳簿上の赤字」が所得税を圧縮し、手取りを増やす効果もあります。例えば一億円の木造アパートなら、建物部分約七千万円を22年で償却できます。毎年三百万円強の非現金費用が発生するため、課税所得が抑えられ、その分を再投資に回せるのです。
また、アパート経営はインフレ耐性が高い資産です。インフレで建築費や土地価格が上がれば、新規供給は鈍り、既存アパートの相対価値が向上します。家賃の上限には賃借人保護の制約がありますが、長期的には物価上昇と連動しやすく、現金より購買力が維持されやすいのが特徴です。
最後に、資産形成を加速させる再投資サイクルを考えましょう。手残りを修繕積立と次の頭金に振り向けることで、五年ごとに追加物件を取得する投資家もいます。複数棟を持つとリスク分散が進み、売却益と家賃収入の両方で資産が雪だるま式に増えていきます。
2025年度の税制と最新データの読み解き
まず押さえておきたいのは、2025年度税制改正でインボイス制度への対応が猶予期間を終えた点です。年間売上一千万円以下でも適格請求書発行の可否が家賃管理会社選びに影響するため、免税事業者オーナーは要確認です。
一方、減価償却制度や小規模宅地等の特例は大枠が維持されています。ただし、資本金一億円超の法人所有物件に対する外形標準課税強化が検討されており、法人スキームで節税を図る際は顧問税理士と早めにシミュレーションすることが必須です。
さらに、国交省は2025年度「賃貸住宅省エネ改修補助金」を継続します。既存アパートの断熱強化や高効率給湯器導入に対し、工事費の三分の一(上限二百万円)が補助されるため、空室対策と修繕費の軽減を同時に狙えます。期限は2026年3月末の工事完了分までなので、応募スケジュールを物件購入計画と合わせて考えると効果的です。
最新データを活かすには地域ごとの空室率を確認することが大切です。たとえば東京都23区の空室率は2025年8月時点で11.8%、対して北関東主要三県の平均は24%を超えています。同じ利回りでも立地によりリスクが大きく異なると理解し、想定空室率をエリア平均+5ポイントで試算するなど、保守的な収支計画を立てましょう。
初心者が押さえるべきリスク管理
実は、多くの失敗例は「資金ショート」と「管理体制の不備」に集約されます。フルローンで購入し、金利上昇や空室が続くと数カ月で手元資金が尽きるケースは珍しくありません。自己資金は物件価格の二割、さらに家賃三カ月分の運営予備費を別口座に確保することが基本です。
また、長期融資を受ける際は金利タイプに注目です。固定金利は返済計画が読みやすく、インフレ期に有利ですが、初期金利が高めです。一方、変動金利は低金利のメリットがありますが、日銀の金融正常化が進めば二%程度の上昇も視野に入ります。金利上昇一%で返済額がどれだけ増えるか、事前に試算しておくと安心です。
管理会社選びもリスクコントロールの要です。賃料送金サイトの導入や24時間トラブル窓口の有無で、入居者満足度と退去率が大きく変わります。管理委託料は家賃の五%前後が相場ですが、単に料率で比較せず、空室対策の提案力や修繕計画の透明性をチェックしましょう。
最後に、出口戦略を決めておくことがリスク低減につながります。築十五年を超えた時点で大規模修繕か売却かを選択すると、資金繰りが読みやすくなります。売却益にかかる譲渡所得税は保有五年超で長期譲渡となり、2025年度税率は一五%(住民税含め二〇%)に下がるため、タイミングを意識するとネットリターンが変わります。
まとめ
アパート経営は、相続税評価を抑えつつ定期的な家賃収入で資産を拡大できる魅力的な手段です。立地と収支計画を慎重に練り、税制や補助金の最新情報を活用すれば、節税とキャッシュフローを同時に最適化できます。一方で、金利上昇や空室リスクに備えた資金管理と、信頼できる管理会社の選定が成功の鍵です。まずは試算表を作り、自己資金と融資条件を把握するところから始めてみましょう。準備を怠らなければ、「アパート経営 相続対策 資産形成」を一歩ずつ着実に実現できます。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅局「住宅市場動向調査2025」- https://www.mlit.go.jp
- 国税庁「令和7年度(2025年度)相続税法令集」- https://www.nta.go.jp
- 総務省統計局「家計調査年報2025」- https://www.stat.go.jp
- 金融庁「金融レポート2025」- https://www.fsa.go.jp
- 独立行政法人住宅金融支援機構「賃貸住宅融資の現状 2025」- https://www.jhf.go.jp

