投資用のワンルームを買ってみたいものの、「本当に資産形成になるのか」「利回りが低いと意味がないのでは」と迷っている人は多いでしょう。実際に私の相談窓口でも、数字の読み方が分からず一歩を踏み出せないケースが目立ちます。本記事では、利回りの基本からキャッシュフローの考え方、2025年度に使える制度までを順序立てて解説します。読了後には、自分に合った投資目線を持ち、堅実に資産形成へつなげる方法が分かるはずです。なお、専門用語は丁寧に説明するので、初めての人でも安心して読み進めてください。
利回りを正しく理解することが第一歩
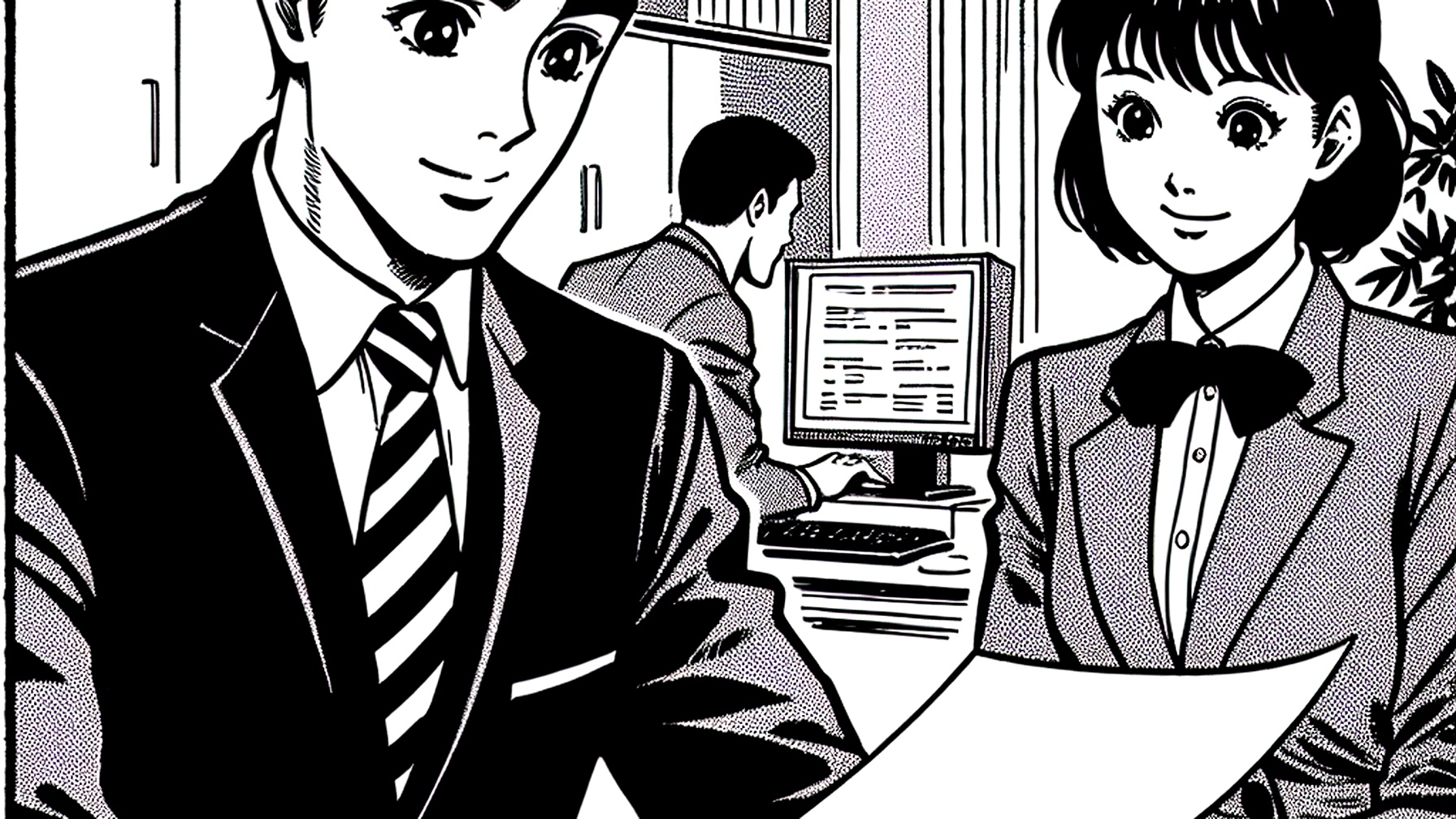
まず押さえておきたいのは、利回りとは投資額に対してどれだけの収益を得られるかを示す指標だという点です。表面利回りと実質利回りの違いを理解しなければ、本当の収益性を見誤ります。
表面利回りは年間家賃収入を物件価格で割った単純な数字です。日本不動産研究所の調査によると、2025年10月時点で東京23区のワンルーム平均は4.2%となっています。一方で修繕積立金や管理費、固定資産税を差し引いた実質利回りは、多くの場合で1〜1.5ポイント低下します。つまり表面だけを見て高いと思っても、手元に残る現金は想像より少ないことが多いわけです。
さらに、利回りはリスクとセットで考える必要があります。都心部は利回りが低めでも空室リスクが小さく、長期的な価格下落も限定的です。これに対して郊外や築古物件は表面利回りが高く見えても、入居付けや修繕でコストがかさむことがあります。重要なのは利回りという数字を鵜呑みにせず、リスク調整後のリターンを見つめる姿勢です。
ここで一度、自身の投資目的を確認しておきましょう。安定収益を求めるなら低利回り・低リスクを選ぶのも有効ですし、積極的な資産拡大を狙うならリノベーションで利回りを上げる戦略もあります。目的と利回りのバランスが投資成績を左右する核心だといえます。
キャッシュフローこそ資産形成のエンジン
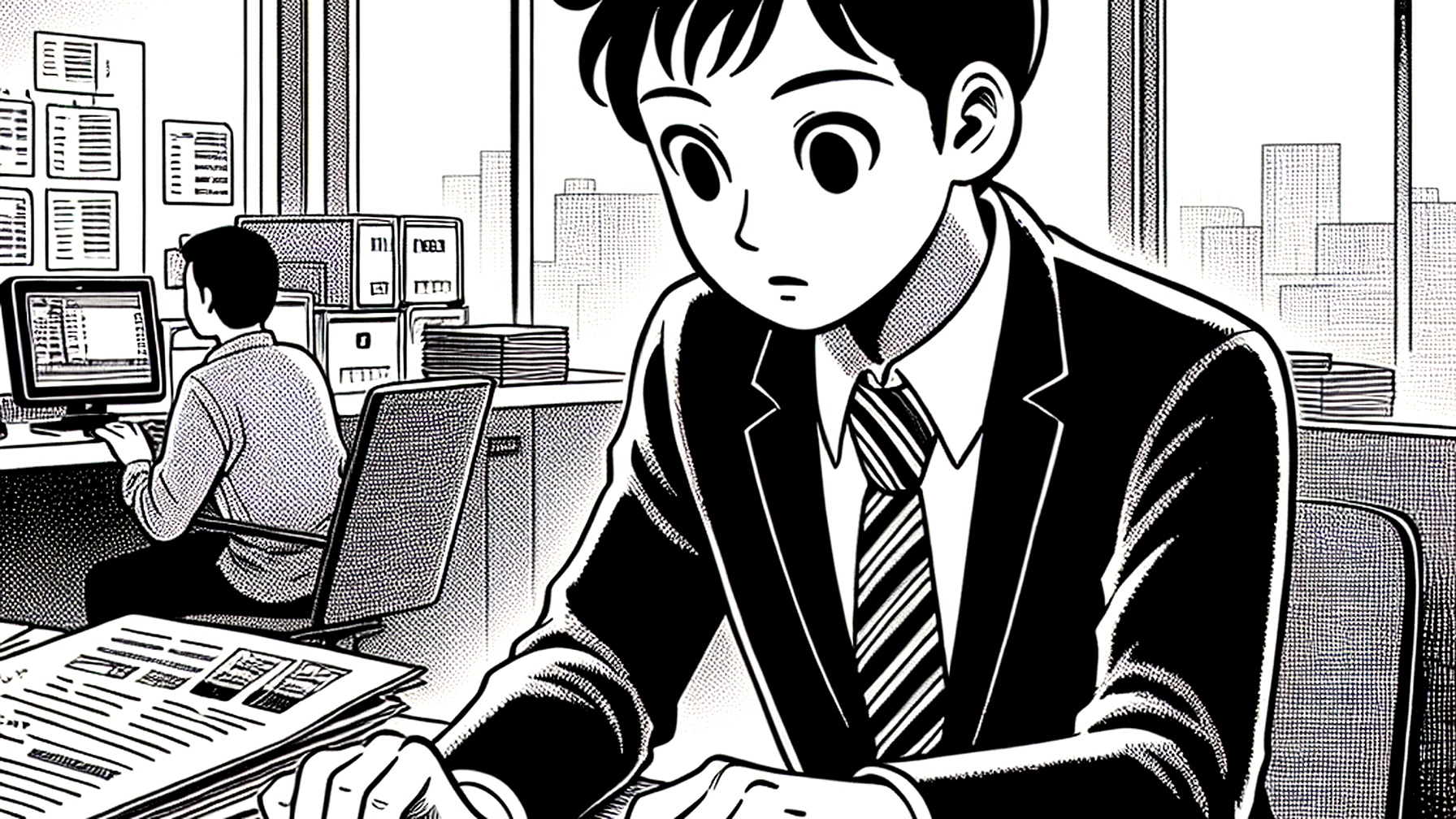
ポイントは、利回りよりもキャッシュフロー(手残り現金)の継続性が資産形成を左右するという事実です。毎月の家賃が安定して銀行口座に残る仕組みを構築できれば、複利のように資産が増えていきます。
家賃収入からローン返済、税金、管理費を差し引いた後に残るお金がキャッシュフローです。例えば2,500万円のワンルームを金利1.8%・35年で購入し、家賃が月8万円なら、東京23区平均の4.2%表面利回りに近い設定です。ここからローン返済6.7万円、管理費1万円、固定資産税0.5万円を引くと、月の手残りはわずか0.8万円になります。言い換えると、実質利回りは1.5%程度に下がるものの、黒字を維持できれば自己資金は徐々に回収されます。
一方で空室期間が2カ月続けば、年間の収支は一気に赤字へ傾きます。そのため入居者ターゲットを具体的にイメージし、駅距離や設備の充実度を吟味することが欠かせません。また、将来的な家賃下落も織り込むべきです。国土交通省の賃貸住宅市場データでは、築20年を超えると家賃は平均で新築時の85%まで低下します。この数字を前提にシミュレーションをバッファ付きで設計すれば、資産形成はより着実になります。
さらに、キャッシュフローを再投資に回すことでポートフォリオを拡大できます。ローン残高が減るにつれて融資枠が空き、追加購入の交渉がしやすくなるためです。複数物件へ分散できれば、空室リスクや修繕リスクを平準化でき、資産形成の土台が一段と強固になります。
投資戦略別に利回りを高める実務
実は、同じ利回りでも戦略次第でリスクとリターンのバランスは大きく変わります。ここでは代表的な三つの手法を紹介し、それぞれの特徴を解説します。
まず、築浅区分マンションを長期保有する「インカム型」は、利回りは3〜4%と低めですが、管理が容易で金融機関の評価も高い点が魅力です。家賃下落も緩やかで、将来的に売却しても値崩れしにくい傾向があります。加えて、一般的に修繕積立金が計画的に増額されるため、突発的な費用が少ないというメリットも見逃せません。
次に、築古物件を購入してリノベーションを行い、家賃を引き上げる「バリューアップ型」があります。この方法では投資初期に500万円程度の改装費を投入するケースが多いものの、入居者ターゲットを絞り込めば表面利回りを2ポイントほど上乗せできます。ただし工事リスクと工期リスクがあるため、工務店との詳細な工程管理が不可欠です。
最後に、複数の木造アパートを一棟ごと取得して管理会社に運営を委託する「規模拡大型」があります。東京23区平均で5.1%の表面利回りが狙え、土地値も割合として多く含まれるため担保評価が高く出る点が特長です。一方で空室や退去時の一括修繕費がキャッシュフローを圧迫しやすいので、入居者属性の分散を意識した部屋づくりが重要です。
これら三つの戦略は、自己資金やリスク許容度、時間的余裕によって向き不向きが明確に分かれます。どの戦略にも共通するのは、「利回りを上げるほど管理の手間やリスクも増える」というトレードオフがある点です。自分のライフスタイルを客観的に見つめ、最適なバランスを選択することが長期的な資産形成につながります。
2025年度制度を活用してリスクヘッジを強化する
まず押さえておきたいのは、制度を上手に使えば実質利回りを底上げできるという事実です。2025年度も継続している減税や補助を理解し、数字に直結させましょう。
住宅ローン控除は自宅用の制度ですが、投資家自身が最初にマイホームを取得して控除枠を活用し、その後に賃貸物件への融資枠を広げるのは有効な手順です。所得税と住民税の還付効果で可処分所得が増えれば、自己資金を早く貯められます。また、法人設立を視野に入れる場合、2025年度の中小企業経営強化税制を適用すると、建物設備への投資に即時償却が使えるケースがあります。これにより初年度の課税所得を大幅に圧縮でき、実質的な手残りを増やせます。
さらに、不動産取得税の軽減措置は2025年3月31日取得分までの期限付きですが、その後も延長される公算が高いと報じられています。仮に軽減措置を受けられれば、評価額1,000万円の建物で約18万円の減額効果があります。固定資産税についても、新築賃貸住宅なら3年間は2分の1に軽減される制度が続いており、利回り計算に大きく寄与します。
加えて、ZEH(ゼッチ)賃貸住宅の普及支援事業が2025年度も継続しており、一定の省エネ基準を満たせば、1戸あたり最大70万円の補助が受け取れます。エネルギーコストが下がるため入居者満足度が高まり、空室期間の短縮にもつながります。制度を活用した物件選びは、表面利回りでは見えない部分でキャッシュフローを底上げする有効な手段となるでしょう。
まとめ
ここまで、利回りの本質、キャッシュフローとの関係、戦略別の具体策、そして2025年度の制度活用までを順序立てて見てきました。結論として、数字だけで物件を選ぶのではなく、リスク調整後の手残り現金をいかに積み上げるかが資産形成の鍵です。まずは自分の投資目的を明確にし、実質利回りを計算した上で現実的なシミュレーションを作ってください。そのうえで、制度を組み合わせてキャッシュフローを厚くし、再投資のサイクルを回すことが、長期的な安定収益への近道になります。今日から一歩踏み出し、数字と向き合う習慣を身に付けましょう。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp/
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_tk5_000198.html
- 総務省 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp/data/jyutaku/
- 日本銀行 金融システムレポート – https://www.boj.or.jp/research/brp/fsr/
- 東京都都市整備局 住宅市場動向 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/juutaku/jutakutoukei.html

