投資用の店舗を探しているものの、「住居系と違って情報が少ない」「テナントが付くか不安」という声をよく聞きます。実際、店舗物件は立地や業種のミスマッチで空室が長期化すると、収益が一気に悪化します。しかし事前にポイントを押さえれば、住宅より高い利回りと安定収入を両立させることも可能です。本記事では店舗の収益物件を選ぶ際に欠かせない視点を、立地分析から資金計画、運営まで体系的に解説します。読み終えるころには、自分に合った物件を見分ける具体的な手順がイメージできるはずです。
店舗物件投資の基礎を押さえる
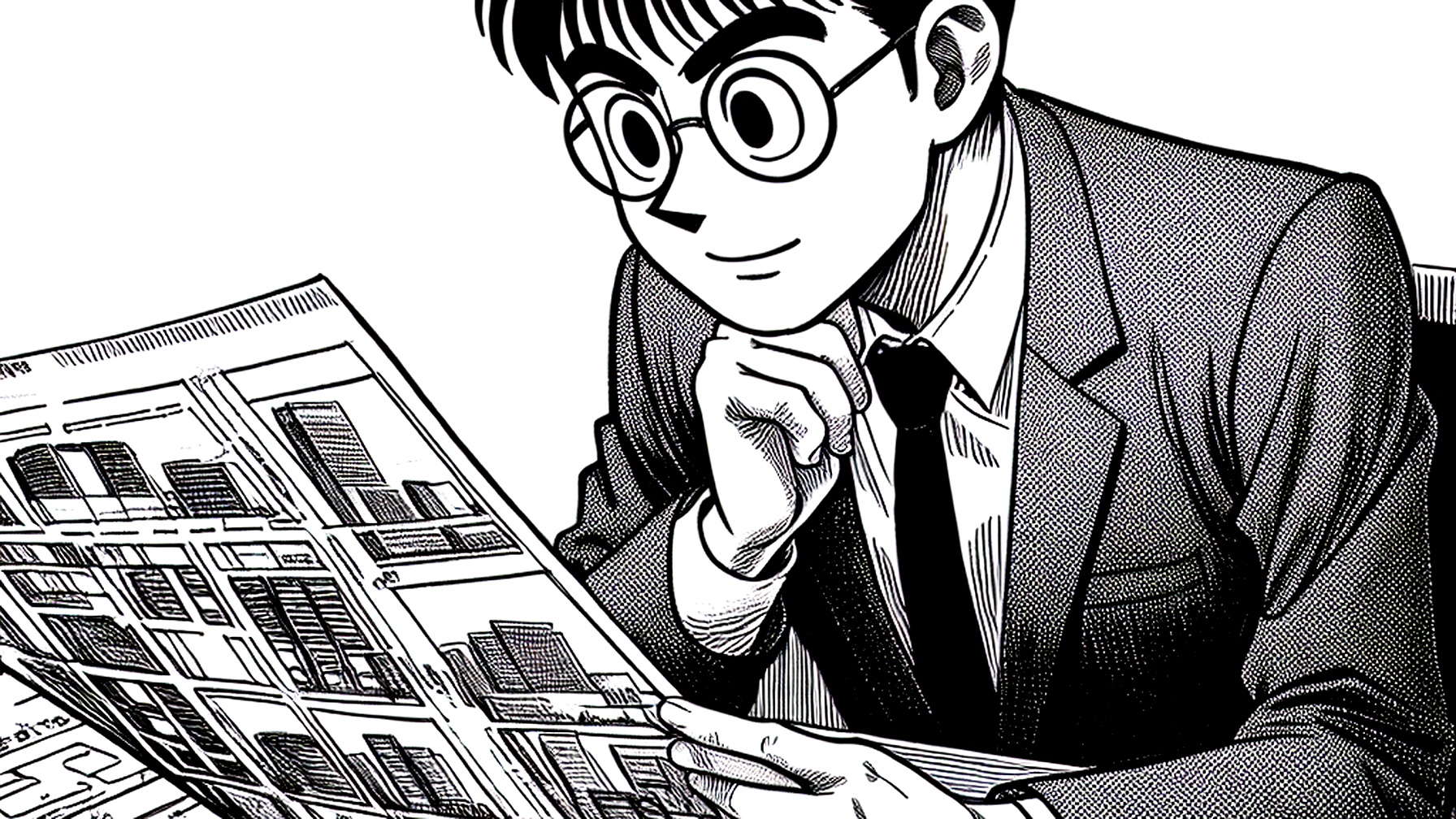
まず押さえておきたいのは、店舗物件は「賃料の決まり方」と「空室リスク」の構造が住宅とは異なる点です。賃料はテナントの事業収益に連動しやすく、景気変動の影響も大きくなります。
国土交通省の不動産価格指数(2025年7月公表)によると、店舗用ビルの価格は全国平均で前年比3.2%上昇しました。一方、同期間の空室率は都心4区で5.8%、地方中核都市で9.4%と差が大きいと総務省「商業動態統計」は指摘します。つまり、賃料が上がるエリアでもテナント付けに苦戦する都市が存在するのです。
また、店舗賃貸借契約は一般に3〜5年の定期借家契約が主流で、原状回復工事の負担割合も交渉次第です。家主が設計段階から内装工事に出資する「居抜き契約」を選べば早期に契約成立しやすいものの、初期投資が増える点を忘れてはいけません。このように、収益物件としての店舗は契約形態と設備負担を組み合わせて総合的に判断する必要があります。
立地分析でリスクを最小化する
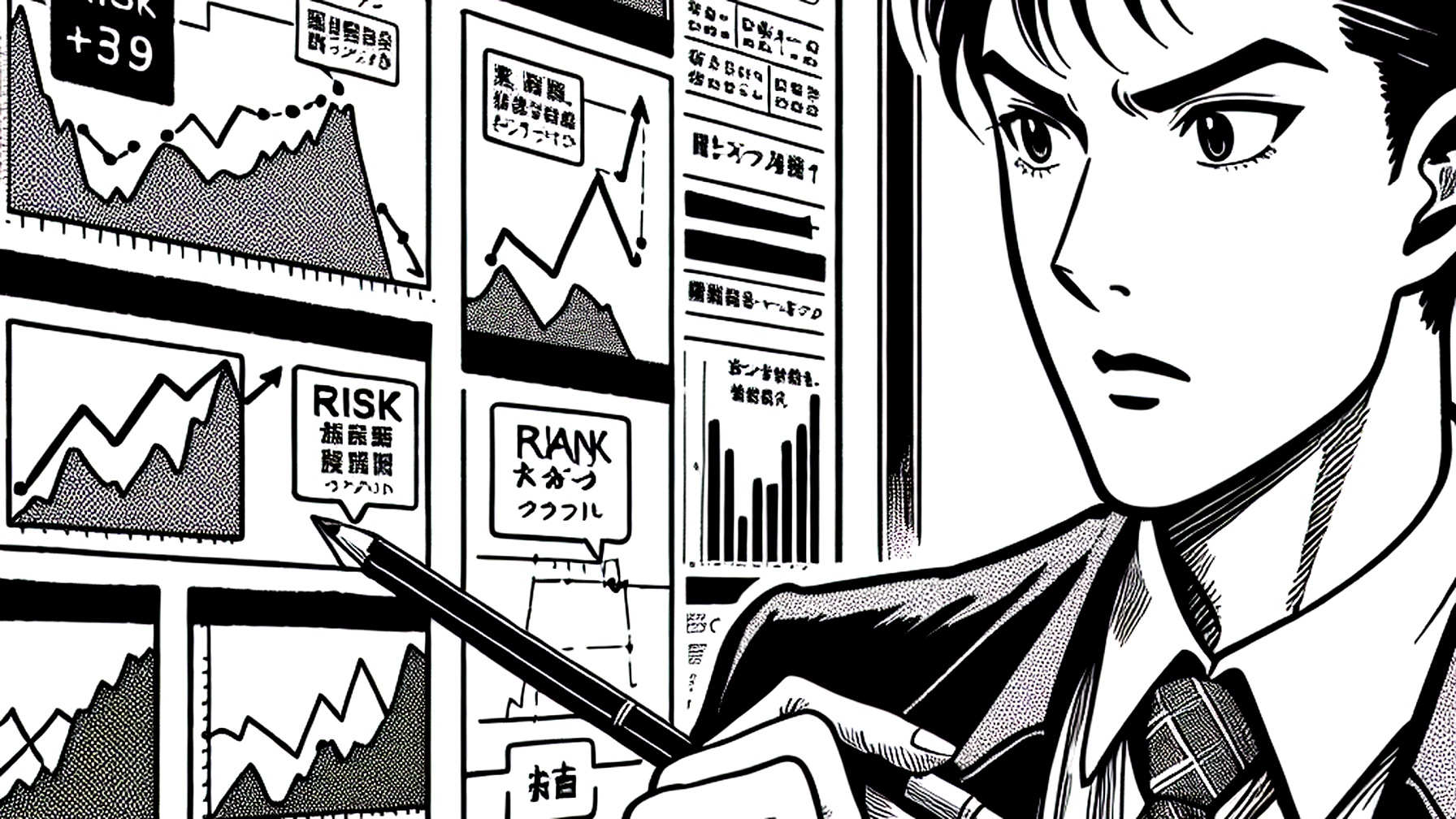
重要なのは、顧客動線と競合状況を同時に検証することです。住宅投資でいう「駅距離」だけに注目すると、思わぬ失敗につながります。
まず、国勢調査の昼間人口データを使い、商圏内にどれだけ消費者が滞在しているかを確認します。例えば札幌市中央区では夜間人口の約2.3倍の昼間人口が流入しており、ランチ需要が高いと中小企業庁「小規模企業白書2025」でも報告されています。次に、競合店舗の数と売上規模を現地調査で把握し、過当競争かどうかを判断しましょう。
一方で、郊外ロードサイド型の物件では車の交通量が鍵となります。国土交通省の交通量調査を参照し、1日2万台を超える道路沿いであれば、飲食やドラッグストアなど幅広い業種が成り立ちやすいとされています。しかし、バス停や信号の位置が変わるだけで客数が激減するケースもありますので、将来の道路計画や再開発情報まで確認すると安心です。
最後に、災害リスクも評価しましょう。ハザードマップで浸水深が最大1m以内、かつ避難路が確保されている立地は、テナントの事業継続計画(BCP)策定に有利です。これらの要素を複合的に見て、長期的に需要が維持されるかを見極めることが欠かせません。
テナント需要を読む実践ステップ
ポイントは「業種適合性」と「賃料負担率」を数値で把握することです。これにより、想定利回りが机上の空論で終わることを避けられます。
まず、出店候補業種の坪当たり売上をリサーチします。日本政策金融公庫「2025年度業種別売上高調査」によると、都市型カフェの平均売上は月12万円/坪です。適正賃料負担率を15%とすると、賃料は月1.8万円/坪以下が目安になります。物件が15坪なら月27万円が上限という試算です。実際の募集賃料がこれを超えていれば、業種を変えるか賃料交渉を検討しましょう。
次に、潜在テナントへヒアリングを行います。近隣で営業中の同業者や商工会議所の創業相談窓口に足を運び、出店意欲と家賃相場の生情報を集めることで、空室期間を短縮できます。また、テナントリーシング会社に依頼する場合でも、事前にヒアリング結果を共有すれば、より現実的な賃料設定が可能になります。
さらに、サブリース契約を検討するケースもありますが、2025年時点で消費税のインボイス制度が完全施行されているため、課税事業者と免税事業者の区分がテナント選定に影響する点に注意が必要です。家主側が課税事業者で賃料を税込表示にする際は、契約書に税抜金額を明記してトラブルを防ぎましょう。
資金計画と融資を有利に進める方法
実は、店舗物件は住宅より自己資金比率を高く求められる傾向があります。金融機関が事業リスクを重視するためで、日本政策金融公庫の2025年融資レポートでは平均25%の自己資金が推奨されています。
まず、物件価格の20〜30%を自己資金として用意し、さらに3カ月分の空室損失と修繕積立金を別枠で確保しましょう。この余剰資金があることで、融資審査の印象が大きく改善します。例えば、3%の金利が1%下がるだけで、5000万円の借入なら年間約50万円、20年で1000万円以上の利息差が生まれます。
次に、店舗物件では「収益還元評価」を重視する金融機関を選ぶと借入可能額が伸びやすいです。地銀や信用金庫は地域の商店活性化を目的とした融資制度を持っており、2025年度も継続中です。ただし、実績あるテナントとのマスターリース契約が前提となる場合が多いため、先にテナント候補を確保しておくと交渉がスムーズになります。
最後に、減価償却の計画も忘れずに立てましょう。鉄骨造(耐用年数34年)の中古物件を築20年で購入した場合、償却期間は残存期間14年を「法定耐用年数×20%」と比較し、いずれか長い年数で計算します。適切に償却を行えば、当初の課税所得を圧縮でき、キャッシュフローも安定しやすくなります。
契約と運営で押さえる法的ポイント
まず押さえておきたいのは、店舗賃貸借は「定期借家契約」が主流で、普通借家契約とは更新の扱いが異なる点です。定期借家契約では契約期間満了で確実に終了するため、将来的な賃料改定や建物取壊し計画を立てやすいメリットがあります。
一方で、退去時の原状回復をめぐるトラブルが増加しています。国土交通省のガイドライン(2024年改訂版)が示すように、通常損耗は貸主負担としつつ、テナントの造作部分についてはテナント負担とするのが基本です。ただし、飲食店のダクトやグリストラップなどは残置物として次テナントが利用できる場合もあるため、撤去義務を明確に規定すると費用を削減できます。
また、消防法と食品衛生法の改正により、2024年12月からダクト清掃の義務化範囲が拡大しました。貸主としては、物件管理規約に年1回の清掃実施を盛り込み、違反時の損害賠償責任を定めておくと安心です。さらに、2025年10月施行の改正インボイス制度への対応として、賃料を総額表示するか税抜表示にするかをテナントと合意し、契約書に明記しておくことも重要でしょう。
運営面では、月次の売上報告を受ける「売上連動賃料」条項を設けると、テナント経営が悪化した際の早期対応が可能になります。ただし、個人情報保護の観点から、売上高を取り扱う目的や保存期間を契約書に明示する必要があります。これらの法的ポイントを押さえておくことで、長期的に安定した店舗経営を支援できるのです。
まとめ
店舗の収益物件で成功するためには、立地とテナント需要を数値で検証し、自己資金と融資条件を戦略的に整えることが欠かせません。さらに、定期借家契約やインボイス制度など最新の法制度に沿った運営体制を整えることで、想定外のコストを抑えられます。この記事を参考に、現地調査と金融機関交渉を同時並行で進め、将来のキャッシュフローを具体的に描いてみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 商業動態統計調査 – https://www.stat.go.jp
- 中小企業庁 小規模企業白書2025 – https://www.chusho.meti.go.jp
- 日本政策金融公庫 2025年度業種別売上高調査 – https://www.jfc.go.jp
- 国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(2024年改訂) – https://www.mlit.go.jp

