忙しい本業をこなしながらも「将来のために収入源を増やしたい」と考えるサラリーマンは多いものです。しかし、株やFXのように日々チャートを追う時間は取りづらい、かといってアルバイトのように身体を使う副業は長続きしない——そんな悩みに応える手段として注目されるのが不動産投資です。本記事では、2025年10月時点の最新情報を踏まえつつ、初心者でも理解できるよう基礎から実践までを解説します。読後には「自分にもできそうだ」と感じられる具体的な行動イメージが得られるはずです。
サラリーマンが不動産投資を選ぶべき理由
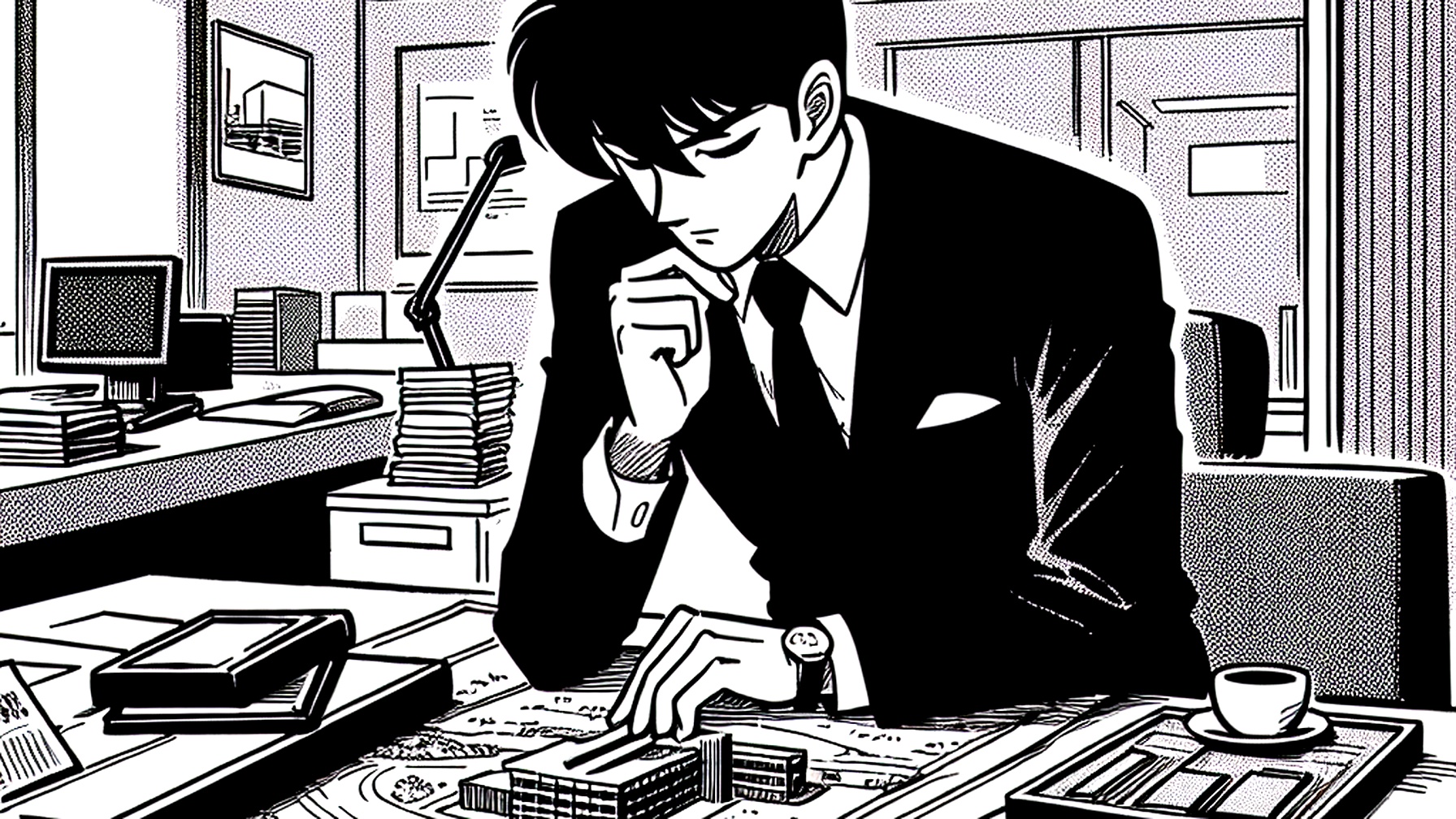
ポイントは、本業の安定収入があるサラリーマンこそ金融機関の信用を得やすく、レバレッジ(他人資本の活用)を効かせやすい点です。加えて、家賃収入は給与と相関が小さく、リスク分散の効果も期待できます。
まず、給与という定常的なキャッシュフローは金融機関にとって返済原資の裏付けとなります。住宅金融支援機構の2024年度調査によると、会社員の不動産投資ローン承諾率は自営業者より約10ポイント高い結果が出ています。つまり、他の副業よりも有利なスタートラインに立てるわけです。
次に、空室が出ても給与で当面の返済をカバーできる安心感があります。株式市場が下落しても家賃が毎月入る構造は、ポートフォリオ全体の安定化に寄与します。言い換えると、サラリーマン特有の「時間はないが信用はある」状況を最大限に活かせる副業が不動産投資なのです。
さらに、一定の節税効果も見逃せません。減価償却費などの経費計上により、所得税・住民税の負担を抑え、手残りを増やす仕組みが作れます。副業収入全体を最適化できる点も大きな魅力です。
物件タイプと立地の選び方
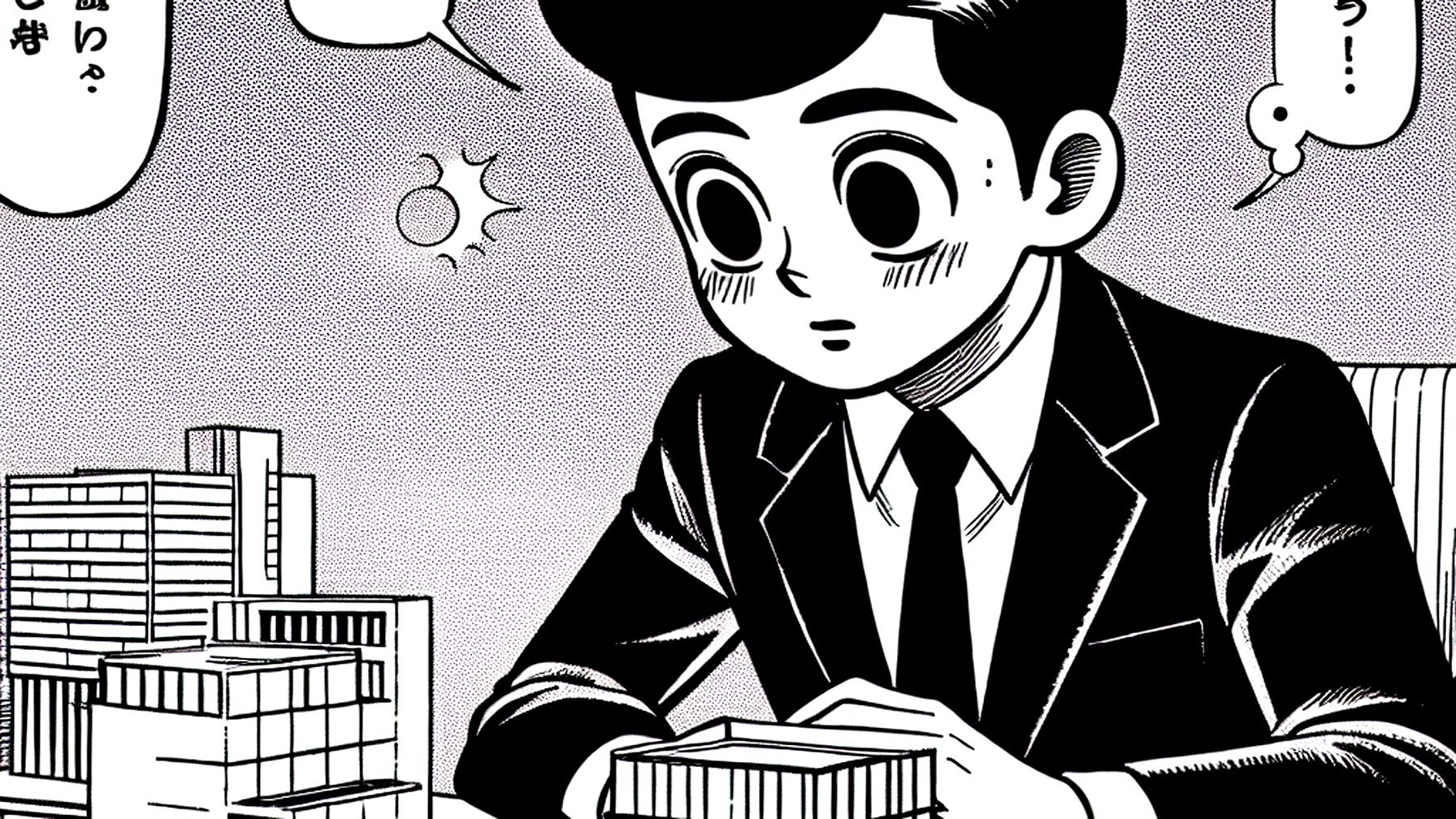
重要なのは、自分の投資目的に合った物件タイプと立地を組み合わせることです。利回りだけを追いかけると空室リスクが跳ね上がり、収益が安定しません。
まず押さえておきたいのは、単身者向け区分マンションとファミリー向けアパートでは収支構造が異なる点です。前者はワンルーム需要の高い都心で安定しやすく、修繕コストも比較的低い反面、価格競争が激しい傾向があります。一方、郊外のファミリータイプは初期投資が抑えられるものの、人口減少エリアでは長期的な需要を見極める必要があります。
立地では、総務省「住民基本台帳人口移動報告(2025年版)」が示す転入超過ランキングを活用すると、将来の入居ニーズを客観的に評価できます。たとえば東京都心6区は依然として転入超過を維持し、空室率も5%前後にとどまっています。一方で地方中核市のなかには転出超過へ転じるエリアがあり、賃料下落リスクが顕在化しています。
最後に、現地調査を怠らないことが成功の分かれ目です。昼夜の駅前の人通り、スーパーや病院といった生活インフラの充実度、自治体の都市計画など、生データを収集するほどミスマッチを防げます。
資金計画と融資のポイント
実は、資金計画を甘く見て破綻するケースが最も多いといわれます。まず自己資金を物件価格の20〜30%確保し、加えて突発的な修繕費として100万円以上の予備資金を持つのが理想です。
融資では金利だけでなく、融資期間と返済方法にも注目してください。たとえば金利1.5%・期間35年の元利均等返済と、金利1.8%・期間30年では、初期の返済負担が大きく変わります。金融機関によっては耐用年数オーバー物件でも期間延長を認めるケースがあり、交渉余地が生まれます。
2025年度の税制では、賃貸用新築住宅に対する固定資産税の減額措置が2026年3月31日取得分まで延長されています。新築を選ぶなら、この期間中に取得すると3年間は税額が1/2に軽減されるメリットがあります。ただし、軽減後の4年目以降にキャッシュフローが悪化しないか、シミュレーションで確認することが大切です。
また、返済負担率(年間返済額÷年間賃料収入)が30%以内なら、安全圏とされています。空室率10%を想定し、金利上昇2%のストレスをかけても返済可能かどうか、シミュレーションを複数作成しておくと安心です。
副業としての税務と時間管理
ポイントは、帳簿を正確に付け、税金と時間を両方コントロールすることです。青色申告を選択すれば、最大65万円の特別控除が受けられ、副業規模でも節税効果が高まります。
具体的には、減価償却費・管理委託料・修繕費などを漏れなく経費計上することで、課税所得を抑えられます。国税庁の「青色申告承認申請書」は開業から原則2カ月以内の提出が必要なので、物件購入前に準備しておくとスムーズです。
時間管理の面では、管理会社の活用が鍵になります。管理委託料は家賃の3〜5%が相場ですが、本業に影響しては本末転倒です。設備トラブルの24時間対応や家賃督促業務をアウトソースすることで、月数時間のチェックだけに削減できます。
さらに、確定申告の時期は税理士にスポット依頼する方法もあります。費用は年間10万円前後ですが、節税提案や将来の法人化の相談まで含めれば、十分に費用対効果が見込めます。
2025年度の支援制度と最新動向
まず押さえておきたいのは、2025年度も国土交通省の「賃貸住宅省エネ化推進事業」が継続されている点です。賃貸住宅の断熱改修や高効率給湯器導入に対し、1戸あたり最大40万円の補助(交付申請は2026年2月末まで)が受けられます。省エネ性能を高めることで、入居者満足度を向上させ、空室リスクを低減する効果も期待できます。
一方で、インバウンド需要の回復を受け、都市型ホテルや簡易宿所の転用案件が増加しています。しかし、旅館業法の許可取得や近隣トラブルのリスクが高く、会社員の副業としてはハードルが高いのが現状です。
不動産クラウドファンディングも選択肢として広がりました。1口1万円から参加でき、実物を持たない分だけ管理手間がかかりません。金融庁の登録事業者は2025年9月時点で70社を超え、利回りは年3〜8%が中心です。ただし、元本保証はなく、分配停止リスクもあるため、ポートフォリオの一部として検討する姿勢が必要です。
最後に、地方自治体が独自に設ける空き家活用補助金も増えています。たとえば北海道札幌市では2025年度、空き家リノベーション費用の1/3(上限150万円)を補助する制度がスタートしました。地方物件を検討する際には、自治体の公式サイトを必ず確認し、支援策を取りこぼさないようにしましょう。
まとめ
本記事では、サラリーマンが副業として不動産投資に取り組む際の考え方と実践手順を解説しました。重要なのは、信用力を資金調達に活かしつつ、立地と物件タイプを慎重に選び、保守的なシミュレーションでキャッシュフローを確認する姿勢です。さらに、青色申告や省エネ補助金など2025年度の制度を上手に組み合わせれば、税負担やコストを抑えながら収益性を高める道が開けます。本業を大切にしながらも、安定した家賃収入という第二の柱を築くために、まずは自己資金の準備と情報収集を今日から始めてみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅局「賃貸住宅市場の概況(2025年版)」 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局「住民基本台帳人口移動報告 2025年版」 – https://www.stat.go.jp
- 住宅金融支援機構「2024年度 民間住宅ローン利用者調査」 – https://www.jhf.go.jp
- 国税庁「青色申告制度の手引き 令和7年版」 – https://www.nta.go.jp
- 金融庁「不動産特定共同事業者登録一覧(2025年9月)」 – https://www.fsa.go.jp

