不動産投資の融資を検討するとき、「変動と固定のどちらが安全なのだろう」と迷う方は多いでしょう。特に金利が上昇傾向にあるとき、毎月の返済額が変わらない固定金利は大きな安心材料になります。しかし固定期間が長いほど金利は高めに設定されるため、選択を誤ると手取りキャッシュフローが圧迫されかねません。本記事では固定金利の基礎から2025年時点の市場動向、具体的な選び方までを体系的に解説します。読後には、自分の投資戦略に合う固定金利商品を自信を持って選べるようになるはずです。
固定金利とは何かを正しく理解する
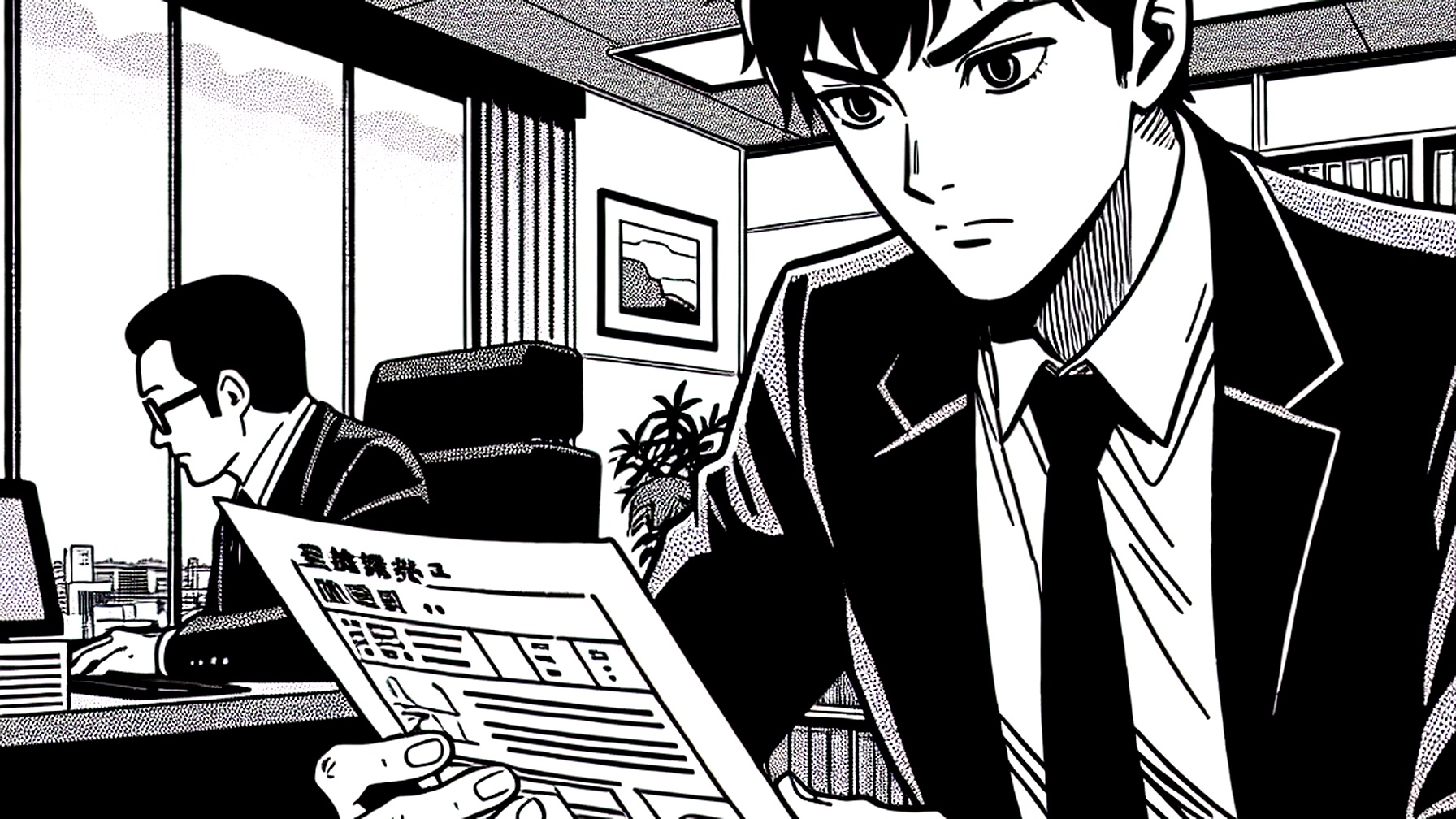
まず押さえておきたいのは、固定金利が「契約時に決めた金利が一定期間変わらない仕組み」だという点です。期間は10年・20年・全期間など多様で、期間が長いほど金融機関は金利リスクを負うため、一般的には金利が高く設定されます。一方、変動金利は半年ごとに基準金利が見直されるため、金利が上がれば返済額も増えるリスクがあります。つまり固定金利は「将来の上昇リスクを保険料として先払いするイメージ」といえます。
住宅金融支援機構のデータによると、2025年10月時点のフラット35(全期間固定型)は、借入期間21〜35年で年1.72%前後となっています。同期間の主要銀行の変動金利は0.45%前後が中心なので、表面上は固定型が割高に見えるかもしれません。しかし日本銀行が2025年7月に実施した追加利上げにより、長期金利は1.1%台へ上昇しており、固定金利との差は縮小傾向にあります。リスクを抑えたい投資家にとって固定型の魅力はむしろ高まっているのです。
金利タイプ別に見るメリットとリスク
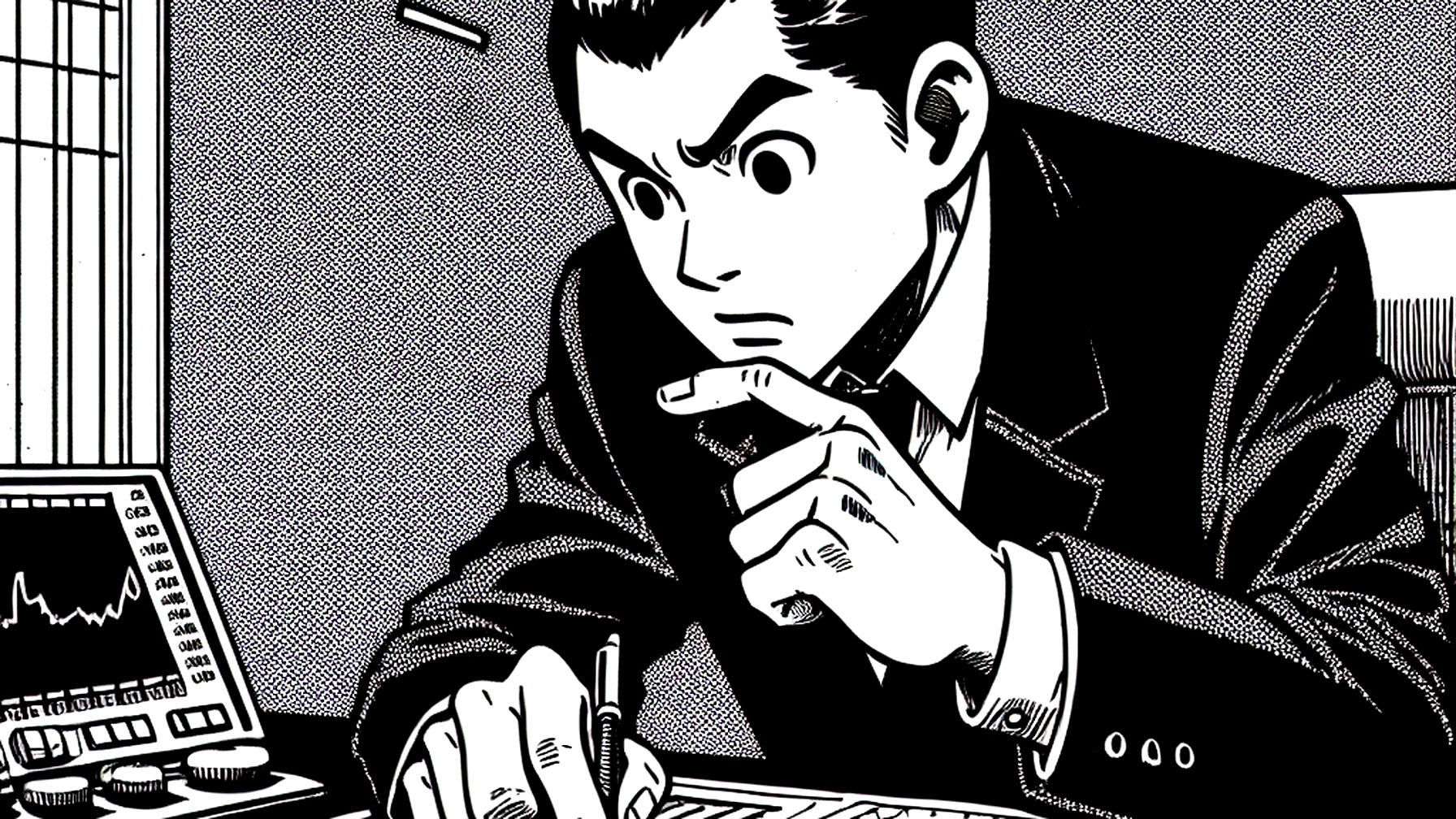
ポイントは、金利タイプごとに「支払いの安定性」と「総返済額」のバランスが異なる点です。固定金利は返済額が一定のため、キャッシュフロー計画が立てやすく、長期保有物件で特に効果を発揮します。また、繰上返済を計画的に行うことで支払い総額も圧縮できます。一方、変動金利は初期コストが低い反面、金利上昇局面では利息負担が急増し、場合によっては家賃収入を上回る返済額になる可能性もあります。
もう少し踏み込むと、固定期間選択型(金利固定期間が10年など限定されるタイプ)は「最初の10年を安全に乗り切り、その後に売却や借換えで柔軟に対応する」戦略に向いています。ただし固定期間終了後には自動で変動金利へ移行することが多く、その時点の金利環境を読み違えると負担が増すリスクもあります。言い換えると、固定期間選択型は出口戦略を明確に描ける投資家向きと言えるでしょう。
2025年度の市場動向と金利予測
実は2025年度の金利環境は、インフレ率と日本銀行の政策運営によって大きく動いています。日銀が掲げる「物価安定の目標」2%はすでに達成水準にあり、2025年9月の消費者物価指数(CPI)は前年同月比2.6%増(総務省統計局)となりました。この結果、政策金利は0.25%へ引き上げられ、長短金利の波及効果で新規固定金利も緩やかに上昇しています。
一方で、住宅投資向けの融資競争はなお激しく、主要都市の不動産価格は横ばいです。価格上昇が鈍化したことで、新規投資家が購入しやすい環境が整い、金融機関も顧客獲得のために金利引き下げキャンペーンを展開しています。つまり市場は「金利は上昇基調だが、競争による割引も同時に存在する」という複雑な状態です。こうしたタイミングで固定金利を選ぶには、金利水準だけでなく、総支払額や物件利回りとの兼ね合いを見極める必要があります。
固定金利 選び方の実践ステップ
重要なのは、自分の投資計画とリスク許容度を数値で把握することです。ここでは最小限の箇条書きで具体的な手順を整理します。
- 物件シミュレーションを作成し、家賃収入の下限と経費の上限を設定する
- 上記シミュレーションに「金利+1%」のストレステストをかけ、キャッシュフローが黒字か確認する
- 固定期間別に総支払額と残高推移を比較し、手取額が最も安定するプランを選ぶ
- 2025年度に対応した各銀行の諸費用(事務手数料・保証料)を合算し、実質コストで評価する
まずシミュレーションですが、空室率10%・修繕積立年10万円といった保守的な設定で行うことで、予想外の支出にも備えられます。次にストレステストを実施し、「金利が1%上昇してもキャッシュフローが年間30万円以上残る」など、具体的な安全ラインを数値で決めましょう。第三に、固定期間ごとの総支払額を比較すると、20年固定と全期間固定で400万円以上差が出るケースも珍しくありません。最後に諸費用を加味すると、表面金利ではわからない実質差が見えてきます。つまり固定金利 選び方では「金利+諸費用」をセットで考えることが欠かせないのです。
投資戦略別に見る固定金利の賢い活用法
基本的に長期保有を前提とする場合、全期間固定は心強い選択肢になります。家賃をインフレに合わせて緩やかに引き上げれば、実質利回りが向上する可能性もあります。また、売却益よりインカムゲインを重視する戦略では、固定コストが読めること自体が大きな価値です。
一方で、物件価値の上昇を見込んで10年以内の売却を計画するなら、固定期間選択型が適しています。10年間は返済額を安定させ、その後に売却益で残債を一括返済すれば、変動移行リスクを回避できます。さらに借換え戦略を視野に入れる場合、2025年時点で諸費用や違約金のかからない金融機関を選ぶことで、将来の機動性が高まります。
最後に短期転売やリフォーム再販を行う場合は、融資期間自体を短く設定し、金利よりもスピードを優先することが多くなります。ただし固定型でも3年や5年の超短期商品が存在するので、返済期間と合わせれば十分に採算が取れるケースがあります。つまり投資期間と出口戦略を明確にすれば、固定金利はどの戦略にも柔軟に組み込めるのです。
まとめ
ここまで固定金利の特徴、市場動向、具体的な選び方を見てきました。最も大切なのは、金利タイプを単体で評価するのではなく、物件の利回りや保有期間と合わせて総合的に判断する姿勢です。2025年度は金利上昇リスクと金融機関の競争が共存するため、固定金利の優位性が以前より高まっています。まずは保守的なシミュレーションを行い、安全ラインを超えるプランを見つけましょう。そのうえで諸費用まで含めて実質コストを比較すれば、自分の戦略に合った固定金利を選び抜けるはずです。
参考文献・出典
- 日本銀行 - https://www.boj.or.jp/
- 総務省統計局 - https://www.stat.go.jp/
- 住宅金融支援機構 - https://www.jhf.go.jp/
- 国土交通省 不動産価格指数 - https://www.mlit.go.jp/
- 全国銀行協会 金利動向レポート - https://www.zenginkyo.or.jp/

