忙しい診療の合間に「資産形成もしたいが時間が足りない」と感じていませんか。不動産投資は手間がかかるイメージが強いものの、安定した年収と信用力を持つ医師であれば、高利回り物件を無理なく取得し長期で資産を増やすことが可能です。本記事では、医師が不動産投資で優位に立てる理由から、2025年時点で有効な制度の活用法までを解説します。読み終えるころには、限られた時間でも実践できる具体的なステップが見えてくるはずです。
医師が不動産投資に向いている理由
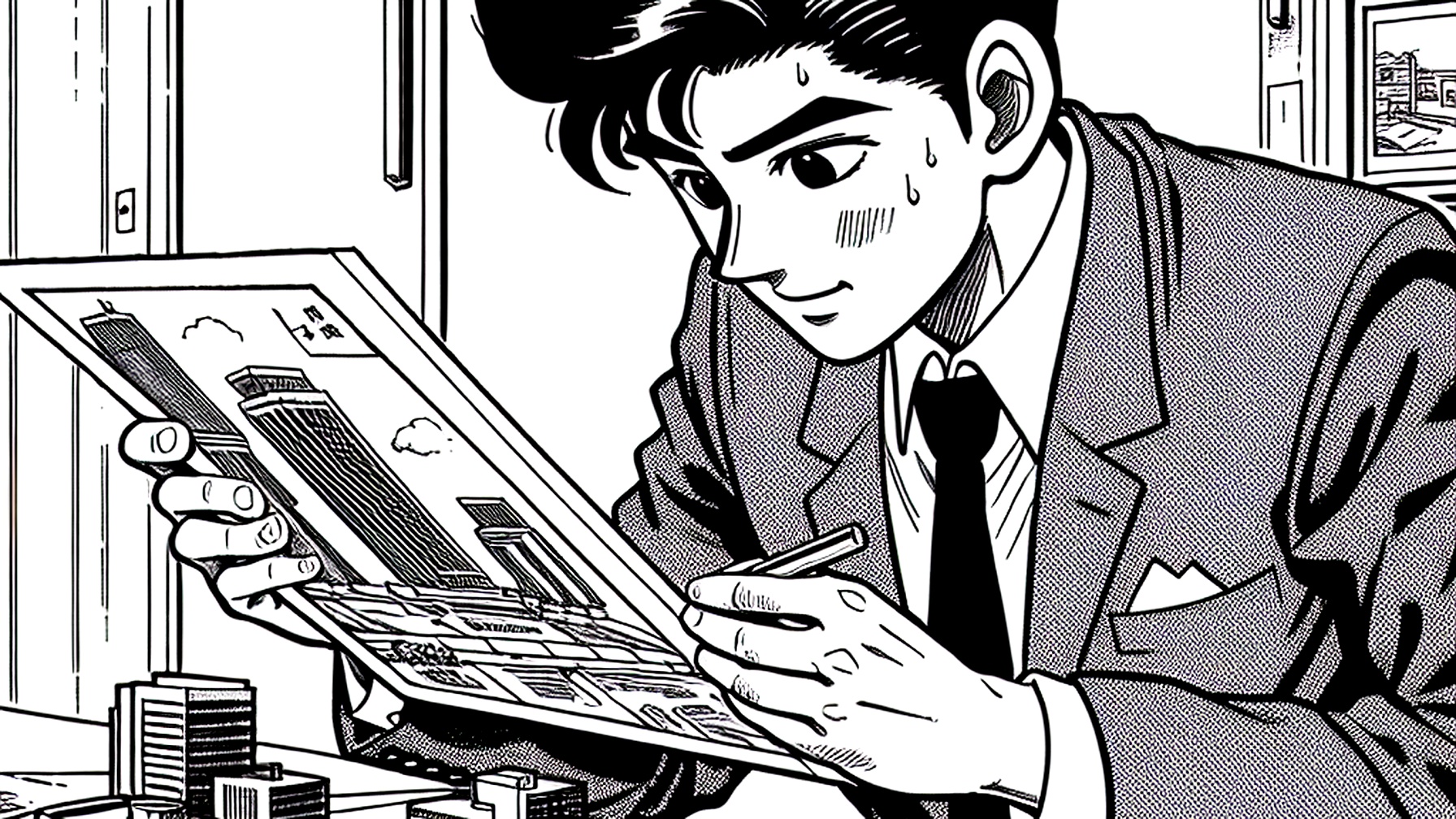
ポイントは、医師がもともと持つ「信用力」と「安定収入」が金融機関の評価を高める点にあります。実際に、同じ物件でも医師が申し込むと金利が0.2〜0.3%低く提示されるケースは珍しくありません。これは、金融機関が将来的な返済不能リスクを低いと判断するためです。
まず安定した給与は、団体信用生命保険を付けた長期ローンでも審査を通りやすくします。特に30〜40代の勤務医は、勤続年数が短くても社会的信用が高いので、フルローンや一部オーバーローンの提案を受けやすい傾向があります。また、高い年収は自己資金を厚く積み増す余裕をもたらし、複数物件を短期間で取得する戦略を取りやすくします。
さらに、医師としての専門性は不動産賃貸業にもプラスに働きます。入居者は職業を気にするため、オーナーが医師だと安心感が生まれやすいといった調査結果もあります。つまり、医師の肩書き自体が金融面と入居者募集の両面で“看板”になるのです。
最後に、医師は夜間や休日も急な呼び出しがある一方で、時間単価が高い職業です。外注費をかけて管理会社へ任せても、時間を買うメリットが収益性を損なわない点も大きな強みと言えます。
高利回りを実現する物件タイプと立地
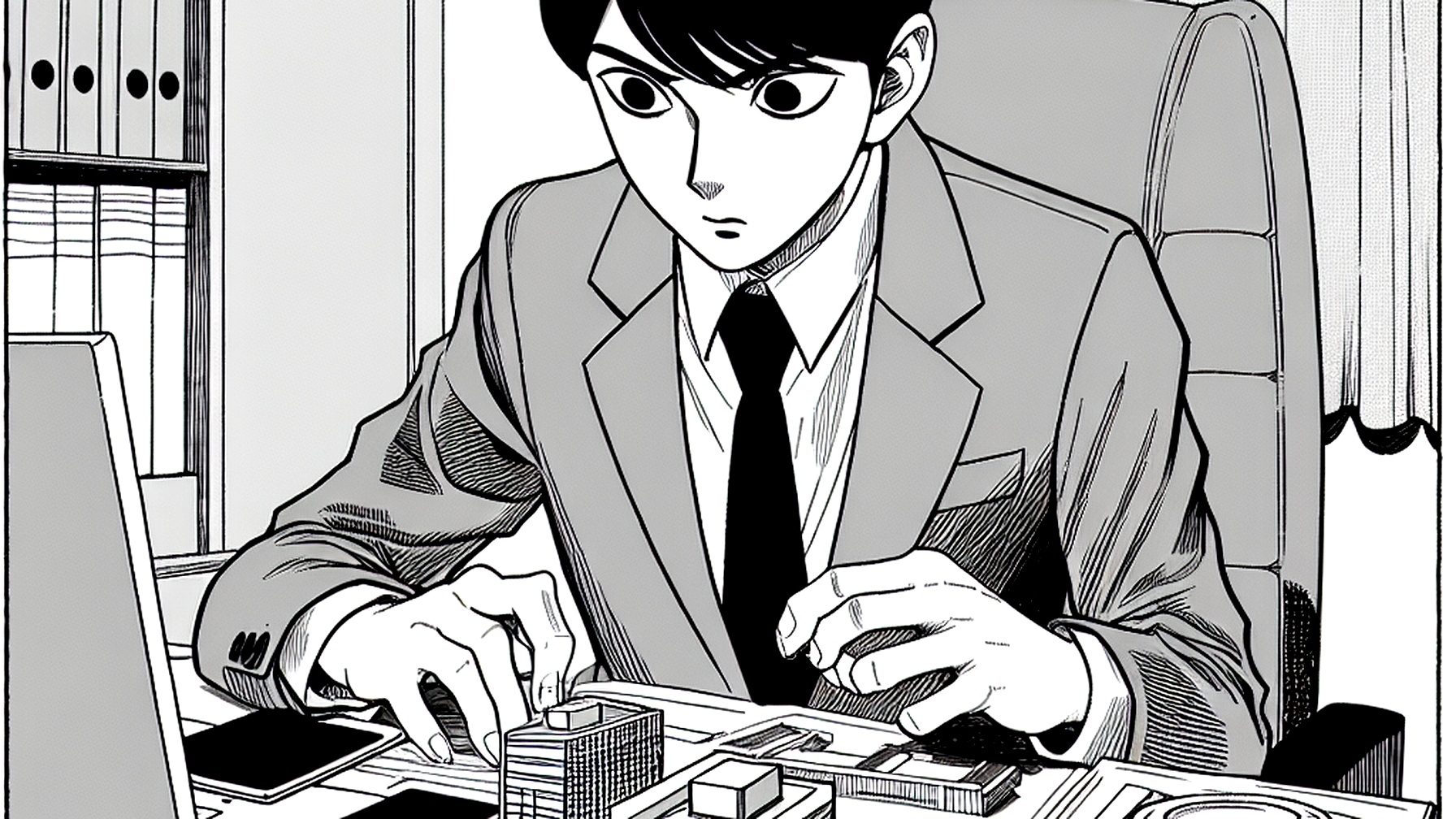
まず押さえておきたいのは、利回りは「収益」と「取得価格」の双方で決まるという事実です。2025年時点で東京23区の平均表面利回りはワンルーム4.2%、ファミリー3.8%、木造アパート5.1%と日本不動産研究所が公表しています。平均を上回る高利回りを狙うには、地方中核都市の築浅アパートや都心周辺の築古区分マンションが候補となります。
築浅アパートは減価償却メリットが小さいものの、設備トラブルが少なく修繕費を抑えられる点が魅力です。土地の比率が高いと評価額は落ちにくく、将来売却するときにキャピタルゲインも狙えます。一方で、都心周辺の築古区分は取得価格が安いため、家賃とのバランス次第で利回り8%超も十分可能です。
しかし、重要なのは単に数字だけを追わないことです。人口動態や就業人口の推移を確認し、今後10年で賃貸需要が減らない地域かを見極める必要があります。総務省「住民基本台帳人口移動報告」によると、2024年時点で流入超過が続く政令市は福岡市・札幌市・仙台市などが挙げられます。これらの都市では単身者向けの需要が底堅く、利回りと安定稼働の両立が期待できます。
空室リスクを抑えるためには、駅徒歩10分圏内や病院・大学近接エリアなどシンプルな需要源を重ねることが効果的です。加えて、医師仲間や職員向けの社宅需要を取り込める物件を狙えば、入居者との信頼関係も築きやすくなります。
資金計画と融資のポイント
実は、資金計画を軽視すると高利回り物件でもキャッシュフローが赤字になることがあります。まず自己資金の目安は物件価格の10〜20%が望ましいです。これにより月々の返済負担率が下がり、ストレス耐性の高い収支構造を組めます。とはいえ、医師の場合はフルローンが組めることも多いため、自己資金を温存し次の投資に備える戦略も選択肢です。
ポイントは、表面利回りだけでなく実質利回りで判断することです。管理委託費5%、修繕積立金や固定資産税を差し引き、かつ空室率を見込んだ上で年7%を超えれば優良といえます。例えば表面利回り9%の区分マンションでも、実質利回りが5%を切るなら見送りが賢明です。
金融機関選びでは、金利だけでなく融資期間と融資割合がキャッシュフローに直結します。変動金利で1.2%、融資期間35年と固定金利1.7%、期間25年を比べると、毎月返済額が大きく変わります。金利上昇リスクを織り込みつつ、医師割引や提携ローンを活用して有利な条件を引き出しましょう。
また、2025年度の税制では、不動産所得が本業収入と損益通算できる点に変更はありません。減価償却費を最大化するために、木造や軽量鉄骨の築古物件を組み合わせると所得税・住民税の負担を抑えられます。ただし過度な節税優先は資産価値の低い物件をつかむリスクがあるため、バランスを保つ視点が不可欠です。
忙しい医師でも回せる運用体制
重要なのは、運用を「仕組み化」してしまうことです。管理会社に委託する際は、入居者募集力とレスポンスの早さを重視します。管理手数料は家賃の3〜5%が相場ですが、医師の時給を考えれば自主管理で時間を奪われるより合理的です。
入居付けの強い会社は、空室期間を短くしてくれるため表面利回りより実質利回りを高める効果があります。契約前にリーシング実績や客付けルートをヒアリングし、IT重説やオンライン内見に対応しているかも確認しましょう。コロナ禍以降、オンライン対応の有無が成約スピードに影響しています。
さらに、修繕・清掃をまとめて発注できる体制を整えることで、突発的な対応を減らせます。医局や勤務先で緊急呼び出しがある生活では、管理会社が24時間受付のコールセンターを持つかどうかが安心材料になります。万一のトラブル対応フローを事前に文書化し、委任範囲を明確にしておくと良いでしょう。
最後に、家賃送金明細と確定申告データをクラウド化しておくと、決算期に慌てる必要がなくなります。医療業務で忙しい3月でも、税理士へワンクリックでデータ共有できる仕組みを作れば、時間的コストを最小化しつつ正確な申告が可能です。
2025年度の税制・制度を味方にする
まず、不動産投資で活用できる2025年度の代表的制度は「住宅ローン減税」と「不動産取得税の軽減措置」です。住宅ローン減税は原則居住用ですが、将来的にマイホーム転用を前提に投資するケースで検討余地があります。不動産取得税の軽減は、取得後に申告することで課税標準額を最大1,200万円控除でき、築20年超の中古物件でも条件を満たせば適用されます。
一方、賃貸経営に直結する補助としては、国土交通省の「2025年度住宅エネルギー性能向上支援事業」が挙げられます。既存賃貸住宅を省エネ改修すると、1戸あたり最大50万円の補助金が受け取れます。省エネ性能の向上は入居者満足度を高めるだけでなく、近年強まるESG投資の観点から将来の物件価値を維持する要素にもなります。
注意点として、補助金は予算上限に達すると早期終了する場合があります。物件購入後すぐに申請できるよう、施工業者と見積書や工事計画を事前にすり合わせておくことが重要です。金融機関によっては補助金を自己資金とみなし、融資条件を柔軟にしてくれるケースもあるため、相談してみる価値があります。
また、医師が法人化して不動産を所有する場合、2025年度の中小企業経営強化税制を利用し、IoT設備導入にかかる即時償却や税額控除を受ける選択肢もあります。スマートロックや省エネエアコンを導入すれば入居者満足度を高めつつ、初年度で大きな節税効果を得られる点が魅力です。
まとめ
ここまで、医師が高利回りを実現するための戦略を解説しました。高い信用力を活かした低金利融資、需要が底堅いエリアでの物件選び、時間を買う管理体制の構築、そして2025年度の制度を組み合わせることで、忙しい日常でも堅実に資産を拡大できます。まずは現在の家計とライフプランを見直し、無理なく投資に回せる資金を把握するところから始めてみてください。行動に移した分だけ、将来の選択肢は確実に広がります。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp/
- 総務省統計局 住民基本台帳人口移動報告 – https://www.stat.go.jp/
- 国土交通省 住宅エネルギー性能向上支援事業 2025年度概要 – https://www.mlit.go.jp/
- 財務省 税制改正資料 2025年度 – https://www.mof.go.jp/
- 中小企業庁 経営強化税制ガイド – https://www.chusho.meti.go.jp/

