年金だけでは老後資金が足りるか不安、しかし株式のような価格変動リスクは避けたい――そう感じる60代の方は少なくありません。マンション投資は家賃収入で毎月の資金繰りを補い、物件の売却益でまとまった資金を得るチャンスもあります。本記事では「マンション投資 60代 ファミリー向け」を軸に、初心者でも理解できるよう基礎から最新制度まで丁寧に解説します。読み終えるころには、自分に合った物件選びのポイントや安全な資金計画、2025年度の税制メリットを押さえ、安心して一歩を踏み出せるはずです。
60代がマンション投資を検討する背景
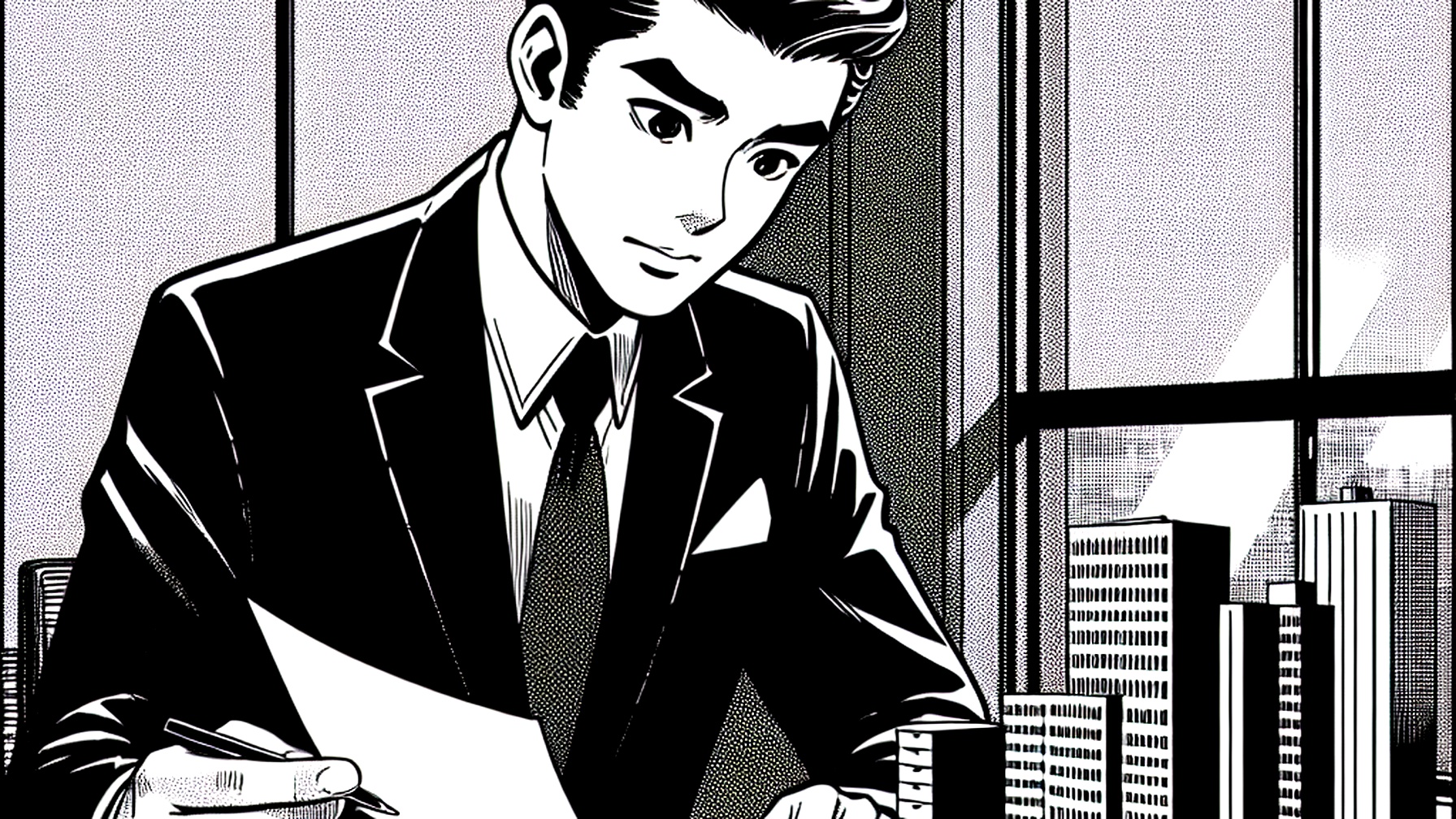
まず押さえておきたいのは、60代が置かれた資産形成の環境です。総務省「家計調査」によると、60歳以上の世帯は金融資産の約35%を預貯金で保有しています。低金利が続く中、預金だけでは資産が増えにくく、年金と合わせても生活費が不足する可能性が高まります。一方で、新しい事業に挑戦するには体力的・時間的な制約があり、無理のないインカム収入を求める傾向が強いのが実情です。
こうした背景から、安定的な家賃収入を得られる不動産投資、とりわけ管理負担の軽い区分マンションが注目されています。実は投資対象をファミリー向け住戸に絞ることで、60代でも無理なく運用できる確率が高まります。理由は空室リスクの低さと長期入居が見込める点にあります。後の章で詳しく触れますが、郊外すぎない利便性の高いエリアを選べば、リフォームを繰り返しながら20年以上運用するシナリオも現実的です。
ファミリー向け物件の安定性と成約力
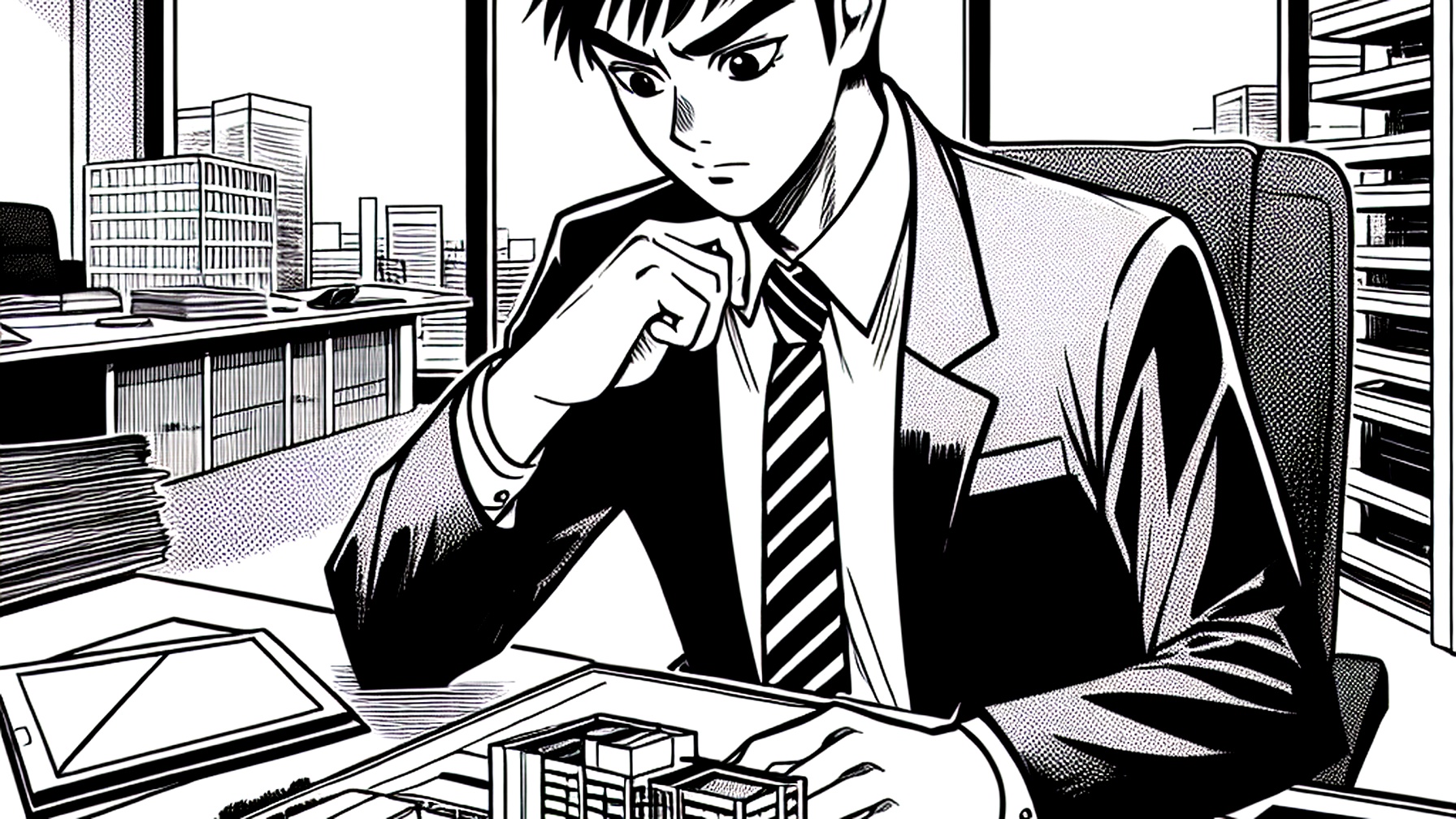
重要なのは、ファミリー向け物件が持つ「長期入居」という特性です。国土交通省の住生活基本調査では、3LDK以上の賃貸に住む世帯の平均居住年数は約6.8年と、ワンルームの倍以上に伸びています。つまり一度入居すれば退去までの期間が長く、高齢投資家がもっとも警戒する空室リスクを低減できます。
さらに、子どもの学区や通勤利便性を重視するファミリーは住み替え先を限定しがちです。例えば最寄り駅から徒歩10分以内、生活利便施設が揃う駅前再開発エリアの物件は、多少家賃が割高でも選ばれる傾向があります。東京23区の新築マンション平均価格は7,580万円(不動産経済研究所、2025年10月発表)ですが、中古の築15年前後であれば4,500万〜5,500万円に下がり、利回り4%台を確保しやすい物件も見つかります。
ポイントは、家族構成の変化に耐えられる間取りと修繕計画です。例えばリビングと隣接する和室をスライドドアでつなげ、子どもが独立した後はリビング拡張として活用できる設計だと、長期的な需要を取り込みやすくなります。また、ファミリー向けは入居中の小修繕が少ないと言われますが、水回り設備の更新だけは10〜15年ごとに必要です。購入前に管理組合の長期修繕計画を確認し、積立金が適正かどうかを見極めましょう。
資金計画とローン活用のコツ
実は60代でも金融機関から融資を受けられるケースは増えています。日本政策金融公庫の「生活衛生貸付」や、地銀が取り扱うシニア向けアパートローンは、完済時年齢を80歳までと設定する商品が多く、70歳前後でも10年〜15年のローンが組めます。返済期間が短いぶん月々の返済額は膨らみますが、退職金や運用中の金融資産を頭金に充当し、借入額を物件価格の50%以下に抑えればキャッシュフローは安定します。
例えば5,000万円の中古マンションを自己資金3,000万円、年利2.1%・15年ローンで購入すると、月々の返済は約23万円です。家賃収入が25万円なら、管理費・修繕積立金を差し引いても毎月数万円のプラスを維持できます。また、退職金を一部投資に回す際は、手元に半年分の生活費と200万円程度の緊急予備資金を残すと安心です。金融庁の「高齢社会に関する市場分析」でも、資産の流動性確保が老後の生活満足度を左右するとの指摘があります。
ローンを利用するメリットは、団体信用生命保険(団信)に加入できる点です。万一の際に残債が完済され、家族へ無借金の不動産を残せます。ただし、持病がある場合はワイド団信や特別条件付に切り替わる可能性があるため、健康状態を正直に申告し、複数行を比較しましょう。
2025年度の税制・制度を活かす方法
まず押さえておきたいのは「住宅ローン控除」が中古投資用マンションでも条件付きで適用されるケースです。2025年度は居住用物件であれば、所得税と住民税から最大455万円まで控除可能ですが、投資用としての購入時点では対象外です。そこで、当初は自宅として1年間住み、その後賃貸に出す「マイホーム転用」スキームが選択肢になります。実際の適用可否は税理士に確認し、転用時点で贈与税や譲渡所得の取り扱いを整理しておくことが肝心です。
固定資産税については、築20年超のマンションでも耐震基準適合証明を取得すると、翌年度の固定資産税が半額になる特例が2025年度も継続しています。耐震補強工事に80万円かかっても、税額軽減と賃料アップで5年程度で回収できる事例がありますので、購入前にマンション全体の適用予定を確認しておくと得策です。
さらに、国土交通省が推進する「良質住宅ストック形成促進事業」は、一定の省エネ改修を行った賃貸マンションに最大100万円の補助金を交付します。2025年度も応募枠が設けられており、窓の断熱化やLED照明の共用部導入が対象です。管理組合単位で申請するため、投資家個人でも理事会で提案し、賃料維持に役立てることが可能です。
運用と出口戦略で老後を守る
ポイントは、運用中のキャッシュフロー管理と売却タイミングを計画的に設定することです。家賃収入は年1回、固定資産税評価の見直しや賃料相場の調査を行い、適正賃料を維持します。また、入居が5年以上続くファミリー世帯には、壁紙の無償アップグレードを提案すると、さらなる長期入居に結び付きやすくなります。
売却を検討する目安は築30年前後です。国土交通省「不動産価格指数」によると、築30年を超えると価格下落が緩やかになる一方、設備更新費が急激に増える傾向があります。つまり、築25〜28年で売却すれば、資本的支出を抑えつつ値崩れ前に出口を取れる可能性が高まります。結論として、60代で購入した物件を70代後半に売却し、介護費用や相続資金に充てる計画を立てておくと安心です。
出口戦略の一環として、リバースモーゲージの活用も検討できます。自宅とは別に投資用マンションを所有している場合でも、収益物件を担保とした「賃料収入併用型リバースモーゲージ」を取り扱う信託銀行が増えています。借入限度額は評価額の50%程度ですが、長生きリスクに備えた資金源として有効です。
まとめ
本記事では「マンション投資 60代 ファミリー向け」をテーマに、物件選びの理由、資金計画、2025年度の制度活用、出口戦略まで一連の流れを解説しました。長期入居が見込めるファミリー向け物件を選び、頭金を厚くしつつ団信付きローンを活用すれば、年金にプラスの安定収入を得ながら家族へ資産を残せます。さらに、固定資産税の軽減や省エネ補助金など現行制度を使うことで、実質利回りを高めることも可能です。まずは信頼できる不動産会社と金融機関に相談し、手元資金とライフプランに合ったシミュレーションを作ることから始めてみてください。
参考文献・出典
- 総務省 家計調査(https://www.stat.go.jp/)
- 不動産経済研究所 新築マンション市場動向(https://www.fudousankeizai.co.jp/)
- 国土交通省 住生活基本調査(https://www.mlit.go.jp/)
- 金融庁 高齢社会に関する市場分析レポート(https://www.fsa.go.jp/)
- 日本政策金融公庫 融資制度一覧(https://www.jfc.go.jp/)

