不動産投資に興味はあるものの、「住居ではなく事務所を購入しても本当に借りられるのか」「変動と固定のどちらが安全なのか」と悩む方は多いはずです。特に初心者にとって、融資条件や金利タイプの違いは複雑に感じられます。本記事では、2025年10月時点で利用できる不動産投資ローンを前提に、事務所物件を固定金利で運用する際のポイントを基礎から解説します。読むことで、資金計画の立て方から金融機関との交渉術まで一連の流れが把握でき、安心して第一歩を踏み出せるようになります。
事務所物件に向く投資戦略とは
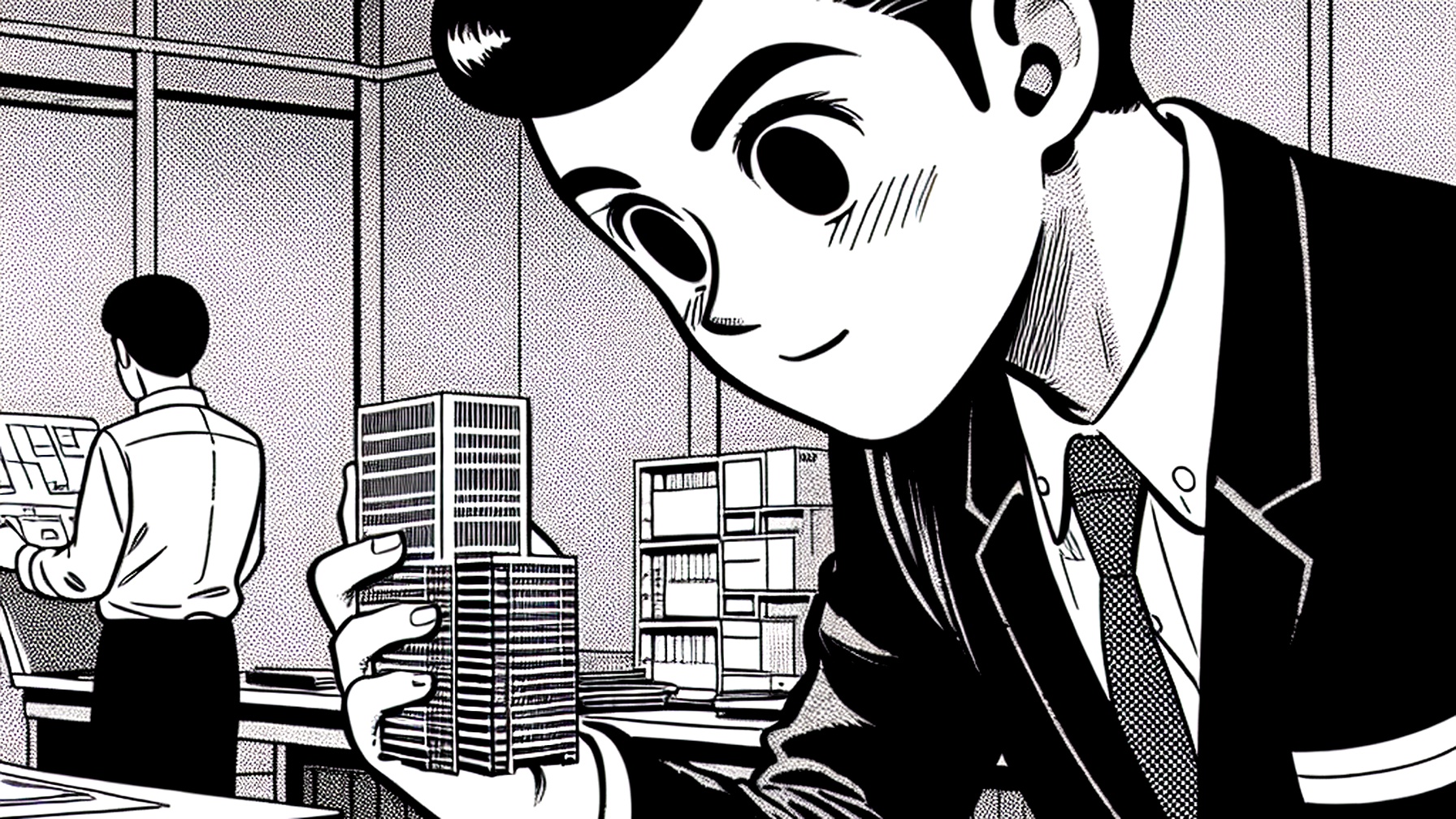
まず押さえておきたいのは、事務所物件が住居用物件とは異なる収益構造を持つ点です。事務所は「テナントが長期契約を結びやすい」「用途変更が比較的自由」の二つが大きなメリットになります。賃料単価は住居より高いものの、立地ニーズが限定されやすいため、空室期間が長引くリスクも存在します。つまり、安定した賃料を得るためには、ビジネス集積地かつ今後も企業が増えそうなエリアを選び、テナント継続率を高める施策が不可欠になります。
さらに、事務所物件は内装をテナントが負担するケースが多いため、オーナー側の修繕費負担が軽減される一方、原状回復義務が明確化されていないとトラブルに発展しやすい点に注意が必要です。契約書で退去時のルールを具体的に定め、退去精算時のキャッシュフローを読み違えないようにしましょう。
不動産投資ローンの基本構造を理解する

重要なのは、投資家自身がローンの仕組みを把握し、金融機関と対等に話せるようになることです。不動産投資ローンは事務所や店舗など「収益物件」を担保に融資が行われ、返済原資は賃料収入となります。金融機関は物件評価と借入人の属性を総合的に審査し、LTV(Loan to Value:担保掛目)とDSCR(Debt Service Coverage Ratio:返済余力)の2指標を重視します。
たとえば、LTVが80%以内、DSCRが1.2倍以上であれば審査は通りやすい傾向にあります。賃料が年間1,200万円、融資返済が年1,000万円の場合、DSCRは1.2倍と算定されます。金融機関が設定する基準を上回ることで、金利や融資期間の条件交渉がしやすくなります。また、2025年10月時点での不動産投資ローン金利は、変動型が1.5〜2.0%、10年固定が2.5〜3.0%(全国銀行協会調べ)です。これらの水準を基準にシミュレーションを行い、返済計画の妥当性を検証することが欠かせません。
固定金利を選ぶメリットと注意点
ポイントは、固定金利が「キャッシュフローの安定と引き換えに期間中の金利変更リスクを排除できる」仕組みであることです。事務所物件は賃料改定のタイミングが長く、家賃上昇で金利上昇を吸収しにくい場合があります。そのため、固定金利を選べば、市場金利の上昇局面でも返済額が増えず、収支ブレを抑えられます。
一方で、固定金利は変動型より初期金利が高く設定されるため、短期間で売却する投資戦略とは相性が悪くなります。たとえば5年後の売却を前提にする場合、変動型との差額利息が利益を圧迫する可能性があります。また、中途解約時に「固定金利補償料」が発生する金融機関もあるため、出口戦略を最初に決めておくことが大切です。
実務上は、①テナントの平均契約期間が10年以上②長期保有による減価償却メリットを狙う、というケースで固定金利が有効に機能します。減価償却により所得税を緩やかに圧縮しつつ、毎年の安定収益を確保することで、将来的な資産組み換えにも余裕が生まれるからです。
金融機関審査を突破するコツ
まず、自己資金を物件価格の20〜30%用意し、事業計画書に具体的な事務所運営シナリオを盛り込むことが重要になります。金融機関は「なぜその立地で事務所を選んだか」を重視するため、周辺のオフィス空室率や平均賃料を根拠データとして提示しましょう。国土交通省の商業地価公示(2025年版)によると、三大都市圏のビジネス地区は前年比3.1%の上昇を維持しており、賃料需要の堅調さを示しています。
また、返済負担率を下げるためには「複数行の事前打診」が効果的です。仮にA銀行が10年固定2.9%、B銀行が2.6%で提示した場合、交渉材料として双方に条件改善を求めることで、0.2ポイント程度の引き下げ余地が生まれることもあります。0.2ポイントの差は1億円を20年返済すると総返済額で約200万円の減少を意味し、投資利回りの向上につながります。
さらに、法人化して借入を行う際は、自己資本比率を30%以上確保し、直近決算で債務超過を避けることが必須です。法人実績が浅い場合は、代表者連帯保証が求められますが、2期以上黒字を継続すると保証解除交渉を進めやすくなります。金融機関との長期的な信頼関係を築き、追加融資やリファイナンスを有利にする布石となるでしょう。
変動金利との比較で見えるリスク管理
実は、固定金利と変動金利のどちらが得かは将来金利に依存するため、正解は一概に決まりません。そのため、両者の特徴を理解したうえでリスク許容度に合わせた選択が求められます。変動型は当初金利が低く、短期で売却する場合やキャッシュフローを重視する投資家に向きます。ただし、日銀が利上げに転じた場合、5年ごとに返済額が見直される仕組みを持つため、予期せぬ支出増に備えた余剰資金が必要です。
一方、固定金利は金利上昇期の保険として機能します。2025年10月時点では、変動と固定の差が約1%あるものの、仮に今後短期間で金利が2ポイント上昇すれば、固定型の方がトータル利息を抑えられるケースが増えます。したがって、「物件保有を10年以上続ける」「テナントが長期契約を結ぶ」「金利上昇リスクを強く感じる」この3条件を満たす投資家は固定金利を選ぶメリットが大きいと言えます。
実務的には、融資残高の半分を固定、残りを変動にする「ミックス融資」も有効です。これにより、金利上昇局面では固定部分で返済額を抑え、金利下落局面では変動部分で利息負担を軽減できます。金利情勢を見ながら部分的に借り換えを行うことで、総返済額とリスクのバランスを最適化できるでしょう。
まとめ
最後に、本記事で押さえたポイントを振り返ります。事務所物件は賃料単価が高く長期契約が見込める反面、立地選定と空室リスク管理が成果を左右します。不動産投資ローンを組む際は、LTVとDSCRを意識し、自己資金2〜3割を用意して金融機関交渉を有利に進めましょう。固定金利を選ぶことで、金利上昇局面でもキャッシュフローを安定させられますが、短期売却との相性には注意が必要です。また、変動金利との比較を通じて自分のリスク許容度を明確にし、場合によってはミックス融資で柔軟に対応することが賢明です。これらを踏まえ、まずは信頼できる金融機関に事前相談を行い、シミュレーションを重ねてから投資を始めてみてください。安定した事務所経営が、長期的な資産形成への確かな一歩となるはずです。
参考文献・出典
- 全国銀行協会 – https://www.zenginkyo.or.jp
- 国土交通省 地価公示2025年 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局 人口推計2025年版 – https://www.stat.go.jp
- 金融庁 主要行貸出金利推移 – https://www.fsa.go.jp
- 国税庁 減価償却資産の耐用年数表 – https://www.nta.go.jp

