多くの会社員や自営業者が「年収をもう一段階伸ばしたい」と考えるなか、アパート経営に興味を持つ人が増えています。しかし、物件価格の高騰や空室率のニュースを目にすると、不安が先に立つかもしれません。本記事では「アパート経営 収益性 年収700万」をキーワードに、投資の基礎から最新データを交えて分かりやすく解説します。読了後には、具体的に年間700万円の手残りを狙うために必要な視点と行動が明確になるはずです。
アパート経営で年収700万を狙う現実性
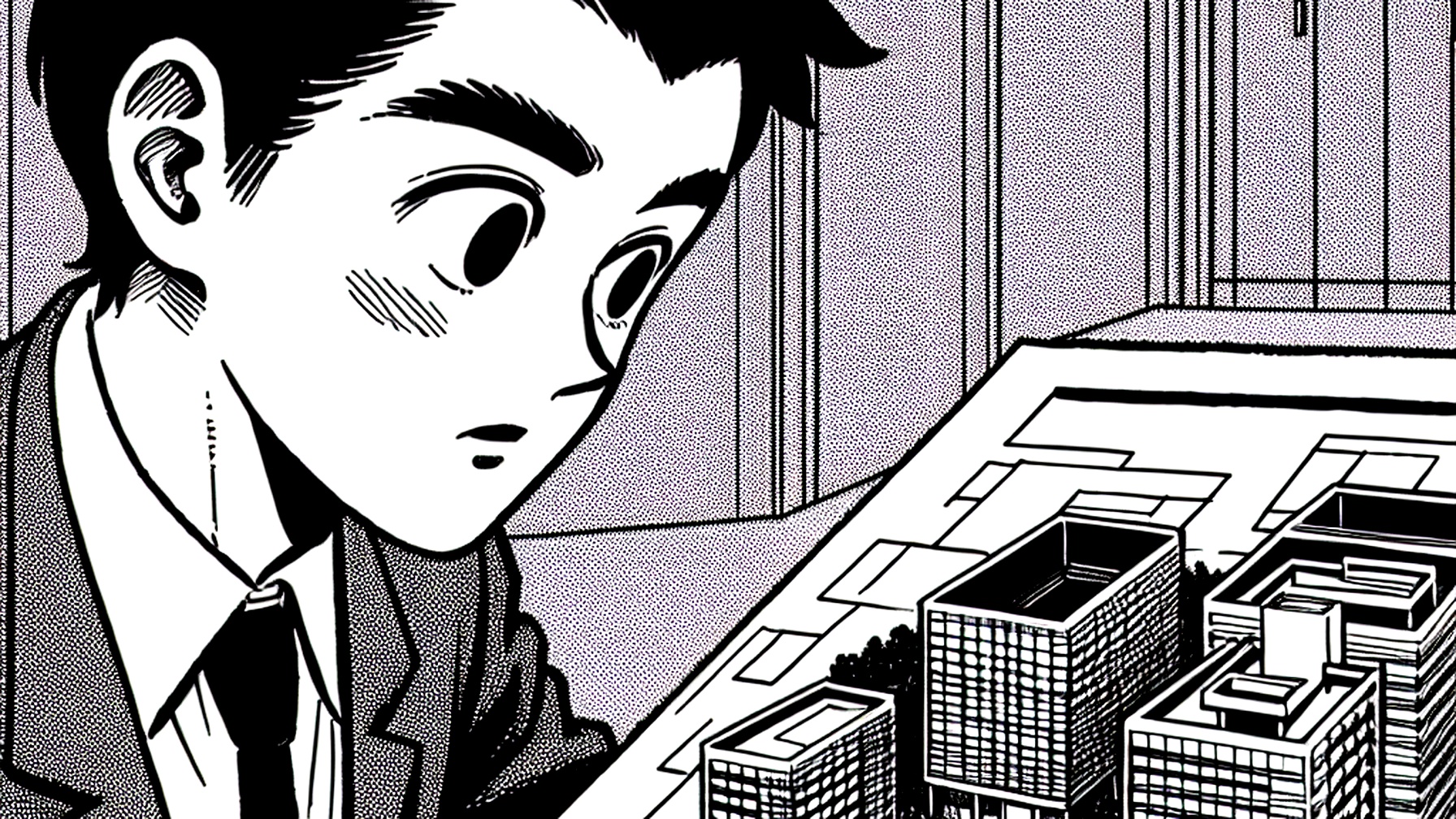
重要なのは、手取りの年間家賃収入が700万円に届くまでの道筋を具体的に描くことです。国土交通省の令和7年(2025年)住宅統計によると、2025年8月の全国アパート空室率は21.2%で前年比0.3ポイント改善しました。つまり、適切な物件管理を行えば依然として高い入居需要を取り込める余地があります。
まず、年間家賃収入が1,000万円程度で経費率30%を想定すると、手残りが約700万円になります。経費には管理委託費や修繕費、固定資産税が含まれますが、減価償却費をうまく活用することで課税所得を抑え、実質的なキャッシュフローを高めることも可能です。
一方で、1棟目から大規模な物件に挑むのはハードルが高いと感じる人も多いでしょう。その場合は、利回りの高い中規模アパートを2棟保有し、合計で1,000万円以上の家賃収入を確保する戦略が現実的です。複数物件に分散することで、空室リスクも抑えられます。
収益性を左右するキャッシュフローの考え方
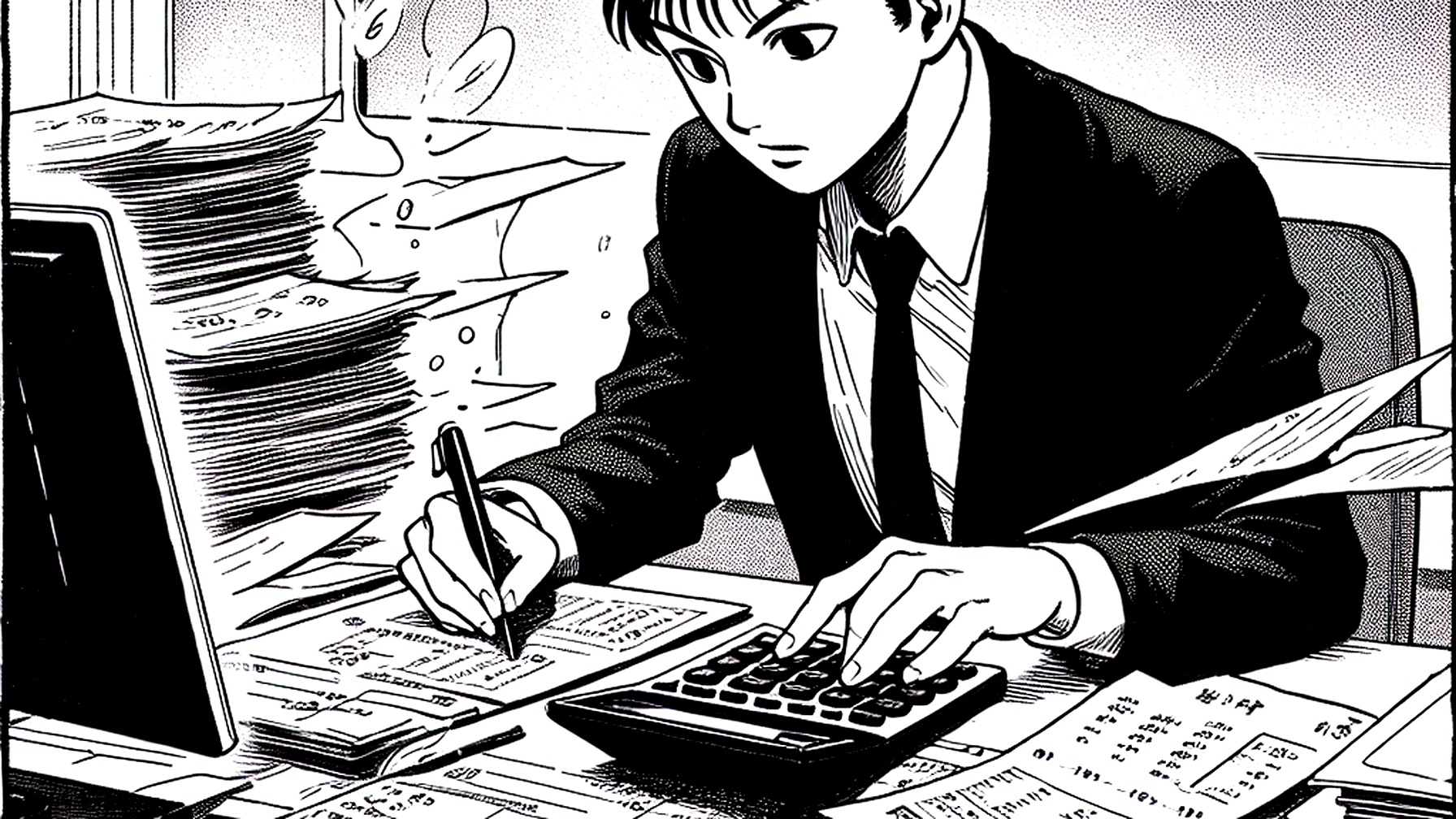
ポイントは、表面利回りよりも実質利回り、つまりキャッシュフローに目を向けることです。表面利回りだけを追うと、古い物件や郊外エリアが魅力的に見えますが、修繕費や広告費がかさみ、本当の手残りが減ってしまうことがあります。
例えば、家賃収入800万円、年間経費250万円、ローン返済250万円のケースでは、手残りは300万円です。ここで空室が2室発生し年間家賃が80万円減ると、手残りは220万円へ一気に下がります。つまり、家賃に対する固定費の割合をなるべく小さく保つ運営が欠かせません。
また、2025年度も継続している住宅ローン控除適用条件を満たす住戸併設型アパートなら、自宅部分の金利控除を受けつつ賃貸収入を得る方法もあります。自らが入居者となることで、管理の目が行き届きやすく、空室対策にもプラスに働きます。
成功する物件選びと立地分析
まず押さえておきたいのは、エリア需要の把握です。人口動態データを見ると、2025年現在でも20代後半から30代前半の単身世帯は都市圏への流入が続いています。したがって、最寄り駅から徒歩10分圏内でワンルーム需要が堅調なエリアを選ぶことが、空室リスクを抑える王道の戦略です。
一方で、郊外でも大学や病院が集まる地域は安定した需要があります。具体的には、総合病院まで車で10分以内、大学の学生数が5,000人以上といった指標が目安になります。現地調査では、平日昼間と夜の人通りを自分の目で確認し、駅からの導線に暗所がないか、安全性をチェックしましょう。
実は、築古物件を再生することで高い利回りを得るケースも増えています。ただし、1981年以前の旧耐震基準物件は、耐震補強工事に多額の費用がかかるため、施工後の利回りシミュレーションを綿密に行う必要があります。
融資と税制を味方に付ける方法
まず金融機関選びが収益性に直結します。都市銀行は金利が低めですが、自己資金20%以上を求められる傾向があります。地方銀行や信用金庫は金利がやや高いものの、柔軟な融資姿勢を示すことが多いです。2025年10月現在、アパートローンの固定金利は年1.6%前後、変動金利は年1.0%前後が目安です。
自己資金を抑えたい場合は、物件評価額と収益性が両立する案件を選び、フルローンも視野に入ります。ただし、フルローンでは毎月の返済額が重くなるため、金利上昇リスクをヘッジする手段として固定金利期間選択型を組み合わせると安心です。
税制面では、減価償却費が節税効果の要です。木造アパートの耐用年数は22年ですが、中古の場合は残存耐用年数の計算によって償却期間が短くなり、初年度から大きな経費計上が可能になります。加えて、2025年度の「住宅省エネ性能向上支援事業」の補助対象となる断熱改修を行えば、ランニングコストを抑えながら入居率アップも期待できます。
リスク管理と長期運営のコツ
実は、安定収益を続けるためには「短期の利益」より「長期の関係づくり」がカギになります。管理会社とのコミュニケーションを密に取り、入居者対応の品質を高めることが空室率低下に直結します。国土交通省の調査でも、退去理由の上位には「管理対応への不満」が毎年挙がっています。
さらに、設備投資のタイミングを計画的に行うことが収益性を底上げします。エアコンや給湯器は10年周期で更新すると、故障による空室期間を減らせます。費用を平準化させるために、毎月の家賃収入から設備更新用の積立金をあらかじめ確保する仕組みを作りましょう。
最後に、自然災害リスクも無視できません。火災保険に加え、2025年度から補償内容が拡充された地震保険特約を付帯することで、復旧資金を確保できます。保険料は経費計上できるため、実質負担は小さくなります。
まとめ
ここまで「アパート経営 収益性 年収700万」をテーマに、物件選びから税制まで幅広く見てきました。ポイントは、キャッシュフローを正しく把握し、空室率を下げるエリアと管理体制を整えることです。また、金融機関の特性や補助制度を活用し、長期視点でリスク分散を図れば、年間700万円の手残りは十分に射程圏内に入ります。今できる第一歩として、気になるエリアの空室率と家賃相場を調査し、数字をもとに自分だけの収益計画を作ってみてください。着実な準備が、将来の安定収入への近道になります。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 令和7年度版 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 統計局 「住民基本台帳人口移動報告」2025年版 – https://www.stat.go.jp
- 日本銀行 「短期金融市場レポート」2025年9月号 – https://www.boj.or.jp
- 財務省 「法人税法 令和7年度改正概要」 – https://www.mof.go.jp
- 経済産業省 「住宅省エネ性能向上支援事業 2025年度」 – https://www.meti.go.jp

