新型コロナが収束に向かい、人の動きが戻った今こそ「マンション投資 アフターコロナ 一棟買い」に挑戦したいと考える方が増えています。しかし、テレワーク定着や金利上昇の懸念など、以前とは違う市場環境に不安を覚えるのも事実です。本記事では、最新の価格動向から資金計画、2025年度に有効な制度までを整理し、初心者でも失敗しにくい一棟買いのポイントをわかりやすく解説します。読み終えるころには、市場の見通しと具体的な行動手順がイメージできるはずです。
アフターコロナで変わったマンション市場の今
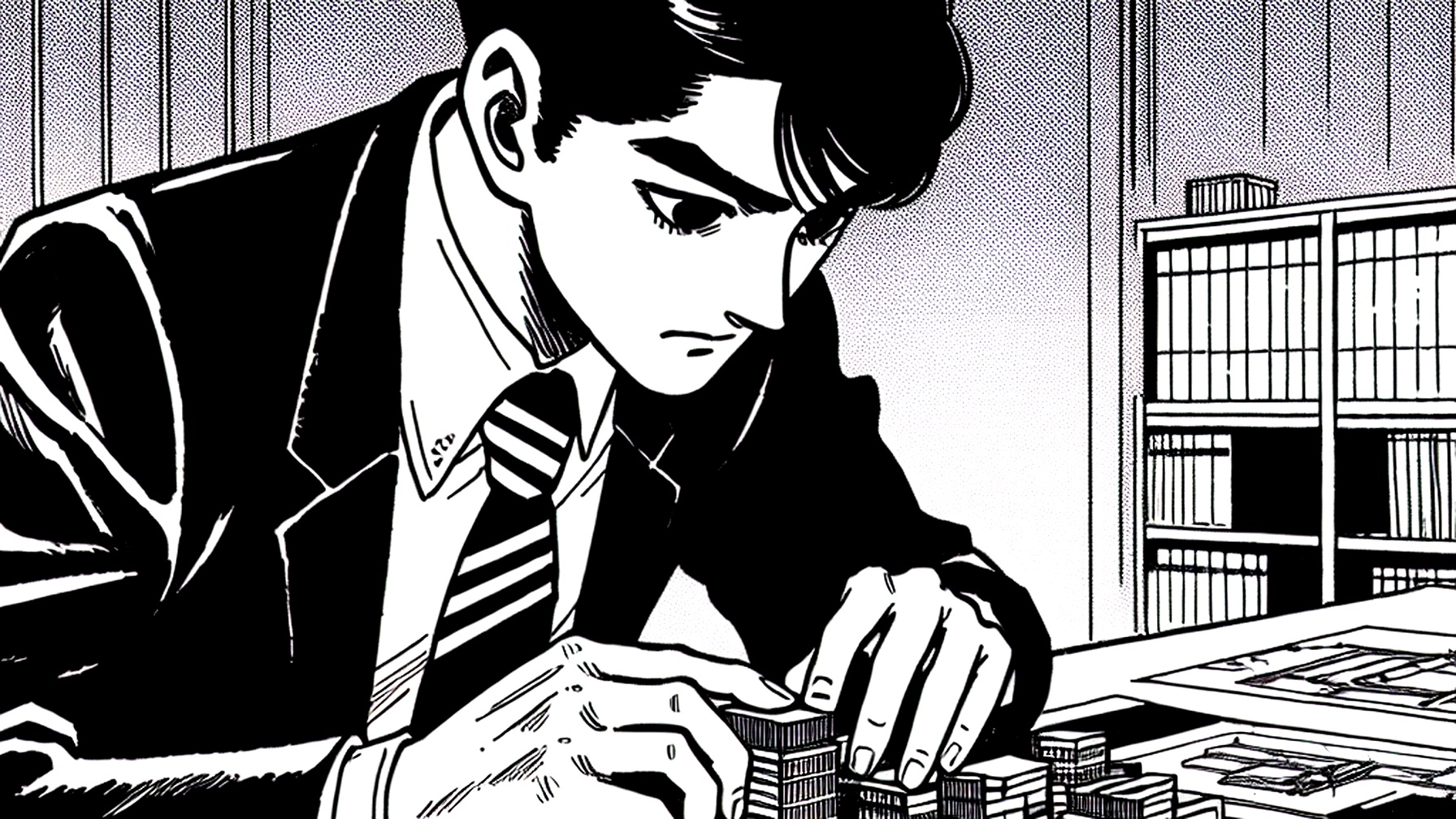
重要なのは、市場全体の空気を正しく読むことです。2025年10月の調査では、東京23区の新築マンション平均価格は7,580万円で前年比3.2%上昇しました。リベンジ消費と都心回帰の動きが同時に進み、価格は高止まりしています。一方で国土交通省の空室率データを見ると、ワンルームよりファミリータイプの空室が増え、需要のゆがみが生じています。つまり、間取りの選択は慎重さが求められます。
次に注目すべきはテレワーク比率の低下です。総務省統計局の調査では、在宅勤務常態化率は2023年の21%から2025年には14%へ下がりました。この数字は都心駅近の賃貸需要を再び押し上げています。また、インバウンド観光客は2019年比で95%まで回復し、民泊転用を視野に入れる投資家も増えました。しかし民泊新法の改正により、営業日数や設備基準が厳格化された点には注意が必要です。
加えて、金融環境も変化しています。日銀は2025年春にマイナス金利を解除し、都市銀行の変動金利は平均1.2%台まで上昇しました。金利上昇はキャッシュフローを圧迫しますが、長期固定金利を選択すればリスクを抑えられます。日本政策金融公庫の統計によると、固定20年1.5%の商品が人気を集めています。アフターコロナの投資戦略は、立地だけでなく金利動向の把握が欠かせません。
一棟買いのメリットとリスク
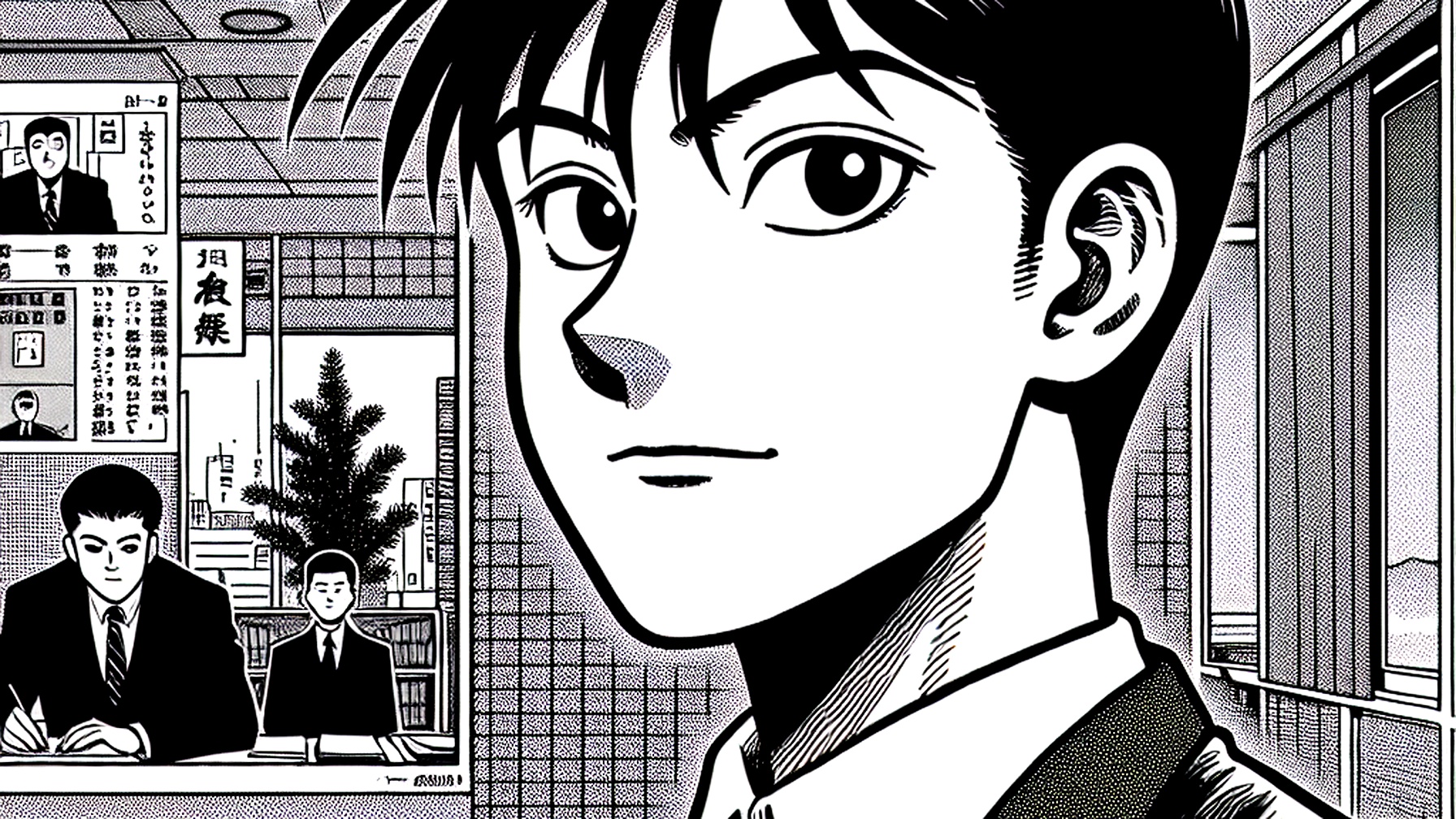
まず押さえておきたいのは、一棟買いが戸別購入とは異なる収益構造を持つ点です。最大のメリットは、複数戸をまとめて管理できるため経費効率が高いことです。管理会社への委託手数料も一括契約で下がりやすく、修繕計画を自分の裁量で組めます。賃料設定の自由度が高いことも魅力で、専有面積や内装を統一してリノベーションすることで付加価値を一気に高めやすくなります。
しかし、リスクも比例して大きくなります。空室が出れば一度に家賃収入が大きく減り、資金繰りへ直撃します。加えて、築古物件では給排水管や屋上防水など大規模修繕のタイミングが重なりやすく、数百万円単位の突発支出が発生することがあります。実は、金融機関の目線も厳しく、一棟物は個人より法人名義の融資が主流です。その場合、自己資金2〜3割と別に、6か月分の返済原資を求められるケースが一般的になっています。
一棟買いを検討する際は、物件の減価償却年数も計算しましょう。木造は22年、RC造(鉄筋コンクリート)は47年という税法上の耐用年数があるため、築古RCを買えば短期で大きな損金計上が可能です。つまり、キャッシュフローが薄い初期段階でも、節税効果で手残りを確保できる場合があります。ただし、節税効果が切れた後の収益力も同時にチェックしなければ、期待利回りを維持できません。
成功する立地・物件選びの視点
ポイントは、人口動態と再開発計画の二つを組み合わせて考えることです。東京都の将来人口推計では、23区全体は2029年まで緩やかに増加し、その後横ばいとなる見込みです。ところが区別に見ると、港区や中央区は世帯数が増える一方、板橋区や足立区は減少傾向に転じると予測されています。つまり、同じ都内でもエリア選定で空室リスクが大きく変わります。
再開発は賃料上昇の起爆剤になります。例えば品川駅周辺はリニア中央新幹線のターミナル工事が進み、国交省資料では2029年以降までオフィス需要が高まり続ける見込みです。このような将来的な需要を見込めるエリアなら、表面利回りが低くても価値の上昇余地があります。一方で再開発が完了し供給過剰が懸念される湾岸部の一部では、賃料が横ばいになりやすい点に注意しましょう。
物件自体のチェックでは、築年数と修繕履歴が最優先です。築20年を超えると外壁や屋上防水の更新が必要になり、国土交通省のガイドラインでは10年周期で大規模修繕を推奨しています。過去の修繕記録が残っていない物件は、将来の支出予測が立てにくいため避けるのが無難です。また、単身者向け中心の物件なら全戸数の10%程度はファミリー向けにリノベーションできるかを考えると、賃料源の多角化につながります。
最後に、取引事例比較法を用いて適正価格を見極めることも欠かせません。レインズ(不動産流通機構)の成約データを調べ、直近3か月の坪単価を参考にします。相場より1割以上高い場合でも、将来の再開発や駅の新設計画があるなら検討余地があります。逆に、利回りだけを頼りに相場より安い郊外物件へ飛びつくと、長期空室のリスクを抱え込みやすいので注意が必要です。
資金計画と融資戦略
実は、一棟買いの成否は資金計画で八割決まるといわれます。まず、購入総額の25%は自己資金として用意するのが近年の主流です。金融庁の融資モニタリング強化以降、頭金ゼロ融資は極めて稀になりました。さらに、修繕積立金として最低でも年間家賃収入の10%を別口座に確保してください。こうした余裕資金が、突発的な空室や修繕費用に備える安全弁となります。
融資面では、金利タイプと期間のマッチングが鍵です。長期保有が前提なら、固定金利でキャッシュフローを安定させるほうが安心です。たとえば、地方銀行Aでは固定30年1.7%、変動10年0.95%の選択肢が提示されており、月々の返済差額は3,000万円借入時で約3万円です。この差額を保険料と考え、金利上昇リスクを転嫁する発想も有効です。
一方、短期での売却益狙いなら変動金利を活用し、繰上返済を織り込んだシミュレーションを行います。収支計算では、空室率15%、修繕費5%上乗せの厳しめシナリオを作成します。日本政策金融公庫のテンプレートを使えば、返済比率や債務償還年数を自動計算できるため便利です。投資判断は、あくまで最悪のケースでも自己資金が枯渇しないかを基準にすると失敗を避けやすくなります。
さらに、法人設立による節税効果も検討しましょう。利益800万円以下の法人税率は15%と個人の所得税より低く、給与所得控除を活用した所得分散も可能です。ただし、設立費用や社会保険料の負担が増えるため、年収500万円以上の家賃収入が見込めるかを一つの目安にしてください。税理士へ早めに相談し、個人と法人どちらが最適か判断することが大切です。
2025年度の制度・税制優遇を押さえる
まず、2025年度も継続される「住宅ローン減税」は、賃貸併用住宅に限り投資家が利用できます。自宅部分が床面積の50%以上であることが条件ですが、自己居住戸と賃貸戸を合わせた一棟買いでは大きな節税効果を狙えます。控除期間は原則13年で、借入残高上限は4,000万円、控除率は0.7%です。投資専用マンションでは使えない点に注意してください。
次に、国土交通省の「賃貸住宅エコ改修支援事業(2025年度)」があります。これは、断熱性能の向上や高効率給湯器の導入に対して、工事費の1/3以内・上限150万円の補助が受けられる制度です。期限は2026年3月末契約分までで、先着順のため早めの申請が必要です。省エネ性能の向上は賃料アップに直結しやすく、補助金を活用すれば投資回収期間を短縮できます。
また、市区町村単位で導入が進む固定資産税の軽減措置も見逃せません。東京都では、2025年度に耐震改修を行った賃貸住宅について、翌年度の固定資産税を1/2に減免する制度が継続されています。耐震診断費用も助成対象になる場合が多く、築古RC物件のバリューアップに役立ちます。具体的な条件は自治体によって異なるため、購入前に必ず確認しましょう。
最後に、不動産取得税の軽減措置は2026年3月まで延長が決定しています。新築または取得後1年以内の中古住宅で、一定の耐震・断熱基準を満たす場合、税額が最大1/2軽減されます。一棟買いで数千万円規模の物件を取得する場合、数十万円の節税インパクトが期待できます。こうした制度は予算枠に達すると終了する可能性があるため、適用要件を早めに確認し、スケジュールを逆算することが成功への近道です。
まとめ
本記事では、アフターコロナで変貌するマンション市場の動向から、一棟買い特有のメリットとリスク、そして2025年度の制度活用までを解説しました。立地と物件選定では人口動態と再開発計画の両面を確認し、資金計画では厳しいシナリオを前提に余裕資金を組み込みましょう。金利上昇局面では長期固定金利も選択肢となり、法人化による節税効果も視野に入ります。さらに、住宅ローン減税やエコ改修補助など期限付きの制度を上手に使えば、投資回収を早めることが可能です。まずは自分の投資目的を明確にし、現地調査とシミュレーションを徹底するところから始めてください。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省「住宅市場動向調査」 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局「就業構造基本調査」 – https://www.stat.go.jp
- 日本政策金融公庫「不動産業向け融資実態」 – https://www.jfc.go.jp
- 東京都都市整備局「都市計画情報」 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp

