不動産投資に踏み出すとき、多くの人は物件選びばかりに気を取られます。しかし実際には、どの金融機関からどのような条件で資金を借りるかが成否を大きく左右します。金利だけを比較して「安い方が得だ」と判断するのは危険で、返済期間や審査基準、融資手数料まで含めた総コストを把握する必要があります。本記事では「収益物件 融資条件 VS」をテーマに、銀行とノンバンクの違い、審査の視点、最新の優遇制度の活用法までを体系的に解説します。読み終える頃には、自分に合った資金調達方法を具体的にイメージできるはずです。
銀行融資とノンバンクの違い
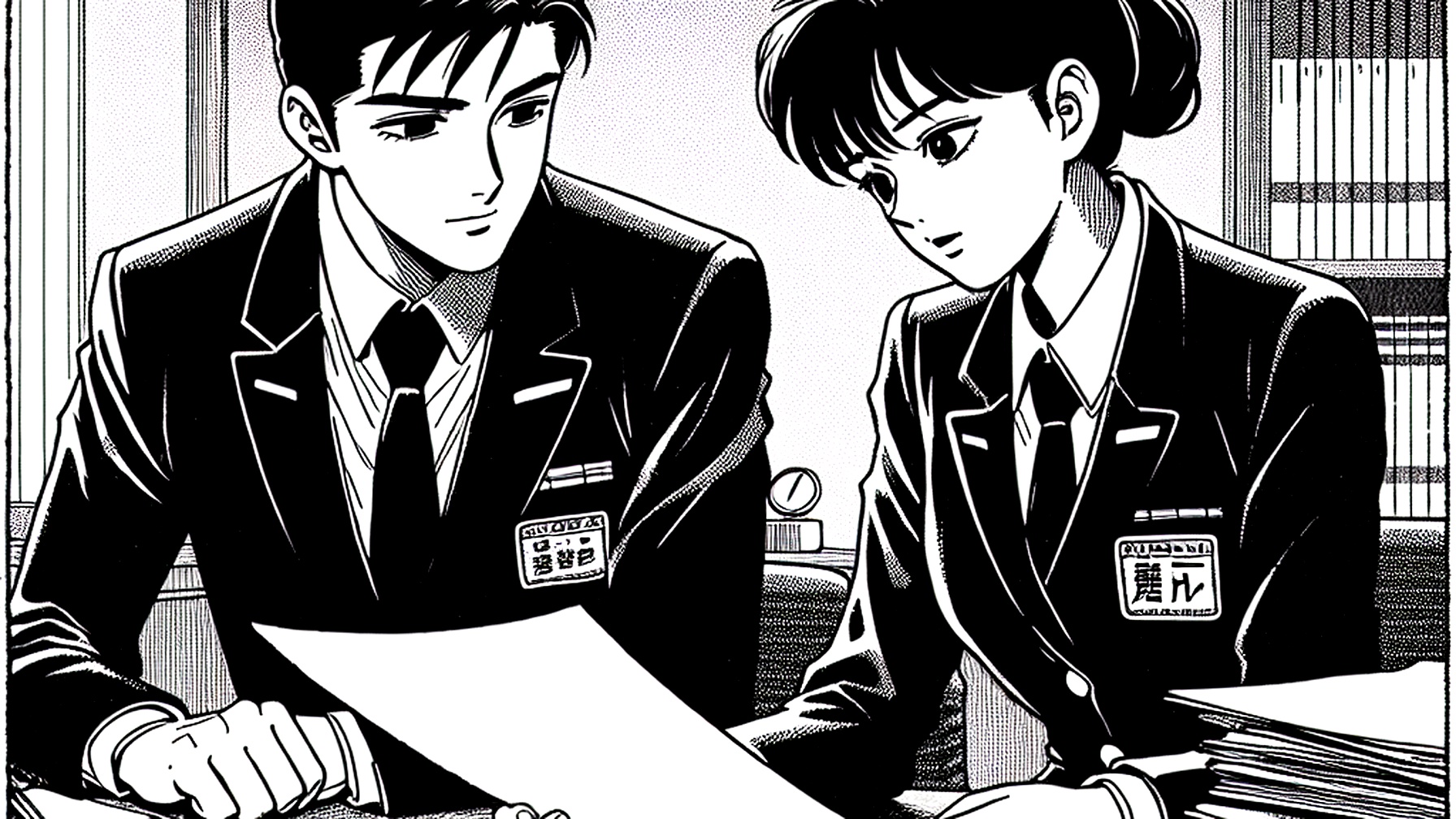
まず押さえておきたいのは、借入先によって資金調達の性格が大きく変わる点です。銀行は金利が低めで長期借入が可能ですが、審査が厳格で自己資金や勤続年数を重視します。一方でノンバンクは金利が高いもののスピード審査が魅力で、事業計画の将来性が響けば自己資金が少なくても借入できる場合があります。
銀行の融資は返済期間が20〜35年と長いことが多く、毎月のキャッシュフローを安定させやすいメリットがあります。しかし、家賃下落や空室リスクを保守的に見たシミュレーションを求められるため、楽観的な計画では通りません。ノンバンクの場合は最長15〜20年が一般的で、その分月々の返済額は大きくなります。高利回り物件で早期に売却益を狙う投資家に向くといえます。
さらに、保証料や事務手数料の有無も総コストを左右します。銀行では金利の中に保証料が含まれるタイプと外付けタイプがあり、外付けでは借入額の2%前後が一括払いになる例が多いです。一方、ノンバンクは事務手数料が数十万円程度に抑えられることもあるため、短期で完済する計画ならトータル費用が逆転する可能性があります。
空室リスクに備えた繰上返済の自由度も確認が必要です。銀行は繰上返済手数料が数万円かかることがありますが、ノンバンクでは無料のケースが増えています。つまり、長期安定を目指すなら銀行、柔軟に元本を減らしたいならノンバンクと、投資戦略に応じた使い分けが重要です。
金利だけでは測れない総コスト
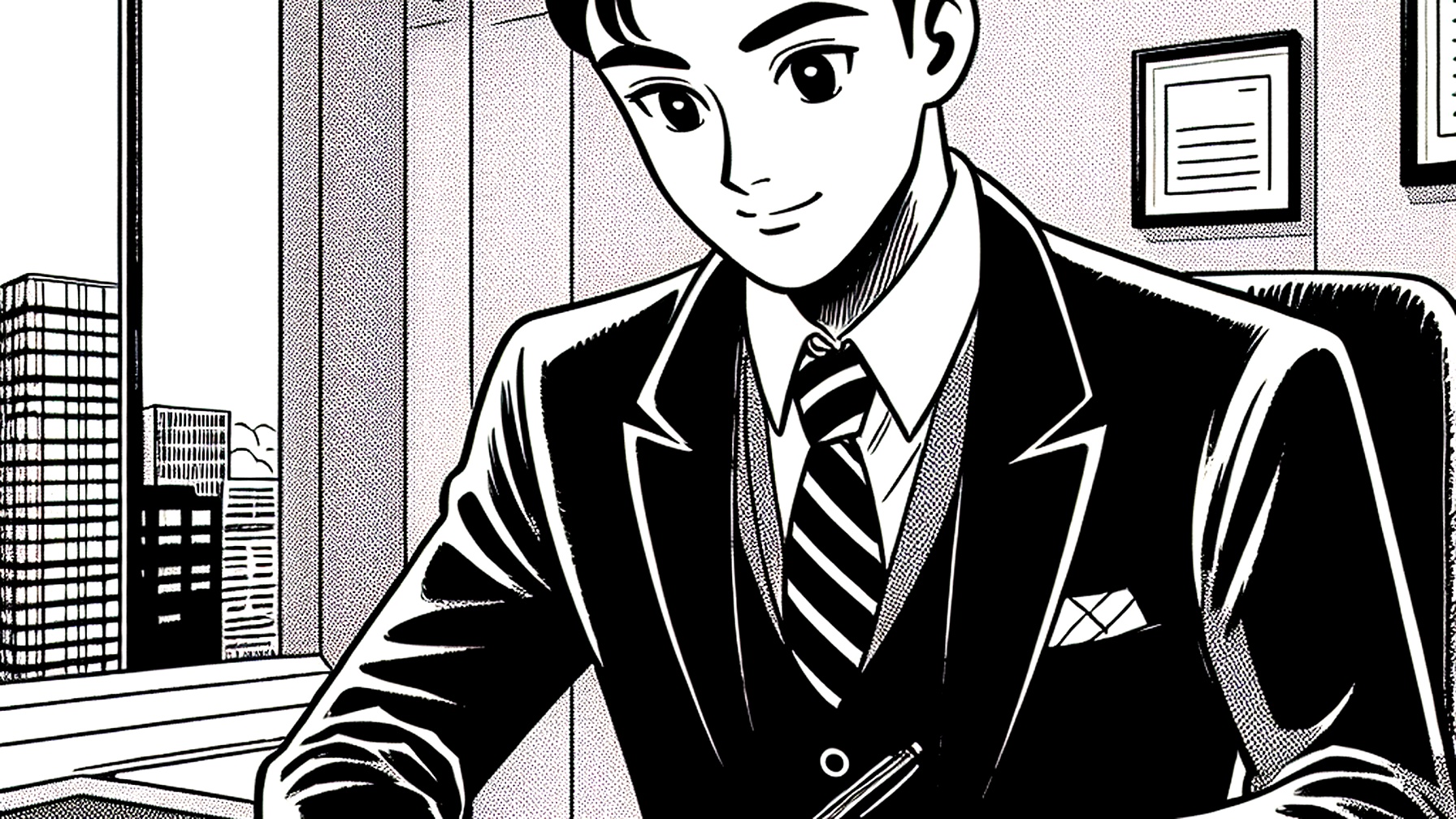
実は、表面金利が低くても総返済額が高くなるケースは珍しくありません。金利タイプ(固定か変動か)、団体信用生命保険(以下、団信)の有無、繰上返済手数料を合わせて考えることで、初めて実質的な負担が見えてきます。
日本銀行の2025年9月時点データによると、主要都市銀行の投資用ローン変動金利は平均2.8%前後です。しかし、全期間固定型では3.5%程度まで上昇します。将来の金利上昇リスクをどう捉えるかで、どちらが得かは変わります。たとえば残債3000万円・期間25年のケースで、金利が1%上がると総返済額は約420万円増える試算になります。
さらに団信の保険料を忘れてはいけません。銀行は金利に0.3〜0.4%上乗せでワイド団信を組み込むことが多く、健康状態に不安がある投資家には安心材料となります。一方、ノンバンクでは団信が任意加入になっている場合もあり、保険料を別途支払うか、そもそも加入できないリスクも存在します。
加えて、修繕積立や入居者募集の広告費といったランニングコストを資金計画に折り込むことが欠かせません。国土交通省「不動産投資市場動向調査」によると、築15年以上の物件では毎年平均家賃の7〜10%を修繕費として見ておくと安全圏です。金利比較に気を取られるあまり、これらの支出を過小評価すると、せっかくの高利回りが帳消しになりかねません。
審査基準のチェックポイント
重要なのは、金融機関が何を見て「貸せる」と判断しているかを知ることです。審査は大きく「個人属性」「物件評価」「事業計画」の三本柱で構成されます。中でも属性については、年収700万円が一つの目安と言われますが、自己資金比率や副業収入でカバーできる場合もあります。
物件評価では、積算価格と収益還元価格のどちらに重きを置くかが機関ごとに異なります。積算重視の地方銀行では、RC造(鉄筋コンクリート造)やSRC造の物件が有利になる傾向があります。一方、収益還元を重んじる都心のメガバンクでは、立地の将来性や賃料の下落余地を細かくチェックします。同じ物件でも評価額が1000万円以上開くことがあるため、複数行に同時打診するのがセオリーです。
事業計画で見られるのは、空室率や修繕費をどの程度盛り込んでいるかという保守性です。例えば、家賃下落率を年1%と設定するか、2%とするかで、30年後のキャッシュフローに大きな差が生まれます。金融機関は過去のデータをベースに、想定が甘いか厳しいかを判断してきます。つまり、現実的な数字を示しつつ、リスクへの対応策を具体的に記載した計画書が、審査突破の鍵になります。
最後に、個人信用情報と過去のローン履歴も厳格に確認されます。クレジットカードの遅延が複数回あるだけで、金利が0.5%上乗せになるケースもあります。投資を考え始めた段階で、まず自身の信用情報をチェックし、不要な借入を整理しておくことが有効です。
2025年度の優遇制度を活用する
ポイントは、制度の恩恵が自己居住用に偏りがちな中で、投資用でも使えるものを見逃さないことです。2025年度も継続している「省エネ性能向上リフォーム融資」は、その代表例です。対象は築20年以上の賃貸住宅で、省エネ改修によりBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)評価を取得すると、金利が最大0.3%引き下げられます。
また、地方自治体によっては空き家を収益物件として再生する計画に補助金を出す取り組みが続いています。例えば、人口減少が進む地方都市では、改修費の3分の1を上限200万円まで補助する制度があるため、自己資金を温存しながら物件価値を高めることが可能です。ただし、申請には工事契約前の事前相談が必須で、予算枠に達すると締め切られる点に注意が必要です。
法人スキームでの投資を検討している場合、日本政策金融公庫の「中小企業経営力強化資金」が活用できます。2025年度条件では、固定金利1.11%(10年以内)という低水準で、事業計画の妥当性が評価基準です。個人で借りるよりも融資枠を広げやすく、修繕費も同時に調達できるメリットがあります。
ただ、優遇制度は申請書類が多く、審査期間も長めになります。スケジュールに余裕を持ち、融資決定前に工事を始めないことが鉄則です。制度の詳細は必ず最新の要綱を確認し、必要に応じて行政書士や税理士に相談すると安心です。
キャッシュフローを守る返済戦略
基本的に、不動産投資は長期運用でこそ安定します。そのためには、返済計画を「最悪のシナリオ」に合わせておくことが欠かせません。例えば、空室率を20%に設定し、家賃下落を年2%で試算しても手残りが出るかを確認します。手残りがマイナスになるなら、融資額を減らすか、返済期間を延ばす必要があります。
繰上返済のタイミングも計画的に行うことで、利息総額を大幅に削減できます。国税庁の「民間給与実態統計」によると、平均賞与は約70万円ですが、その30%を繰上返済に充てるだけで、25年ローンの総返済額が100万円以上軽くなるケースがあります。ただし、繰上返済手数料が高いとメリットが薄れるため、契約時点で「手数料無料」もしくは「一部無料」の条件を確保しておくと安心です。
一方で、手元資金を全て返済に回すのは危険です。修繕リスクや突発的な空室対策費に備えて、家賃収入の3か月分以上を運転資金として確保しておくと、資金ショートを回避しやすくなります。言い換えると、返済と内部留保のバランスがキャッシュフロー経営の肝となります。
最後に、定期的な金利交渉を忘れないことです。借入先の業績や市場金利の低下に合わせて、金利見直しを申請すると、0.2〜0.3%の引き下げにつながることがあります。一度でも金利が下がれば、残りの期間全体で数十万円単位の効果が期待できるため、半年ごとに試算してみる価値があります。
まとめ
本記事では、収益物件の融資条件を銀行とノンバンクで比較し、金利以外の総コスト、審査基準、2025年度の優遇制度、そして返済戦略までを整理しました。要するに、自身の投資目的とリスク許容度をはっきりさせ、複数のシナリオでキャッシュフローを検証する姿勢が成功の近道です。これから物件を探す方は、物件情報と同時に融資相談も進め、最新の制度や金利動向をキャッチアップしながら、最適な資金調達を実現してください。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産投資市場動向調査 2025年版 – https://www.mlit.go.jp/
- 日本銀行 金融システムレポート 2025年9月 – https://www.boj.or.jp/
- 全国銀行協会 住宅ローン金利推移データ – https://www.zenginkyo.or.jp/
- 総務省 統計局 人口推計 2025年10月 – https://www.stat.go.jp/
- 国税庁 民間給与実態統計調査 2024年分 – https://www.nta.go.jp/

