不動産投資を考え始めたとき、多くの人は「そもそも収益物件で何を重視すればいいのか」と迷います。利回りや立地だけでなく、資金計画や制度の活用など複数の視点が絡み合うため、初心者ほど判断が難しいものです。本記事では、収益物件を選ぶ際の基本から2025年度時点で利用できる制度、リスク管理までを丁寧に解説します。読み終えるころには、自分に合った物件選びの軸が見え、次の一歩を踏み出す自信が生まれるでしょう。
収益物件とは何かを理解する
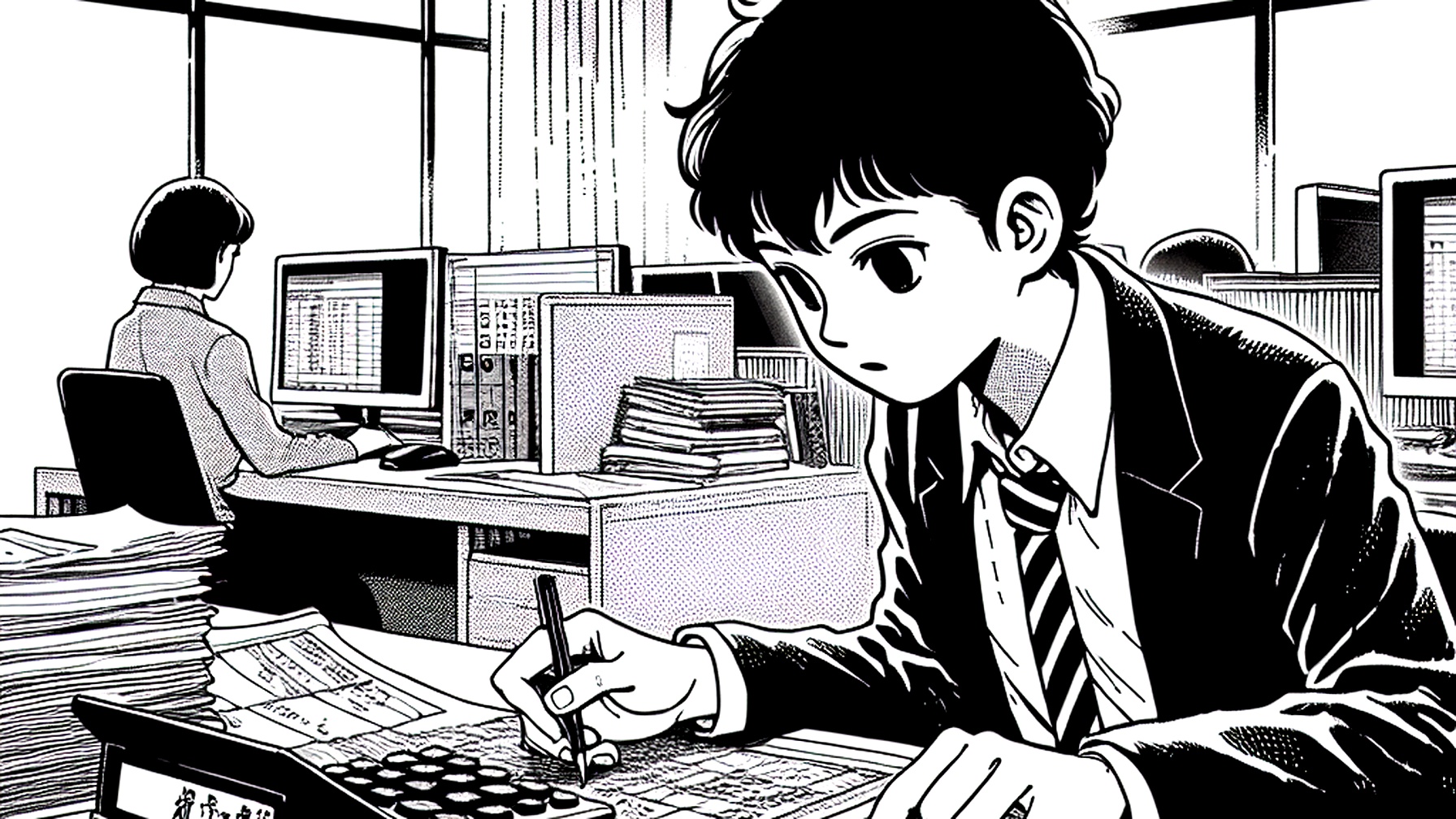
まず押さえておきたいのは、「収益物件」という言葉が指す範囲です。不動産業界では、家賃収入や売却益などキャッシュフローを生む物件全般をこう呼びます。区分マンションや一棟アパート、さらには商業ビルまで多岐にわたるため、投資目的に応じた選択が欠かせません。
区分マンションは少額から始めやすく流動性も高い一方、管理費や修繕積立金が毎月発生します。一棟アパートは戸数が多いため空室が出ても収入がゼロになりにくいですが、修繕費用が大きく突発的に発生するリスクが高まります。また、戸建てのサブリース運用は長期入居が期待できるものの、地域の人口動向に強く左右される特徴があります。
総務省「住宅・土地統計調査2023」によると、全国の空室率は13.6%で、特に郊外の木造アパートで数字が高い傾向にあります。つまり収益物件を「何を」選ぶかは、空室率を含む市場環境を同時に読み解く必要があるのです。自分のリスク許容度と資金力を照らし合わせ、物件種別を決めることがスタートラインとなります。
利回り計算で押さえるべきポイント

重要なのは、表面利回りだけを見て判断しないことです。表面利回りは年間家賃収入を物件価格で割っただけの単純な指標で、管理費や修繕費を含めないため、実態とかけ離れた数字になりやすいのです。
実利回りを計算する際には、年間家賃から管理費、固定資産税、将来の大規模修繕積立を差し引きます。国土交通省「賃貸住宅修繕費実態調査2024」によれば、築20年を超えるアパートでは10年あたり平均280万円の外壁改修費が発生しています。この数値を念頭に置き、毎月のキャッシュフロー計算書に反映させると過度な期待値を避けられます。
また、家賃下落シナリオを織り込むことも欠かせません。日本銀行「住宅市場動向レポート2025」は、東京23区の平均家賃が年0.3%の緩やかな下落傾向にある一方、地方都市では下落幅が1%以上になるケースが示されています。つまり将来の家賃調整を2段階で見積もり、資金繰りに余裕を持たせることが安全策となります。
加えて、金融機関が重視するのは返済比率です。毎月返済額が家賃収入の70%を超えると追加融資が難しくなる傾向があります。融資審査で不利にならないためにも、実利回りを正しく把握し、最低でもキャッシュフローが毎月プラス5万円程度を維持できるシミュレーションを作成することが求められます。
良い立地と市場調査の進め方
ポイントは、駅距離や人口だけでなく、用途地域や将来計画まで含めた多面的な視点です。立地調査では「現在の需要」と「将来の供給バランス」を同時に検証することで、長期の安定収入を確保しやすくなります。
国土交通省の地価公示2025によると、再開発計画のある準工業地域は平均で前年比3.2%上昇しています。再開発が進むエリアは住宅供給も進むため、賃料維持につながる可能性が高いといえます。一方で、郊外の第一種低層住居専用地域は地価が横ばいでも空室率が高止まりしているケースが多く、収益性は低下しがちです。
現地調査では平日昼と夜、休日の3回に分けて人通りを観察するだけでも、入居者の属性を推測できます。例えば昼間は高齢者が多く夜は学生が増える地域では、間取りと設備をターゲットに合わせて調整することで空室リスクを下げられます。さらに、近隣の家賃相場を不動産ポータルだけでなく、実際の募集図面で比較すると、募集賃料と成約賃料のギャップを把握できます。
将来の人口動向も見逃せません。総務省「地域別将来人口推計2024」では、地方中核都市でも中心部はわずかながら人口増が続く一方、周辺部は減少傾向が明確です。人口流入が期待できるエリアに絞り込むことが、安定した入居率を生む最もシンプルな方法になります。
ファイナンスと資金計画の基礎
実は、融資の組み方次第でキャッシュフローは大きく変わります。自己資金割合、金利タイプ、返済期間を最適化することで、同じ物件でも利回りが向上する場合が珍しくありません。
自己資金を物件価格の20%用意すると、金融機関の審査で金利が0.3%ほど下がるケースがあります。金融広報中央委員会の統計では、0.3%の金利差は3000万円借入・30年返済の場合、総返済額に約150万円の差を生むとされています。つまり頭金を増やすことは、長期的にはコスト削減策になるのです。
返済期間は長いほど毎月返済額が下がりキャッシュフローが改善しますが、総支払利息は増えます。たとえば25年と30年で比較すると、月々の支払差は約1.2万円でも総利息差は200万円以上になる場合があります。リスク許容度が高く早期返済を目指すなら短期、キャッシュフロー重視なら長期と、目的を明確にして選択することが大切です。
融資先の比較も欠かせません。地方銀行や信用金庫は地域密着で柔軟な審査が期待できますが、金利がやや高い傾向です。ネット銀行は金利が低くても、法人名義融資で自己資金30%以上を求める例があります。複数行に同時打診し、条件面を数値で並べて検討するプロセスが、後悔のない資金計画を支えます。
2025年度の制度とリスク管理
まず押さえておきたいのは、2025年度に実施されるエネルギー性能向上に関する補助制度です。「2025年度 賃貸住宅省エネ化推進事業」では、断熱改修や高効率給湯器の導入費用の3分の1(上限150万円)が補助対象になります。期限は2026年2月末までの着工分で、賃貸住宅も対象となるため、改修を計画している投資家には魅力的な選択肢となるでしょう。
一方、自然災害リスクも増しています。気象庁の統計では、2020年代に入ってから台風の線状降水帯発生回数が年平均1.8回に増え、洪水被害のリスクが高まっています。ハザードマップの確認はもちろん、保険料の比較も必須です。火災保険は築年数や構造で料率が変わり、RC造は木造より約30%割安になるケースがあります。
さらに、インフレと金利上昇に備える視点も欠かせません。日本銀行は2025年4月に長期金利誘導目標を0.75%に引き上げ、市場金利は徐々に上昇傾向です。固定金利と変動金利の混合型ローンを活用し、金利リスクを分散させる方法が注目されています。
最後に家賃保証会社の活用です。保証料は家賃の0.5〜1か月分ですが、滞納リスクを外部化できるメリットがあります。保証会社の決算情報を確認し、代位弁済率が5%未満の会社を選ぶと、長期的な安心感が高まります。
まとめ
本記事では、収益物件で「何を」重視すべきかを、物件種別の理解、利回り計算、立地調査、資金計画、そして2025年度の制度やリスク管理の五つの視点から整理しました。各ステップで数字と公的データを使い、過度な期待を排除する姿勢が安定運用の鍵になります。次の行動として、まずは気になるエリアを一つ選び、実際に家賃相場と空室率を調べてみましょう。調査を通じて得た一次情報が、あなたの投資判断を強力に後押ししてくれるはずです。将来の目標に合わせて学びを深め、自分だけの収益物件戦略を築いてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅局「賃貸住宅修繕費実態調査2024」 – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省「地価公示 2025」 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局「住宅・土地統計調査2023」 – https://www.stat.go.jp
- 総務省「地域別将来人口推計2024」 – https://www.soumu.go.jp
- 日本銀行「住宅市場動向レポート2025」 – https://www.boj.or.jp
- 気象庁「気候統計データ 2025」 – https://www.jma.go.jp

