不動産投資に興味はあるものの、「店舗付きの物件は専門知識が必要そうで踏み出せない」と感じていませんか。実は住宅系よりも高い利回りが期待できる反面、立地や賃貸契約の読み違いで赤字化する例も少なくありません。本記事では15年以上の実務経験を持つ筆者が、店舗 収益物件 選び方の基本から2025年10月時点で活用できる制度までを丁寧に解説します。読み終えたとき、あなたはリスクとリターンをバランスさせる判断基準を手に入れ、次の行動に自信を持てるはずです。
店舗収益物件の特徴と住宅物件との違い
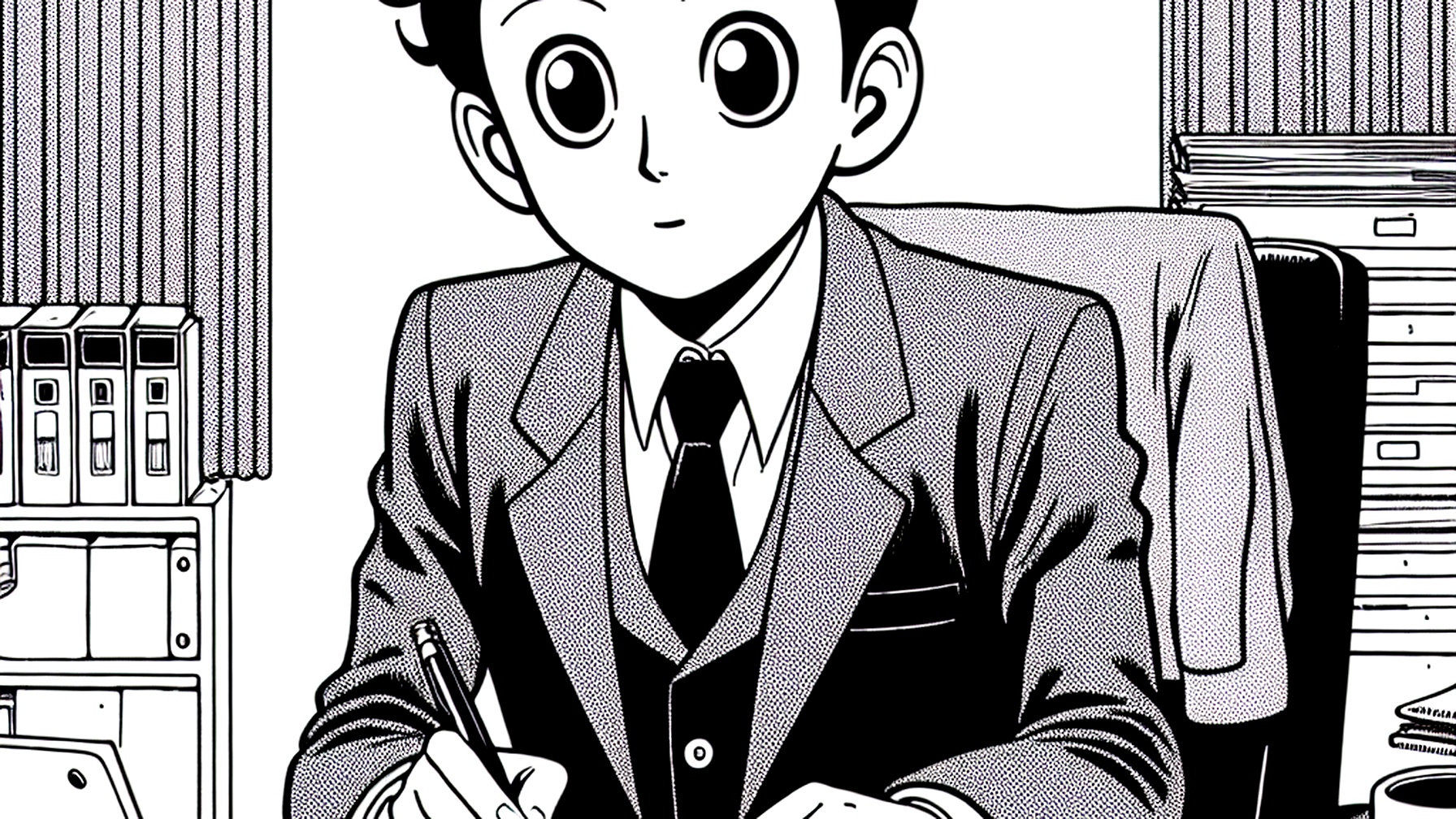
まず押さえておきたいのは、店舗収益物件が住宅系と根本的に異なる点です。最大の違いは賃料の決まり方にあります。住居は周辺家賃相場でおおむね決まりますが、店舗は売上期待値に応じて賃料が上下するため、同じ階段下の区画でも業態が変われば家賃が倍近く開く場合があります。つまり、テナントが利益を出しやすい環境を提供できるかどうかが家賃収入を左右します。
次に、賃貸期間が比較的長い点も見逃せません。飲食店などは内装に多額を投じるため、平均で五〜十年の長期契約を結ぶ傾向があります。長い空室は避けやすい一方、退去時に原状回復費が高額化しやすい点が住宅系との大きな差です。また、原則として住居用の借地借家法より貸主に有利な民法契約が適用されるため、更新料や修繕範囲を柔軟に定められるメリットがあります。
さらに、利回りは表面で六〜十%が目安とされ、住宅より二〜三ポイント高いケースが多く見られます。国土交通省の「不動産投資市場動向調査(2025年上期)」によると、主要三大都市圏の路面店舗平均利回りは7.4%でした。一方で、郊外型ショッピングモールの空室率はコロナ収束後も12%前後で推移しており、立地や物件タイプによる振れ幅が大きい点に注意が必要です。
立地分析の基本は「人の流れ」と「用途地域」
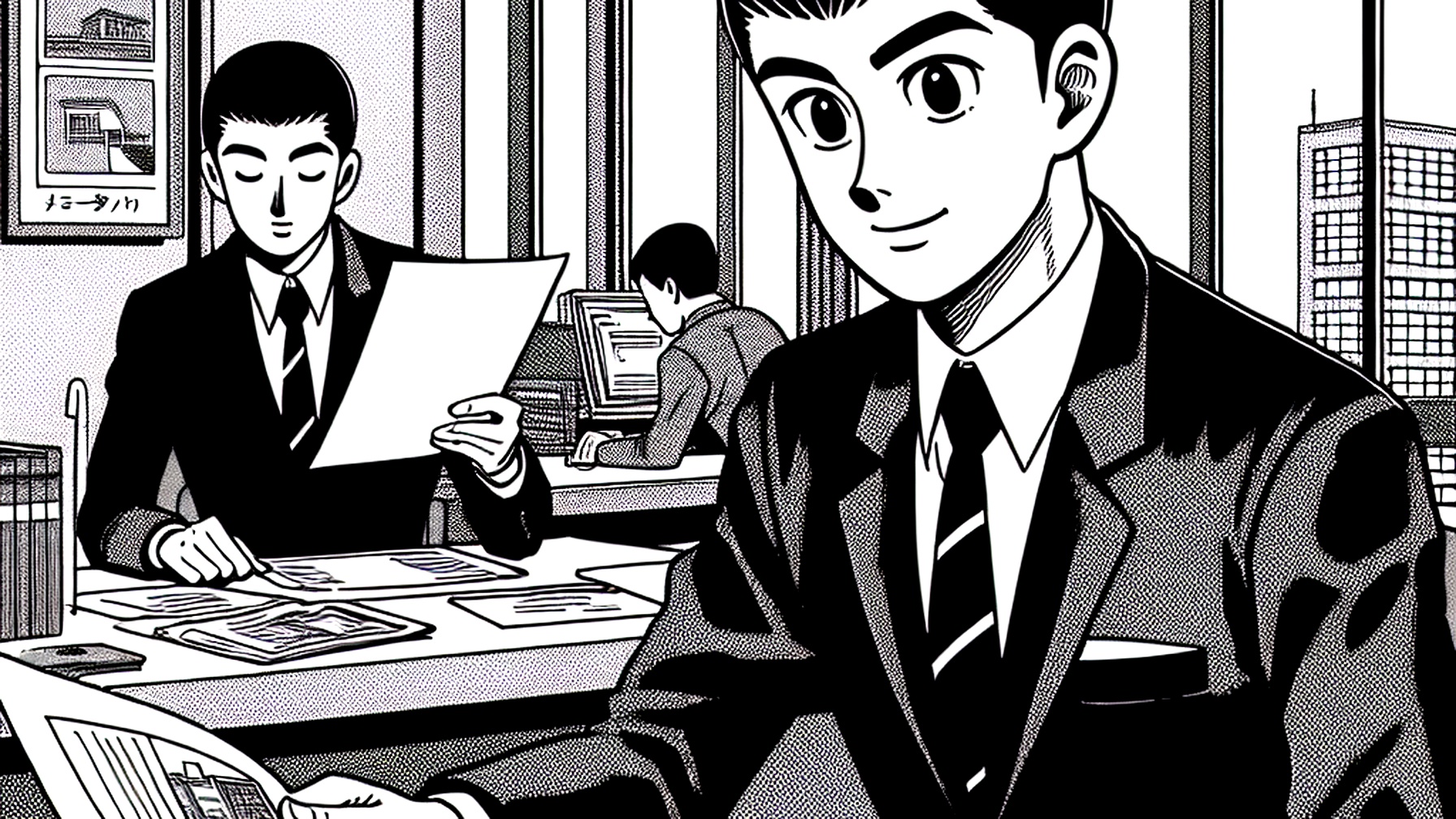
重要なのは、住宅投資でおなじみの駅距離だけに頼らない視点です。店舗収益物件を評価する際は、人がどこから来てどこへ向かうかという「動線」を把握することが第一歩になります。例えば繁華街の交差点は人通りが多いものの、通行者が目的地へ急いでいる場合、立ち寄り率が低く売上につながりにくいこともあります。国土交通省の都市計画基礎調査を参照し、時間帯ごとの歩行者量を把握すると具体的な家賃設定がしやすくなります。
加えて用途地域による制限も見逃せません。商業地域なら深夜営業が可能でも、近隣商業地域では騒音規制が厳しいといったケースがあります。新規テナントの業態が制限に抵触すれば、せっかくの高家賃テナント候補を逃すことになりかねません。事前に自治体の都市計画課へ相談し、出店可能業種を確認する習慣を付けておくと安心です。
また、競合店舗の密集度も売上に直結します。総務省の経済センサスでは業種別の店舗数を町丁目単位で閲覧できるため、似た業態が過剰に集中していないかを数値で判断できます。徒歩一分圏内に同業が三店舗以上あると価格競争に巻き込まれやすいとの調査結果もあり、将来の退店リスクを上げる要因となります。
一方、郊外型のロードサイド物件では、駐車場の出入りしやすさが来店数を左右します。敷地への右折入庫が必要かどうか、道路拡幅計画の有無などを土木事務所の資料で確認し、数年後の交通量変化も視野に入れるべきです。立地分析を通じて売上ポテンシャルが見込めれば、賃料の安定に直結するため、物件価格が多少高くても投資妙味は残ります。
賃料設定とキャッシュフローを読み解くコツ
ポイントは、表面利回りだけでなく実質利回りを算出し、季節要因まで視野に入れることです。店舗賃料には共益費のほか売上歩合を組み合わせる「売上連動賃料」が存在します。仮に基本賃料が月八十万円で歩合率が三%なら、売上二千万円を超えた部分から歩合賃料が発生する設計も可能です。オーバーキルではなく、テナントの損益分岐点より少し低い水準に設定すると長期入居の動機づけになります。
次に、家賃収入から管理費や修繕積立、固定資産税を差し引いたネットキャッシュフローを見ます。日本政策金融公庫の「店舗向け設備の耐用年数表」によると、厨房設備は六年、空調は十五年が目安です。これらの更新費用を毎月数万円積み立てておかないと、退去時に数百万円の出費が一度に発生し、黒字が吹き飛ぶ恐れがあります。
また、テナント業態による季節変動を考慮したシミュレーションも不可欠です。例えばビアレストランは夏場に売上が四割増える一方、冬場は三割減る傾向があります。このような変動を平均値だけで捉えると、歩合賃料の見込み違いが起こりやすくなります。過去三年分の同業態売上を統計局の商業動態統計で確認し、下振れシナリオでも返済が滞らないかをチェックしましょう。
さらに、2025年時点で基準金利は一時期より上昇傾向にあり、借入金利が一%台後半に達するケースも出ています。三十年返済で金利が0.5%上がると総返済額は物件価格の一割近く増えるため、ストレスシナリオに金利上昇二%を織り込むと保守的な計画となります。これにより、景気後退局面でも売却益なしでローンを完済できる安全域を確保できます。
テナントリスクと契約条件の見極め
実は、店舗収益物件の成否を大きく分けるのはテナント選定と契約交渉です。飲食店は初期投資が大きく倒産率も高い一方、美容院やクリニックは長期安定が期待できるといった業界特性があります。東京商工リサーチの「業種別倒産率(2024年度)」では、飲食業3.7%に対し理美容業1.1%と約三分の一でした。数字を冷静に読み、賃料だけでなく倒産リスクを加味したテナントポートフォリオを構築する視点が欠かせません。
契約書では、保証金と敷金の違いを理解し、更新料や造作譲渡の取り扱いを細かく定めます。保証金の償却率を退去時に二割とするか三割とするかで、想定利回りに数%の誤差が生じるため注意が必要です。また、造作買取請求権を制限する特約を入れれば、退去時に高額な買い取りを迫られるリスクを軽減できます。民法改正(2020年)後もこの特約は有効であり、2025年現在においても広く実務で利用されています。
さらに、家賃保証会社の活用は住宅以上に重要です。店舗系の家賃滞納は金額が大きく、滞納二カ月で数百万円に膨らむケースが珍しくありません。保証料は年間家賃の一割前後と高めですが、リスクヘッジ効果を考えると十分に回収できるコストと言えます。保証会社を利用する場合、同時にテナント損害保険加入を義務づけ、火災や漏水による営業不能時の家賃補填が受けられるようにしておくと安心です。
最後に、サブリース契約を活用する方法もあります。ただし、賃料改定条項が曖昧だと将来の減額リスクが高まります。サブリース会社の財務状況や平均空室率を確認し、賃料改定条件を数値で明記することがトラブル回避につながります。契約書チェックを専門家に依頼する費用は十万円前後が相場ですが、長期的に見れば安い保険と言えるでしょう。
2025年度に活用できる税制・補助金の最新情報
まず、2025年度も継続する中小企業庁の「事業再構築補助金」は、飲食店やサービス業向けに店舗改装費の三分の二(上限2000万円)を補助する枠が設けられています。オーナーがテナントと共同で申請し、改装後の賃料増額を狙う戦略も現実的です。期限は2026年3月申請分まで延長が決定しているため、計画段階での準備が可能です。
一方、固定資産税については、店舗用家屋であっても新築後三年間は税額が二分の一となる措置が住宅と同様に適用されます。この特例は2025年度税制改正で延長が決まり、2027年3月31日までに建築確認を受けた物件が対象です。利回り計算の際、取得後三年間は税負担が軽くなるため、キャッシュフローが改善しやすい点を忘れずに織り込みましょう。
また、国税庁の通達では、内装と設備の一括償却資産(取得価額30万円未満)の特例が2025年度も有効です。例えば個別空調機一台25万円を複数設置する場合、三年で一括償却できるため、投資初年度に大きな節税効果が見込めます。テナントが設備費を負担する場合でも、オーナー側で一時的に立替えて賃料に上乗せする形を取れば減価償却を利用できます。
さらに、ゼロゼロ融資後の借換え需要に対応し、日本政策金融公庫が2025年4月に創設した「省力化・店舗改善資金」は、金利年0.9%(当初5年固定)という低利で最大20年の長期融資が利用できます。テナントの設備投資とセットで提案することで、長期入居を引き出す交渉材料となります。オーナー自身が借り入れる場合も、返済期間を長く取れるためキャッシュフローの平準化に役立ちます。
そして、インボイス制度対応として2025年度末まで続く「インボイス発行事業者登録支援補助金」も見逃せません。レジや会計ソフトの導入費用の一部をテナントが補助申請できるので、初期費用の負担軽減が空室解消につながります。オーナーはこれらの制度を把握し、テナント候補へ積極的に情報提供すると信頼を得やすくなります。
まとめ
店舗 収益物件 選び方の核心は、立地分析で売上ポテンシャルを見極め、テナントリスクを数値で把握し、制度や税制を活用してキャッシュフローを最適化することに尽きます。人の動線や用途地域を調べ、実質利回りを厳しめに算出し、倒産率の低い業態と長期契約を結べば、安定収益の基盤が築けます。さらに、2025年度に利用できる補助金や税制特例を織り込み、設備更新費を抑えることでリスクヘッジが可能になります。次の一歩として、候補物件の現地調査と収支シミュレーションを行い、今日得た視点を実践で試してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 都市計画基礎調査 – https://www.mlit.go.jp/
- 国土交通省 不動産投資市場動向調査(2025年上期) – https://www.mlit.go.jp/
- 総務省 経済センサス – https://www.stat.go.jp/
- 日本政策金融公庫 店舗改善資金案内 – https://www.jfc.go.jp/
- 東京商工リサーチ 業種別倒産率(2024年度) – https://www.tsr-net.co.jp/
- 中小企業庁 事業再構築補助金 – https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
- 国税庁 一括償却資産の取り扱い – https://www.nta.go.jp/

