賃貸経営で安定した利益を得るには、そもそも収益物件をどこで購入するかが最大の関門です。駅近が良いという声もあれば、再開発エリアが狙い目という意見もあり、情報が多すぎて判断に迷う人は少なくありません。私も相談を受けるたびに「場所だけで勝敗の七割が決まる」と繰り返しています。本記事では2025年10月時点の公的データを参照しながら、初心者でも体系的に立地を選べる視点と手順を解説します。読み終えるころには、自身の投資目的に合ったエリアを絞り込み、次に取るべき行動が具体的に見えるようになるでしょう。
立地選びで最初に考える指標
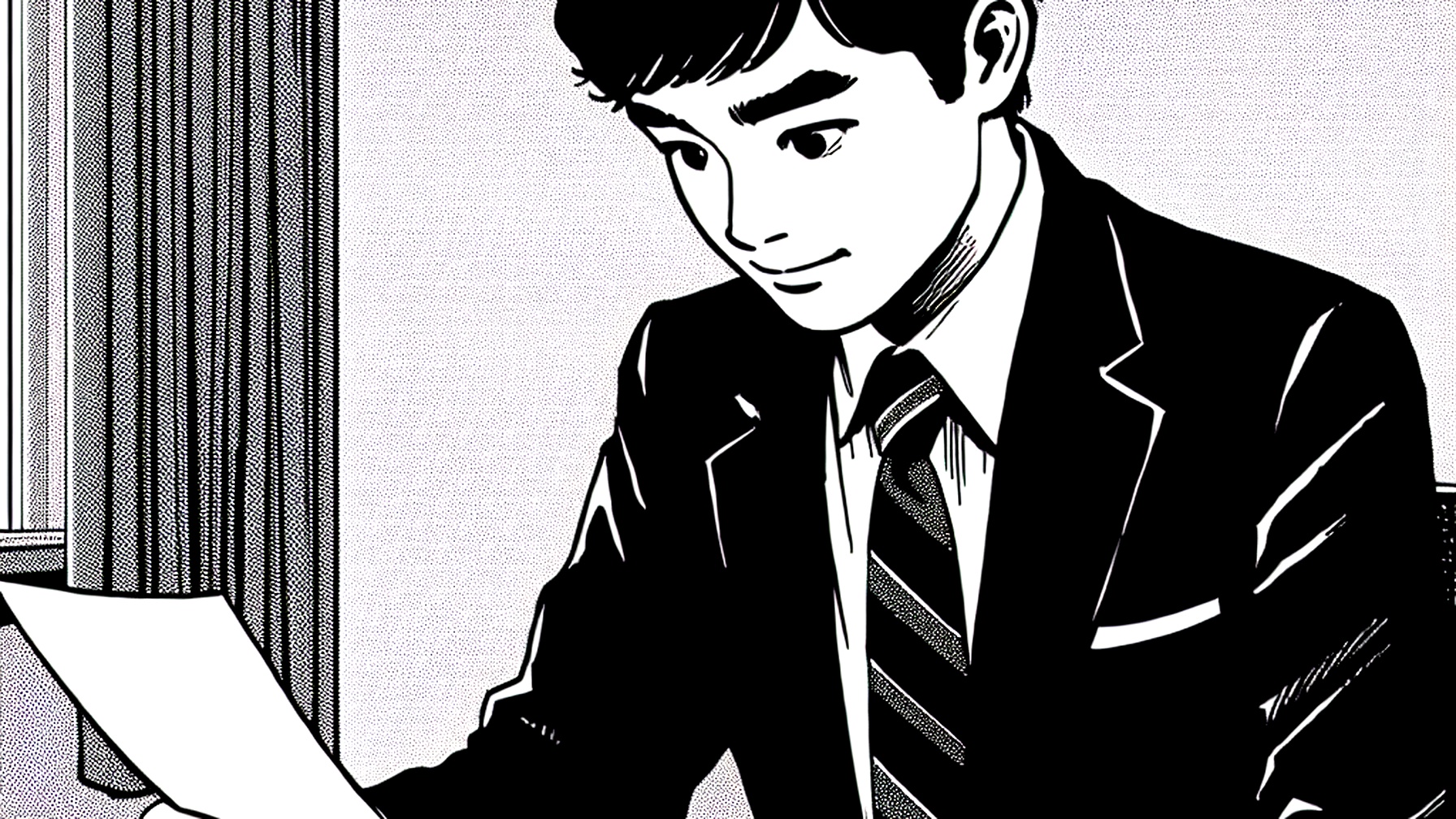
重要なのは、家賃収入が長期にわたり維持できるかを示す定量指標を把握することです。賃貸需要の裏付けがあるかどうかを、人口規模、世帯数、流動性の三点から確認すると失敗が減ります。
まず人口規模は、市区町村単位で10万人を一つの目安にすると判断しやすいです。総務省「住民基本台帳人口移動報告」によると、人口10万人未満の自治体の約六割が過去五年間で人口減を経験しました。人口が減る地域では家賃下落が先行するため、利回りが高く見えても実質的なキャッシュフローが縮むおそれがあります。
次に世帯数の増減をチェックします。国勢調査データを細かく見ると、世帯数が増えている自治体でも単身世帯比率が高い場合、ワンルーム向きかファミリー向きかで結論が変わることがわかります。言い換えると、世帯構成を読み違えると「空室は埋まるのに家賃が上がらない」という状況になりかねません。
最後に流動性、つまり転入転出の出入りです。自治体が公表する転入超過数を確認し、毎年転入が続いているエリアは急激な空室増のリスクが低くなります。2025年時点で転入超過が続くのは東京都区部、福岡市、札幌市などの政令市が中心ですが、北陸新幹線の延伸効果で金沢市の中心部もプラスが継続中です。これらの数値を組み合わせ、まずは需要の底堅さを定量的にとらえることが立地選定の出発点となります。
都心・準都心・地方都市それぞれの現実
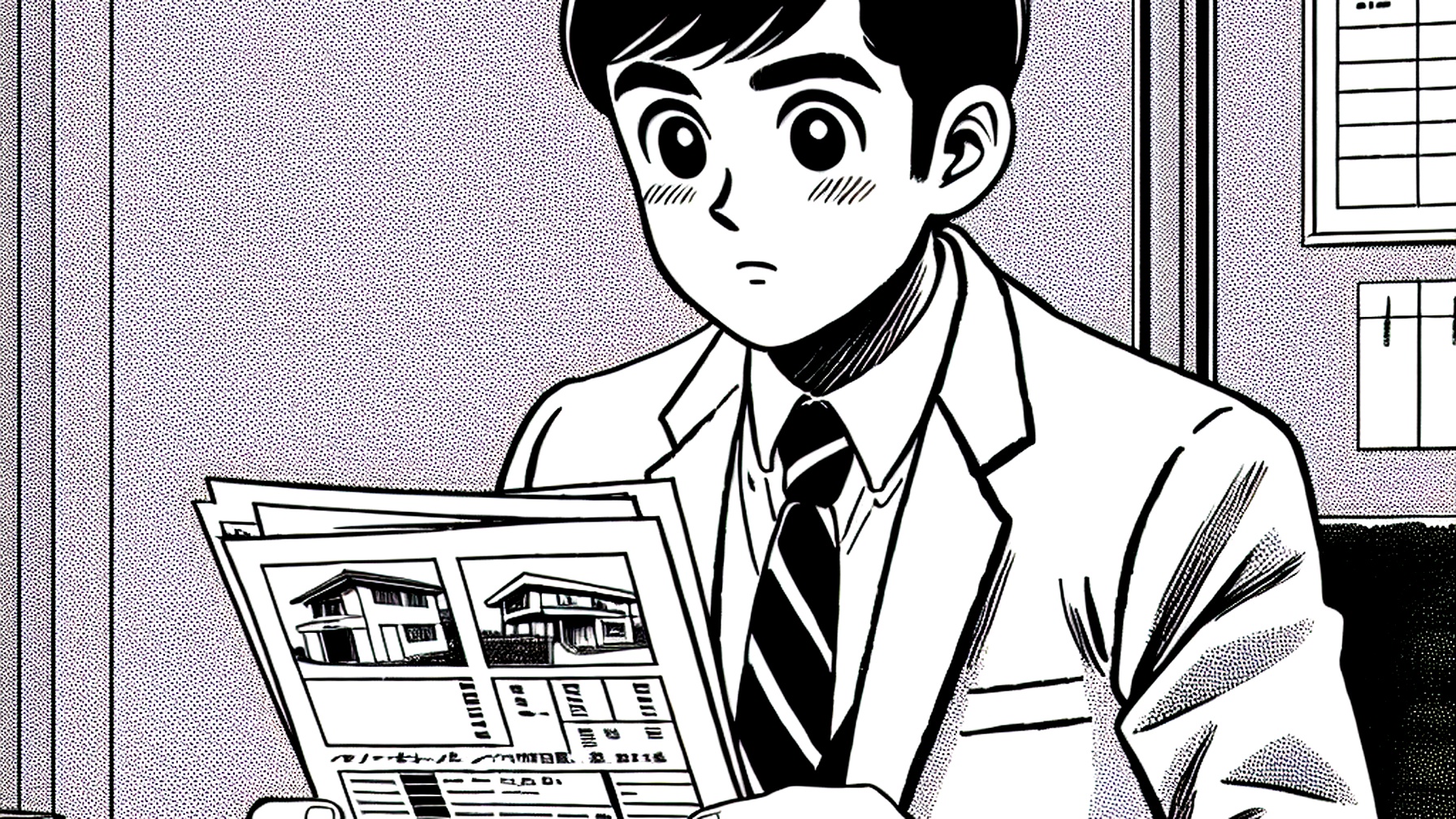
ポイントは、同じ家賃収入でもリスク構造が地域により大きく異なることです。都心は価格が高くても空室リスクが低く、地方都市はその逆になる傾向があります。
東京都心五区では2025年時点の平均空室率が4%前後と低位で推移しています。日本賃貸住宅管理協会の調査によれば、同エリアの平均賃料は前年比で1.8%上昇し、金利上昇局面でも家賃の伸びである程度吸収できる状況です。一方、初期投資額が大きいため自己資金2割以上を入れないとキャッシュフローが細くなる点に注意が必要です。
準都心、たとえば川崎市や千葉市の主要駅周辺では平均空室率が6〜7%とやや高いものの、物件価格が都心より2〜3割安く、グロス利回りで0.5〜1%高く取れるケースが目立ちます。つまり、適切な管理体制を敷けば都心よりキャッシュフローを厚くできる余地があります。
地方都市はさらに価格が下がる一方で、空室率が二桁に達するエリアも珍しくありません。総務省の住宅・土地統計調査では、人口20万人未満の市で空き家率が平均16%と報告されています。ただ、地方中核都市の中心部では再開発による賃貸需要が底上げされる事例もあるため、駅徒歩5分以内など需要のコアに絞れば勝負できる物件も見つかります。
データで読む人口動態と賃貸需要
実は、データを読み解く力があるかどうかで「収益物件 どこで」という問いへの答えは変わります。国立社会保障・人口問題研究所の2040年推計では、全国人口が減少する中でも20代〜30代人口が増える市区町村が約100カ所残ると示されています。
こうしたエリアは大学や企業の集積が背景にあり、単身世帯向け物件の需要が底堅い傾向があります。たとえば福岡市は若年人口比率が政令市でトップクラスで、2025年時点でも市全体の人口が増加中です。家賃水準は東京より1〜2割低いものの、物件価格はさらに低いことが多いため、利回りが出やすい構造になっています。
一方、高齢化が進む郊外団地ではファミリー需要が伸び悩み、リノベーション費用をかけても家賃単価を上げにくい課題があります。特に築40年以上の大型団地は、管理組合の修繕積立不足が表面化しており、将来的な大規模修繕負担を考慮する必要があります。つまり、人口動態は単なる増減だけでなく、年齢分布や住宅ストックの状況まで踏み込んで分析することが欠かせません。
さらに、テレワーク普及で「職住分離」が再進行している点も押さえておきたいところです。総務省「通信利用動向調査」によると、週三日以上のテレワーク実施率は全国平均で28%に達しました。これにより駅近物件一択だった需要が、周辺環境や室内スペースを重視する方向へ多様化しています。立地判断では、交通利便性に加え住環境指標もセットで評価する時代になったと言えます。
物件タイプ別に見る場所の最適解
まず押さえておきたいのは、物件タイプごとに「正解の場所」が異なることです。ワンルーム、ファミリー向け、戸建て賃貸、それぞれに適した立地条件があります。
ワンルーム投資は転入者が集中する駅徒歩10分圏が基本です。徒歩圏を外す場合は、大学のキャンパスや大規模工場の寮代替需要を取りに行く戦略が必要になります。私の顧客で、札幌市の地下鉄駅からバス15分の築浅ワンルームを購入した方は、大学と連携した学生向けプロモーションを行い、年間稼働率98%を維持しています。
ファミリー向けマンションは学区と買い物環境が鍵です。2025年のリクルート住まいカンパニー調査では、小学校徒歩10分以内の物件は家賃が平均4%上乗せされるという結果が出ました。郊外でも人気校区を選べば空室期間が短く、長期入居も期待できます。反面、学区改編のリスクがある地域は避けるべきです。
戸建て賃貸は駐車場需要が強いエリアが狙い目です。地方都市の主要駅から車で15分以内、かつ敷地内駐車2台を確保できる物件は、管理が簡単でファミリーに長期利用されやすい傾向があります。表面利回りは低めに見えても、退去時原状回復コストがマンションより抑えられるため、実質キャッシュフローは安定します。
2025年度の支援制度をどう活用するか
基本的に、2025年度は省エネ改修や耐震補強に対する補助金が引き続き利用可能です。国土交通省の「住宅エコリフォーム推進事業」は、中小規模の賃貸物件が対象で、断熱改修費用の三分の一以内(上限120万円)が補助されます。期限は2026年3月申請分までと発表されています。
この制度を活用すると、築古物件でも光熱費削減を訴求でき、競合物件との差別化に役立ちます。たとえば、窓の二重サッシ化により年間1室あたり約1.2万円の光熱費が低減するという環境省の試算があります。家賃を月1,000円上げても入居者メリットが大きいため、改修費の回収は十分可能です。
また、地方自治体が提供する空き家活用補助金も見逃せません。大阪市では「民間住宅活用型支援事業」を2025年度も継続し、賃貸転用時に最大150万円を助成しています。地方投資を検討する場合は、市町村の公式サイトで補助対象と条件を確認しましょう。
ただし、補助金ありきで場所を決めると本末転倒です。先に賃貸需要が見込める立地を選定し、そのうえで利用可能な制度を組み合わせるという順序が成功への近道になります。
まとめ
本記事では、人口規模、世帯構成、流動性という三つの定量指標を中心に、都心・準都心・地方都市のリスク構造の違いを整理しました。さらに、人口動態とテレワークの影響を踏まえた需要分析、物件タイプ別の適地、2025年度の補助金活用まで流れを追って解説しました。次に取るべき行動として、まず気になるエリアの人口推移と空室率を公的データで確認し、現地視察で生活利便性をチェックしてください。そのうえで、対象物件が支援制度の条件に合うかを調べ、収支シミュレーションに落とし込めば、立地選びの失敗は大幅に減らせるはずです。
参考文献・出典
- 総務省 統計局「住民基本台帳人口移動報告」 – https://www.stat.go.jp
- 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」 – https://www.ipss.go.jp
- 日本賃貸住宅管理協会「全国家賃動向別調査」 – https://www.jpm.jp
- 総務省「通信利用動向調査」 – https://www.soumu.go.jp
- 国土交通省「住宅エコリフォーム推進事業」 – https://www.mlit.go.jp
- リクルート住まいカンパニー「住まいの購入・賃貸に関する実態調査2025」 – https://suumo.jp

