不動産投資を始めたばかりの方にとって、最初の壁は「この物件はいくらで買うのが妥当なのか」という疑問でしょう。価格が高すぎれば利回りが下がり、安すぎてもトラブル物件をつかむかもしれません。実は、物件価格は査定方法によって大きく異なります。本記事では「収益物件 査定方法 VS」という視点で主要な査定手法を比較し、どの場面でどの方法を優先すべきかをわかりやすく解説します。読み終える頃には、数字の裏にあるリスクとリターンを読み解く力が身につくはずです。
査定手法はなぜ複数あるのか
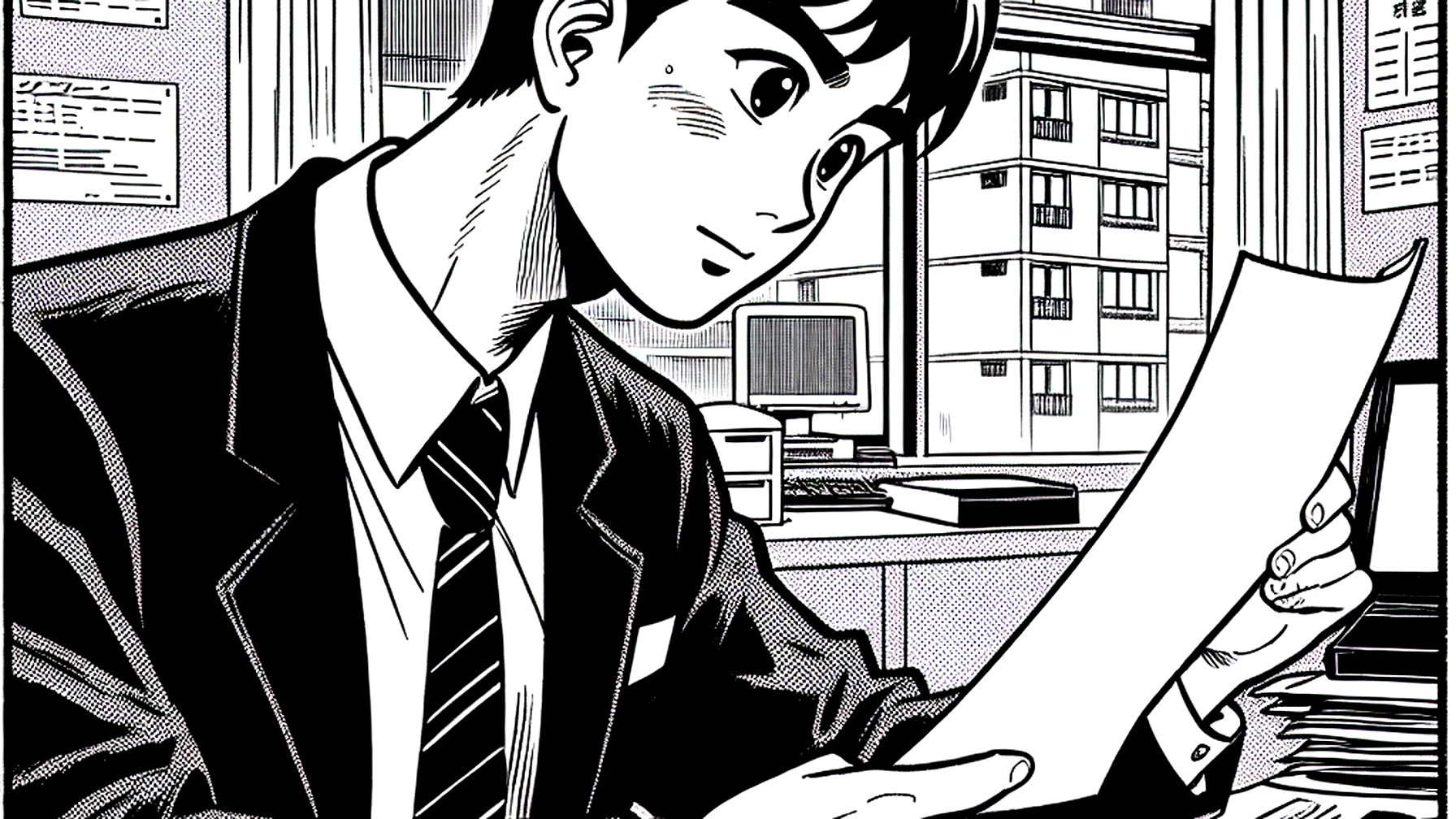
まず押さえておきたいのは、査定手法が複数存在するのには理由があるという点です。投資家、金融機関、売主といった立場の違いが、物件の価値を測る物差しを変えるのです。収益還元法は将来の収益性を重視しますが、取引事例比較法は市場の相場感を映し出します。さらに原価法は建物の再調達コストを基準とし、老朽度や修繕履歴を浮き彫りにします。
国土交通省の不動産価格指数によると、2024年から2025年にかけて住宅系収益物件の価格は平均3.2%上昇しました。しかし上昇分の内訳を見ると、都心部は賃料期待の上昇が主因で、地方都市は建築コスト高が影響しています。つまり、どの手法で査定するかによって同じ3.2%の上昇でも評価額がずれるのです。投資判断を誤らないためには、複数の査定手法を理解し、立場や物件特性に合わせて使い分ける視点が欠かせません。
収益還元法の基礎と落とし穴
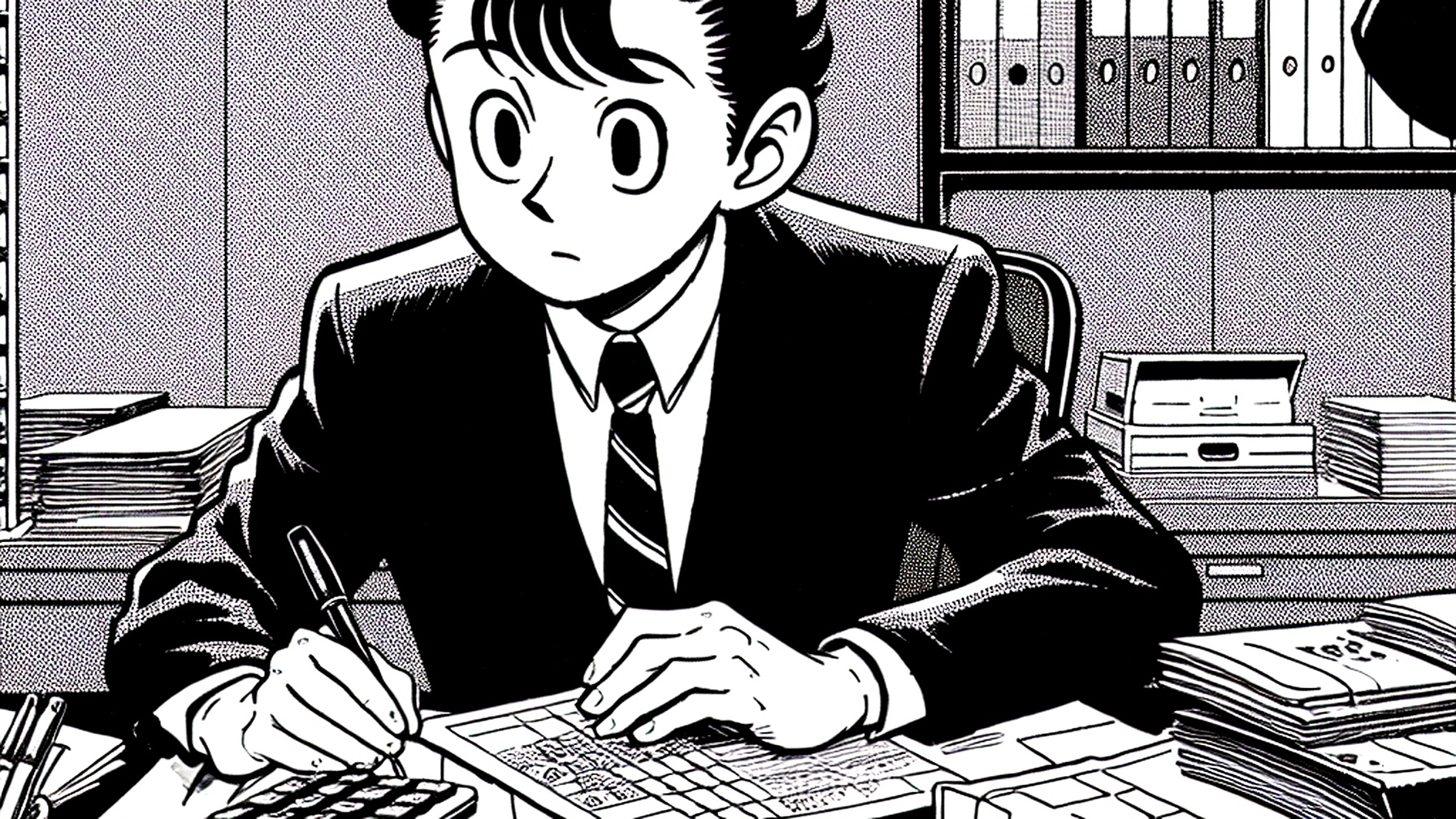
重要なのは、収益還元法がキャッシュフローに基づく唯一の査定手法だという点です。将来得られる家賃を現在価値に割り引き、その合計で物件価格を算出します。金融機関が融資可否を判断する際にも多用されるため、投資家はまずこのロジックを理解する必要があります。
手順はシンプルですが、割引率(キャップレート)の設定を誤ると結果は大きく狂います。2025年時点で日本政策投資銀行が公表するレポートでは、東京23区の住宅系キャップレート中央値は3.8%です。一方、地方主要都市では5.2%前後と差があり、単純に全国平均を当てはめると試算が甘くなります。また、家賃水準の将来的な下落率をどう組み込むかもポイントです。人口推計に基づき、5年後に空室率が3%上がるシナリオまで織り込むと、表面利回り8%の物件でも実質利回りは6%台に落ちるケースが珍しくありません。
さらに、税引き後キャッシュフローを考慮しないと、節税効果だけを強調する提案に惑わされる恐れがあります。つまり、収益還元法を使う際はキャップレートの妥当性と将来の空室リスクを同時に精査する姿勢が欠かせないのです。
取引事例比較法で相場を読むコツ
ポイントは、取引事例比較法が「市場で実際に成立した価格」を基準にする点です。不動産流通機構のレインズデータや国土交通省の「不動産取引価格情報検索」を参照すると、類似物件の成約価格を確認できます。特に2025年は低金利継続による投資家需要が強く、表面的な価格上昇が見られるため、過去一年以内の事例を中心に比較することが推奨されます。
一方で、事例と対象物件の条件が微妙に異なると価格調整が必要になります。築年数、最寄り駅からの距離、利回りなどを加味しなければ、見かけ上の相場に引きずられて高値掴みするリスクが高まります。また、成約事例には公開されない値引き交渉の結果が反映されていない場合がある点も要注意です。たとえば広告価格の平均より実際の成約価格は3〜5%下がるという統計もあります。言い換えると、取引事例比較法は市場の温度を知るには有効でも、そのまま買付価格を決定するには粗い指標だということです。
最後に、人口動態や再開発計画といった非価格情報も組み合わせると相場の読みが深まります。具体例として、2025年に地下鉄延伸が決定した名古屋市北部では、取引事例より10%高い募集価格が出ているものの、完成時期が2030年と遠いため即時のキャッシュフローには寄与しません。このような背景を理解しないまま事例だけを信じると、期待利回りが下がる恐れがあります。
原価法から見える修繕リスク
実は、原価法は建物の再調達価格から減価償却分を差し引くことで価値を求める手法です。築古アパートやRCマンションなど、建物比率が高い物件で特に威力を発揮します。日本建築学会の試算によると、2023年からの資材高騰で新築RCの建設単価は過去5年間で約18%上昇しました。原価法を用いると、この上昇分を評価に反映できるため、取引事例比較法より高い価格が算出されるケースもあります。
しかし、原価法には落とし穴があります。減価償却の進み具合を精緻に見極めなければ、帳簿価格と市場価格が乖離してしまうのです。築25年のRCマンションを例にすると、会計上の残存価値が1,000万円でも、外壁補修や給排水管の交換に1,500万円かかる場合があります。つまり、再調達価格だけでなく、将来必要となる大規模修繕費を差し引いたネット価値を算出する必要があります。
原価法を活用する際は、長期修繕計画やマンション管理状況のチェックが不可欠です。国交省の「マンション管理計画認定制度」(2022年度開始、2025年度も継続)に適合している物件は修繕リスクが低く、金融機関の評価も高まりやすい傾向があります。原価法を学ぶことで、帳簿には現れにくいメンテナンスコストを見抜く目が養われるでしょう。
収益物件 査定方法 VS 使い分け戦略
重要なのは、単一の査定手法に依存しない姿勢です。収益物件 査定方法 VS の視点で整理すると、投資フェーズごとに最適な手法が異なります。物件を探す段階では取引事例比較法で相場感を掴み、買付価格を決める場面では収益還元法でキャッシュフローを確認、そしてデューデリジェンスでは原価法で修繕リスクを洗い出すとバランスが取れます。
具体的な流れを示すと、まずレインズや不動産価格情報で近隣事例を調査し、表面利回りがエリア平均の1.0〜1.5%上なら詳細検討に進みます。次に、家賃下落シナリオを含む収益還元法で内的利回り(IRR)を試算し、自己資金比率を変えても年7%以上を確保できるか確認します。最後に、原価法で算出した将来修繕費を10年間のキャッシュフローに反映させ、ネット利回りが5%を割らないかをチェックします。この三段階を経ることで、数字の裏に潜むリスクを可視化できるのです。
一方で、金融機関は収益還元法に重きを置く傾向が強いものの、地方銀行は取引事例比較法を重視するケースもあります。融資担当者がどの査定手法に注目しているかを把握し、提示資料をカスタマイズすることで、融資条件を有利に引き出せる可能性が高まります。つまり、査定手法の使い分けは物件選定だけでなく、資金調達の交渉力にも直結するのです。
まとめ
ここまで、主要な査定手法を比較し、それぞれの強みと弱点を見てきました。ポイントは、取引事例比較法で市場動向をつかみ、収益還元法でキャッシュフローを検証し、原価法で修繕リスクを評価するという三位一体のアプローチです。この手順を踏めば、高値掴みや見かけ倒しの利回りに惑わされにくくなります。まずは小規模物件で実践し、査定結果と実際の運営データを突き合わせながら精度を高めてください。数字の裏側を読み解く力が身につけば、不動産投資はより安定した資産形成の手段になるはずです。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 不動産取引価格情報検索(国土交通省) – https://www.land.mlit.go.jp
- RENOSY 不動産投資レポート2025 – https://www.renosy.com
- 日本政策投資銀行 不動産市場動向2025 – https://www.dbj.jp
- 不動産流通機構(REINS)統計情報 – https://www.reins.or.jp

