老後の安定収入を得ながら、子どもたちへの資産承継を円滑に進めたい――そんな願いを持つ方は多いでしょう。ところが、相続対策と収益性を同時に満たす方法を探しても、専門用語や制度が複雑で途中であきらめてしまうケースが少なくありません。本記事では「アパート経営 相続対策 築浅」という三つのキーワードを軸に、初心者でもわかるよう基礎から最新制度までを解説します。読み終えたときには、築浅アパートを活用した具体的な手順と注意点が整理でき、自信を持って第一歩を踏み出せるはずです。
なぜ築浅アパートが相続対策に適するのか
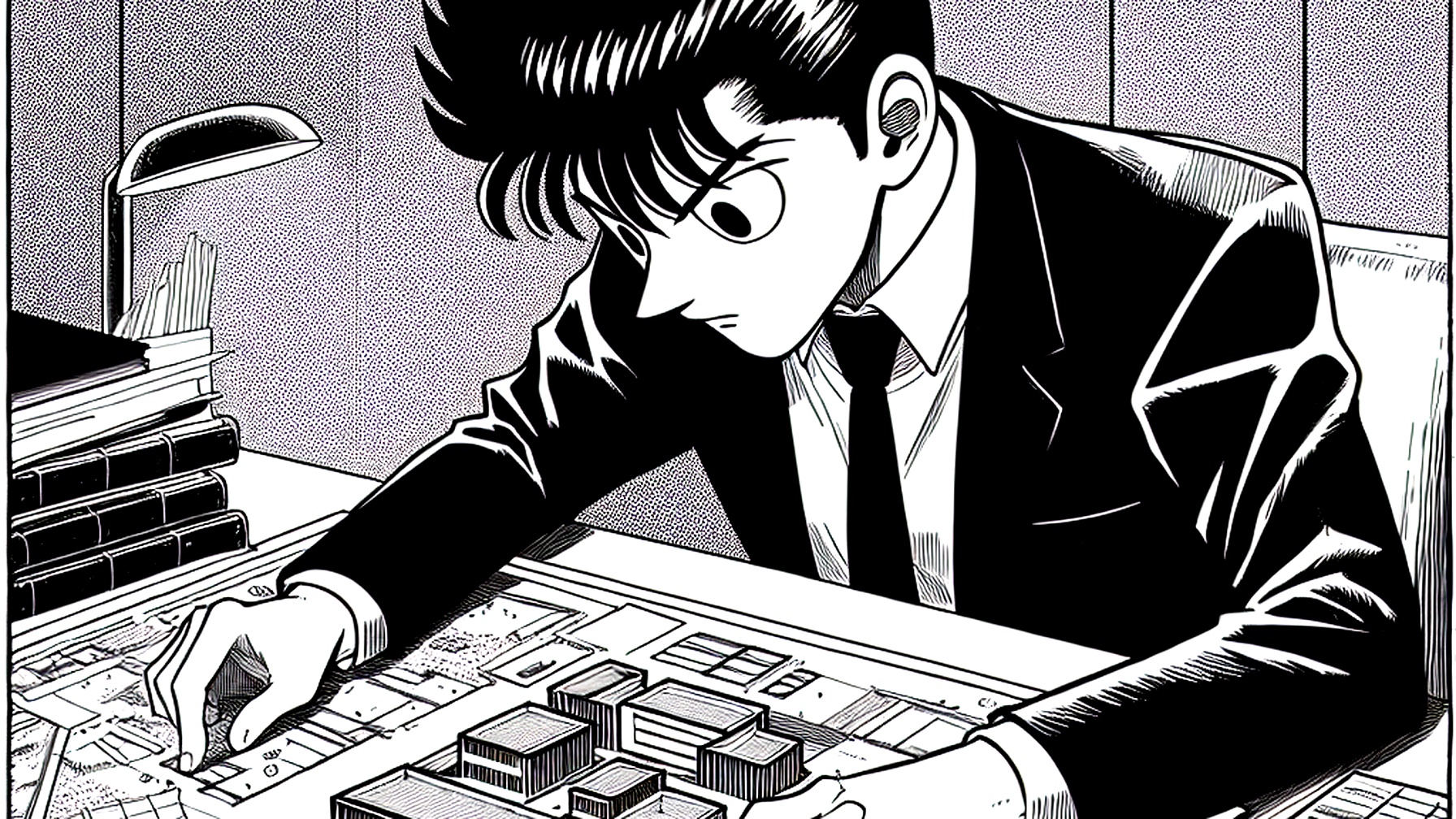
重要なのは、築浅物件が持つ資産評価のバランスです。建物は年数とともに減価償却が進み、相続税評価額が下がります。ところが築浅であればまだ十分に価値を保ちつつ、評価額は実勢価格より低く算定されるため、節税と安全性を両立できます。
次に空室リスクを確認しましょう。国土交通省住宅統計によれば、2025年8月時点の全国アパート空室率は21.2%で前年より0.3ポイント改善しています。築浅物件は設備の新しさと省エネ性能が魅力となり、この平均より低い空室率で推移する傾向があります。つまり、安定入居が見込めるため長期のキャッシュフロー計画が立てやすいのです。
さらに、築浅なら大規模修繕のタイミングが遠いため、購入から数年間は資金繰りに余裕が生まれます。修繕積立金を外部積立に回せば、いざ相続が発生した際の納税資金としても活用できるでしょう。このように築浅アパートは、評価額・入居率・修繕費の三点で相続対策に有利といえます。
資金計画と融資のポイント
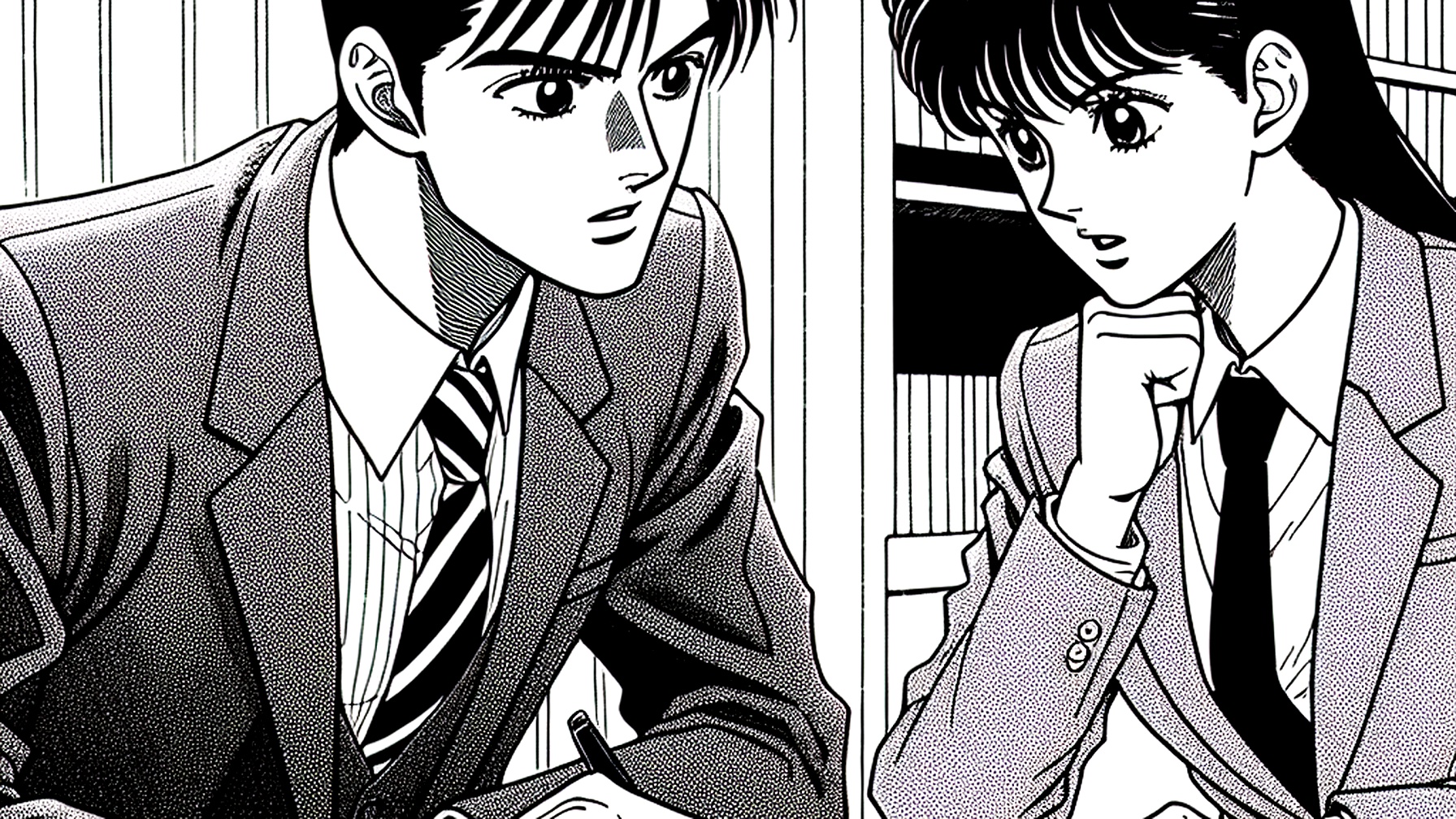
まず押さえておきたいのは自己資金の割合です。一般的に物件価格の20〜30%を自己資金で用意すると、金融機関の審査が通りやすく金利も有利になります。自己資金を減らしてレバレッジ効果を高める方法もありますが、相続対策が目的なら過度な借入は世代をまたぐ負担となるため、慎重に判断すべきです。
融資条件を比較する際は、固定金利期間の長さに注目してください。築浅物件の家賃は高水準で推移しますが、金利上昇が収支を圧迫するリスクは残ります。固定期間10年と20年では総返済額が数百万円単位で変わるケースもあるため、複数行から見積もりを取りましょう。
また、融資返済期間を法定耐用年数いっぱいに設定できるかも大きなポイントです。木造アパートの場合、残耐用年数にプラス数年を認める金融機関も増えています。返済期間が長ければ月々の返済負担が軽くなり、キャッシュフローが安定します。その結果、相続後に子どもたちが経営を引き継ぎやすくなるのです。
キャッシュフローを安定させる運営術
ポイントは、収入と支出を細かく管理し、早期に予防策を講じることです。家賃収入は毎月のベース収入ですが、礼金や更新料の波動も加味して年間収支をシミュレーションしましょう。管理会社から届く月次レポートを読み込む習慣をつけると、小さな異変にすぐ気づけます。
支出面では、固定資産税・都市計画税の納税時期がキャッシュアウトのピークになります。築浅アパートは建物評価が高めに算定されるため、初年度の固定資産税が思ったより高額になる場合があります。納税資金を毎月積み立てておけば、資金繰りが乱れません。
入居者サービスの向上も欠かせません。通信速度の速いインターネット無料設備や非接触型のスマートロックは、築浅物件との相性が良く若年層の入居促進に効果的です。長期入居が続けば退去時のリフォーム費用を抑えられ、結果的に手元キャッシュが増えます。こうした小さな工夫が相続後の安定経営を支えます。
2025年度の税制と制度を正しく活用
実は、2025年度税制改正では相続時精算課税制度の手続きが簡素化され、贈与から相続へのスムーズな移行が後押しされています。築浅アパートの一部持分を早めに贈与し、将来の相続税負担を段階的に下げる戦略が取りやすくなりました。ただし、一度選択すると暦年贈与との併用ができないため、シミュレーションが不可欠です。
不動産取得税の軽減措置も2025年度まで継続しています。新築または築後1年未満のアパートを取得した場合、建物部分の評価額から1,200万円が控除されます(要件を満たす場合)。この控除は購入後に遡って適用できないため、契約前に必ず確認しましょう。
さらに、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進制度(セーフティネット制度)を活用すると、改修費補助や登録住宅向けの税優遇が得られます。築浅アパートを登録すると、社会的意義を果たしつつ家賃保証スキームが使えるため、収益安定と相続対策を同時に進められます。
専門家との連携でリスクを抑える
基本的に、相続と不動産の知識を一人で完璧にカバーするのは困難です。税理士には相続税評価と贈与プランを、司法書士には登記や遺言の作成を、それぞれ相談することでミスを防げます。
不動産会社を選ぶ際は、管理戸数だけでなく入居率の公開方法や修繕計画の提案力に注目してください。アパート経営は購入後の運営が9割と言われるほど、管理の質が成否を分けます。定期的な家賃見直しやリフォーム提案を積極的に行う会社ほど、築浅のメリットを長く維持できます。
加えて、保険代理店に火災保険と地震保険を相談し、付帯サービスとして弁護士費用特約をつけておくと安心です。将来、入居者トラブルや相続人間の交渉が発生した場合でも、法的コストを抑えつつ迅速に対応できます。このように各分野の専門家と連携することで、リスクを最小化しながらアパート経営を次世代へ引き継げます。
まとめ
築浅アパート経営は、相続税評価を抑えつつ安定収益を確保できる実践的な対策です。自己資金と融資のバランスを整え、家賃と支出を丁寧に管理すれば、長期にわたりキャッシュフローを生み続けます。さらに、2025年度の税制優遇や制度を活用し、専門家チームと連携することでリスクを限りなく小さくできます。今から行動を起こせば、将来の相続時に家族間トラブルを避け、資産をスムーズに承継できるでしょう。まずは信頼できる不動産会社と税理士に相談し、具体的なシミュレーションを始めてみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省住宅局 住宅統計調査 2025年8月速報 – https://www.mlit.go.jp
- 財務省 税制改正大綱 2025年度版 – https://www.mof.go.jp
- 総務省 固定資産税評価基準 2025年度 – https://www.soumu.go.jp
- 東京都住宅政策本部 セーフティネット住宅ガイド 2025 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp
- 日本政策金融公庫 不動産賃貸業融資の手引き 2025年改訂版 – https://www.jfc.go.jp

