不動産投資に興味はあるものの、まとまった資金や物件管理の手間が気になって一歩踏み出せない人は多いものです。そこで注目されているのが、不動産投資信託「REIT(リート)」です。株式と同じように少額から購入でき、多様な物件に分散投資できる点が魅力ですが、「REIT 誰が 始め方」を検索しても専門用語が多く、かえって混乱する初心者も少なくありません。本記事では、REITの基本と始め方を2025年10月時点の制度を踏まえてわかりやすく解説します。読み終えるころには、自分に合ったスタート方法が見えてくるはずです。
REITとは何かをまず押さえておきたい

重要なのは、REITが「複数の投資家から集めた資金で不動産を購入し、その賃料や売却益を分配する仕組み」だという点です。つまり個人がマンションを一棟買うのではなく、運用会社を通じてオフィスビルや商業施設などに間接的に投資します。
金融庁の定義によると、国内の上場REIT(J-REIT)は投資信託及び投資法人に関する法律に基づき、資産の75%以上を不動産関連に投資することが義務づけられています。さらに、利益の90%以上を分配すれば法人税が実質非課税となるため、高い分配利回りにつながる仕組みです。一方で、価格は株式市場の需給で変動するため、地価や金利、景気動向に影響を受けやすい点も理解しておきましょう。
実は、J-REITの平均分配利回りは東証が公表する2025年8月末時点データで4%前後と、上場株式の平均配当利回りを上回っています。分配金は年2回が主流で、売却益を狙わなくてもインカム(保有収益)を得やすい点が初心者に支持される理由です。
どんな人がREITに向いているのか
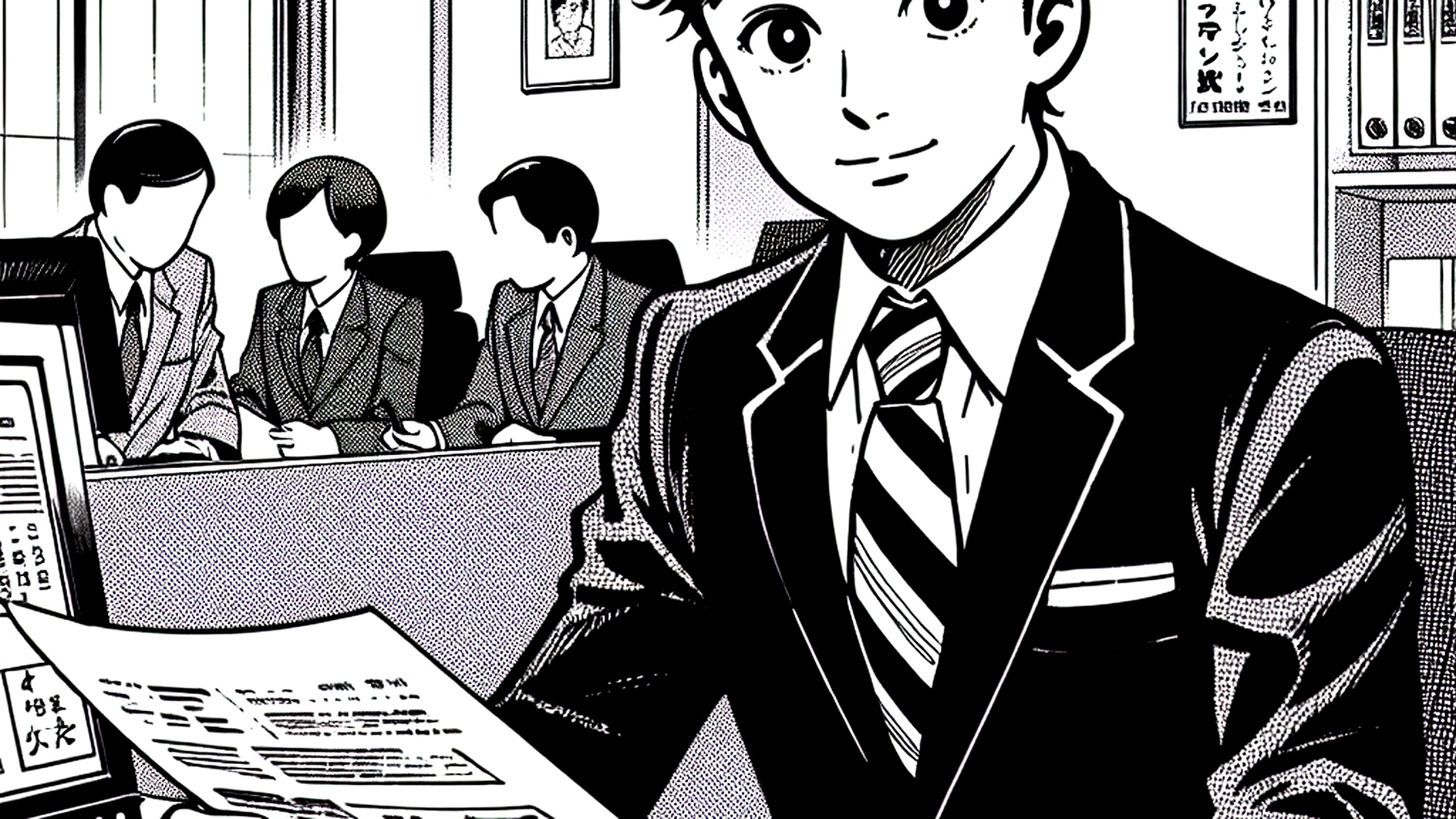
ポイントは、投資目的とライフスタイルの相性です。物件管理の時間が取れない会社員や、少額から不動産に触れたい学生・主婦層にとってREITは現実的な選択肢となります。
たとえば、仕事が忙しく現地視察が難しい会社員でも、証券口座さえあればスマホで売買が完結します。また、まとまった自己資金がなくても1口5万円前後から購入できる銘柄が多く、積立投資にも適しています。一方、物件を自己裁量でリフォームして価値を高めたい人や、長期で相続対策を考える人には現物不動産のほうがメリットが大きい場合もあります。
さらに、日本在住の外国人投資家や国内の高齢者にも人気が広がっています。言語や体力に制約があっても、公開情報を基に投資判断ができるためです。つまり、REITは「誰が」始めてもハードルが低い一方で、目的によって向き不向きがある点を押さえておきましょう。
REITの始め方をステップ別に解説
まず押さえておきたいのは、証券口座の開設です。2025年度も継続している「新しいNISA」の成長投資枠を利用すれば、年間240万円までのREIT投資益が非課税になります。期限は恒久制度化されているため、現時点で終了予定はありません。
次に銘柄選定ですが、分配利回りだけでなく、保有物件の用途や地域を確認することが重要です。オフィス中心の銘柄は景気変動に敏感で、物流施設中心の銘柄はEC需要の拡大から安定した賃料収入を期待できます。また、物件取得価格に対する有利子負債比率(LTV)が60%以下かどうかも財務健全性を測る指標として参考になります。
最後に、購入タイミングと保有戦略を決めます。東証REIT指数が直近高値から10%以上下落した場面を狙う、あるいは毎月定額で買い続けるドルコスト平均法を採用するかは、リスク許容度に応じて選択しましょう。いずれにしても、複数銘柄に分散投資することでリスクを抑えられる点がREITの強みです。
リスク管理と出口戦略も忘れずに
実は、REITにも金利上昇や不動産市況の悪化といったリスクがあります。日本銀行が2025年4月に実施したマイナス金利解除後、長期金利は1%台で推移していますが、今後さらに上昇すれば資金調達コスト増によって分配金が圧迫される可能性があります。
言い換えると、保有中は金利動向と空室率の推移を定期的にチェックすることが欠かせません。運用報告書や決算説明資料を読めば、物件ごとの稼働率や賃料改定状況が把握できます。また、含み益が20%を超えたら一部売却して利益確定するなど、出口戦略をルール化しておくと心理的な迷いを減らせます。
加えて、自然災害リスクにも目を向けましょう。日本取引所グループのガイドラインでは、主要物件の所在地や保険加入状況の開示が義務化されています。地震保険の加入率が高い銘柄や、複数地域に分散投資している銘柄を選ぶことでリスクを軽減できます。
税制と手数料を味方につけるコツ
ポイントは、投資コストを最小限に抑えることです。REITの売買手数料はネット証券であれば取引額の0.1%前後が一般的ですが、1日定額プランを導入する証券会社なら実質無料になる場合もあります。投資信託型のREITファンドを選ぶ場合は、信託報酬が年1%を超えないものを目安にすると良いでしょう。
2025年度税制では、特定口座(源泉徴収あり)を利用すれば、分配金にかかる所得税・住民税が自動で徴収され確定申告が不要です。ただし、給与所得が2,000万円を超える人や損益通算を行いたい人は申告が必要なので注意しましょう。NISA口座内で受け取った分配金と売却益は非課税ですが、損失が出ても他口座と通算できない点は理解しておくべきです。
つまり、NISAでコア銘柄を保有しつつ、特定口座でサテライト銘柄を売買するハイブリッド運用が、コストと損益通算のバランスを取りやすい方法といえます。
まとめ
REITは少額から不動産に分散投資できる手軽さが最大の魅力です。証券口座を開設し、分配利回りだけでなく物件タイプや財務健全性を確認しながら複数銘柄に分散することで、安定的なインカム収入と値上がり益の両方を狙えます。また、2025年度の新しいNISAを活用すれば非課税メリットも享受できます。一方で金利動向や市況悪化リスクを常にチェックし、出口戦略を明確にしておくことが長期的な成功の鍵です。今日から情報収集と口座開設を始め、あなたに合ったREIT投資をスタートしてみましょう。
参考文献・出典
- 金融庁 – https://www.fsa.go.jp/
- 日本取引所グループ (JPX) – https://www.jpx.co.jp/
- 東証REIT指数 月次レポート – https://www.jpx.co.jp/markets/indices/j-reit-index/
- 国税庁「新しいNISAの概要」 – https://www.nta.go.jp/
- 日本銀行 長期金利推移データ – https://www.boj.or.jp/
- 国土交通省 不動産市場動向調査 – https://www.mlit.go.jp/

