不動産投資を始めようとすると、物件探しや融資条件ばかりに目が向きがちです。しかし、購入後に「思ったより手元に残らない」「税金が高くて赤字になった」と悩む人は少なくありません。そこで欠かせないのが収支計算です。この記事では、初心者がつまずきやすいポイントを整理しつつ、収支計算をどう活用すれば長期的に安定した運用につながるかを解説します。読了後には、自分に合う物件かどうかを数字で判断できるようになるはずです。
収支計算が投資の羅針盤になる理由
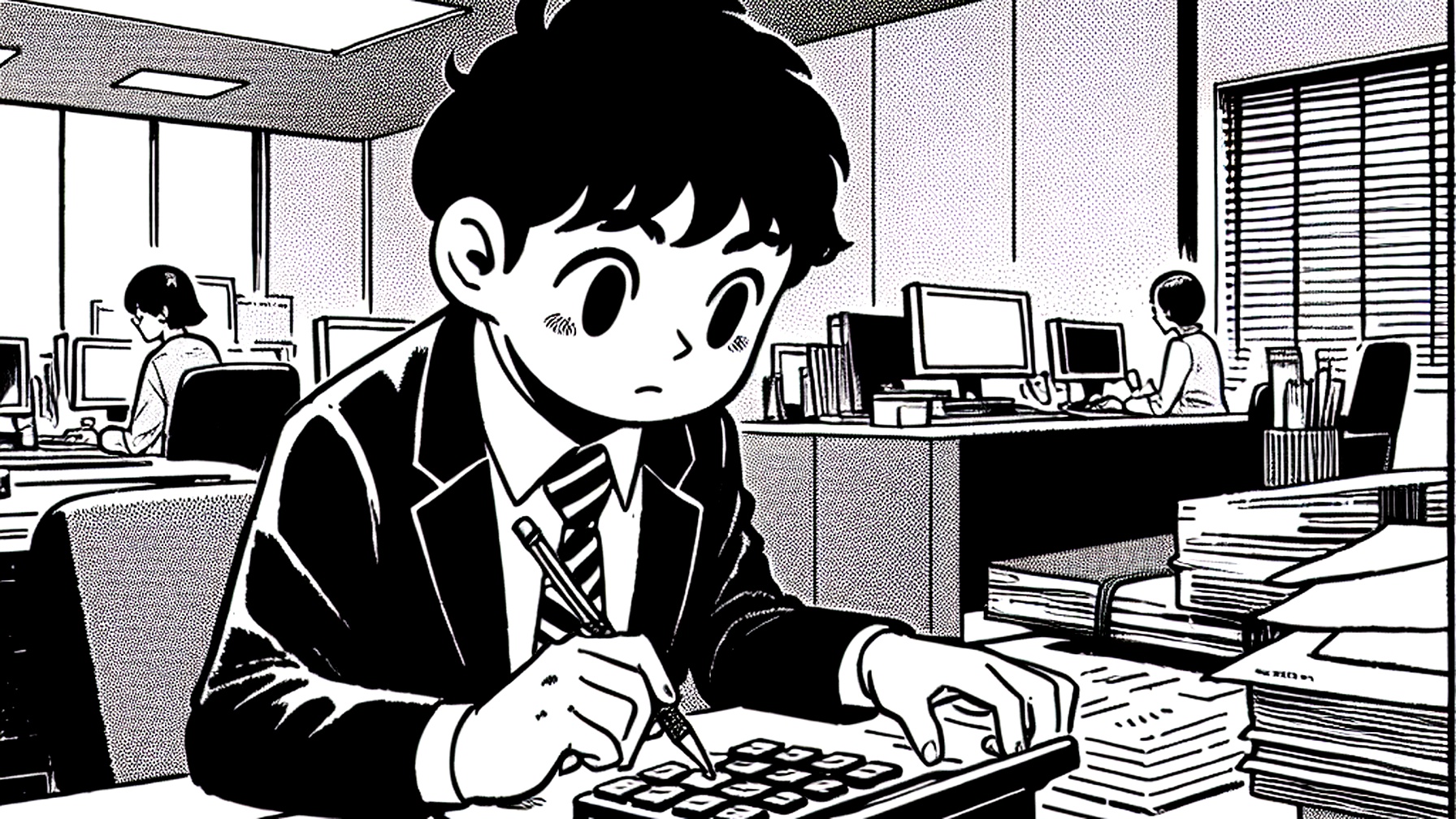
まず押さえておきたいのは、収支計算が将来のキャッシュフローを可視化し、投資判断の軸を提供してくれる点です。不動産は株式と違い流動性が低いため、購入後に赤字が続くと簡単には撤退できません。購入前に年間の収入と支出を具体的に試算し、最悪のシナリオにも備えておくことがリスク管理の出発点になります。
収益物件の利回りは広告に記載された「表面利回り」だけでは判断できません。空室リスクや修繕費を加味した「実質利回り」を求めることで、手残りの現金をイメージできます。国土交通省の「令和6年賃貸住宅市場動向調査」によると、築20年超物件の平均空室率は12%前後で推移しています。この数字を計算に組み込むかどうかで、収支の見通しは大きく変わります。
さらに、金融機関の融資姿勢も収支計算で見える化できます。返済比率(年間返済額÷年間賃料収入)は50%以内が目安とされ、これを超えると追加融資や金利交渉が難しくなる傾向があります。つまり、収支計算は「買うかどうか」だけでなく、「買った後に続けられるかどうか」を判断する羅針盤なのです。
収入項目を正確に洗い出す方法
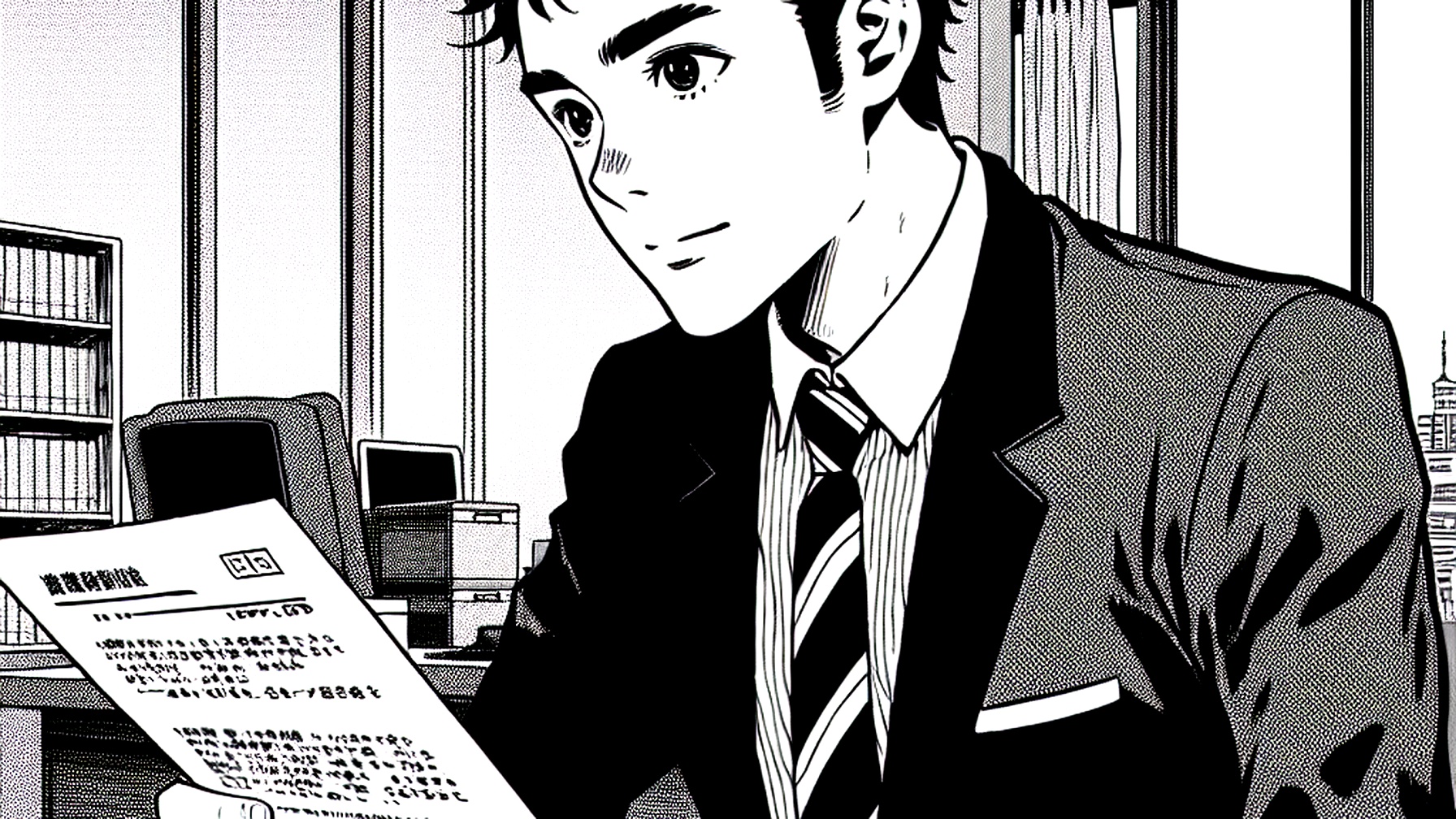
ポイントは、賃料以外の小さな収入源も漏れなく拾い上げることです。賃料は管理会社が提示する相場を基に設定しますが、礼金や更新料、駐車場代などの副次的収入を含めると年間キャッシュフローが数十万円変わるケースがあります。
例えば、東京都23区のワンルームを月8万円で貸し出す場合、更新料1ヶ月を2年ごとに受け取れると仮定すると、年間平均で月額に換算して約3,300円の上乗せになります。国税庁の「家賃等の動向調査」では、更新料を設定している物件は全体の63%に上るため、この収入を無視すると実質利回りが過小評価されてしまいます。
一方で、将来的な賃料下落リスクも織り込む必要があります。総務省の消費者物価指数では直近10年間で住宅家賃はほぼ横ばいですが、地方都市や築年数が進むほど下落傾向が強いデータもあります。したがって、シミュレーションでは「現賃料」「10%下落」「20%下落」と三段階で計算し、収入が減っても耐えられるか検証することが欠かせません。
支出を漏らさないためのチェックポイント
実は支出の計上漏れが赤字の最大要因です。ローン返済や管理費のほかに、固定資産税・都市計画税、修繕積立金、火災保険料が年間コストとして重くのしかかります。特に見落とされやすいのが「大規模修繕費」です。築30年を迎えるマンションでは、外壁塗装や給排水管交換に一戸あたり100万円以上かかる例もあり、区分所有者でも負担は避けられません。
修繕積立金が不足している管理組合では、将来一時金として数十万円を請求されるケースがあります。日本住宅性能評価・表示協会の2024年調査では、積立不足があるマンションは全体の37%に上ると報告されています。このリスクを反映して、毎月1万円程度を別途修繕用に積み立てると、キャッシュフローは安全寄りになります。
また、税金面では2025年度も継続する「住宅ローン控除」が区分所有の投資用には適用されません。代わりに、減価償却費を計上することで課税所得を圧縮できますが、建物価格の按分や法定耐用年数の設定がシミュレーションに大きく影響します。税理士に試算を依頼する費用も支出に含めると、より現実的な数字になります。
キャッシュフローをどう判断材料にするか
基本的に、キャッシュフロー(手残り現金)がプラスであることが投資継続の最低条件です。しかし、短期的にプラスだからといって安易に購入を決めるのは危険です。重要なのは、金利上昇や空室発生といったストレスがかかったシナリオでもキャッシュフローがプラスか、もしくは損失を補える余剰資金があるかという点です。
日本銀行の2025年7月金融政策決定会合では、長期金利の上限を1.5%に柔軟化する方針が示されました。変動金利型ローンを利用する場合、金利上昇が返済額を押し上げ、キャッシュフローを圧迫する恐れがあります。これを踏まえ、長期シミュレーションでは金利を現在より1.5%上乗せして試算しておくと安心です。
さらに、損益計算だけでなく貸借対照表(バランスシート)も確認しましょう。物件価格が下がってもローン残高も同程度に減れば、売却損を回避できる可能性があります。資産と負債のバランスを定期的に見直すことで、「保有継続」「売却」「買い増し」という戦略の選択肢が広がります。
2025年時点の制度とシミュレーション活用法
ポイントは、制度変更を正しく把握し、シミュレーションに反映することです。2025年度も「投資用不動産の減価償却ルール」「固定資産税の経過措置」は継続予定ですが、建物評価額の引き下げに伴い減価償却費が年々減少する点は見落とせません。つまり、初年度の節税額だけでなく、5年後、10年後の税負担まで計算に入れる必要があります。
また、エネルギー価格高騰を背景に、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)マンションへの補助金が2025年度も継続します。ただし、事業者向けで個人投資家が直接受け取れる制度ではないため、収支計算では物件価格に補助金分の値引きが織り込まれているかを確認する形になります。誤って自己のキャッシュフローに組み込まないよう注意が必要です。
シミュレーションソフトを使う際は、初期設定の空室率や修繕率が自分の投資エリアに合っているか必ず確認しましょう。総務省統計局「住宅・土地統計調査」では、地方中核都市よりも三大都市圏の空室率が平均3ポイント低いと報告されています。エリアごとのデータを入力することで、シミュレーションの精度が格段に向上します。
まとめ
ここまで、収支計算が投資判断の羅針盤となる理由から、具体的な収入・支出の洗い出し方、キャッシュフローの見方、制度変更の反映までを解説しました。数字をもとに最悪のシナリオでも赤字を最小限に抑えられるかを検証することが、長期的な成功への近道です。読者の皆さんも、今日から自身のシミュレーション表を作成し、気になる物件を複数の条件で検証してみてください。数字が教えてくれるリアルなリスクと向き合うことで、安心して次の一歩を踏み出せるはずです。
参考文献・出典
- 国土交通省 令和6年賃貸住宅市場動向調査 – https://www.mlit.go.jp/
- 総務省統計局 住宅・土地統計調査 2023 – https://www.stat.go.jp/
- 日本銀行 金融政策決定会合議事要旨 2025年7月 – https://www.boj.or.jp/
- 国税庁 家賃等の動向調査 2024 – https://www.nta.go.jp/
- 日本住宅性能評価・表示協会 修繕積立金調査 2024 – https://www.hyouka-sumai.or.jp/

