不動産投資信託(REIT)は少額から不動産に分散投資できる便利な商品ですが、「分配金にはどれだけ税金がかかるのか」「節税の方法はあるのか」など、税制面の疑問が尽きません。特に2025年現在は新NISAやインフレ対策で投資環境が変化しており、知識の有無がリターンを左右します。本記事ではREITの基本から税金計算、制度活用のコツまでを体系的に整理します。読み終えた頃には、ご自身で納税額を概算し、注意点を踏まえて投資判断ができるようになるはずです。
REITの仕組みと投資メリット
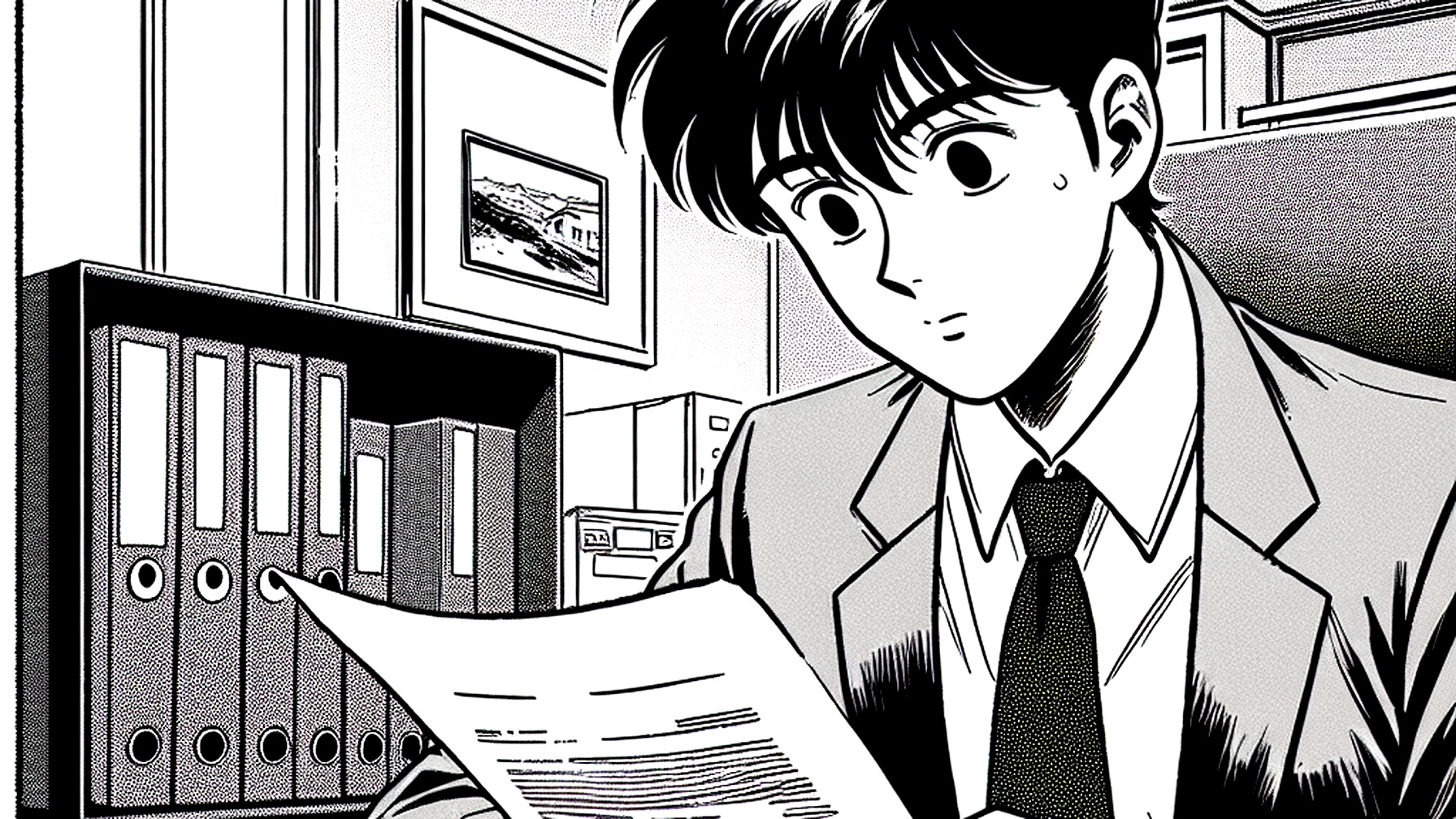
まず押さえておきたいのは、REITが「投資家から集めた資金で複数の不動産を保有・運用し、賃料収入や売却益を分配する仕組み」だという点です。東京証券取引所のデータによると、2025年9月時点で国内上場REIT(J-REIT)の時価総額は約19兆円に達し、オフィス、物流、住宅など多様なアセットが組み込まれています。少額から購入でき、個別物件より流動性が高いことが魅力です。
次に重要なのは、REITが法律上「投資法人」に分類され、利益の90%超を分配すれば法人税が実質的に免除される点です。つまり投資家は、物件で得られたキャッシュフローの大部分を分配金として享受できます。分配金利回りは平均4〜5%台で推移し、長期の低金利環境下では比較的高いインカムを狙える商品といえます。
一方で、値動きは東証REIT指数に連動し、株式市場の影響も受けます。また賃料下落や空室率の上昇が利益に直結するため、根底には不動産市場特有のリスクがあることも忘れてはいけません。メリットを最大化するには、後述する税金と合わせた総合的なリターン管理が欠かせないのです。
分配金・譲渡益にかかる税金の基礎
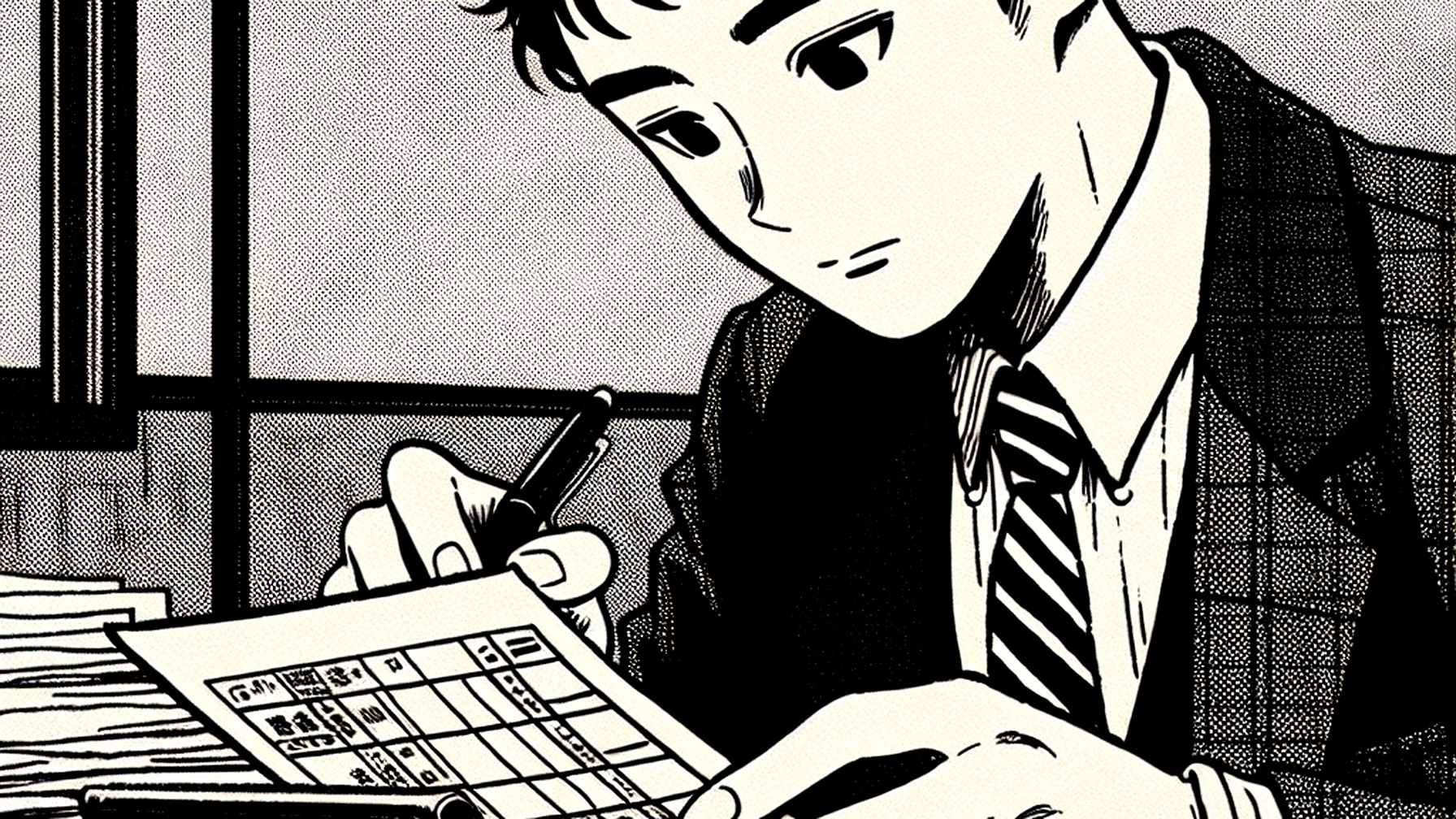
ポイントは、REITの収益が「分配金」と「売買による譲渡益」の二本立てで課税されることです。個人投資家の場合、分配金には所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%を合わせた20.315%が源泉徴収されます。証券口座で自動的に控除されるため納税手続きは不要ですが、収入の2割が目減りする点は頭に入れておきましょう。
譲渡益も同じ税率で課税され、特定口座(源泉徴収あり)を利用すれば確定申告は原則不要です。ただし年間で損失が出た場合、株式やETFと損益通算できるため、確定申告をすると税負担を軽減できる可能性があります。国税庁の統計では、損益通算を活用した還付件数は年々増加しており、投資初心者でも選択肢に入れておきたい手法です。
なお法人が保有する場合、分配金と譲渡益は法人税の対象となり、実効税率は約30%と個人より高くなります。一方で減価償却費や金利などの経費算入が可能となるため、キャッシュフロー次第では法人保有が有利になるケースも存在します。投資スタイルと規模に応じて、個人か法人かの選択は慎重に行いましょう。
2025年度の節税策と制度活用
実は、節税の鍵を握るのが「2025年度の新NISA」です。新NISAは年間360万円、非課税保有限度額1,800万円と拡充され、REIT ETFも成長投資枠で購入できます。非課税期間は無期限となったため、分配金と譲渡益の20.315%が丸ごと節税できる点は大きな魅力です。
ただし、成長投資枠の年間上限は240万円であり、積立投資枠120万円と合わせた資金配分が必要です。金融庁の資料によると、口座開設者の約7割が積立投資枠を優先しているため、枠をREIT ETFに振り向けたい場合は早めに資金計画を組むと取りこぼしを防げます。
また、上場株式等の配当控除はREITの分配金には適用されません。株式配当と同列に考えて確定申告すると控除対象外であることに気づき、税務署から修正を求められるケースが散見されます。制度名称と対象範囲を正確に押さえることが、トラブル回避につながります。
投資前に押さえたいリスクと注意点
まず、REITの分配金は必ずしも固定ではありません。物件売却益を厚く計上した翌期に空室が増えれば、一口当たり分配金が減少することもあります。過去の実績だけで将来を判断するのは危険だという点を意識しましょう。
また、金利上昇に伴い借入コストが増えると分配原資が圧迫されます。日本銀行は2024年3月にマイナス金利を解除し、その後緩やかな利上げを進めています。仮に長期金利が1%上がると、借入比率が高いREITの収益が数%程度低下するシミュレーションが東証の開示資料に掲載されています。
さらに、物件の含み損が拡大しても簿価を大幅に下げない限り損失計上されにくい仕組みのため、表面上の指標だけではリスクを見抜きにくい点があります。投資法人財務諸表のキャッシュフローステートメントやLTV(Loan to Value:総資産に対する有利子負債比率)を確認し、財務健全性までチェックする習慣が欠かせません。
長期保有で変わる税負担の考え方
基本的に、REITはインカムゲイン中心の長期投資に向いていますが、税負担の推移も長期視点で捉えることが大切です。分配金は毎期課税されるため、複利効果が阻害されがちです。そこで非課税口座の活用や分配金再投資の自動化によって、課税後キャッシュフローを最大化できます。
一方、譲渡益課税は売却時点で確定するので、保有期間中に価格上昇があっても含み益であれば課税されません。売却タイミングをずらすことで、課税の繰り延べ効果を得られる点は株式と同様です。老後資金として取り崩す場合、退職金控除や公的年金等控除との兼ね合いで、年単位のキャッシュアウトを調整すると合計税負担を抑えられます。
結論として、税金は「払い方」を設計することで総額が変わります。制度の枠と自身のライフプランを重ね合わせ、分配金の受け取り方法と売却戦略を立体的に組み立てることが、REIT投資を成功に導くカギとなるのです。
まとめ
REITは不動産分散投資の手軽な手段ですが、分配金と譲渡益に対する20.315%の税金をどうコントロールするかで手取りが大きく変わります。新NISAの非課税枠活用、損益通算による還付、金利リスクの見極めなど、注意点を押さえてこそ安定的なリターンが期待できます。まずはご自身の年間投資枠とライフイベントを照らし合わせ、制度を味方につけたプランを描いてみてください。小さな一歩が、将来の大きな安心につながります。
参考文献・出典
- 金融庁 – https://www.fsa.go.jp
- 国税庁 – https://www.nta.go.jp
- 東京証券取引所 – https://www.jpx.co.jp
- 総務省統計局 – https://www.stat.go.jp
- 日本銀行 – https://www.boj.or.jp

