不動産に興味はあるけれど、まとまった資金や管理の手間が心配という理由で、REITに目を向ける人が増えています。しかし検索すると「REIT デメリット 評判」といった不安げなキーワードが並び、踏み出せない方も多いはずです。本記事では、2025年10月時点の最新情報をもとに、初心者にも分かりやすくREITの仕組みと弱点、実際の投資家の声、そしてリスクを最小化する具体策まで丁寧に解説します。読み終えるころには、REITが自分に合うかどうかを判断できるようになります。
REITとはそもそも何か
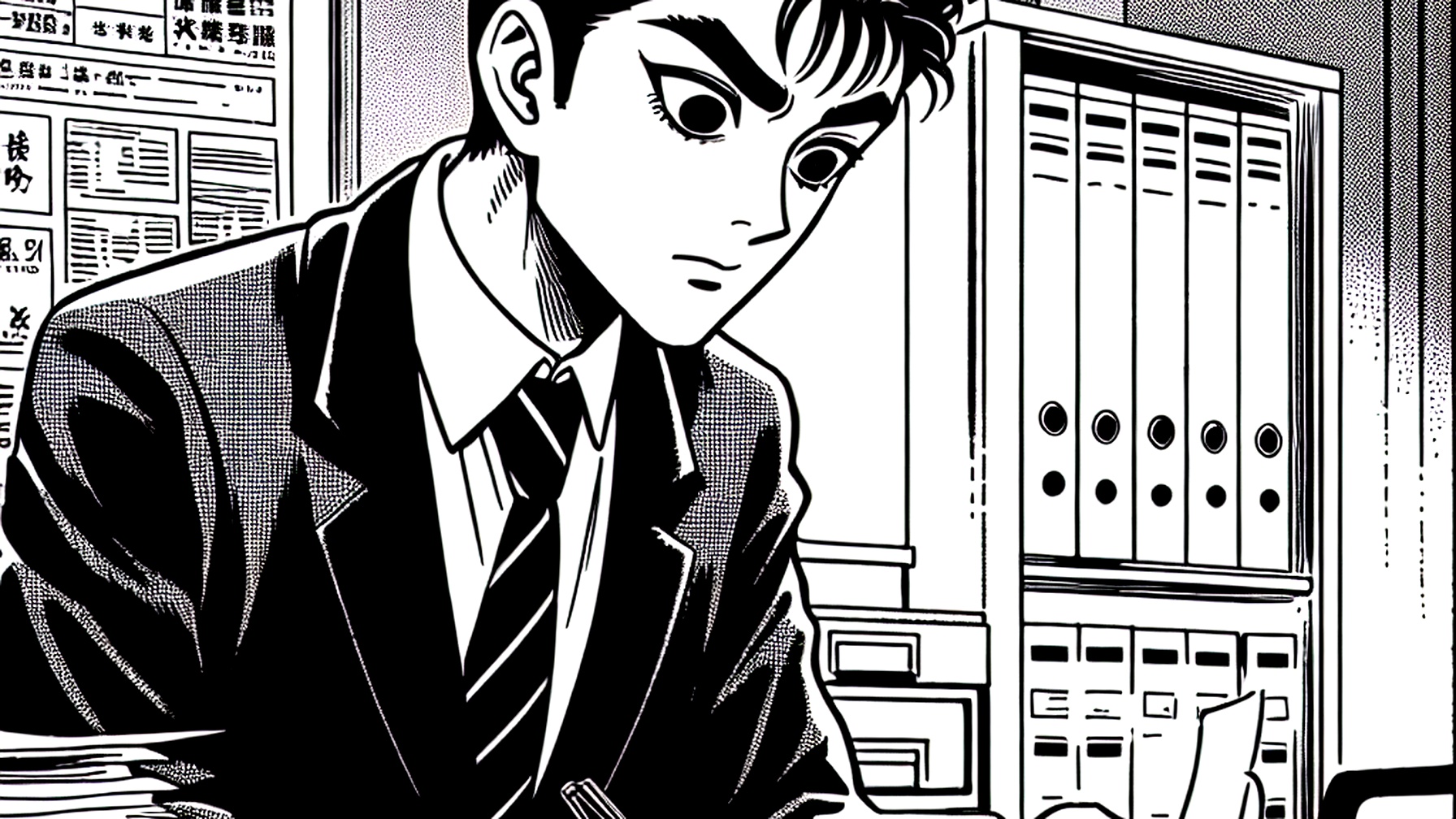
まず押さえておきたいのは、REITが不動産投資信託の略称で、複数の投資家から集めた資金でオフィスビルや商業施設などを購入し、賃料や売却益を分配する仕組みだという点です。株式と同じ取引所で売買でき、少額から始められる点が人気の理由になっています。
実は、REITには「法人税が実質免除される」「運用の透明性が高い」という強みがあります。ただし、そうした長所だけを見ると判断を誤りがちです。金融庁のデータによると、2025年6月末時点で東証REIT指数は前年同期比で約4%下落しており、価格変動リスクは確実に存在します。この変動を自分の許容範囲内と考えられるかが、投資判断の最初の分かれ道になります。
次に、REITの分配金は法律上90%以上の利益を配当に回す義務があるため、高い利回りが期待されます。しかし、分配金の原資は物件の賃料収入です。空室率の上昇や賃料の下落が発生すると、配当が減る可能性もあると理解しておきましょう。
一方で、上場しているからこそ情報開示はきわめて細かく、決算書類や物件一覧が誰でも確認できます。つまり、個々の銘柄を比較する材料は十分にあるものの、内容を読み解く力が求められる側面もあります。
知っておきたい主なデメリット
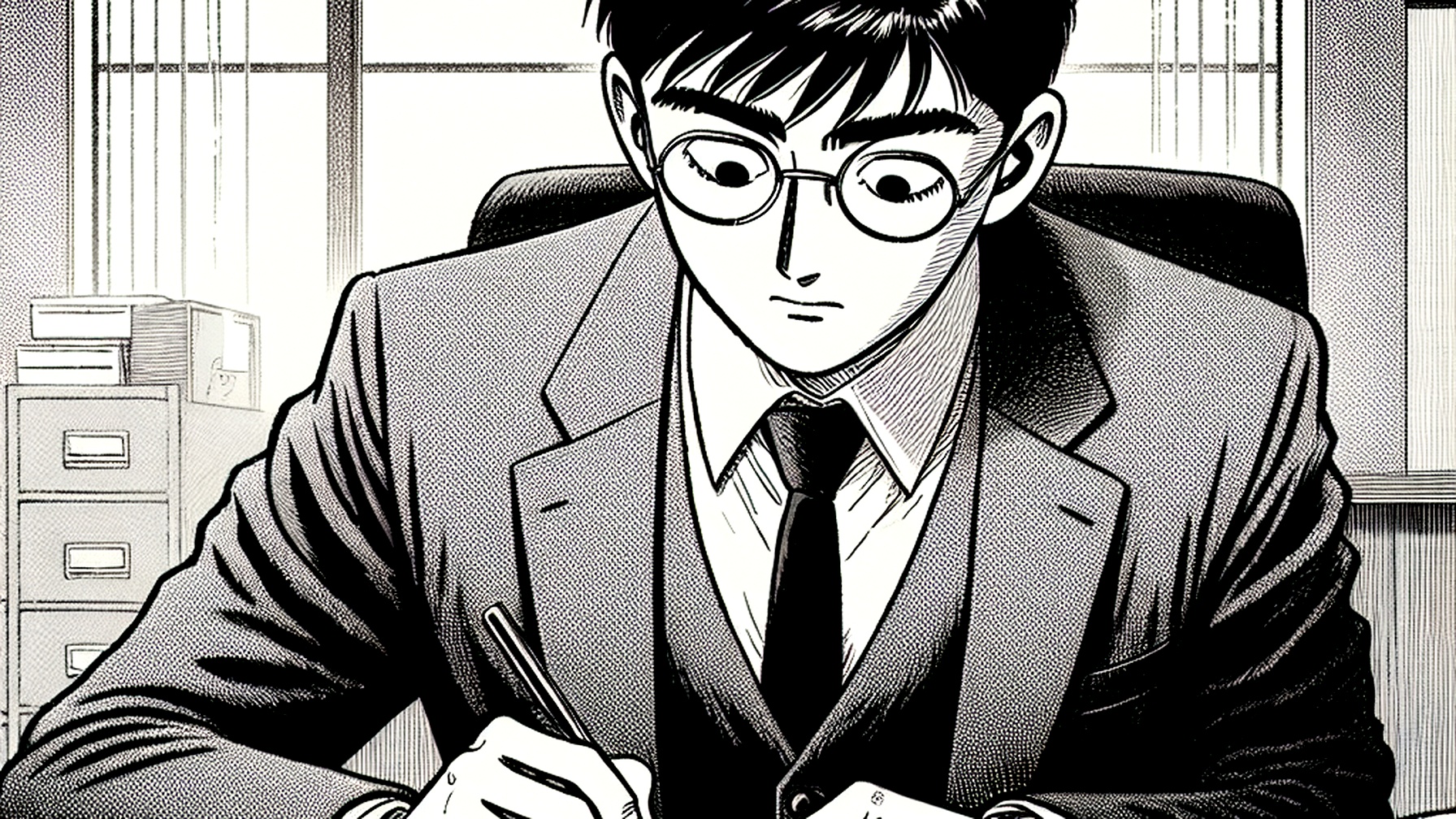
ポイントは、REIT特有のリスクを具体的に把握し、他の金融商品と比較しながら位置づけることです。ここでは代表的なデメリットを四つ取り上げます。
最初に挙げたいのが価格変動リスクです。REITは株式と同様に市場で売買されるため、金利上昇や景気後退のニュースで値動きが大きくなります。例えば2025年2月の米国利上げ観測時、東証REIT指数は一週間で3%以上下落しました。短期の値動きに振り回されると、想定外の損失を抱える恐れがあります。
次に流動性リスクです。株式より出来高が少ない銘柄では、売りたいときに思った価格で売れない場合があります。特に地方物件に偏った小規模REITは売買注文が薄く、急いで換金しようとすると価格が大きく下がる可能性があります。
三つ目は物件集中リスクです。複数物件を持つと言っても、特定の用途や地域に偏るREITは少なくありません。オフィス主体のREITはテレワークの浸透で賃料が下がると打撃を受けやすく、物流特化型は新規供給が増え過ぎると競争が激化します。投資口を買う前にポートフォリオの分散度を必ずチェックしましょう。
最後に金利リスクがあります。REITの多くは物件購入時に長期ローンを利用しており、日銀の利上げで金利負担が増えると分配金に影響します。2025年10月時点ではマイナス金利が解除され、長期プライムレートが1%台後半で推移しています。今後さらに上昇すれば、分配金利回りの低下は避けられません。
実際の投資家の評判と感じるリスク
実は、REITに対する評判は「手軽で高配当」という肯定的な声と「値動きが読みにくい」という否定的な声が二極化しています。金融広報中央委員会が2025年4月に行った調査では、REIT保有者の満足度は63%とまずまずですが、「値下がりで慌てた経験がある」と答えた人も48%に達しました。
肯定的な意見では「都心オフィスを間接的に所有できる感覚が楽しい」「株主優待と違いキャッシュで入る分配金が生活費の足しになる」といった実利面が強調されています。また、NISA口座で買えば分配金に対する税金がかからない点も評価されています。2025年度の新しいNISAは年間投資枠が拡大し、分配金非課税期間が恒久化されたため、長期保有者のメリットは大きいです。
一方で否定的な意見は「高利回りにつられて買ったら相場急落で含み損」「海外金利の動向に影響を受けやすく難しい」という声が目立ちます。特に初心者は、分配金利回りだけを見て判断しがちですが、実際には物件取得価格の高騰や修繕費の上昇が利益を圧迫しているケースもあると知っておきましょう。
また、SNSでは「REITは配当が安定しているから安全」という短絡的な投稿が散見されます。こうした口コミをうのみにせず、IR資料や有価証券報告書を確認する習慣を持つことで、評判に振り回されない投資判断が可能になります。
デメリットへの具体的な対処法
重要なのは、デメリットを完全に避けるのではなく、影響をコントロールする戦略を取ることです。ここでは再現しやすい三つの対処法を紹介します。
まず分散投資を徹底しましょう。REIT自体が複数物件を保有していますが、一銘柄に集中させると物件集中リスクは残ります。オフィス、住宅、物流、商業とセクターを分けて複数銘柄を保有すれば、景気変動の影響を受けにくくなります。東証には60本以上のREITが上場しているため、分散は十分に可能です。
次に積立投資の仕組みを活用します。証券会社によっては毎月1万円からREITを自動購入できるサービスがあります。価格が高いときは少なく、安いときは多く買うドルコスト平均法が働き、短期的な価格変動リスクを和らげます。特に2025年の新NISAでは月間の積立上限が広がったため、計画的な資金投入がしやすくなりました。
最後に、金利上昇期にはLTV(Loan to Value:負債比率)が低いREITを選びます。負債比率が高いと金利負担増の影響が大きくなりますが、LTVが40%台前半の銘柄なら、利上げ局面でも分配金の減少幅を比較的小さく抑えられます。IR資料には平均借入金利や借入期間も記載されているため、必ずチェックしてから投資しましょう。
REITが合う人・合わない人の判断基準
まず押さえておきたいのは、自分の投資目的とREITの特性を照らし合わせることです。REITはフロー収入を重視する人に適していますが、短期の値上がり益を狙うトレーダーには不向きな面があります。
具体的には、毎月のキャッシュフローを増やしたい人、物件管理の手間を避けたい人、少額で不動産に分散投資したい人にはREITが向いています。反対に、価格変動による含み益を追求したい、投資対象を自分で細かくコントロールしたい、レバレッジを高くかけたい人には物足りない可能性があります。
また、税制面のメリットを最大化したい場合、NISAやiDeCoの活用余地を考えることが大切です。2025年度のNISAでは年間360万円までの投資が非課税対象となるため、高配当のREITと相性が良いと言えます。ただし、長期保有が前提になるため、途中で資金が必要になるライフプランの人は計画的な資金配分が必要です。
結論として、REITは手軽さと高配当が魅力ですが、価格変動と金利動向に左右される金融商品である点を忘れてはいけません。自分のリスク許容度と投資目的を明確にし、分散と積立を組み合わせれば、デメリットを抑えた堅実な運用が期待できます。
まとめ
ここまで「REIT デメリット 評判」という切り口で、仕組みの基礎から主なリスク、投資家の生の声、対処法、向き不向きの判断基準まで解説しました。価格変動リスクや金利上昇の影響といった弱点を理解し、IR資料を読み込んで分散と積立を実践すれば、REITは堅実なキャッシュフロー源になり得ます。まずは少額から試し、マーケットの動きと分配金の推移を体感するところから始めてみてください。
参考文献・出典
- 金融庁 – https://www.fsa.go.jp/
- 日本取引所グループ – https://www.jpx.co.jp/
- 金融広報中央委員会 – https://www.shiruporuto.jp/
- 東証REIT指数データ – https://www.jpx.co.jp/markets/indices/j-reit-index/
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp/

