不動産投資に興味はあるけれど、物件を直接買うのはハードルが高い――そんな悩みを抱える人が増えています。特に最近は「少額で分散投資できるREIT(不動産投資信託)が気になるけれど、始め方がわからないし、誰がサポートしてくれるのか不安」という声が多く聞かれます。本記事では、REITの基本から購入までの流れ、2025年10月時点で活用できる制度、頼れる専門家の選び方までを網羅的に解説します。読み終えた頃には、あなた自身が次に取るべき一歩が具体的に見えてくるでしょう。
REITとは何かをまず押さえよう
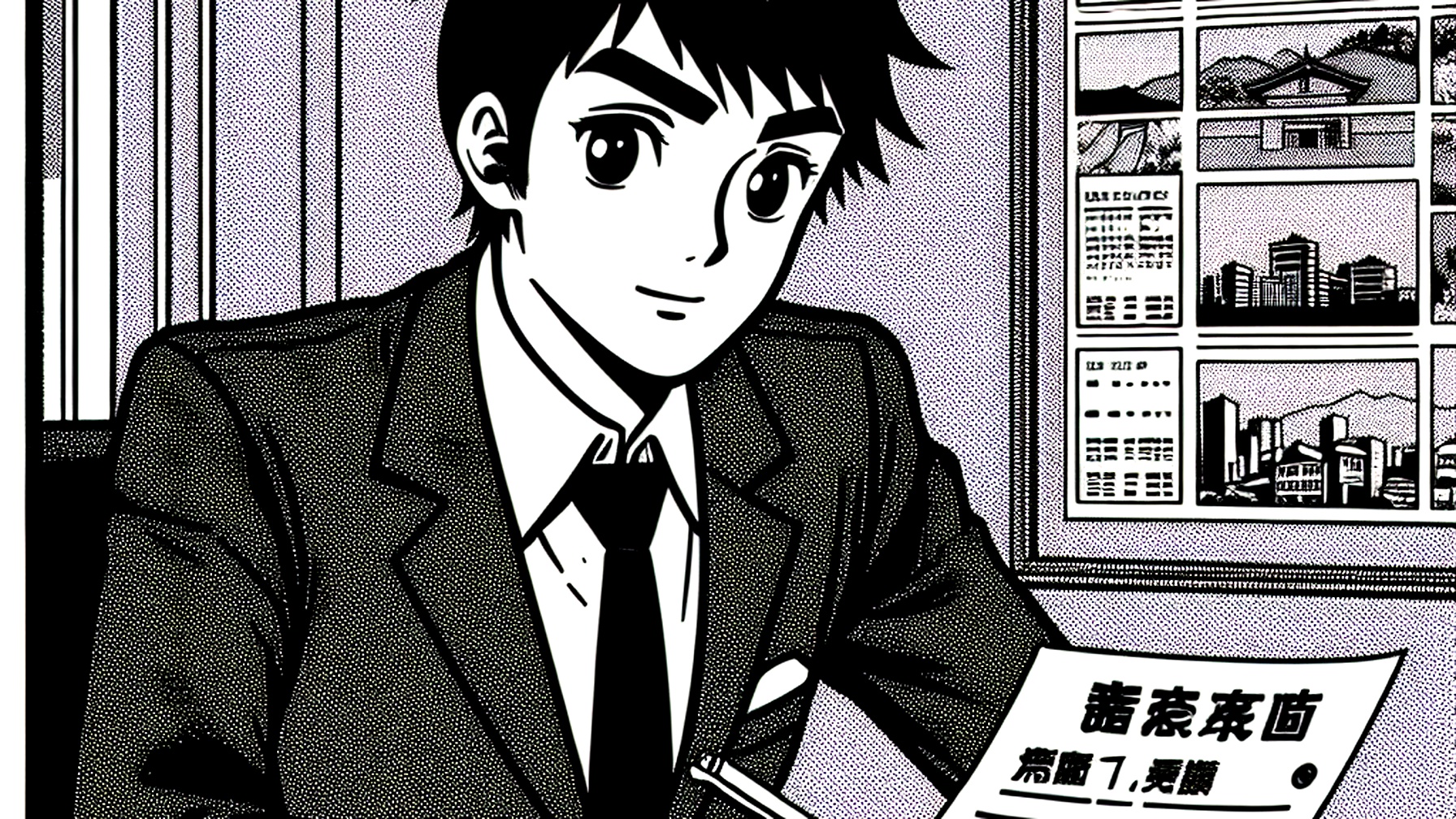
重要なのは、REITが「多くの投資家から集めた資金で複数の不動産を保有・運用し、その賃料や売却益を分配する仕組み」である点です。株式と同じように証券取引所に上場しているため、1口数万円から売買でき、流動性が高いのが特徴です。 さらに、金融庁の「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づき、利益の90%以上を分配すれば法人税が実質的に免除されるという優遇があるため、分配金利回りは上場株より高めで推移する傾向があります。一方で価格変動リスクや金利上昇リスクもあるので、仕組みの理解が不可欠です。 また、2025年10月時点の東証REIT指数はコロナ禍前の水準を回復しつつあり、国土交通省の不動産価格指数でもオフィス・物流施設の堅調さが示されています。こうした背景を把握すると、REITが中長期の資産形成に適した商品だとわかります。
口座開設から購入までの流れを具体的に理解する
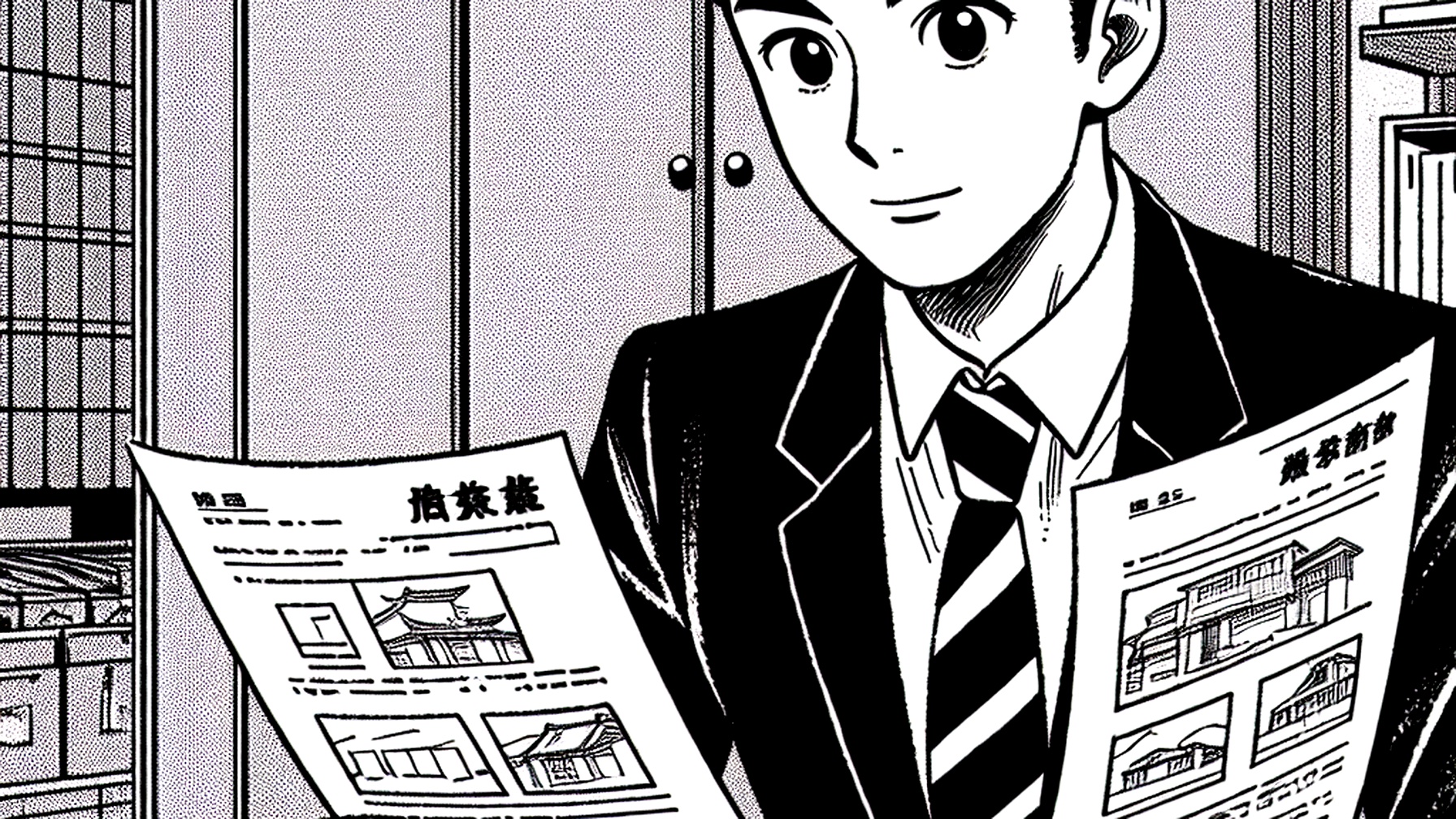
まず押さえておきたいのは、REIT購入には証券総合口座が必要になることです。国内最大手のネット証券であれば、スマホから最短1日で口座を開設できます。マイナンバーカードを使ったオンライン本人確認が主流となり、紙の書類を郵送する手間はほとんどありません。 口座開設後は、入金→銘柄選定→発注という3ステップで売買が可能です。株式と同様に指値注文、成行注文が使え、売買単位は1口。つまり実際の取引画面は株とほぼ同じなので、株式経験者なら操作はすぐに慣れるでしょう。 発注後はT+2(約定日から2営業日後)で受渡しが完了します。分配金の権利付き最終日を意識して購入する人も多いですが、実は価格変動を落ち着いて観察するためには、分配金目的だけにとらわれず長期視点でのタイミングを計る方が合理的です。
誰がサポートしてくれるのか―専門家と情報源の見極め
ポイントは「手数料の透明性」と「利益相反の少なさ」で専門家を選ぶことです。証券会社の担当者は商品を提案してくれますが、販売手数料や推奨理由を必ず確認しましょう。独立系ファイナンシャルプランナー(FP)は中立的な立場で助言を行うため、初回相談を活用して資産全体のバランスを見直すのも一案です。 さらに、投資信託協会や日本取引所グループ(JPX)が提供する無料セミナーは実務的な内容が豊富で、初心者にもわかりやすく構成されています。オンライン配信が主流となった2025年現在、移動時間をかけずに質の高い情報を得られるのは大きなメリットです。 身近なSNSやブログも便利ですが、発信者がREIT運用会社から広告収入を得ていないかをチェックする姿勢が欠かせません。つまり、「REIT 始め方 誰が」を考える際は、立場と収益構造を意識して情報の質を見極めることがリスク管理につながります。
2025年度に活用できる税制・制度のポイント
実は、REIT投資は少額投資非課税制度(NISA)との相性が良いのが特徴です。2024年に恒久化された新NISAは年間360万円まで非課税で投資でき、上場REITも対象に含まれています。非課税保有期間が無期限になったことで、分配金を全額非課税で積み上げられるメリットが極めて大きいと言えます。 また、2025年度税制改正ではインカムゲイン(分配金)に係る税制優遇の維持が確定していますので、20.315%の課税を回避する手段としてNISAを使わない手はありません。一方、iDeCo(個人型確定拠出年金)はREITを直接買えないため、REIT組入比率の高い投資信託を選ぶことになります。制度ごとの特徴を理解し、非課税枠を最大限に活用してください。 さらに、総務省の家計調査によると、投資信託保有額がある世帯の金融資産は非保有世帯より平均1.8倍多い結果が出ています。税制メリットを活用する人ほど、資産形成が加速する傾向がデータからも裏付けられています。
リスク管理とポートフォリオの組み方
基本的に、REITは物件種別や地域が偏ると価格変動リスクが高まるため、複数銘柄に分散することが第一歩です。例えばオフィス中心の銘柄に加え、物流施設主体や住宅主体の銘柄を組み合わせるだけで、賃料収入の変動を平準化できます。 また、金利上昇局面では借入比率(LTV)が高い銘柄ほど分配金の伸びが鈍る傾向があります。JPX公表のデータによると、平均LTVが50%を超える銘柄群は40%未満の銘柄に比べて2023~2025年の分配金成長率が約2ポイント低下しました。金利感応度を把握し、ポートフォリオ全体でリスクを抑える視点が欠かせません。 さらに、株式や債券との相関係数は0.3前後で推移しており、伝統資産との分散効果が期待できます。ただし、リーマンショック時のように金融市場全体が動揺すると同時に下落する可能性もあります。したがって、キャッシュポジションを10~20%確保し、再投資の余力を持っておくことが安定運用への鍵となります。
まとめ
REITは少額から不動産に分散投資でき、分配金利回りも比較的高い魅力的な商品です。しかし、価格変動リスクや金利感応度を理解せずに始めると、想定外の損失を抱える恐れがあります。だからこそ、信頼できる情報源と専門家を活用し、NISAなどの税制優遇を組み合わせ、複数銘柄への分散投資でリスクを抑えることが重要です。今日紹介した流れを踏まえ、まずは証券口座を開設し、少額で市場に触れるところから始めてみてください。行動することでしか得られない学びが、将来の資産形成を大きく後押ししてくれるはずです。
参考文献・出典
- 金融庁 – https://www.fsa.go.jp/
- 日本取引所グループ(JPX) – https://www.jpx.co.jp/
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp/
- 総務省統計局 家計調査 – https://www.stat.go.jp/
- 投資信託協会 – https://www.toushin.or.jp/

