会社員として毎月の給与を得ながら「将来の年金だけでは不安」「早期退職も視野に入れたい」と考える人は年々増えています。とくに中古マンション投資は自己資金を抑えつつ安定収入を得られる手段として注目されています。しかし、物件選びや融資、税金の仕組みを誤解したまま参入すると、思わぬ赤字を抱えてしまうケースも少なくありません。本記事では、不動産業界で15年以上の経験を持つ筆者が、サラリーマンでも無理なく始められる中古マンション投資の基礎から実践までを丁寧に解説します。読み終えるころには、物件選定の判断軸から2025年度の最新税制まで、押さえるべきポイントが体系的に理解できるはずです。
サラリーマンが中古マンションを選ぶ理由
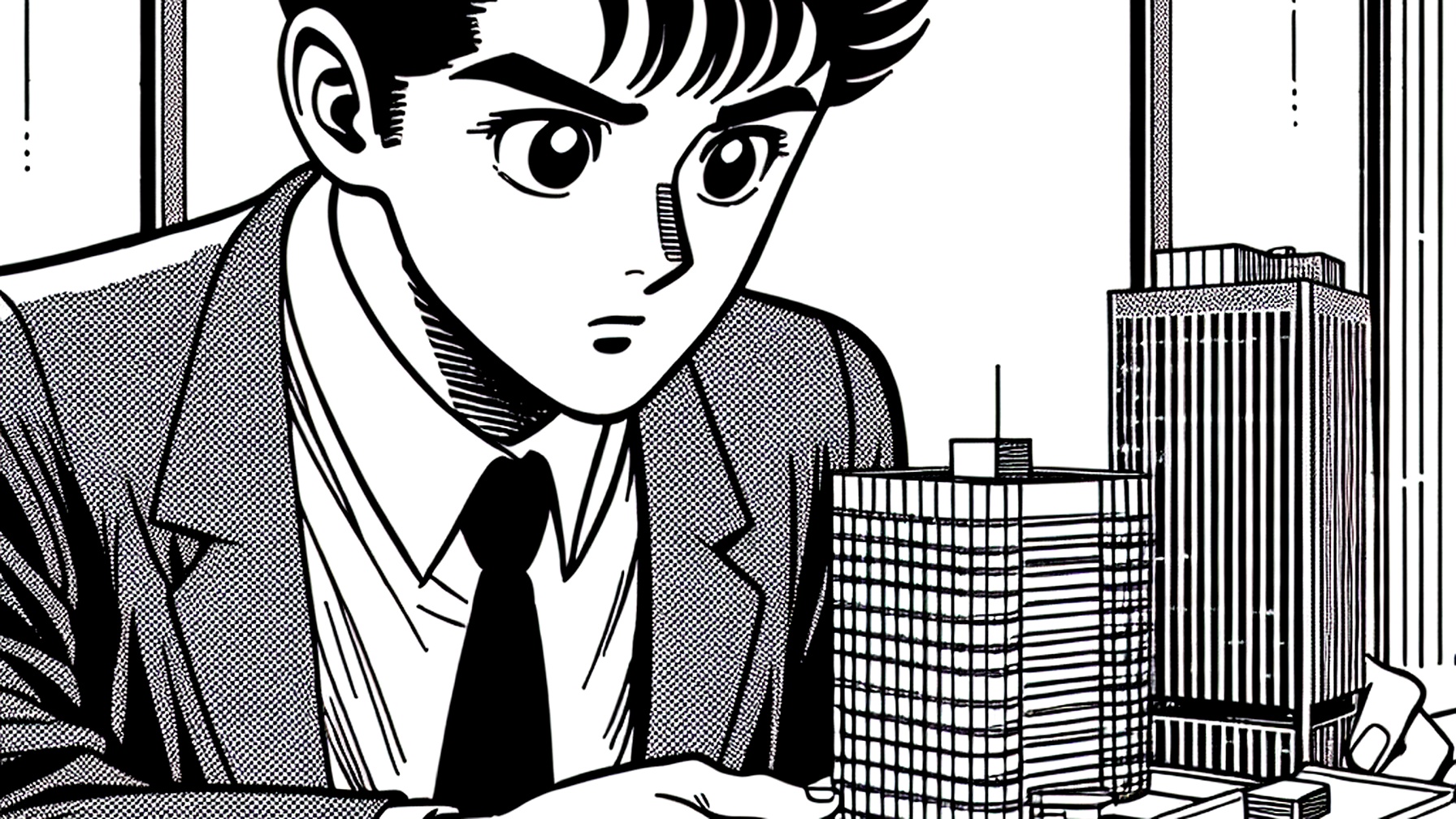
まず押さえておきたいのは、中古マンション投資とサラリーマンの相性の良さです。給与収入があることで金融機関の審査に通りやすく、毎月の返済計画も立てやすいからです。
重要なのは新築と比較した際の費用対効果です。2025年10月時点の新築マンション平均価格は東京23区で7,580万円ですが、不動産経済研究所のデータによると築15年前後の中古は同エリアで4,900万円前後に落ち着いています。つまり、家賃水準が大きく下がらないエリアなら、同じ賃料収入でも初期投資額を抑えられるため利回りが高くなります。
さらに、サラリーマンは時間の制約が大きい一方で安定したキャッシュフローを求めます。この点で分譲仕様の中古ワンルームやファミリータイプは管理組合が機能しており、大規模修繕の計画も明確です。専門知識が乏しくても管理会社に委託しやすく、手間を最小限に抑えられる利点があります。
一方で築年数が進むほど修繕リスクは増します。国土交通省の「マンション総合調査」では、築30年超の建物で計画修繕を行った割合が約80%に達する一方、資金不足を指摘する管理組合も15%存在します。こうした統計を踏まえ、修繕積立金の残高や長期修繕計画書を必ず確認しましょう。
キャッシュフローを安定させる資金計画
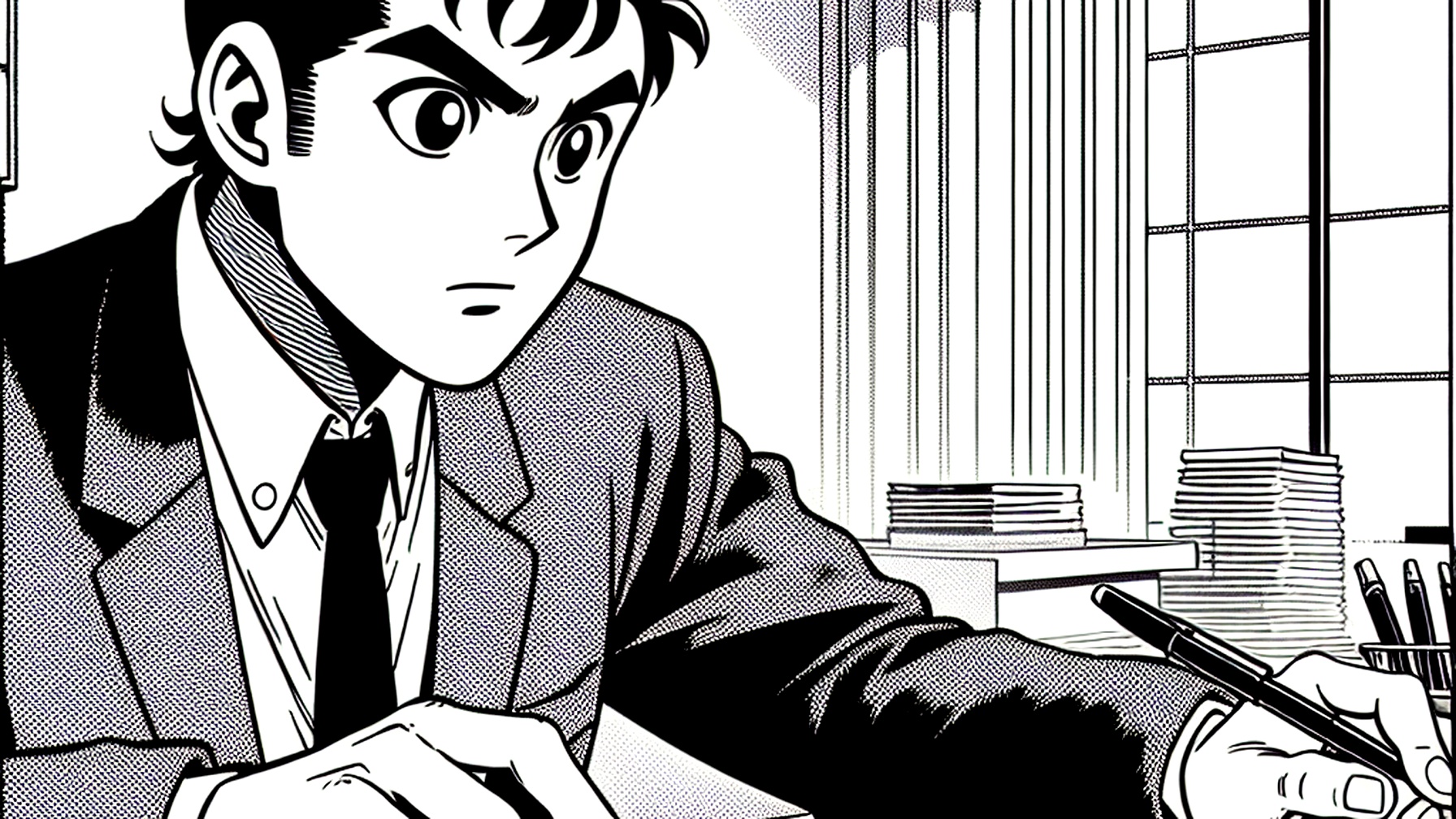
ポイントは、収入と支出を細部まで可視化し赤字月をゼロにすることです。家賃収入が安定していても想定外の出費が続けば投資の意義が薄れます。
まず自己資金として物件価格の20%を用意すると、金融機関からの信用が高まり金利交渉を有利に進められます。例えば3,000万円の中古マンションを金利1.8%、期間30年で借り入れた場合、月々の返済額は約10万7,000円です。家賃が13万円なら理論上の毎月キャッシュフローは2万3,000円ですが、空室率を10%、修繕費を家賃の10%とすると手残りは月8,000円まで下がります。このように保守的なシミュレーションが欠かせません。
また、2025年度の個人向け不動産投資ローンは変動金利が1.2〜2.0%で推移しています。日銀の政策修正を受け、金利は緩やかに上昇傾向にあるため、固定と変動のミックス融資でリスク分散を図る手法も有効です。金融機関ごとに融資姿勢が異なるので、同僚やネット情報だけで決めず、複数行に事前相談することが大切です。
さらに、突発的な修繕や賃借人の入れ替えに備えて運転資金を家賃の6カ月分は確保しておくと、心のゆとりが大きく違います。筆者の経験では運転資金の不足が原因で急いで高金利のカードローンを利用し、キャッシュフローを悪化させた事例が少なくありません。
物件選びで外せない三つの視点
実は、立地・管理・価格のバランスを見誤ると利回り試算は一瞬で崩れます。ここでは三つの視点を順に整理します。
まず立地です。東京都都市整備局の空室率データによると、駅徒歩10分圏内と15分圏外では平均空室率に約4ポイントの差が出ています。サラリーマン投資家は管理現場に頻繁に通えないため、流動性の高いエリアを選ぶことで退去時の再募集期間を短縮できます。
次に管理の質です。中古 マンション投資 サラリーマンという組み合わせでは、日々の管理をプロに委ねるケースが大半です。管理組合の議事録で滞納率が高い、理事長が長期間不在といった兆候がある物件は避けるべきです。管理状態は資産価値に直結し、融資審査でも重視されるからです。
最後が価格の妥当性です。相場より安い物件には必ず理由があります。国土交通省「不動産取引価格情報検索」で近隣事例を確認し、築年、階数、方角を揃えて比較しましょう。価格交渉では、水回り設備の更新年や大規模修繕の積立状況を根拠にすることで5%前後のディスカウントが現実的です。
2025年度の税制優遇を活用する方法
基本的に、賃貸用マンションは自宅と異なり住宅ローン控除の対象外ですが、経費計上と減価償却を駆使すれば手残りを増やせます。2025年度税制では、木造22年・RC造47年という法定耐用年数が据え置かれており、中古購入の場合は残存耐用年数を基準に償却できます。
ポイントは青色申告特別控除です。電子申告と複式簿記を採用すれば最大65万円を所得から控除でき、給与収入との損益通算によって所得税・住民税を圧縮できます。国税庁の試算例では、課税所得500万円の会社員が65万円控除を受けると約13万円の税負担が軽減されます。
また、所得税の超過累進税率は2025年度も最高45%で維持されています。高所得層ほど節税効果が大きいため、個人名義だけでなく法人設立を検討する動きも活発です。ただし設立コストと社会保険料の増加がデメリットになるため、年間家賃収入が1,000万円を超えるあたりが分岐点とされています。
なお、不動産取得税や登録免許税の軽減措置は居住用が中心で、投資用には適用外の場合が多い点に注意が必要です。最新の適用要件は必ず自治体の公式サイトで確認してください。
管理と出口戦略で投資を完結させる
重要なのは、購入した時点で出口を決めておくことです。賃貸経営は長期戦ですが、保有期間を見誤ると売却益も家賃収入も得られないまま老朽化リスクだけが残ります。
まず管理フェーズでは、サブリースを安易に選ばず、管理委託契約の内容を精査しましょう。管理手数料は家賃の3〜5%が相場ですが、入居者対応や家賃保証など業務範囲は会社によって異なります。筆者は安価な管理会社に乗り換えた直後、トラブル対応が遅れ空室期間が3カ月続いた経験があります。手数料の差額より機会損失が大きい典型例です。
一方で出口戦略としては、賃借人付きで売却する「オーナーチェンジ」、退去後にリフォームして売却する「実需販売」、そして物件を担保に新規融資を受ける「リファイナンス」の三択が現実的です。2025年現在、都心部の表面利回りは4〜5%で横ばいのため、築20年前後でも需要は底堅い状況が続いています。この局面で適切なバリューアップを施せば、購入価格の10%程度の売却益を狙うことも可能です。
加えて、相続を視野に入れるなら、賃貸用マンションは路線価評価が時価の7割程度に圧縮されるメリットがあります。資産継承を目的とする場合でも、キャッシュフローと管理の手間のバランスを忘れずに検討しましょう。
まとめ
サラリーマンが中古マンション投資で成果を上げるには、立地選定と資金計画を両輪で進め、2025年度の税制を味方につける視点が欠かせません。給与という安定収入を背景に、保守的なシミュレーションと運転資金の確保でキャッシュフローを守りつつ、管理と出口までを一気通貫で設計することが成功の鍵です。今日得た知識を基に、まずは自宅周辺の家賃相場や金融機関の融資条件を調べる一歩を踏み出しましょう。行動を起こすことで、将来の選択肢は確実に広がります。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 マンション総合調査 – https://www.mlit.go.jp
- 東京都都市整備局 賃貸住宅市場分析 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp
- 国税庁 タックスアンサー – https://www.nta.go.jp
- 総務省統計局 人口推計 – https://www.stat.go.jp

