不動産投資に慣れてくると、「もっと安定的にリターンを上積みできないか」と考える瞬間が増えます。とくにREIT(不動産投資信託)は株式より値動きが緩やかで、物件を直接持たなくても賃料収入に近いキャッシュフローが得られる仕組みです。しかし利回りの差は銘柄選定や運用方法によって意外なほど広がります。本記事では、REIT 利回り 経験者向けの視点で、2025年時点の最新データに基づきながら実践的な利回り向上策を解説します。読み終える頃には、ポートフォリオの見直し手順と税制活用のポイントがクリアになり、次の一手が具体的に描けるはずです。
いま改めてREITの利回りを測る意味
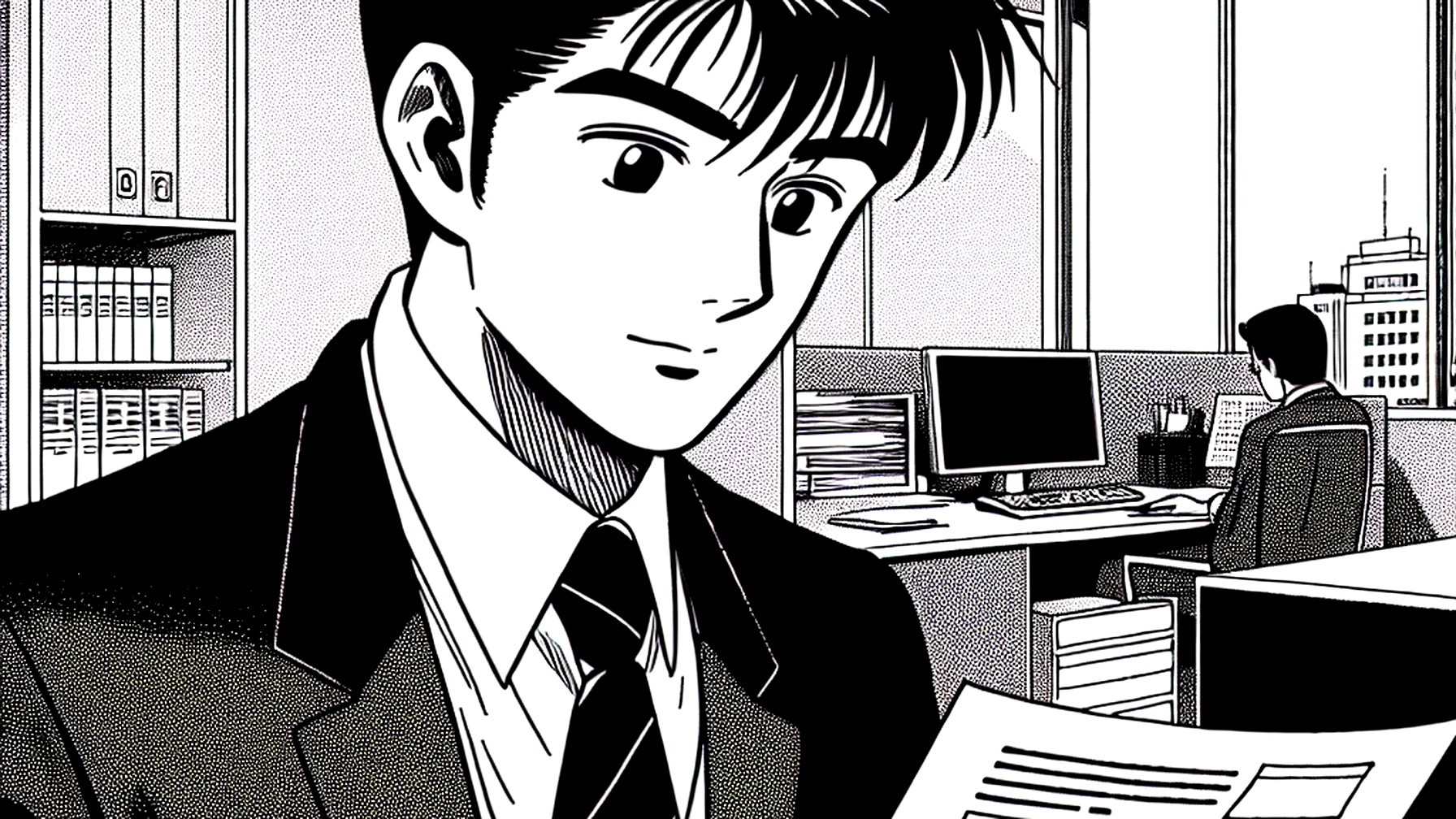
まず押さえておきたいのは、REITの利回りが「分配金利回り」と「総合利回り」の二つに分かれる点です。前者は年間分配金を基準価額で割った指標で、後者は値上がり益を含めた実質的な収益率を示します。2025年10月時点で東証REIT指数の平均分配金利回りは3.7%前後ですが、個別銘柄では2%台から6%台までばらつきがあります。
さらに、REITは内部留保が限られるため、物件売却益をどう分配するかによって将来の分配原資が変わります。つまり利回りだけでなく、運用会社の売却方針や開示姿勢も確認しなければ実情をつかめません。また、日本不動産研究所が公表する東京23区の表面利回り(ワンルーム4.2%など)が年々低下傾向にあるなか、REITは物件の組み合わせでリスクを分散しているという点も踏まえて比較する必要があります。
このように利回りを測る目的は、単に高い数字を追うことではなく、将来の安定性とリスク許容度を把握するための指標づくりにあります。経験者ほど数字だけでなく“中身”を点検する意識が欠かせません。
分配金利回りを押し上げる三つの視点
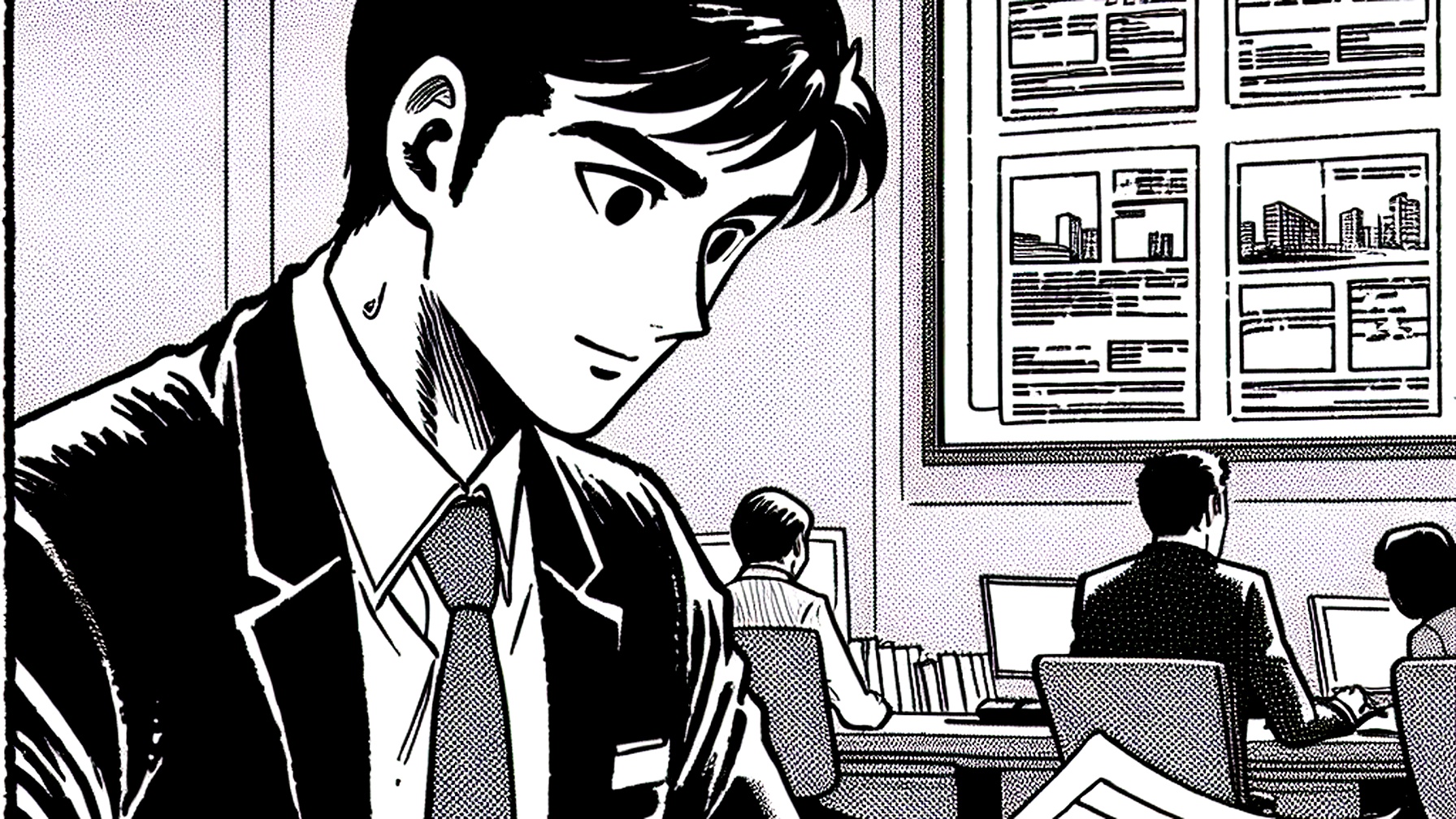
ポイントは「物件タイプ」「資本政策」「入替戦略」の三点を同時に見ることです。まず物件タイプでは、物流施設やデータセンター系REITの需要がなお旺盛で、稼働率が高水準を維持しています。例えば2025年上期の稼働率は平均98%台とオフィス系を2ポイント上回ります。この高稼働が分配金を押し上げる源泉になるため、使用用途の違いを意識して銘柄を選ぶだけでも利回り向上余地が生まれます。
次に資本政策です。REITは増資によって物件を取得しますが、一口当たり分配金を希薄化させるリスクがあります。そこでLTV(総資産に対する有利子負債比率)が55%以内で、かつ増資後のDPU(1口当たり分配金)がプラスになるシナリオを提示している銘柄を選ぶと、長期的な分配金成長を享受しやすくなります。
さらに入替戦略が見逃せません。成熟物件を売却して含み益を実現し、その資金で成長余地の高い新規物件へ乗り換える方針を持つ運用会社は、キャピタルゲインを分配金に充当しやすい傾向があります。実はこうしたアクティブな売却姿勢が、平均利回りを1%以上押し上げる事例も珍しくありません。経験者ならポートフォリオの回転率と売却益の分配方針をIR資料で必ず確認しておきましょう。
ポートフォリオ再編の実務ステップ
重要なのは、売却タイミングと買付タイミングを機械的に合わせることではなく、キャッシュポジションを確保しつつ分配金のブレを抑える計画性です。まず既存銘柄をリスト化し、利回り低下の要因が外部環境にあるのか運用会社固有の問題なのかを切り分けます。その上で、想定DPUが下方修正された銘柄を段階的に縮小し、高成長セクターのREITへ振り替える方法が基本となります。
例えば、オフィス系REITを売却して物流系へ移行する場合、権利落ち日直後に売却すると分配金を受け取った上で価格下落リスクを抑えやすいというテクニックがあります。反対に購入は権利付き最終日から配当基準日の間で押し目が出やすい局面を狙うと平均取得単価を引き下げられます。ここで分配金ギャップが生じても、キャッシュリザーブを半年分用意しておけばポートフォリオ全体の利回りが急低下する事態を防げます。
また、貸借取引を利用してヘッジを掛ける方法もありますが、貸借料や逆日歩が発生すると収益を大きく削る場合があります。したがってヘッジコストと期待利回りの差額が1%未満になる局面では、現物のみで時間分散を図る方が結果的に効率的です。
2025年度の税制と費用最適化
まず押さえておきたいのは、REIT分配金が「配当所得」として課税され、所得税と住民税を合わせた20.315%が源泉徴収される点です。2025年度もこの税率に大きな変更はありませんが、特定口座(源泉徴収あり)を利用すると確定申告不要で課税が完了します。ただし外国税額控除の適用を受けたい場合や損益通算したい場合は申告が必要です。
NISA(新しいNISA)は年間360万円までの投資上限があり、成長投資枠でREITを購入すれば分配金と売却益が非課税になります。期限は恒久化されているため、長期的な非課税メリットを活かせる点が魅力です。一方でJ-REITは投資法人税が実質0%に近い仕組みを採用しているため、法人本体の税負担は軽く、その分配金が投資家に直接届きます。つまり投資家側の課税を抑える制度を併用することで、トータル利回りが実質1.3倍程度まで拡大するケースもあります。
経費面では、信用取引の金利や貸株料を計上することで課税所得を圧縮できます。ただし私的な交通費や通信費を按分する場合、税務署は合理的な計算根拠を求めるため領収書の保存が必須です。経験者であっても「なんとなく」で按分すると否認リスクが高まる点には注意が必要です。
プロ投資家が注目する市場指標の読み方
実は利回りの先行指標として、NAV倍率(純資産価値倍率)とFFO利回り(運用キャッシュフロー利回り)が広く使われています。NAV倍率が1倍以下のREITは市場価格が純資産を下回っており、理論上割安と判断されます。しかしFFO利回りが低い場合、キャッシュフローが細い可能性があるため単純な割安判断は危険です。
また、JGB10年物国債利回りとの差も見逃せません。2025年10月時点で長期金利は1.1%台、REIT平均分配金利回りは3.7%なのでスプレッドは約2.6%です。この幅が2%を切ると海外勢の資金流入が鈍り、価格調整圧力が高まる傾向があります。逆に3%以上に拡大すると買い需要が増えやすく、分配金利回りは低下するものの総合リターンが伸びる場面が多いと覚えておくと売買判断がスムーズになります。
最後に、東証が公表する日次の「投資部門別売買動向」を参照すれば、海外投資家の売買が一目でわかります。直近4週で海外勢が純買いに転じている銘柄は、短期的な押し目でも下値が硬いという経験則が働くため、利回り向上とキャピタルゲインの両取りを狙いやすいでしょう。
まとめ
ここまで、REIT 利回り 経験者向けの視点で利回りを底上げする方法を解説しました。重要なのは、単純に高い数字を追うのではなく、物件タイプや資本政策、税制メリットまで含めて総合的に判断することです。ポートフォリオを定期的に棚卸しし、分配金の下支えを見極めつつリスクを抑える工夫を続ければ、年間利回りを1〜2ポイント上乗せすることも十分に可能です。今日得た知識をもとに、自身の投資方針と市場環境を照合し、最適な再編計画を立ててみてください。
参考文献・出典
- 日本取引所グループ – https://www.jpx.co.jp
- 日本不動産研究所「不動研住宅価格指数 2025年版」 – https://www.reinet.or.jp
- 財務省「国債金利情報 2025年10月」 – https://www.mof.go.jp
- 金融庁「新しいNISA制度の概要(2025年度)」 – https://www.fsa.go.jp
- 東証REIT指数データベース – https://www.j-reit.jp

