空室が続くと家賃収入は一気に減り、ローン返済や修繕費の支払いに頭を抱える人は少なくありません。実際、国土交通省の統計によれば2025年8月の全国アパート空室率は21.2%で、いまだ高止まりの状況です。だからこそ、アパート経営では購入前の立地選定が成果を大きく左右します。本記事では、「アパート経営 おすすめ 立地選定」の観点から、人口動態や駅距離、周辺施設などの具体的なチェックポイントを順番に解説します。読み終えるころには、自分に合ったエリアを数字と現場感の両面から判断できる視点が身につくはずです。
需要を見極める人口動態の読み方
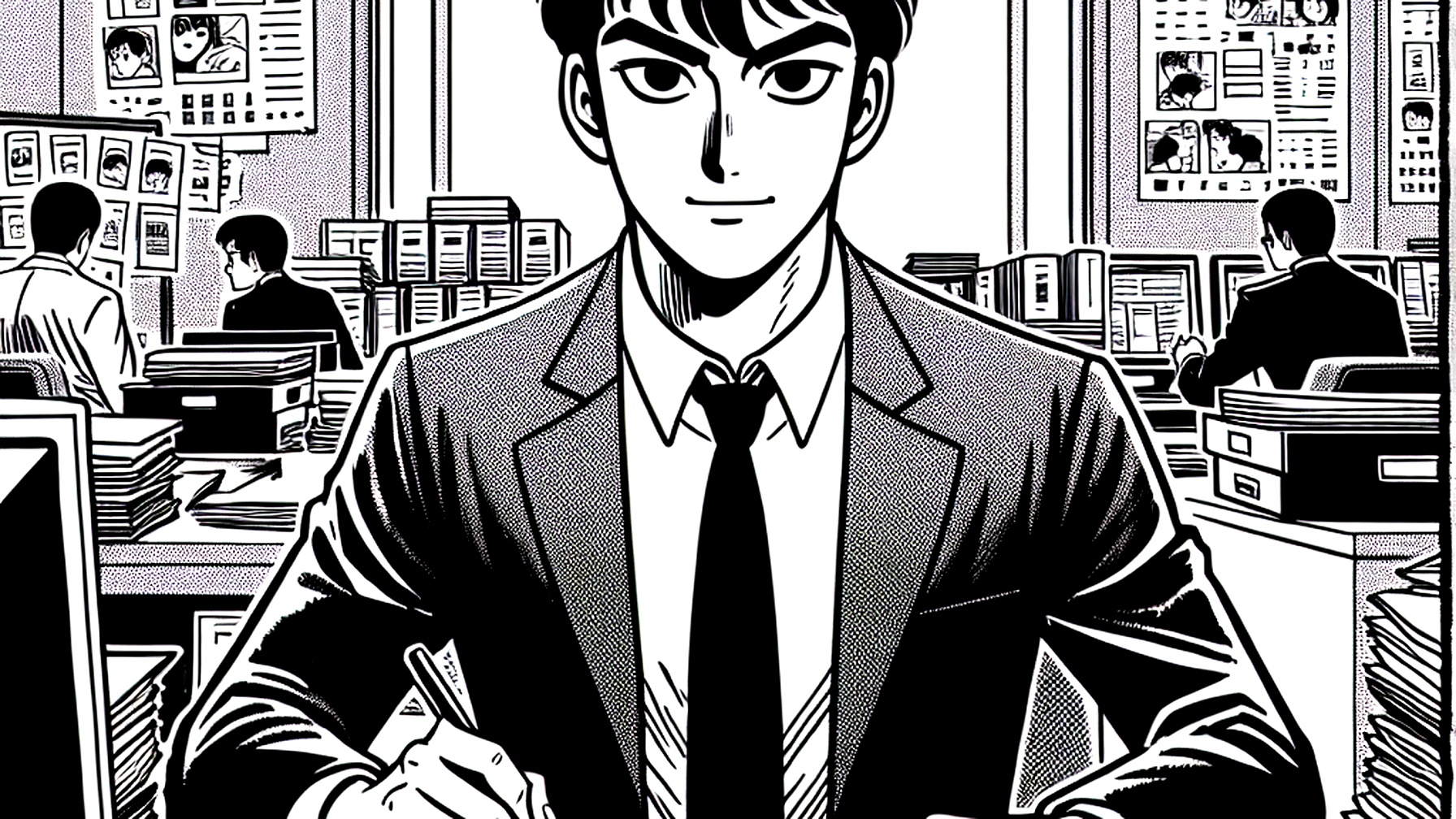
まず押さえておきたいのは、需要が長期的に維持されるエリアかどうかです。人口増減だけでなく、年齢構成や世帯構成の推移を確認すると、将来の空室リスクを抑えられます。
総務省「住民基本台帳人口移動報告」では、同じ人口増地域でも単身世帯が伸びている市区とファミリー世帯が伸びている市区で傾向が大きく異なると示されています。単身世帯が増えるエリアなら、20㎡前後のワンルームを中心にプランを組むと収益効率が高まります。一方でファミリー層が伸びる郊外では、40〜50㎡の2DKや2LDKが選ばれやすいという具合です。
また、国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口を確認すると、駅周辺でも高齢化が進む自治体があります。その場合、階段しかない古い物件は敬遠されがちです。エレベーター付きやバリアフリー対応の新築・改修を計画すると、競合との差別化につながります。
駅距離と生活利便施設
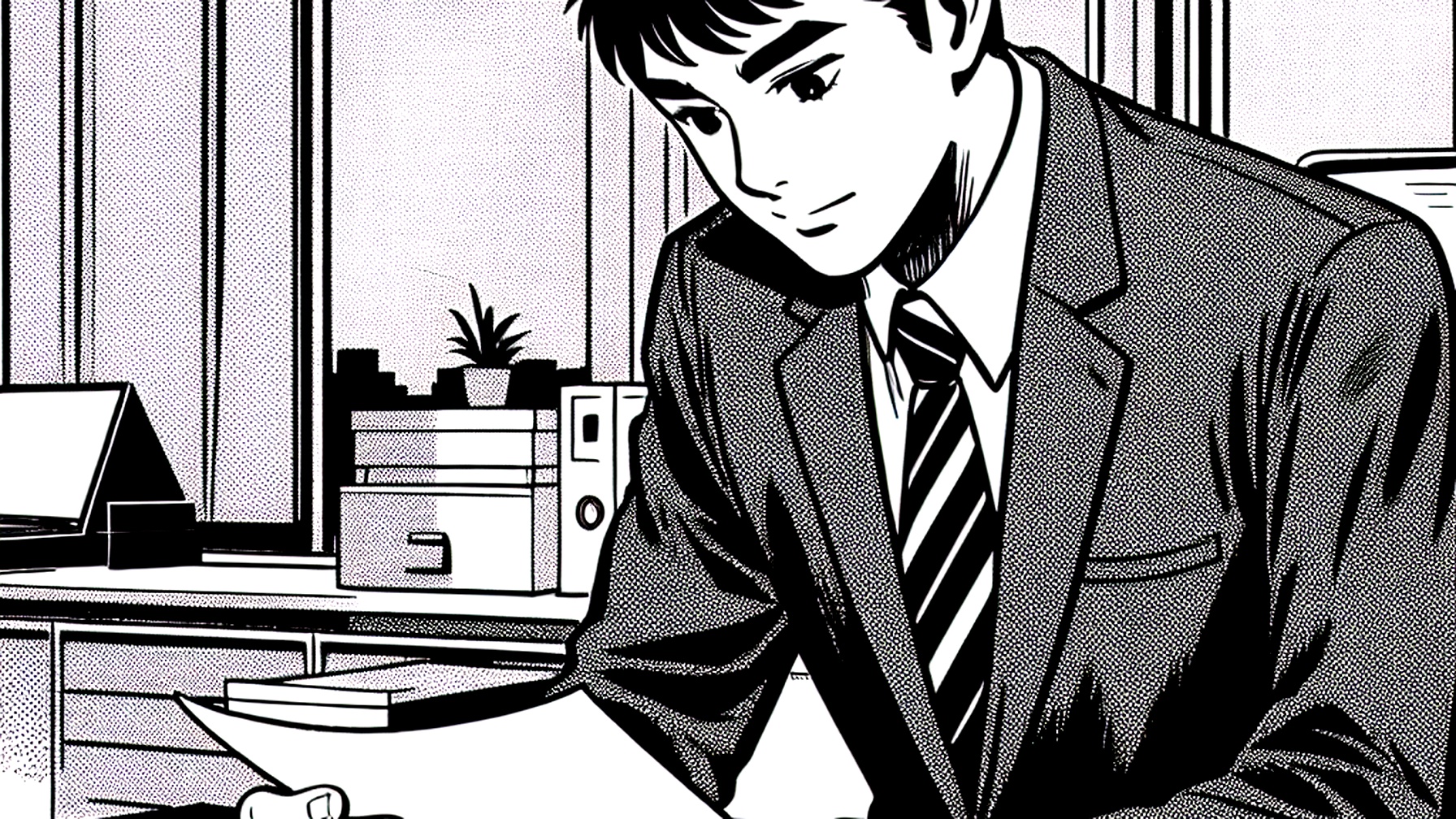
ポイントは、駅距離と生活利便施設をセットで考えることです。徒歩圏が少し長くても、スーパーやドラッグストアが近ければ入居率は保たれます。
国土交通省「都市計画基礎調査」では、駅徒歩10分圏内の家賃は同5分圏内より平均8%高い傾向が続いています。しかし、駅から12分でも24時間スーパーが隣接するエリアでは、空室率が5%程度低い事例がありました。つまり、駅近のプレミアムだけでなく、生活利便性を横並びで比較する視点が欠かせません。
さらに、新線や再開発の予定がある場合は、完成後の交通網改善を織り込むとキャピタルゲイン(資産価値の上昇)を期待できます。地方都市でもLRT(次世代型路面電車)の開業予定地では、家賃相場が事前に上向くデータが見られます。将来計画を市役所の都市計画課で確認し、時差を狙った投資ができるか検討しましょう。
大学・工業団地周辺の可能性
実は、地方都市で安定した賃貸需要を生むのが大学と工業団地です。キャンパス移転や企業進出は短期間で賃貸ニーズを押し上げるケースが多く見られます。
文部科学省の資料によると、2020年代後半に地方大学が都心回帰する動きは落ち着き、2025年度は地方キャンパスの設備更新が中心です。そのため、既存キャンパス近くで築20〜30年の木造アパートを取得し、Wi-Fiや宅配ボックスを追加するだけで、家賃を1割程度底上げできる事例があります。
一方、経済産業省の「地域未来投資促進法」支援を受ける工業団地では、期間社員向けの短期賃貸が伸びています。家具家電付きで入居期間を1カ月単位に設定すると、表面利回りが2〜3ポイント上昇することも珍しくありません。大学周辺と工業団地周辺では、同じ単身需要でも入居期間が異なるため、賃貸借契約の形態を柔軟に組み立てると収益が安定します。
災害リスクと行政のサポート
重要なのは、ハザードマップでリスクを確認し、行政のサポート制度を活用することです。災害に強い物件は保険料が下がり、入居者の安心感も高まります。
国交省の「重ねるハザードマップ」で浸水想定区域を確認し、想定水位が3m以上の地域は避けるか、高床式の新築計画を検討することが望まれます。また、耐震補強や省エネ改修に対しては「2025年度 住宅省エネキャンペーン」で補助率が最大1/2になるメニューが継続中です(戸当たり上限250万円、申請期限は2026年3月末予定)。この補助を利用し、古いRC造の空室フロアを断熱改修したオーナーは、改修後の家賃を平均12%アップさせながら実質負担を抑えました。
さらに、自治体が発行する「防災ガイドブック」を入居者に配布し、入居前の説明時に避難経路まで案内すると、クレーム減少と口コミ向上の効果が期待できます。物件そのものだけでなく、災害対応も含めて付加価値を高める視点が求められます。
ファンを生む地域コミュニティ戦略
まず、入居者が地域に愛着を持つ仕組みを整えると、長期入居につながります。コミュニティ形成は広告費削減とリピート率向上の両面で効果的です。
例えば、地方鉄道沿線の築浅アパートで、月1回のマルシェを敷地内で開催し、近隣農家と連携した事例があります。参加費は無料でも、入居者同士の交流が進み、平均入居期間が3.2年から4.8年へと延びました。結果として、広告料や仲介手数料が年30万円以上削減でき、キャッシュフローが改善しています。
最近は管理アプリを通じてゴミ出し当番やイベント情報を共有する物件も増えました。ICTを活用して入居者の声を拾い上げ、Wi-Fi速度の改善や宅配ボックス増設など小さな要望を迅速に反映すると、SNSでの好意的な口コミが増え、紹介入居の比率が高まります。地域コミュニティへの投資は表面化しにくいものの、長期運営を安定させる重要なピースです。
まとめ
ここまで、人口動態、駅距離と利便施設、大学・工業団地、災害リスク、コミュニティ戦略の五つの観点でアパートの立地選定を解説しました。結論として、数字と現場感を行き来しながら、多面的にリスクとリターンを測る姿勢が成功への近道です。まずは市区町村の統計とハザードマップを確認し、現地の昼夜の雰囲気を自身の足で確かめてみてください。行動を起こすことで、将来のキャッシュフローと安心感の両方を手に入れられるでしょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 – https://www.soumu.go.jp
- 国立社会保障・人口問題研究所 将来推計人口 – https://www.ipss.go.jp
- 経済産業省 地域未来投資促進法関連資料 – https://www.meti.go.jp
- 文部科学省 大学等の設置状況データ – https://www.mext.go.jp

