不動産投資に興味はあるものの、「減価償却は難しい」と感じていませんか。私も15年前は同じ悩みを抱え、数字を見るたびに頭が痛くなりました。しかし、適切に減価償却を活用すれば、手元のキャッシュフローは大きく改善します。本記事では、実際の体験談 不動産投資 減価償却の事例を交えながら、2025年10月時点で有効な税制の範囲でわかりやすく解説します。読み終える頃には、減価償却を味方にして投資戦略を立てるコツが身につくはずです。
減価償却の基本とキャッシュフローの関係
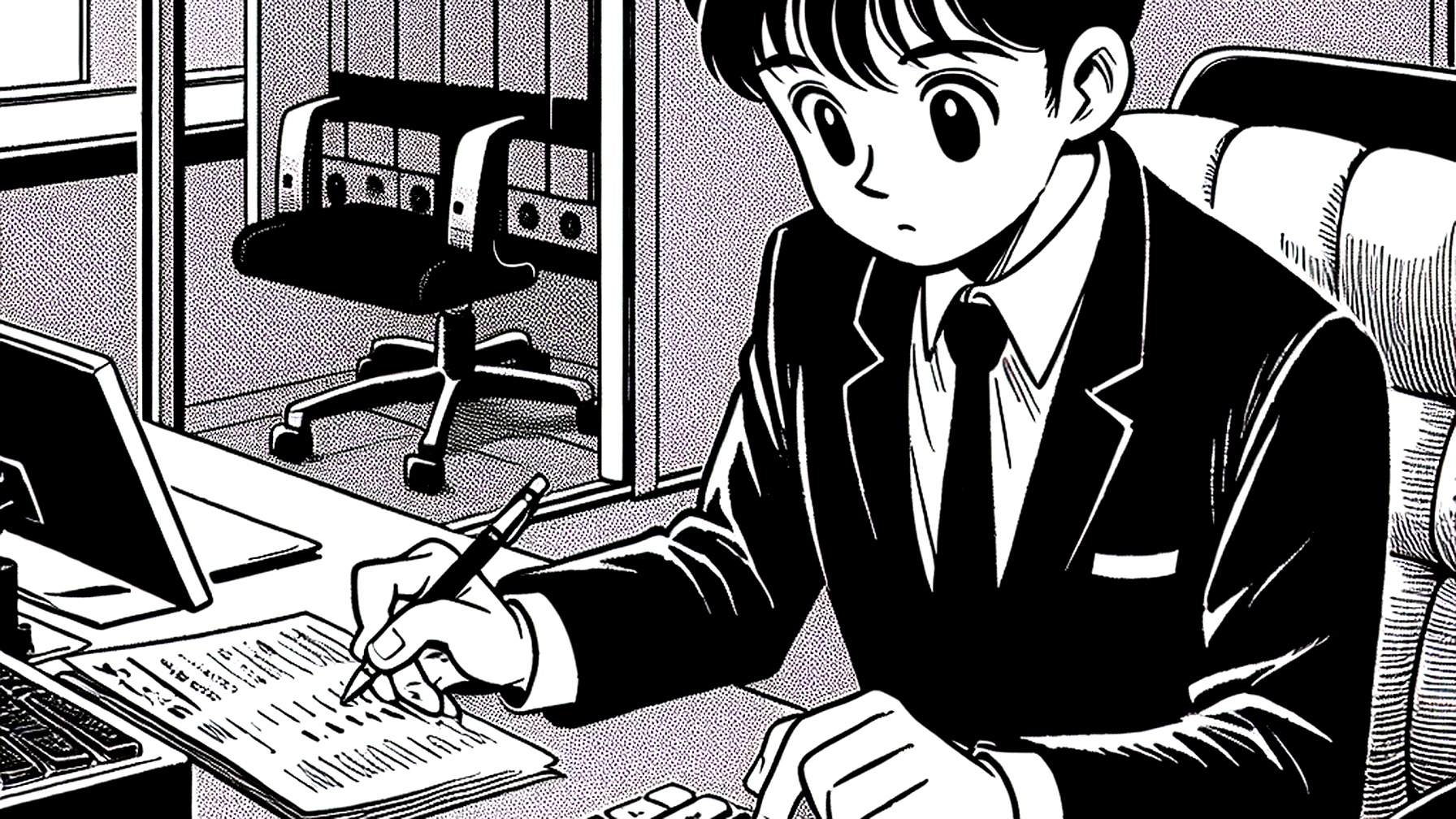
まず押さえておきたいのは、減価償却が「帳簿上の経費」である点です。建物や設備は時間とともに価値が目減りします。その価値の目減り分を毎年経費計上するのが減価償却で、現金支出を伴わないため節税効果が高いのが特徴です。
国税庁の2025年度耐用年数表によると、木造住宅は22年、鉄筋コンクリート造は47年が基本とされています。つまり、同じ価格の物件でも構造により年間の償却額が大きく異なるわけです。減価償却によって課税所得が抑えられれば、手元に残るキャッシュが増え、繰り上げ返済や次の物件への再投資余力が生まれます。
一方で、減価償却が進むと帳簿上の建物価値は下がります。そのため、売却時の譲渡所得が増える可能性もあるので、取得時だけでなく出口戦略まで含めたシミュレーションが欠かせません。
中古木造アパートを活用した加速償却の体験談

重要なのは「築年数」が短縮償却に直結する点です。私は築20年の木造アパート(価格3,000万円、土地1,200万円、建物1,800万円)を2022年に購入しました。中古資産の耐用年数は「残存耐用年数×0.2+築年数」で算出でき、最低でも2年と定められています。今回のケースでは22年−20年=2年、2年×0.2=0.4年ですが、最低2年ルールが優先されました。
結果として1,800万円を2年で償却することになり、年間900万円を経費計上できました。表面利回り10%でも家賃収入は年間300万円程度です。しかし、減価償却を加味すると2年間はほぼ無税となり、返済後も200万円弱のキャッシュが手元に残りました。
とはいえ、加速償却が終わる3年目以降は税負担が急増します。そのため購入当初から融資の繰り上げ返済を進め、キャッシュフローの急減に備えました。加速償却を狙うなら、短期で元本を減らす計画が不可欠だと痛感しました。
区分RCマンションで安定償却を得た事例
一方で、長期安定型の減価償却を選んだ例もあります。2024年に購入した築15年の鉄筋コンクリート区分マンション(価格2,400万円、土地600万円、建物1,800万円)は、残存耐用年数47年−15年=32年となりました。中古RCの短縮計算では32年×0.2+15年=21.4年、端数切り捨てで21年が耐用年数です。
年間の減価償却費は1,800万円÷21年≒85万円となり、所得を緩やかに圧縮します。賃料収入は年間140万円、ローン返済は元利均等で90万円です。減価償却と管理費を差し引くと、課税所得はゼロ近くに抑えられました。
このケースではキャッシュが毎年30万円程度残り、将来の大規模修繕積立にも回せます。短期的な節税効果は小さいものの、長期で安定した収支が確保できる点が魅力でした。出口を10年以上先に想定している投資家には相性が良いと感じます。
減価償却を最大化するための実務ポイント
ポイントは「土地と建物の按分」です。固定資産税評価額をそのまま用いると、都市部では土地割合が高くなり、償却できる建物の価値が減る傾向があります。私は鑑定評価を取得し、建物割合を高めることで年間償却費を約15%増やしました。鑑定費用は10万円ほどかかりましたが、税負担の軽減効果は初年度で回収できました。
また、設備と建物を分離して計上すると、設備部分は最短6年で償却できます。2025年度税制でもこの区分は有効で、エアコンや給湯器などを取得価格から明確に抜き出すことで、追加の節税余地が生まれます。ただし、過度な按分は税務調査で否認リスクがあるため、根拠資料の保存が欠かせません。
さらに、青色申告特別控除や家族への給与支払いによる所得分散も組み合わせれば、手残りキャッシュは一段と増えます。減価償却と他の税制を立体的に使うことこそ、資金効率を高める鍵になります。
2025年度税制と将来への備え
実は、2025年度の所得税法では、個人の不動産所得にかかる減価償却ルールに大きな変更はありません。ただし、国税庁は中古資産の耐用年数計算について、根拠書類の提示をこれまで以上に求める方針を示しています。また、赤字の損益通算を利用した節税スキームへの監視も強化されています。
一方で、住宅省エネ改修に伴う特別償却制度は2025年度も継続される予定です。省エネ性能を一定基準まで高めた場合、建物価格の10%を追加で一括償却できるため、長期保有を前提とする投資家にとって魅力的です。期限は2026年3月31日取得分までなので、活用するなら早めの計画が必要です。
将来の税制改正リスクに備えるには、長期的なキャッシュフロー表を毎年更新し、金利上昇や空室率悪化も織り込んだシナリオ分析を行うと安心です。不透明な時代こそ、数字に裏打ちされたプランニングが投資家を守ってくれます。
まとめ
減価償却を正しく理解すれば、不動産投資は想像以上にキャッシュが残ります。体験談 不動産投資 減価償却の事例が示すように、築年数や構造で節税インパクトは大きく変わります。大切なのは、短期の税メリットだけでなく、出口戦略と修繕計画を含めて長期視点で判断することです。今日学んだポイントを自分のシミュレーションに落とし込み、次の物件選びに役立ててください。数字に強くなるほど、投資の自由度は広がります。
参考文献・出典
- 国税庁 – https://www.nta.go.jp
- 国土交通省 住宅局 – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku
- 財務省 – https://www.mof.go.jp
- 総務省統計局 – https://www.stat.go.jp
- 日本銀行 – https://www.boj.or.jp

