家賃収入で将来の安心を得たいと思いつつ、「何を基準に物件を選べば失敗しないのか」と悩む人は多いものです。実は、物件選びを誤ると高い利回りどころか赤字に転落するケースも珍しくありません。本記事では不動産投資の第一歩となる物件選びに焦点を当て、メリットとデメリットを整理しながら、初心者でも実践できる判断軸を紹介します。読み終えたとき、立地や物件タイプの違いが収益にどう影響するかを具体的にイメージできるはずです。
なぜ物件選びが投資の成否を左右するのか
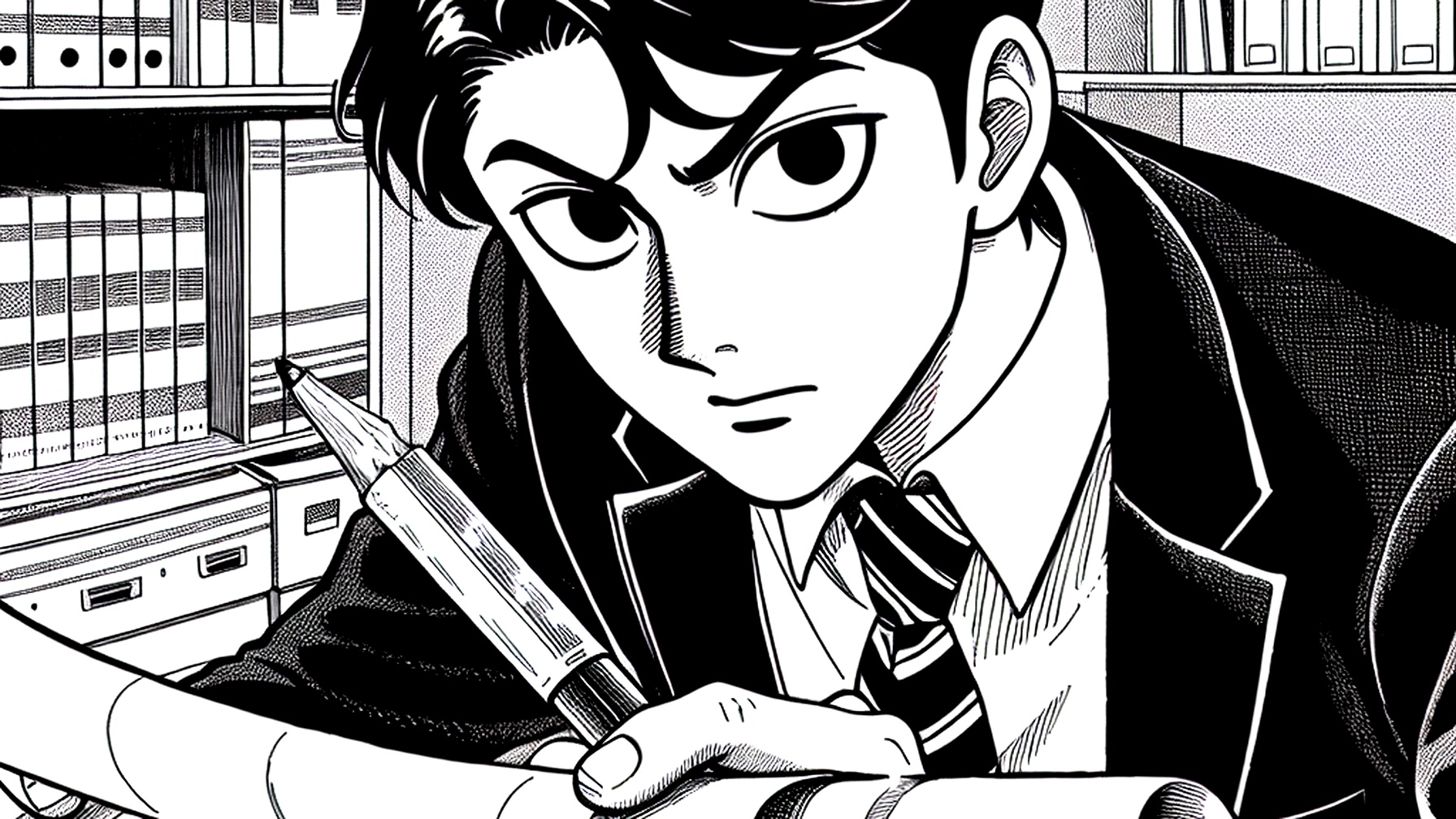
重要なのは、物件選びがキャッシュフロー(手元に残る現金)の八割を決めると言われるほど影響力が大きい点です。不動産投資は入居者が安定して住み続けることで収益が積み上がります。空室が続けばローン返済や固定資産税が重荷となり、最終的に持ち出しが増える結果になりかねません。
まず押さえておきたいのは、物件そのものの魅力と周辺需要のバランスです。国土交通省の「住宅市場動向調査2024」によると、入居者が重視する項目の上位は「通勤利便性」と「生活利便施設の充実」でした。つまり、設備が整っていても通勤に不便な立地では長期入居につながりにくいということです。
一方で、立地が良くてもメンテナンスが不足し、共用部が劣化している物件は入居者の満足度を下げます。資産価値が下落しやすく、出口戦略(売却)でも不利になる恐れがあります。したがって、立地の魅力度と建物の管理状態の両方を俯瞰し、総合的な視点で評価することが大切です。
立地判断の基本と最新トレンド
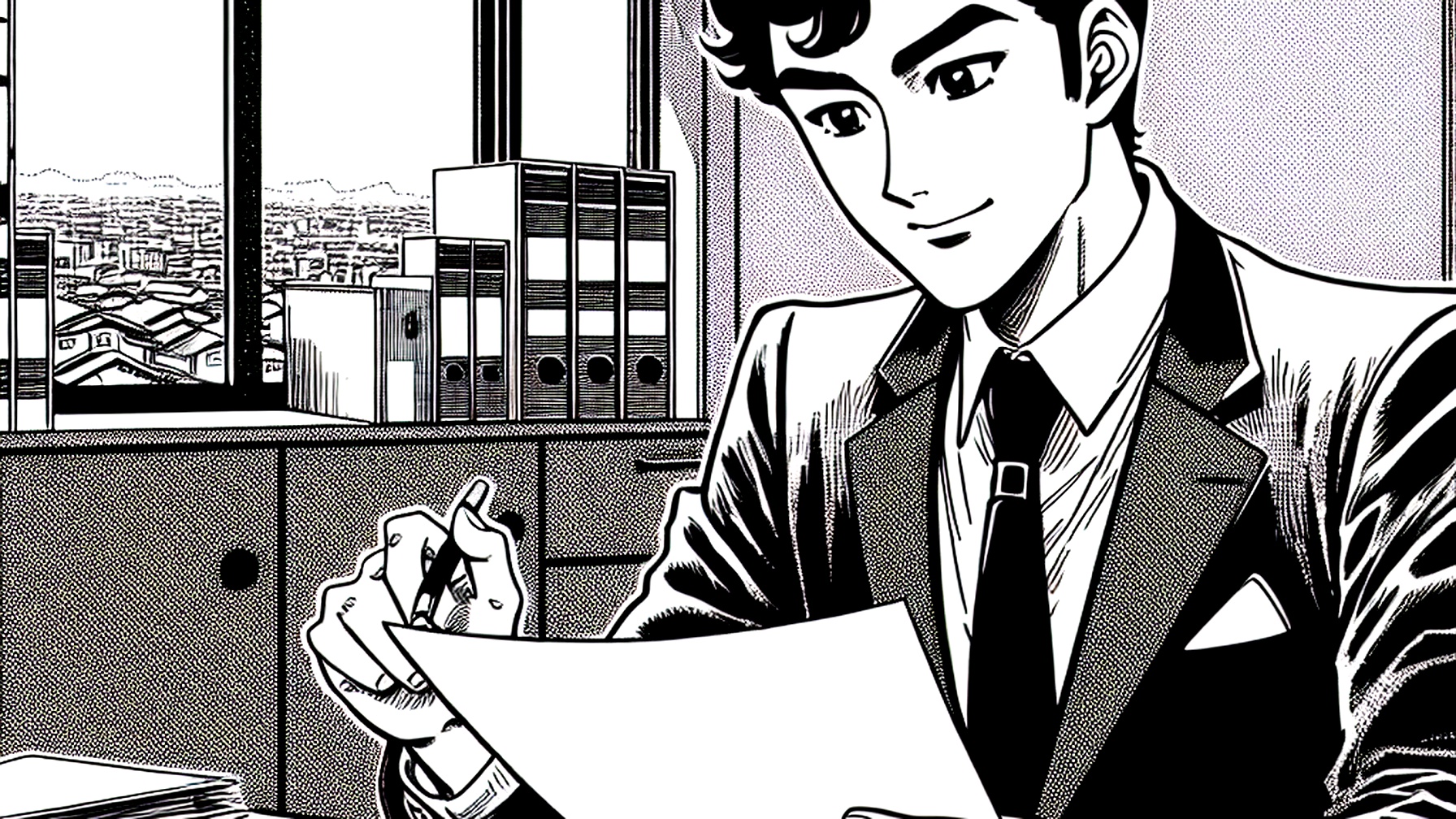
ポイントは、人口動態と交通インフラの二軸で将来性を見極めることです。総務省「住民基本台帳人口移動報告2025年版」では、都心三区と政令指定都市の中心部に人口流入が続く一方、郊外ベッドタウンの一部で転出超過が拡大しています。数字で見ると、東京23区への転入超過は前年比6.2%増で、特に単身世帯の流入が顕著です。
まず、駅から徒歩10分圏内は古くから空室リスクが低いとされています。ただし、2023年の相鉄・東急直通線開業のように新線が開業すると、従来は敬遠されていたエリアでも需要が急増する場合があります。最新の都市計画や再開発情報をチェックし、将来の交通利便性向上を予測する視点が求められます。
一方で、テレワーク普及による郊外回帰も無視できません。国交省「住宅着工統計」では2024年以降、郊外の戸建て着工戸数が前年比4.1%増となりました。郊外型ファミリー物件は家賃下落が緩やかで長期入居が多いというメリットがあります。しかし、人口減少局面では地域ごとの需給バランスが二極化する恐れがあるため、行政の人口ビジョンや再開発計画を確認する習慣をつけると安心です。
物件タイプ別メリットとデメリット
実は、同じ立地でもマンションとアパート、築浅と築古で収益構造が大きく異なります。ここでは代表的な物件タイプを取り上げ、それぞれのメリット・デメリットを整理します。
まず区分マンション(1室単位で所有)は少額から始められ、管理は管理組合に任せられるため手間が少ないという利点があります。デメリットは管理費と修繕積立金が定期的に発生し、表面利回りが下がりやすい点です。築20年超でも都心駅近であれば賃料下落が緩やかな反面、内装リフォームを定期的に行わないと競争力を保てません。
次に木造アパート一棟投資は、土地と建物を同時に保有するため売却時に土地値が下支えになりやすい特徴があります。ローン控除が使える場合もあり、2025年度の「投資用住宅ローン金利優遇制度」は固定1.5%台が主流です。ただし、木造は法定耐用年数22年と短く、金融機関の融資期間が制限されることで月々の返済負担が重くなるリスクがあります。
最後にRC造(鉄筋コンクリート)マンション一棟は、耐久性と遮音性に優れ、総戸数が多ければ空室損失を分散できます。日本政策金融公庫のデータによると、RC造の平均空室率は木造より1.8ポイント低い結果となっています。反面、建築コストが高く、取得価格が大きく膨らむため自己資金比率を高めに設定しないとキャッシュフローが圧迫されやすい点に注意が必要です。
収益シミュレーションで見るリスク管理
まず押さえておきたいのは、想定家賃と実質利回りのギャップを小さくすることです。金融機関に提出する事業計画書では、空室率を5%程度で作成するケースが多いものの、実務では10~15%の空室を見込んでおく方が安全です。家賃6万円、10戸、満室時年収720万円のアパートを例にすると、12%の空室(1.2戸分)を加味すると年収は634万円に下がります。
さらに、修繕費と管理費も忘れがちです。国交省「民間賃貸住宅の維持管理実態調査」では、年間家賃収入の平均15%が維持管理費に充当されています。つまり先ほどの物件なら約95万円が純収入から差し引かれる計算です。このように、空室・維持管理費・金利上昇を同時に組み込んだシミュレーションを行えば、ストレスシナリオに耐えられるかを定量的に確認できます。
また、出口戦略として売却益を期待する場合は、購入時に利回りと同時に流動性をチェックすることが不可欠です。レインズ(不動産流通機構)の2025年9月レポートでは、駅徒歩5分以内の区分マンションの平均成約期間は57日ですが、徒歩15分超では84日に延びています。将来売る可能性があるなら、短期で現金化できる立地を優先した方がリスクを抑えられます。
2025年の制度を踏まえたチェックポイント
ポイントは、現行制度を味方につけて収益と安全性を高めることです。まず、2025年度も住宅ローン減税は投資用には適用されませんが、自己居住用区分を併用するケースでは13年間の控除が継続します。副次的に、金融機関は自己居住部分を含む物件に対して金利を下げる傾向があり、平均0.3%ほど低い金利が提示される例があります。
一方で、賃貸住宅の省エネ性能表示が2025年4月から努力義務化されました。省エネ基準に適合すると入居者募集で優位に立てるうえ、東京都では同年7月から省エネ適合住宅の登録費用を5万円補助する制度が始まっています(現時点で2026年3月までの予定)。つまり、断熱改修や高効率設備を導入しておくことで、空室率低下と補助金の双方を享受できる可能性があります。
また、固定資産税の負担調整措置として、小規模住宅用地の税額が本来の6分の1に軽減される特例は2025年度も継続しています。土地面積200平方メートル以下の部分が対象となるため、都心の小規模アパートや区分マンション敷地権では恩恵を受けやすいです。購入前に土地の規模と分筆状況を確認することで、長期のランニングコストを計算しやすくなります。
まとめ
投資家が最初に直面する「不動産投資 物件選び メリット デメリット」というテーマは、収益の柱であるキャッシュフローと資産価値を同時に左右します。立地の将来性、物件タイプの特徴、そして2025年時点で利用できる制度を総合的に比較することで、リスクを限定しながら安定収入を狙えます。結論として、シミュレーションと現地確認を怠らず、人口動態と制度の変化を定期的にアップデートする姿勢が成功への近道です。まずは気になるエリアを歩き、具体的な数字を当てはめた計画書を作成するところから始めてみましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅市場動向調査2024 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告2025年版 – https://www.soumu.go.jp
- 国土交通省 住宅着工統計 – https://www.mlit.go.jp
- 日本政策金融公庫 2024年度住宅関連調査 – https://www.jfc.go.jp
- 不動産流通機構(レインズ)2025年9月成約動向 – https://www.reins.or.jp

