不動産投資に興味はあるものの、「本当に儲かるのか」「損をしたらどうしよう」と不安を抱える人は多いでしょう。私自身も15年前、初めて区分マンションを購入する際に同じ悩みを抱えました。本記事では、不動産投資の感想を率直に語りつつ、見落とされがちなデメリットを具体例とともに解説します。読むことで、リスクを可視化し、適切な対策を立てるヒントが得られます。これから物件を探し始める初心者でも理解できるよう、専門用語は丁寧に説明するので安心してください。
なぜデメリットに目を向ける必要があるのか
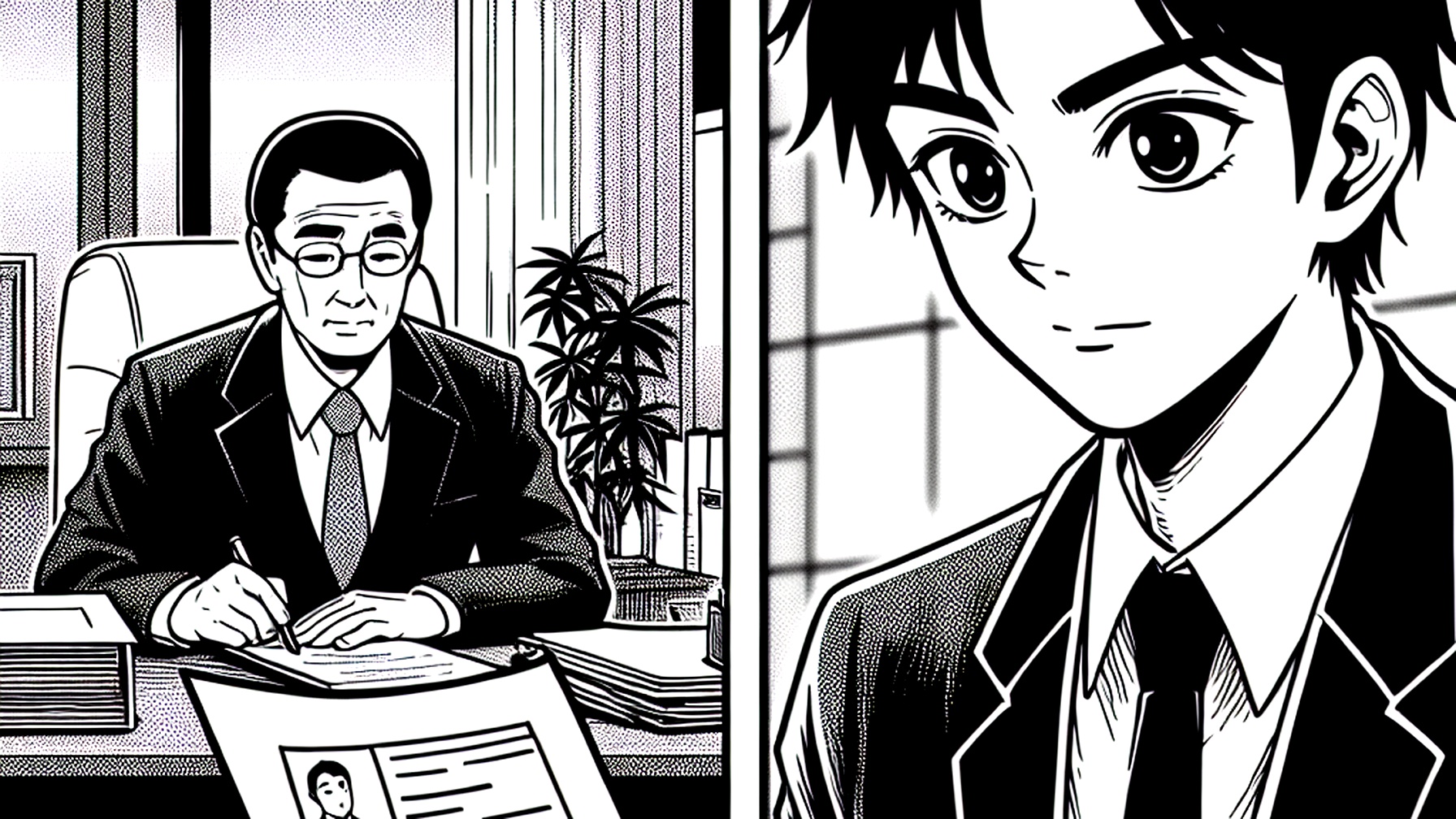
重要なのは、最初に「良い面も悪い面も把握する姿勢」を持つことです。不動産投資は株式と違い、売却や管理に時間がかかるため、一度始めると簡単には後戻りできません。また、日本の総務省「住宅・土地統計調査」によると、2023年の空き家率は13.5%と過去最高を更新し、立地によっては空室リスクが高まっています。つまり、リターンだけで判断すると、想定外の損失に直面する恐れがあります。感想ベースの体験談と公的データを併せて確認し、デメリットを事前に洗い出すことが成功への近道となります。
まず押さえておきたいのは、自己資金をどこまで投下するかです。フルローンで始めた友人は初年度の収支が黒字でも、2年目の想定外の修繕費でキャッシュフローが一気に赤字になりました。私は頭金を3割入れたため、同じトラブルでも月々の返済に余裕があり、心理的ストレスを軽減できました。このように投資戦略の違いがリスク許容度を左右します。
代表的なデメリットと実体験から得た教訓
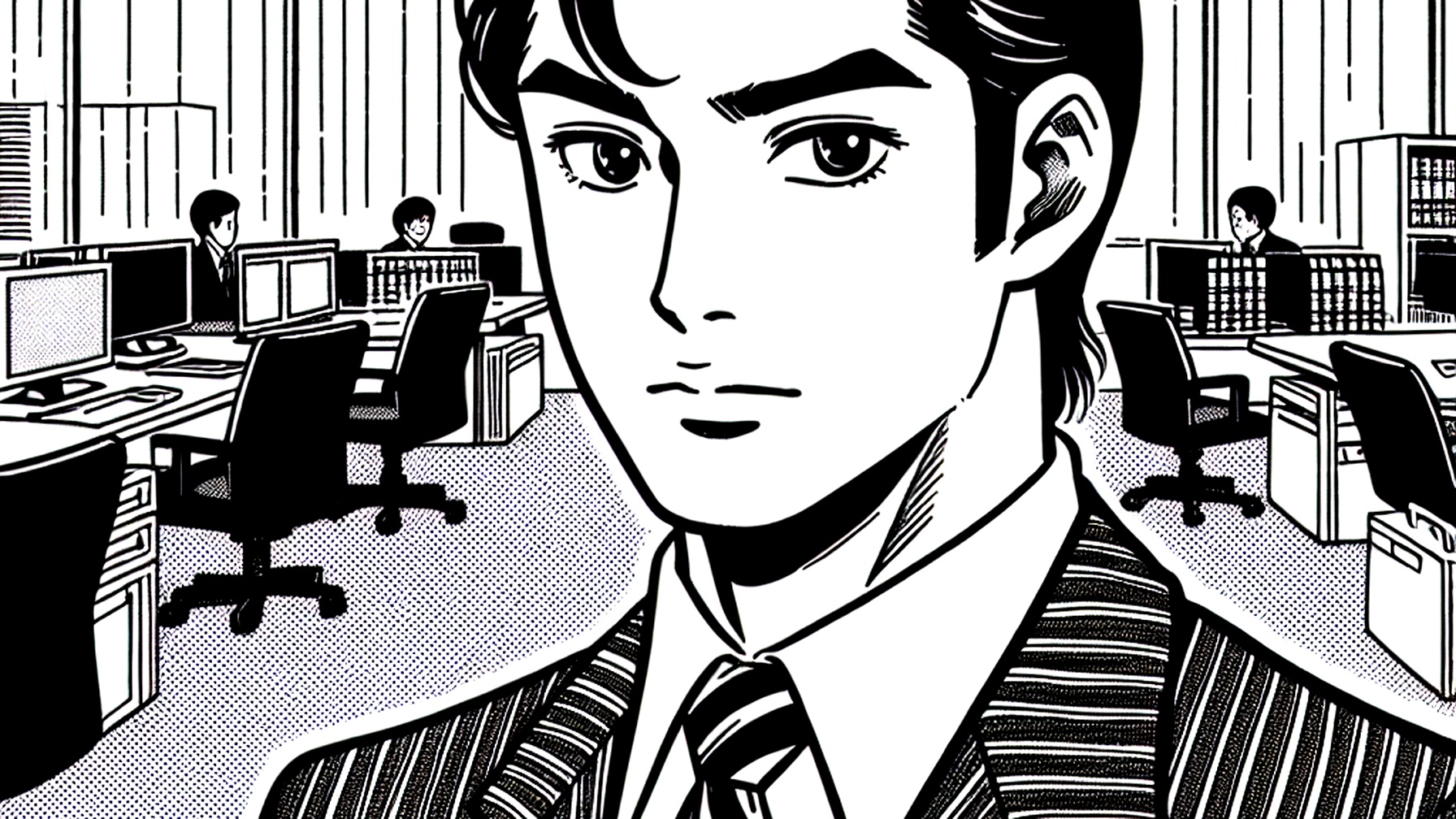
実は、不動産投資のデメリットは「お金」だけに限りません。時間的負担や精神的ストレスも見逃せない要素です。ここでは、多くの初心者が直面する三つの壁を紹介し、私の感想を交えて対策を考えます。
第一に、空室リスクです。賃貸需要が読めず家賃収入が途切れると、ローン返済を自己資金で補う必要があります。私は郊外ワンルームを購入後、平均空室期間が2ヵ月続きました。管理会社との家賃設定を見直し、駅徒歩7分でも1,000円下げるだけで回転率が改善しましたが、想定利回りは0.8ポイント低下しました。
第二に、修繕コストのブレです。築20年の木造アパートを保有する知人は、屋根防水工事に150万円を要しました。一方、私が保有するRC造(鉄筋コンクリート造)マンションでも、大規模修繕に備えた積立金が不足し、臨時徴収が発生しました。長期修繕計画を確認し、毎月のキャッシュフローから1割を積立てておくと安心です。
第三に、保険や税金の手続きの煩雑さがあります。不動産取得税や固定資産税に加え、2023年度から始まった区分所有者の火災保険料値上げで、ランニングコストが増大しました。私は税理士と顧問契約を結び、青色申告特別控除65万円を活用したことで、実質的な負担を抑えられました。
デメリットを抑える物件選びと資金計画
ポイントは、購入前の情報収集の徹底です。国土交通省「不動産取引価格情報検索」を活用し、近隣の売買価格と賃料水準を比べることで、過度に高い物件を避けられます。私が2024年に購入した築12年のファミリーマンションは、利回り6.2%と平均的でしたが、保育園やスーパーが徒歩5分圏にそろい、空室率は1%以下を維持しています。立地と生活利便性の両方を確認することで、長期的な入居需要を期待できます。
資金計画では、自己資金の「余白」を確保しましょう。住宅金融支援機構のデータによると、2025年10月時点の賃貸住宅ローン平均金利は固定1.9%前後ですが、0.5%の上昇で月々の返済額は約8%増加します。私は金利上昇2%でも黒字が保てるシミュレーションを作り、複数金融機関に事前相談しました。結果として、地方銀行から当初10年固定1.75%の融資を獲得でき、リスクを抑えた運用が可能になりました。
さらに、火災・地震保険の見直しも欠かせません。2025年度の割引制度では、省エネ性能の高い住宅に対し保険料が最大20%減額されます。私が保有するZEH(ゼロエネルギーハウス)基準の戸建賃貸は、この制度で年間1.8万円のコスト削減に成功しました。
それでも不動産投資を続ける理由とメリットとの比較
基本的に、不動産投資はデメリットを上回るメリットがあると感じています。その最大の理由はキャッシュフローの安定性です。金融庁「家計の金融行動に関する世論調査」によると、60歳以上の世帯の平均金融資産は1,730万円ですが、公的年金だけでは将来不安が残ります。私の場合、家賃収入が毎月15万円の純利益を生み、老後資金の柱となっています。
また、インフレ対策としての資産保全効果も見逃せません。日本銀行「物価指数」の推移では、2024年から24カ月連続で前年同月比2%以上の上昇が続きました。物価が上がると家賃も緩やかに上昇する傾向があり、実質的な購買力を保ちやすくなります。
最後に、節税効果です。青色申告で赤字を給与所得と損益通算できれば、所得税・住民税の還付を受けられます。私は2023年度に減価償却費250万円を計上し、所得税を約60万円軽減できました。これらのメリットがあるからこそ、デメリットを許容できるのです。
失敗談から学ぶリスクマネジメント術
まず押さえておきたいのは、情報の偏りを防ぐ姿勢です。かつて私はセミナー講師の「利回り10%保証」に魅了され、地方築40年アパートを衝動買いしました。結果として、シロアリ被害で全面リフォームが必要になり、見積は700万円に達しました。この失敗から得た教訓は、第三者の専門家に事前調査を依頼することです。
次に、出口戦略の重要性です。不動産は売却までが投資サイクルと言われます。私は2021年に区分マンションを売却し、手取り250万円の利益を確定させました。事前に周辺売却事例を調べ、リノベーション業者と協力して内装を刷新したことで、相場より2割高い価格で成約できました。
さらに、融資先の分散もリスクを減らします。メガバンクの審査が厳しくても、地方銀行や信用金庫は地域活性化を目的とした融資に積極的です。私は3行と取引を持つことで、金利交渉の余地を広げ、借り換え時に0.3%の金利削減を実現しました。
まとめ
本記事では「不動産投資 感想 デメリット」という切り口から、空室や修繕、手続きの煩雑さといった課題を具体例で紹介しました。同時に、立地調査や資金計画、保険見直しでリスクを軽減できる方法も示しました。重要なのは、メリットとデメリットを天秤にかけ、自分の目標に合った戦略を選ぶことです。まずは小規模でもいいので、数字に基づいたシミュレーションを作り、信頼できる専門家に相談してみてください。行動を起こすことでしか、リスクもチャンスも具体的には見えてきません。
参考文献・出典
- 総務省統計局「住宅・土地統計調査」 – https://www.stat.go.jp
- 国土交通省「不動産取引価格情報検索」 – https://www.land.mlit.go.jp
- 住宅金融支援機構「民間住宅ローンの金利動向」 – https://www.jhf.go.jp
- 日本銀行「消費者物価指数」 – https://www.boj.or.jp
- 金融庁「家計の金融行動に関する世論調査」 – https://www.fsa.go.jp

