不動産投資に興味はあるものの、物件を直接買う勇気が持てずに悩む人は少なくありません。そんなとき「手軽に始められる」と聞くREIT(不動産投資信託)が候補に上がりますが、実際に投資した友人から「思ったより値動きが激しい」と聞くと不安になるものです。本記事では、初心者が抱きやすい疑問に寄り添いながら、リアルな体験談と客観的なデータを組み合わせてREITのデメリットを丁寧に解説します。最後まで読むことで、表面的な魅力だけでなく落とし穴まで把握したうえで、自分に合った投資判断ができるようになります。
REITの仕組みを整理しよう
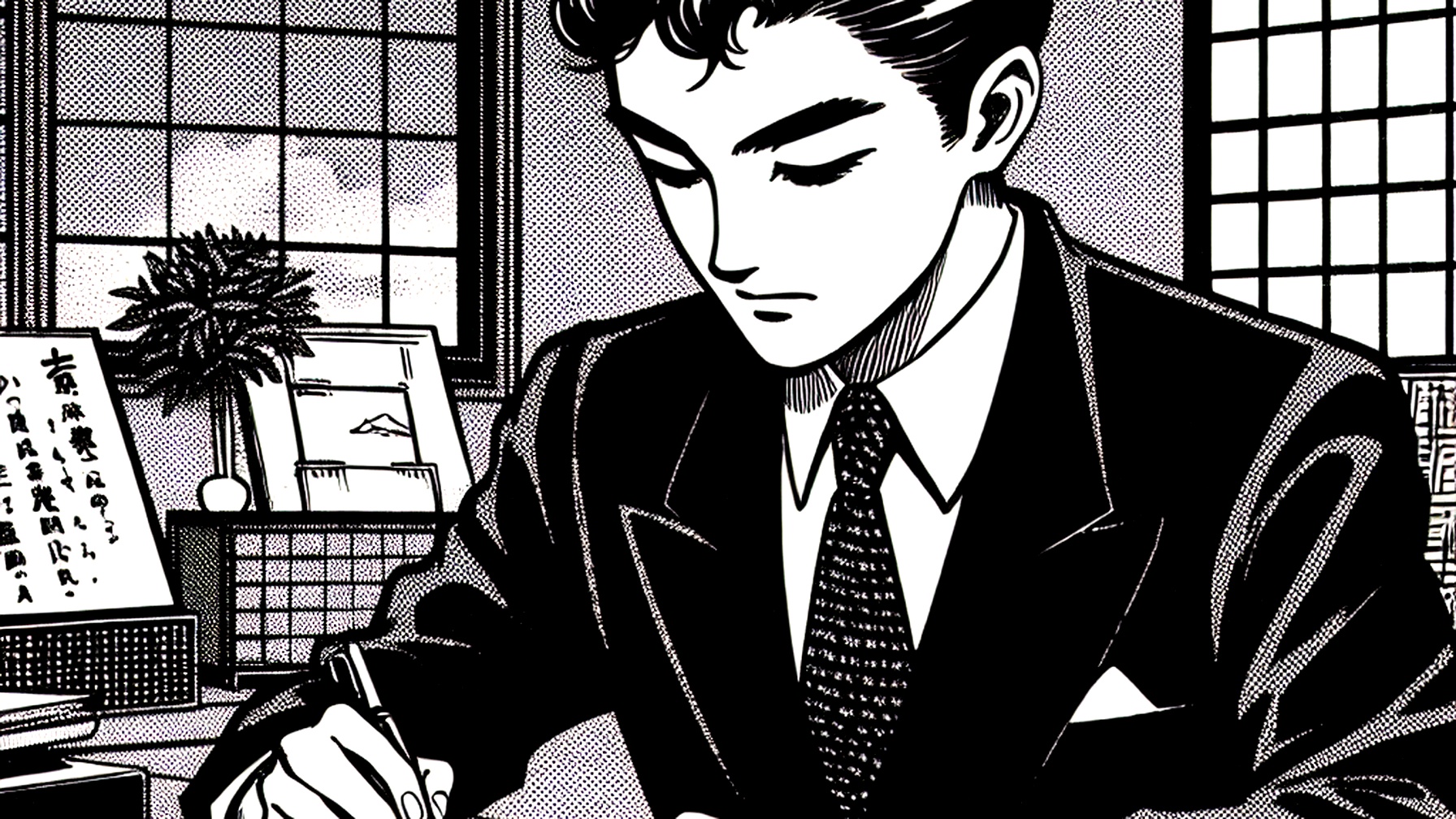
まず押さえておきたいのは、REITが「不動産版の株式投資信託」であるという点です。複数の投資家から集めた資金でオフィスビルや商業施設などを購入し、賃料収入を分配金として届けてくれます。つまり直接物件を持たずに不動産収益を得られる点が魅力ですが、その裏側には株式市場と同じ値動きリスクが潜んでいます。
東京証券取引所のデータによると、2025年9月末の東証REIT指数は年初来で9%下落しました。背景には利上げ観測やオフィス空室率の上昇といった要因があり、価格変動が思ったより大きいことがわかります。言い換えると、銀行預金の延長線で捉えると痛い目を見る可能性があるのです。
また、一般的なREITは分配金利回りが4%前後と言われますが、実際の手取りは課税後で3%程度に下がります。さらに、信託報酬や運用報酬といった内部コストが毎日差し引かれており、長期で持つほど運用成績に影響します。このように、表面利回りと手取り利回りの差をきちんと理解しておく必要があります。
一方で、少額から複数物件に分散でき、空室や修繕リスクを自分で管理しなくていい点は間違いなく利点です。重要なのは、メリットと表裏一体で存在するデメリットを把握し、自分のリスク許容度に照らして選択することだと覚えておきましょう。
体験談が教えてくれる意外な落とし穴
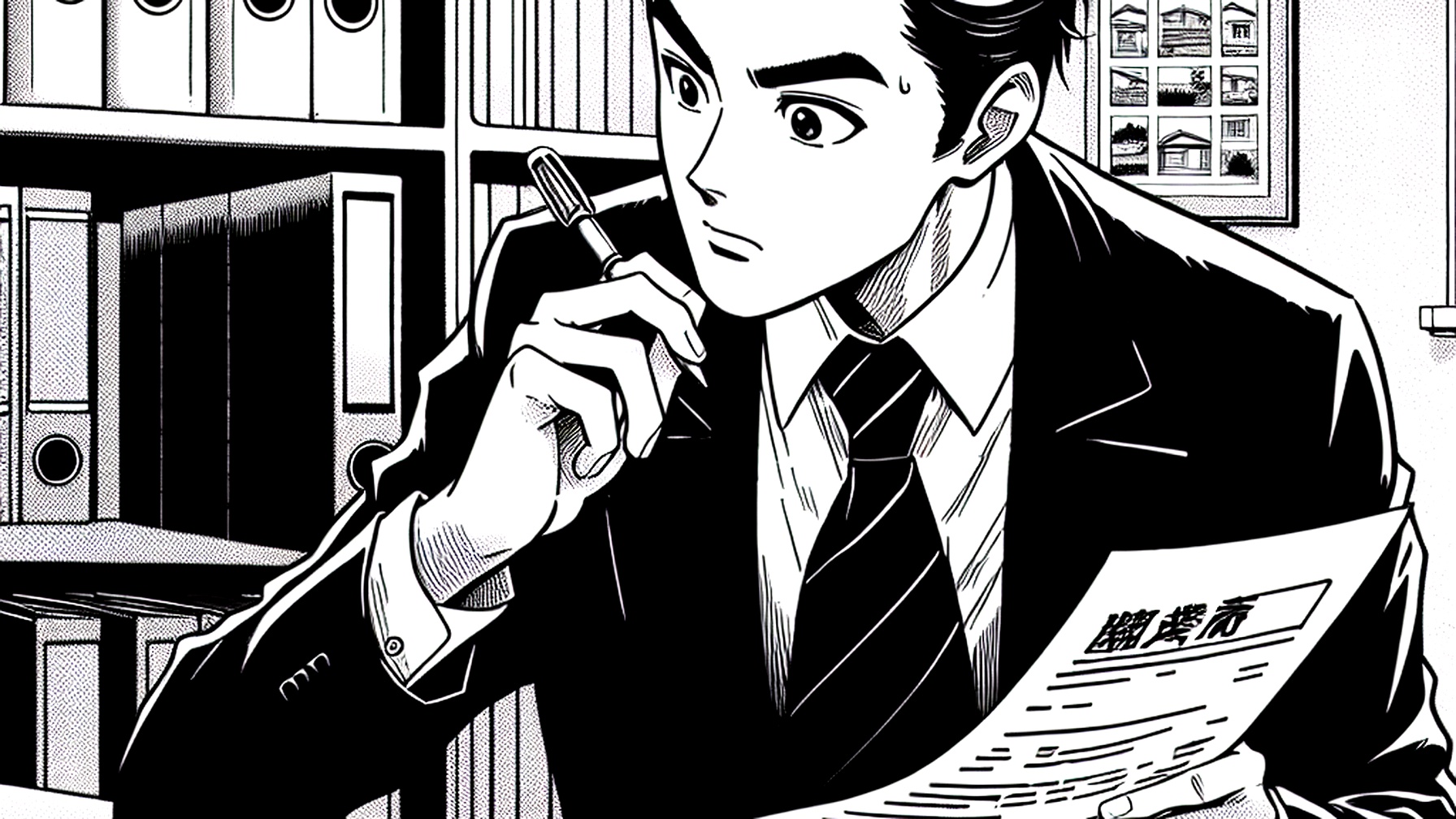
実は、数字だけでは見えにくいデメリットが体験談から浮かび上がります。ここでは筆者の投資仲間AさんとBさんのケースを紹介し、共通する失敗パターンを考察します。
まずAさんは2024年末にオフィス主体のREITを200万円購入しました。配当利回り5%に惹かれたものの、2025年春のテレワーク再拡大報道で価格が一時15%下落し、精神的に動揺して損切りしてしまったそうです。Aさんは「不動産だから値動きは小さいはず」という先入観があり、株並みのボラティリティを想定していなかった点が敗因でした。
一方Bさんは、毎月分配型の私募REITファンドに30万円ずつ積立投資を続けています。配当を家計に充当できると喜んでいましたが、運用報告書を読むと内部コストが年3%近く差し引かれており、元本は当初より7%減少していました。Bさんは「分配金=利益」と考え、元本取り崩しによる分配という仕組みを理解していなかったのです。
この2つのケースに共通するのは、パンフレットで強調されるメリットだけに注目し、値動きの幅や手数料体系を十分に精査していなかった点です。つまり、REITは「手軽さ」の裏で情報不足による失敗を招きやすい商品だといえます。
加えて、体験談では「分配金が想定より減った」という声も多く聞きます。2025年の金融庁資料では、分配金水準は金利上昇局面で圧縮されやすいと指摘されています。分配金目当てで購入した場合、想定利回りがぶれることに耐えられるかどうかを事前に確認しておく必要があります。
デメリットを数字で読み解く
ポイントは、感情に左右されず客観的なデータでリスクを把握することです。国土交通省の市場動向によれば、過去10年間の東証REIT指数の年間変動幅は平均16%でした。これはTOPIXの13%よりやや高く、REITが「不動産価格+金利動向+株式市場」の影響を複合的に受けるためと分析されています。
さらに、投資信託協会の資料では、国内REIT型公募投信の平均信託報酬は年0.8%前後です。直接上場REITを買えば証券会社の売買手数料程度で済みますが、投信を経由するとコストがかさむ点に注意が必要です。長期シミュレーションでは、年0.5%のコスト差が20年後に約10%のリターン差となりうることが示されています。
利上げリスクも看過できません。日本銀行は2025年4月にマイナス金利政策を解除し、長期金利が1.2%まで上昇しました。REITは分配金利回りが国債利回りとの差で評価されるため、金利が上がると価格が調整されやすい構造です。実際、4月から6月にかけて東証REIT指数は7%下落しています。
空室率の上昇も分配金に影響します。三幸エステートの調査では、2025年7月時点の都心5区オフィス空室率は5.9%で前年より1.2ポイント悪化しました。賃料下落が続けば分配金減少につながるため、用途別ポートフォリオを確認し、住居系や物流系に分散する工夫が求められます。
つまり、数字に基づきリスクの「大きさ」と「発生確率」を可視化することで、単なる不安ではなく具体的な対策を講じられるようになります。
デメリットを抑えるための実践的アプローチ
重要なのは、デメリットを完全に避けるのではなく、影響を許容範囲に収めることです。まず、購入前に値動きのシミュレーションを行い、15%下落しても保有を続けられるかをチェックしましょう。これにより、Aさんのような早期損切りを防ぎやすくなります。
次に、投資対象を上場REITに限定し、自分で銘柄を分散する方法があります。例えば、住居系、物流系、ホテル系など用途が異なる銘柄を3~5つ組み合わせれば、特定セクターの不調を緩和できます。投資信託型に比べて自動分配はありませんが、信託報酬を抑えられるメリットが大きいです。
さらに、分配金を再投資する仕組みを作ると複利効果が働きます。証券会社の自動再投資サービスを利用すれば、配当再投資が手間なく行えます。これにより、配当減少局面でも合計リターンを底上げしやすくなります。
加えて、NISAを活用することで税負担を軽減できます。2024年から恒久化された新NISAは年間360万円の投資枠があり、REITにも適用可能です。非課税期間は無期限となったため、分配金にかかる20.315%の税金を長期にわたり削減できます。
最後に、情報収集の習慣を持つことが不可欠です。上場REITは四半期ごとに決算資料を公表しており、物件の稼働率や資金調達コストが詳しく載っています。数字を読み解く力を付けることで、市場の雑音に振り回されずに投資判断ができるようになります。
向いている人と向かない人を見極める
実は、REITは「完全な不動産投資代替」ではなく、「価格変動を伴う金融商品」として認識することが成功の鍵です。元本の安全性を最優先する人や値動きで眠れなくなる人には向きません。一方で、株式投資の経験があり、キャッシュフローよりもトータルリターンで判断できる人には適しています。
また、短期で大きな値上がりを狙いたい人には物足りない可能性があります。分配金を含めた年5~7%程度の期待リターンをコツコツ積み上げられる人こそ、REITの利点を享受できます。したがって、自分の性格や投資目的を棚卸しし、向き不向きを見極めることが遠回りに見えて最短の成功ルートといえるでしょう。
まとめ
ここまで、体験談とデータを交えながらREITのデメリットを詳しく見てきました。値動きの大きさ、内部コスト、金利上昇リスク、そして用途特化型物件の空室リスクが主なポイントでしたが、それぞれ対策を講じれば許容可能な範囲に抑えられます。つまり、手軽さに流されず「自分で理解しコントロールできるか」が成否を分ける要因です。この記事を参考に、まずは少額で試しながらシミュレーションと情報収集を習慣化し、納得感のある不動産投資への一歩を踏み出してください。
参考文献・出典
- 国土交通省「不動産投資市場動向調査」 – https://www.mlit.go.jp
- 日本取引所グループ「東証REIT指数推移」 – https://www.jpx.co.jp
- 投資信託協会「投資信託の手数料に関する調査」 – https://www.toushin.or.jp
- 金融庁「資産形成に関するワーキング・ペーパー」 – https://www.fsa.go.jp
- 総務省統計局「家計調査報告」 – https://www.stat.go.jp

