家賃収入だけでなくテナント賃料も得られる店舗付き物件は、収益の柱を二本に分散できるため魅力的です。しかし住宅ローンとは違い、金融機関の審査基準や返済計画の立て方が複雑で、初心者は戸惑いがちです。本記事では「不動産投資ローン 店舗」をテーマに、最新の金利動向から融資商品、審査対策までを整理します。読み終えるころには、必要な準備と具体的な行動ステップがクリアになり、安心して次の一歩を踏み出せるはずです。
店舗付き物件に投資する魅力とリスクを整理しよう
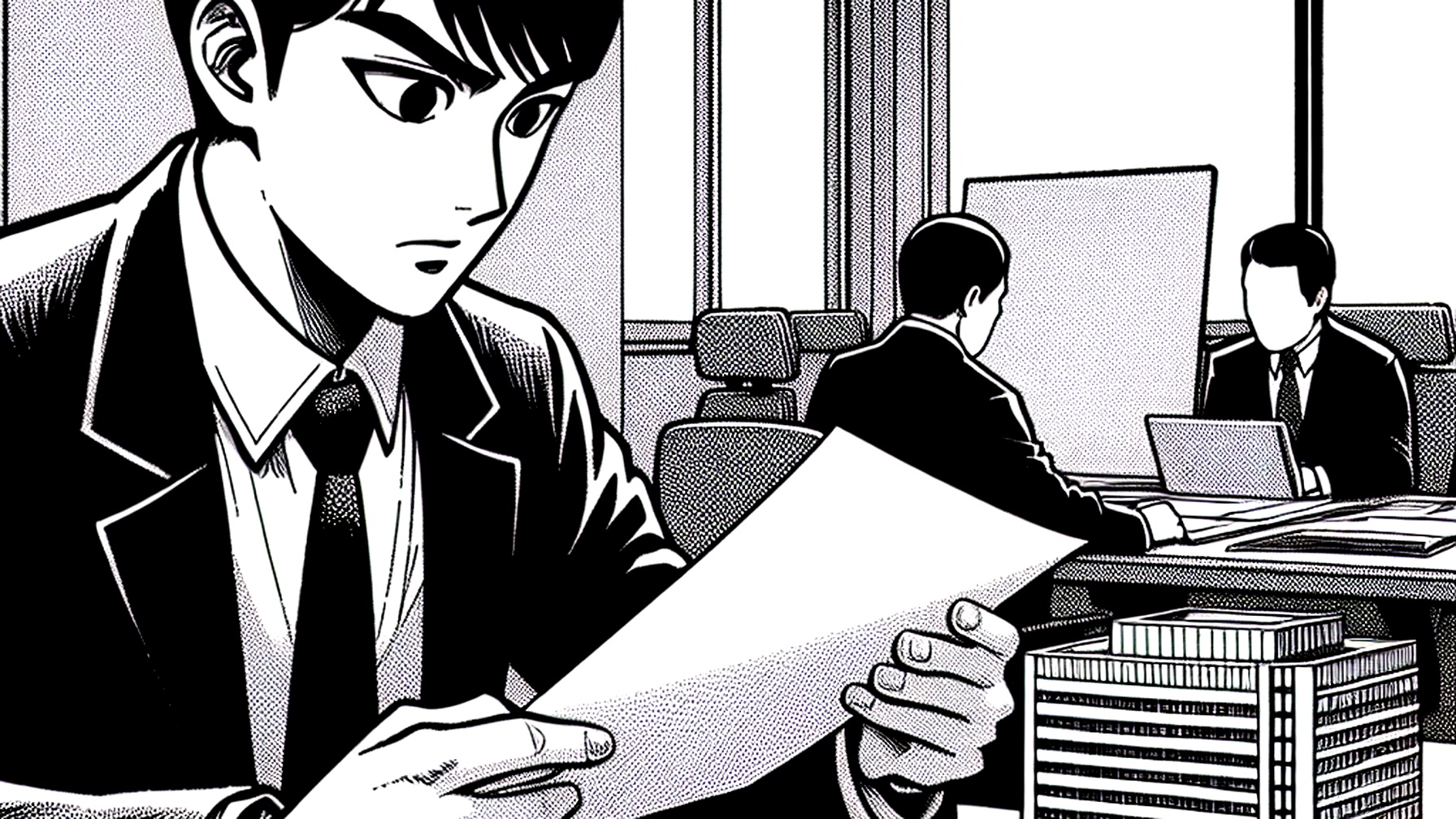
重要なのは、店舗付き物件が住居専用物件と比べてどのような収益構造を持つかを理解することです。住居部分の家賃に加えてテナント料が入るため、満室時の単月キャッシュフローは大きく伸びます。ただし、飲食や物販など業種による売上変動を受けやすく、テナントが退去すると空室期間が長引く傾向があります。
まず収益面のメリットを見てみましょう。国土交通省の「2025年版賃貸市場統計」によれば、同規模・同立地のワンルームマンションと比べ、店舗付き物件の平均利回りは約1.5ポイント高い数値を保っています。また、テナント契約は2年更新が一般的ですが、事業が軌道に乗れば長期継続される例も多く、安定収益を狙えます。
一方で、リスク管理も欠かせません。例えば飲食店が入居している場合、油煙や臭気対策の設備投資が必要です。さらに、居住者とのトラブルを避けるため用途規制や管理規約を整えておくことが不可欠です。つまり、高い利回りの裏側には専門的な運営ノウハウが求められる点を押さえましょう。
最後に、出口戦略にも言及します。テナントが付かず収益が下がると、物件売却時の価格評価が想定より低くなる恐れがあります。購入段階から将来の売却シナリオを描き、立地や用途の汎用性もチェックすることが店舗付き物件の成功条件です。
不動産投資ローン 店舗で利用できる主な融資商品
ポイントは、店舗部分があるだけで住宅ローンの対象外になるケースが多い点です。そのため投資家向けのアパートローンや事業用ローンを選択するのが一般的です。ここでは代表的な三種類の借入方法を比較します。
・アパートローン 住居部分の賃料を主な返済原資とみなす商品です。店舗面積が延床の50%未満であれば適用されることがあり、金利は変動1.5〜2.0%前後と比較的低水準です。
・プロパーローン 金融機関が自社審査のみで実行する融資形態で、店舗面積が大きい物件でも柔軟に対応します。金利は2.0〜3.5%程度と高めですが、融資期間を長く取りやすい利点があります。
・ノンリコースローン 物件から得られる収益のみを返済原資とする非遡及型の融資です。借入人の個人保証が不要な反面、LTV(Loan to Value)が60%程度に制限され、頭金を厚く積む必要があります。
実は金融機関ごとに審査の切り口は大きく異なります。都銀は長期安定収益を重視し、地方銀行や信用金庫は地域活性化の観点から柔軟に判断する傾向があります。複数行を比較し、条件交渉を行うことで金利や期間が改善する例も珍しくありません。つまり、準備段階で融資戦略を立てることで総返済額を大きく圧縮できるのです。
金利と返済計画を組み立てる三つのコツ
まず押さえておきたいのは、金利の違いが長期の収益性に与える影響です。全国銀行協会の2025年10月時点データによると、変動金利型は1.5〜2.0%、10年固定型は2.5〜3.0%が相場です。金利差0.5%でも、借入1億円・期間25年の場合、総返済額は約700万円変動します。
次に、返済期間をどう設定するかが重要です。期間を短く設定すれば返済総額は減りますが、月々のキャッシュフローは圧迫されます。店舗付き物件はテナント退去時に収入が途絶えることを想定し、空室率20%でも赤字にならない期間に調整するのが賢明です。返済期間は15年を下限に、収支シミュレーション上無理のない範囲で決めましょう。
もう一つのポイントは、固定・変動の組み合わせです。例えば借入額の70%を固定金利、30%を変動金利で組むと、金利上昇リスクを抑えつつ低金利メリットも取り込めます。金融機関によっては部分固定を認めない場合もあるため、事前に相談しておくとスムーズです。一方で、将来の金利上昇を織り込み、シミュレーション時に2%程度の上乗せ金利で試算しておくと安全域が確保できます。
最後に、返済比率の目安を示します。不動産投資ローン 店舗の場合、年間返済額を年間家賃収入の50%以下に抑えることが推奨されます。テナント退去や設備更新費まで含めた保守的な計画を立てることで、長期運営の安定性がぐっと高まります。
審査を通過するための書類準備とアピール方法
基本的に、金融機関は物件の収益力と借り手の返済能力を総合評価します。物件資料としては、賃貸借契約書の写し、過去3年分の収支表、テナントの業種概要が求められます。加えて、建築確認済証や耐震診断報告書など建物の安全性を示す書類も重要です。
申込人側の資料としては、直近3期分の確定申告書や法人決算書、納税証明書が定番です。会社員の場合も、源泉徴収票だけでなく副業許可証や給与明細を添付すると信頼度が向上します。特に店舗付き物件では「事業運営能力」を評価する銀行が多いため、これまでの投資実績や管理体制をレポート形式で提出すると効果的です。
さらに、空室対策や内装リノベーションの計画資料を準備し、将来の収支改善シナリオを示しましょう。銀行担当者が稟議を書く際、具体的な数字と行動計画があると審査が通りやすくなります。言い換えると、「収益改善の道筋を提示できる投資家」が高評価を得るわけです。
最後に、面談時のコミュニケーションも無視できません。金融機関は人間関係を重視する文化が根強く、質問に対して正直かつ論理的に回答する姿勢が信用につながります。身だしなみや時間厳守など基本的なビジネスマナーを徹底することで、審査の印象が大きく左右される点を忘れないでください。
2025年度の支援制度と税メリットを活用する
実は2025年度も、不動産投資家が利用できる公的支援や税制優遇がいくつか存続しています。代表的なのが「中小企業経営強化税制」です。耐震改修や省エネ設備を導入した場合、一定条件を満たせば即時償却または税額控除が受けられます。店舗部分のエネルギー効率を高めることでテナント募集にもプラスに働くため、一石二鳥です。
また、住宅確保要配慮者向け賃貸住宅供給促進制度(いわゆるセーフティネット住宅制度)は2025年度も継続されます。住居部分を登録すると改修工事費の補助が出る場合があり、その費用を店舗改装費に充当することで物件全体の質を底上げできます。ただし用途や入居者属性に条件があるため、自治体窓口で詳細を確認することが前提となります。
さらに、固定資産税の特例措置も見逃せません。店舗付き住宅で床面積の2分の1以上を住居用とする場合、住居部分は小規模住宅用地の評価減(課税標準が6分の1)を受けられます。つまり、テナント面積を調整して住居比率を高めるだけで、ランニングコストが大きく下がる可能性があります。
自治体独自の補助金も複数続いていますが、申請期間は年度内に限られるケースが多いです。補助率や上限額は自治体により差があるため、必ず公式サイトで最新情報を確認しましょう。制度の組み合わせ次第で実質利回りが1ポイント以上改善する事例もあるため、活用しない手はありません。
まとめ
店舗付き物件への投資は、家賃とテナント料の二つの収入源を確保できる点が大きな魅力です。ただし、リスク管理や専門的な運営ノウハウが欠かせず、資金計画の精度が成功を左右します。本記事で紹介したとおり、不動産投資ローン 店舗には複数の融資商品があり、金利や期間を工夫することで収益を最大化できます。必要書類を整え、銀行とのコミュニケーションを意識すれば審査のハードルも下がります。最後に、2025年度の税制優遇や補助制度を組み合わせて、キャッシュフローをさらに強化してみてください。今日から具体的な行動を始めることで、安定した店舗付き物件経営への道が開けます。
参考文献・出典
- 国土交通省 賃貸市場統計2025年版 – https://www.mlit.go.jp/
- 全国銀行協会 2025年10月住宅ローン金利データ – https://www.zenginkyo.or.jp/
- 中小企業庁 中小企業経営強化税制の手引き2025 – https://www.chusho.meti.go.jp/
- 総務省 固定資産税に関するFAQ 2025年度版 – https://www.soumu.go.jp/
- 国土交通省 セーフティネット住宅制度ガイドライン2025 – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/

