家賃収入を得られる「収益物件」に興味はあるものの、「どこから手を付ければいいのか分からない」「資格がないと買えないのでは」と不安を抱える方は多いでしょう。実は、正しい手順と基本的な知識を押さえれば、大半の人が参入できるのが不動産投資の魅力です。本記事では、15年以上の実務経験を持つ筆者が、物件選びから購入後の運用までをやさしく解説します。さらに、購入時に必要な資格や、持っていると優位に立てる資格も紹介しますので、読み終えるころには自分が取るべき行動が明確になるはずです。
収益物件の基礎を押さえる
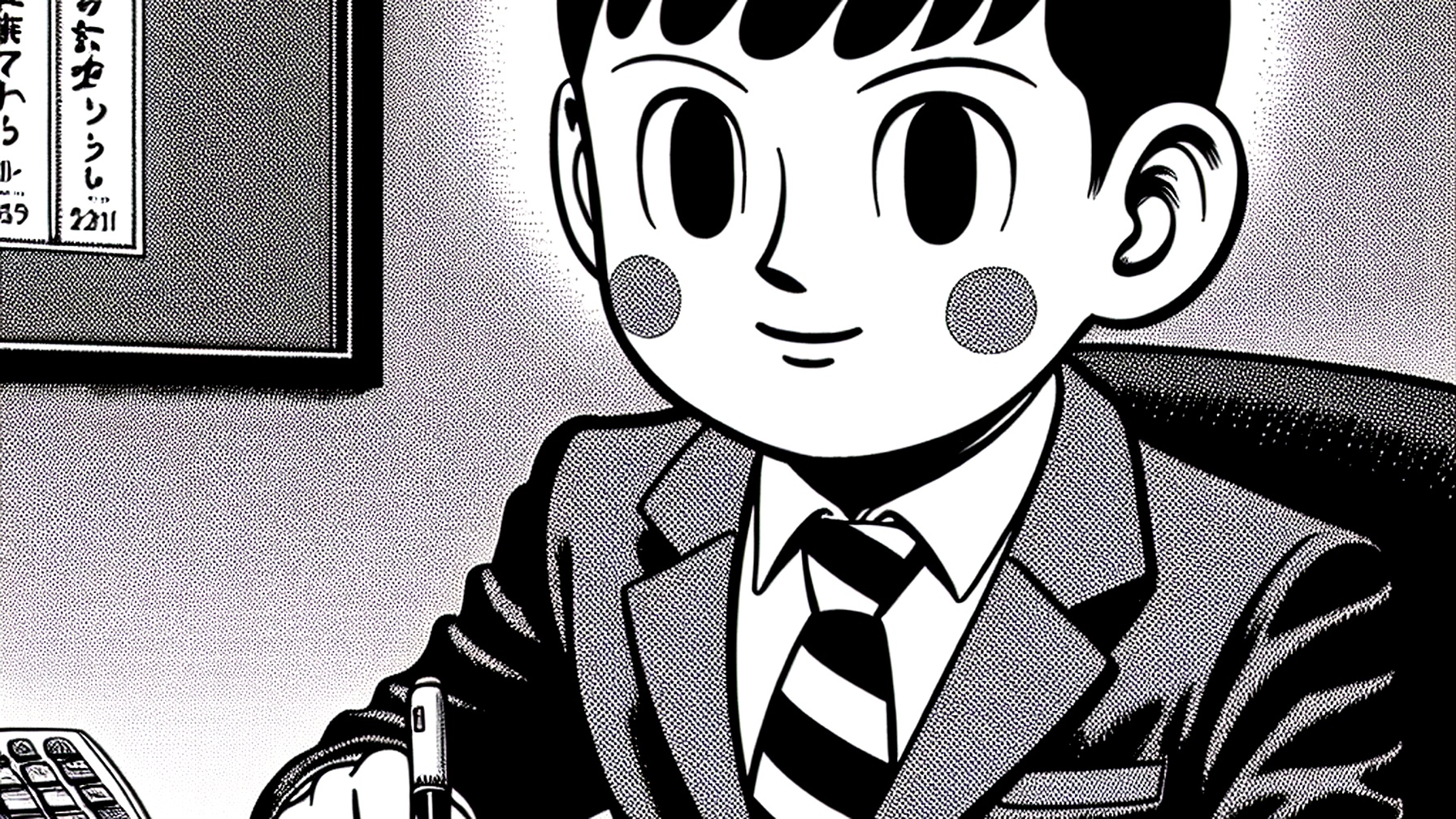
まず押さえておきたいのは、収益物件が「賃貸によるインカムゲイン(継続収入)」と「将来の売却益」という二つの利益を生む資産である点です。家賃収入は毎月のキャッシュフローを安定させ、売却益は最終的なリターンを高めます。しかし、立地や物件タイプを誤ると空室リスクや値下がりリスクが増大します。
2025年の総務省人口推計では、依然として三大都市圏への集中が続いており、特に都心部の単身者向け物件は空室率が低い傾向にあります。一方で、地方都市や郊外では人口減少が進むエリアもあり、利回りが高く見えても長期運用では苦戦するケースが少なくありません。つまり、賃貸需要を予測するデータを読み解き、自分の資金と目的に合った立地を選ぶことが最初のハードルになります。
さらに、表面利回りだけで判断するのは危険です。固定資産税や修繕費を差し引いた実質利回りこそが手取りを左右します。国土交通省「不動産投資市場調査」によると、築20年超のマンションでは共用部修繕費が家賃収入の10%近くに達するケースがあります。数字の裏に隠れたコストを見抜く眼力を養いましょう。
購入手順をステップで理解する
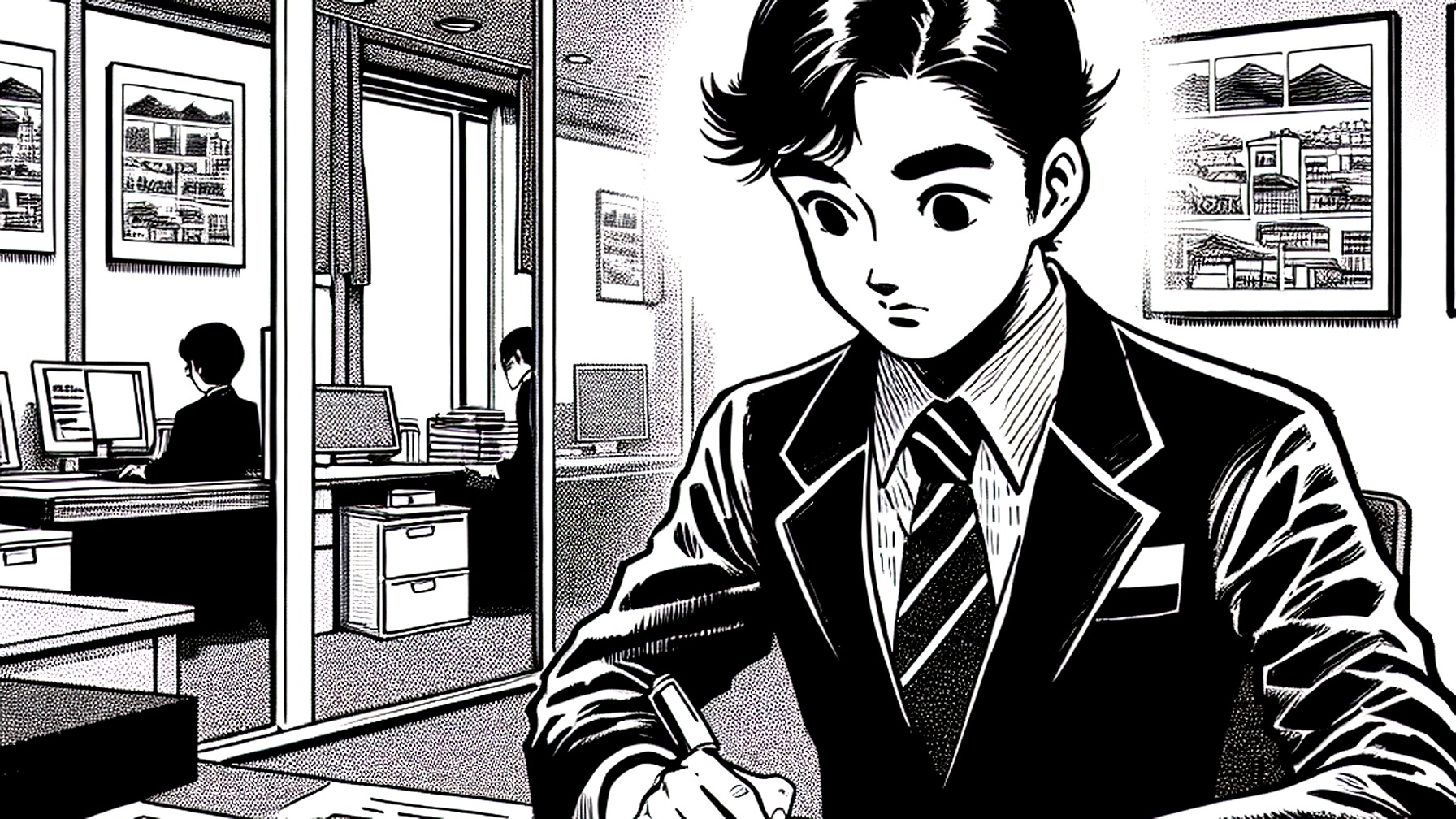
ポイントは、調査、資金計画、契約、引渡しの四段階を順序よく進めることです。最初に行う物件調査では、レントロール(家賃明細)や重要事項調査報告書を取り寄せ、現在の入居状況と過去の修繕履歴を確認します。この段階で手を抜くと、購入後に多額の改修費用が発生するリスクが高まります。
次に、金融機関で事前審査を受け、自己資金とローンの比率を固めます。2025年時点で主要銀行のアパートローン金利は変動型で年1.8〜2.8%が中心です。自己資金を2割入れると金利が0.2%下がるケースもあるため、総返済額の圧縮につながります。ここでは、家賃収入の50〜60%を返済に充ててもキャッシュフローがプラスになるかを試算することが不可欠です。
売買契約では、手付金(物件価格の5〜10%)を支払い、重要事項説明を受けます。宅地建物取引士が法的リスクを説明しますが、疑問点は必ずその場で確認しましょう。引渡し当日は、登記移転と残代金の支払いを同時に行い、鍵を受け取って完了です。スムーズに進めるためには、司法書士や税理士と早めに連携し、必要書類を事前に揃えておくことが望ましいです。
融資と資金計画を堅実に立てる
重要なのは、金利や返済期間だけでなく、自己資金割合と修繕積立をセットで考えることです。日本政策金融公庫のデータによれば、自己資金を1割増やすと貸付可決率が約15%向上します。また、返済期間を延長すれば月々の負担は軽くなりますが、総支払利息は増えるため、35年ローンを採用する場合でも10年目までに繰上返済を行う計画を立てると総返済額を抑えられます。
修繕積立は年間家賃収入の5〜10%を目安に別口座で管理すると安心です。築浅物件なら初期負担は小さいものの、10年を過ぎると給湯器交換や屋上防水といった高額修繕が発生します。金融庁の「サステナブルファイナンス指針」では、長期保有資産へのメンテナンス計画を重視する姿勢が示されており、銀行審査でも修繕積立の有無が評価対象になっています。
さらに、2025年度の住宅ローン減税は居住用が対象ですが、併用住宅(半分以上を自宅とする賃貸併用住宅)なら一部控除が適用されます。賃貸併用を検討する場合は、床面積要件や入居割合など細かな条件を満たす必要があるため、税理士と相談してシミュレーションを行いましょう。
必要な資格とあると有利な資格
実は、収益物件を購入するだけなら特別な資格は要りません。個人でも法人でも、売買契約書に署名押印できれば取引は成立します。ただし、知識不足で高値掴みをしたり、入居者対応でトラブルを招くリスクは決して小さくありません。
そこで、宅地建物取引士(宅建士)は最も役立つ国家資格と言えます。宅建士を持っていれば、法律や税制を体系的に理解でき、仲介手数料を抑えられる場合もあります。また、賃貸経営管理士は管理会社との交渉や自主管理を行う際に威力を発揮します。2021年に国家資格化され、2025年10月時点で管理業登録制度の重要項目になっているため、取得すれば金融機関からの信頼も得やすいです。
一方で、ファイナンシャル・プランナー(FP)は資金計画を総合的に組み立てるのに便利です。税金、保険、相続まで横断的に学べるため、複数物件を保有する中長期戦略を描けます。資格取得には時間がかかりますが、学習過程で得られる知識が投資判断を大きく底上げします。つまり、資格は必須ではないものの、長期的な利益を追求するなら取得する価値は十分あるといえます。
2025年の法制度と実務上の注意点
まず押さえておきたいのは、インボイス制度への対応です。課税売上が年間1,000万円を超えるオーナーは、2023年開始の適格請求書保存方式に従い、賃貸収入にも消費税区分を記載した請求書を発行する必要があります。登録番号の取得が済んでいない場合は、早急に税務署へ申請しましょう。
また、2025年度税制改正では「空き家対策特別控除」の延長が決まりました。相続した空き家を耐震改修後に売却する場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できます。投資家がリノベーションを想定して取得する際にも大きなメリットがあるため、適用条件を把握しておくと戦略の幅が広がります。
一方で、住宅性能表示制度の改正により、新築アパートでも省エネ基準への適合が義務化されました。省エネ等級が低い物件は資産価値が下落しやすく、金融機関の評価も厳しくなる傾向があります。環境省は省エネ基準適合によるランニングコスト低減効果を公表しており、10年で数十万円単位の光熱費差が出るとしています。長期保有を前提にするなら、建物性能にも注目すべきです。
さらに、2025年4月から改正民法が施行され、敷金精算のルールが明確化されました。国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」に準拠した対応が求められるため、旧来の慣行で運用しているオーナーは更新契約のタイミングで見直しが必要になります。トラブル防止だけでなく、退去立会いの時間短縮にもつながるため、実務面でのメリットは大きいです。
まとめ
最後に、本記事で紹介した手順とポイントを振り返りましょう。まず、人口動態と実質利回りを分析し、需要のあるエリアで物件を選ぶことが成功の土台になります。次に、調査、資金計画、契約、引渡しという四段階を着実に進め、金融機関や専門家と連携しながらリスクを最小化する姿勢が欠かせません。資格は必須ではないものの、宅建士や賃貸経営管理士を取得すれば知識面でも交渉面でも大きな武器になります。法制度は毎年改正されるため、最新情報を追い続ける姿勢が長期の安定収益に直結します。今日得た知識をもとに、まずは気になるエリアの市場調査からスタートしてみてください。具体的な行動が、将来の安定したキャッシュフローへの第一歩になります。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産投資市場調査2025年版 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局 人口推計(2025年10月) – https://www.stat.go.jp
- 金融庁 サステナブルファイナンス指針 – https://www.fsa.go.jp
- 日本政策金融公庫 融資統計2025年3月 – https://www.jfc.go.jp
- 環境省 省エネ基準関連資料(2025年度) – https://www.env.go.jp

