不動産投資を始めたいものの、毎月のローン返済に追われるのは不安という声をよく耳にします。実際、利回りが低下しつつある新築ワンルームでは手取りがほとんど残らず、「これでは投資と言えない」と感じる人も多いでしょう。そこで注目されるのが中古物件です。取得コストを抑えつつ分配金を確保できるため、手元キャッシュフローを重視する初心者には魅力的な選択肢になります。本記事では、分配金 中古というキーワードを軸に、仕組みから物件選び、税制までを丁寧に解説します。読み終えるころには、自分に合った中古物件で安定収益を生み出すステップが具体的にイメージできるはずです。
分配金とは何か
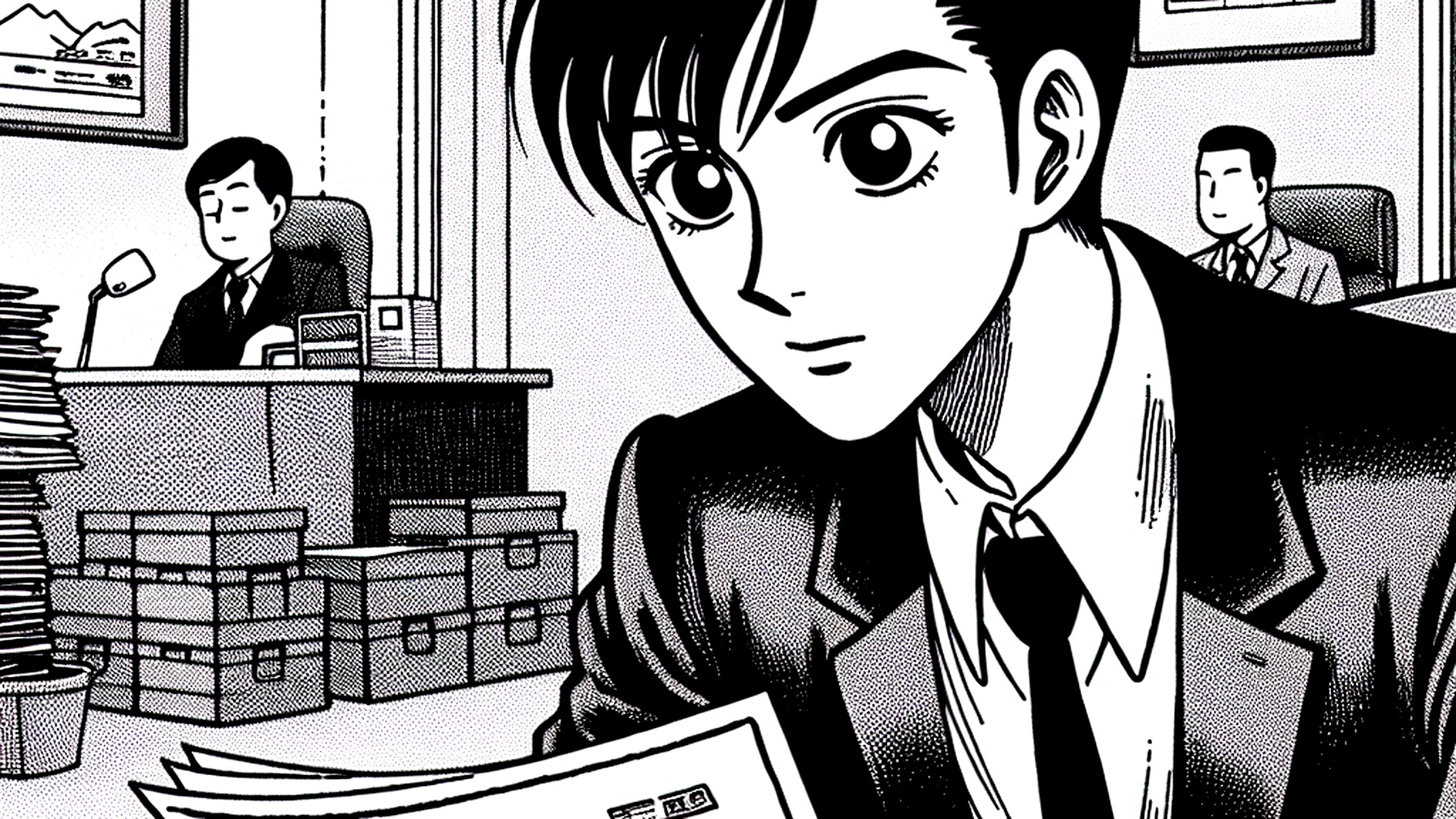
ポイントは、分配金が単なる「家賃の取り分」ではないという理解です。分配金とは、家賃収入から運営費やローン返済などを差し引いた後に投資家が受け取る純粋なキャッシュフローを指します。株式でいう配当と同じく、不動産投資のリターンを「現金で実感」できる部分です。
まず家賃がそのまま手元に残るわけではありません。管理委託料、修繕積立、固定資産税が差し引かれ、さらにローン返済の元利金が控除されます。つまり毎月の分配金を正確に把握するには、入出金を網羅したキャッシュフロー計算が不可欠です。
2025年時点で、国土交通省「不動産価格指数」によると首都圏中古マンションの平均利回りは約3.8%ですが、地方政令市の築20年超区分マンションでは6%前後の事例もあります。利回りが高いほど分配金は増えますが、空室リスクや修繕コストも上がるため、表面利回りだけでなく実質利回りを必ず試算しましょう。
中古物件投資のメリットと注意点

まず押さえておきたいのは、価格メリットと情報量の豊富さです。中古は同じ立地でも新築より2〜4割安く購入できるケースが珍しくありません。その分ローン元本が少なくなり、毎月の返済が軽くなるため分配金が出やすくなります。
一方で、築年数が進むほど修繕費の振れ幅が大きくなります。国土交通省の「長期修繕計画ガイドライン」では、築25年を過ぎると大規模修繕の周期が短くなると指摘されています。購入前に管理組合の長期修繕計画書を確認し、積立金が不足していないかチェックすることが肝心です。
さらに、中古市場は情報の非対称性が高い点も見逃せません。売主と買主で保有情報に差があるため、レントロール(賃貸借条件一覧)や過去の修繕履歴を必ず取り寄せ、数字が示すリアルな収支を検証しましょう。ここを怠ると分配金どころか赤字転落のリスクすらあります。
キャッシュフロー計算と分配金の関係
実は、分配金を最大化する鍵は購入前のシミュレーションにあります。まず家賃収入から空室率を控除し、運営費率を掛け、ローン返済額を差し引くことで毎月の純キャッシュフローを算出します。空室率は地域平均より少し厳しめ、運営費率は区分マンションで20%前後を目安にすると現実的です。
ここで重要なのは、ローン金利と期間の組み合わせです。日本銀行の「貸出約定平均金利」では、2025年4月時点の10年以上固定金利が2.2%前後となっています。期間を30年に延ばせば返済額は減り分配金は増えますが、総支払利息は大きくなります。逆に15年返済にすると利息を圧縮できますが、月々の分配金がほとんど残らない恐れがあります。
つまり、自己資金を何%投入するかがバランス調整のツールとなります。物件価格の30%を頭金にすれば、返済比率が下がり、安全余裕が広がるためキャッシュフローは安定しやすくなります。分配金 中古戦略では、無理のない自己資金投入こそリスク管理の第一歩です。
2025年度の税制と分配金を守るコツ
重要なのは、税負担をコントロールすることで手取り分配金を守る点です。2025年度の所得税法では、不動産所得は総合課税が原則で、家賃収入から必要経費を差し引いた黒字部分が課税対象となります。青色申告を適用すれば最大65万円の特別控除が使え、損益通算も可能です。
固定資産税に関しては、築年数が経過した中古マンションでも建物部分の評価額が下がるため、新築より税額が低くなる傾向があります。総務省の「固定資産税評価のあらまし」によると、評価額は3年ごとに見直されるため、築15年を過ぎると税額は購入当初より1〜2割減る事例が多いです。
さらに、2025年度も適用される「月次家賃等支援給付金」のようなコロナ特例は終了していますが、登録免許税の軽減措置(中古住宅の一定要件※適合など)は継続中です。適用条件を満たせば、取得時のコストを抑えられ、その分分配金に回せる余力が増えます。必ず司法書士に事前確認しておきましょう。
成功事例に学ぶ中古物件運用術
まず、東京都心近郊で築22年の区分マンションを2,200万円で購入したAさんの事例を見てみます。家賃は月11万円、ローンは金利1.9%・期間25年で毎月返済額は約9万円です。管理費・修繕積立金を合わせて1.8万円、固定資産税を月割りで0.5万円とすると、手残りは月1.7万円になります。年間ベースで約20万円の分配金が確保でき、自己資金300万円を投下したAさんの表面利回りは6%、実質自己資金利回りは約6.7%に達しました。
一方、大阪市で築30年のワンルームを700万円で取得したBさんは、現金一括購入を選択しました。家賃4.5万円、運営費0.9万円、税金0.2万円とすると、月々3.4万円がそのまま分配金となります。年間で40万円を超えるため、購入価格に対し実質利回りは5.7%です。ローン返済がない分キャッシュフローは安定し、空室時の負担も軽く済む点がメリットと言えます。
これらの事例が示すのは、ローン活用型でも現金一括型でも、計算通りのキャッシュフローを実現できれば分配金 中古戦略は十分機能するという事実です。重要なのはシミュレーション通りに運用し、修繕費の積立を怠らないこと。それが中長期での安定収益につながります。
まとめ
中古物件で安定した分配金を得るには、価格メリットを活かしつつ、修繕リスクや税負担を丁寧に織り込むことが欠かせません。具体的には、購入前に実質利回りを試算し、自己資金とローンのバランスを調整し、青色申告や登録免許税軽減などの制度を活用することで手取りを最大化できます。最後に行動提案として、気になるエリアの家賃相場を調べ、レントロールが開示されている中古物件を1件でも多く内覧してみましょう。数字と現場の両面を確認することが、分配金 中古戦略を成功に導く最短ルートです。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp/
- 国土交通省 長期修繕計画ガイドライン – https://www.mlit.go.jp/
- 日本銀行 貸出約定平均金利の推移 – https://www.boj.or.jp/
- 総務省 固定資産税評価のあらまし – https://www.soumu.go.jp/
- 国税庁 所得税法基本通達 – https://www.nta.go.jp/

